ワクチン接種をネットで予約したのだが、出遅れもあって、予約できたのは同じ岐阜市でも私の住まいする南西部から対角線の北東部の岩小学校というところであった。
なんか、濃尾平野の突き当りで三方が山に囲まれている。


そこへ行く経路としては、岐阜市を斜めに進むより、東の各務原市へ入り、そこから北上したほうがいいというのでそれに従う。

そのルートで、6月12日に第一回を済ませ、7月3日が第2回であった。これで安全なのか、それとも変異株に対してはまだ免疫性がないのか、よくわからない。
帰途各務ヶ原市に数年前に亡くなった高校時代の友人の家があったので、そこへ立ち寄ることとする。しかし、そこへと辿り着けない。過去何度も来ていて、たしかにこの道だと思うのだが、それらしいところはない。
諦める。今度、ナビに彼の住所を入れて訪問してみよう。
2度目の接種のあとは、何らかの影響が出る可能性が高いというが、それらしき兆候はない。生まれつき鈍感なのだ。

味噌をのせる前
夕餉に、昨日買った米茄子のしぎ焼きを作る。何度も作った料理だが、相方が亡くなってからは作っていない。数年ぶりだ。
しかし、身体が覚えていたのか、うまくできた。

茄子に皮に沿ってとその身部分に切込みを入れておかないと、食べにくい。決め手は味噌の味だ。伝統的な赤味噌に砂糖、味醂に隠し味に醤油をほんの少し入れる。
ネットのレシピには白味噌や信州味噌を使ったものがあるが、やはりこれは赤味噌でしょうといいたくなる。

合わせたのは日本酒。食中酒は吟醸香などは不要で、最近はもっぱら純米酒にしている。
マケドニアと聞いて私たちはどれだけのことを知っているだろう。
私に関していえば、古代マケドニア王国にはアレクサンドロス大王という英雄がいて、南はエジプトから東はインドをも征服したが、若干31歳で毒殺か酒の飲みすぎかで命を落としたことは知っている。その後の歴史はほとんど知らず、戦後史においてはユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部となったことは知っていた。

そして、1991年の社会主義圏崩壊により、旧ユーゴスラビアも解体され、マケドニア共和国になったのだと了解していた。ここで取り上げた映画も、チラシなどさまざまなところで「マケドニア映画」として紹介されている。しかし、厳密に言うとマケドニアという国は存在しない。
それは、古代マケドニアの栄光を自らのものとするギリシャのクレームによってその国名は封じられ、2019年、「北マケドニア」に国名を変更したからだ。なぜ国名まで変更したのかは、それにによってEUへの加盟の道が開かれるからだという(現在審議中)。

まったく余計なトリビアになったが、「北」の有無にかかわらず、私にとっては初めてのマケドニア映画であった。
主人公ペトルーニャは歴史学で大学を卒業し、学歴はあるものの、それを生かした職業にはありつけないままに過ごしてきた32歳のやや肥満体の風采の上がらない女性である。生活態度もどこか投げやりなところが目立ち、だらしない感が目立つ。
面接試験に出かけるのだが、そこでもセクハラ的な扱いを受けるだけで相手にされない。
その帰途、ギリシャ正教のある催事に遭遇する。それは、日本でもよくあるはだか祭に似ていて、川のなかで待機する裸の男性のなかに、橋の上から司祭が十字架のイコンを投げ込み、それを拾ったものが幸運を保証されるというものだ。
川岸で視ていたペトルーニャは、衝撃的に川に飛び込み、その十字架のイコンを拾ってしまう。

問題はここに発する。実はこの行事、伝統的な不文律として女人禁制だったのである。そのイコンを離さない彼女に対し、家族も離反し警察へと連行され取り調べを受けることになる。映画の後半は、警察署が舞台となる。
しかし、彼女はある特定の宗教団体の私的なタブーを犯したのみで、刑法上の規定には何らの抵触もしていないし、社会的な意味でも周辺にどんな迷惑をも及ぼしてはいない。
ペトルーニャの拘束をTVの女性レポーターは懸命に伝えようとするが、一般市民も、TV局もまったく関心を示すことなく、レポーターと同行したカメラマンは局の命令に従って帰ってしまう。ただし、レポーターの要請に応じてカメラはおいてゆく。
一方、狂信的な裸の男達は警察署へと押しかけるが、窓ガラスを割ったりして建造物損壊で逮捕されたりもする。
そんななか、ペトルーニャへの恫喝や哀願を交えた説得が続くが彼女はそれに応じない。イコンは私がとった、私にも幸運が保証される権利がある、だから返さない・・・・と。

彼女の主張は、ジェンダー論などに裏打ちされたものではなく、その発端も衝動的であったし、その後の経過もただ頑なであるかのようにみえるのだが、そのみどころは、この警察署での経過のうちで、当初、怠惰でだらしなくみえた彼女の挙動や表情がどんどん引き締まり、美しくさえ視え始めるところだ。
こうした女性の変貌には既視感がある。
2014年、主演の安藤サクラの体当たり演技が話題になった『百円の恋』の主人公の変遷を思わせるものがあるのだ。

ペトルーニャの取り調べには、検事まで登場するのだが、いかなる法的権威をもっても彼女を拘束し続けることはできないだろう。そしてやがて、彼女は放たれるだろう。
そしてその折、彼女がとった行動は、どこか拍子抜けするような、でもどこかホッとするようなものであろう。
そして、私は期待するのだ。これを経過したペトルーニャは、これまでとは違った生を方を辿るかもしれないと。

カメラワークが面白い。会話などが画面中央で行われるのではなく、登場人物の頭しか映っていないところで行われたり、時折、登場人物がまったくのカメラ目線で登場し、「あんた、どう思うの?」と問われているような気になったりする。
監督はテオナ・ストゥルガー・ミテフスカという女性だが、この映画で初めて知った。

そのなかで、私がある意味、衝撃的に受け止めたのは人類そのものが終焉を迎えているのではないかということだった。
それらのうちには、BT=バイオテクノロジーによる生物としての「人」そのものの変革管理があったが、同時に、デジタル技術の最先端としての人工頭脳=AI の進化による人智そのものの凌駕とそれによる人間への支配の可能性であった。
こうしたAI による人類の追い越しと人類への管理はシンギュラリティ(=特異点)といわれ、早ければ2045年には起きるとされている。
その折、人間はAI の目指すところ(それ自身が何かはわからない)に有用な部分と、無用な部分(無用者階級)とに分断されるとする。

このSFのような推測はまんざら根拠がないわけではない。私たちはすでにして意識するとしないとに関わらず、デジタル監視社会に属しているのであって、これは視られるのみではなく、その監視の結果、それによりセレクトされた情報が与えられ、私たちの欲望そのものがコントロールされるに至っている。
たとえば、何かを検索すると、それに即した情報や商品などがどんどん紹介される仕組みはすでにして日常のものである。
私が今回読んだのは、彼の次なる書、『哲学と人類』なのだが、この書が、『哲学と人間』ではなく「人類」であるところにこの書のコンセプトがある。
というのは、この書が、人間が哲学をはじめた文字言語以降の、いわゆる「哲学史」を問題にしているのではなく、人類発生以来の「メディア」の変遷に注目しながら「人類」の行方を考察しているからである。

メディアというのはいわゆる「媒体」であり、「伝達手段」である。したがって、かつては、そうした手段はともかく、それによって伝えられるものこそが重要だと考えられていた。
それを覆したのがハーバート・マーシャル・マクルーハンであった。彼の思想を簡潔に表す言葉、それは「メディアはメッセージである」である。
彼は、メディア=媒体は、手段にとどまらず、それ自体が人間にとって有意味な何者かであると主張したのであった。
音声言語の時代、文字の時代、印刷技術によるその大衆化の時代、写真、録音、その集大成の映画などによる感覚的対象の再現の時代(ベンヤミンの『複製技術時代の芸術』。ベンヤミンは実はマクルーハンに先立ってメディアのもつ「手段」にとどまらない役割を論じていた)、そして、テレビによる映像氾濫の時代、これが二〇世紀前半までのメディアの歴史であった。

それぞれのメディアは、単に伝達手段の進化にとどまらず、それ固有の歴史的現象を生み出した。
文字は思想や芸術作品、歴史的事実の後世への伝達を可能にし、印刷術は情報の大衆化、とりわけ西欧では聖書の普及による宗教革命の推進を実現した。
その他のメディアの出現もそれ固有の状況を生み出してきた。例えば写真や録音、ラジオといったメディアは、文字に還元されていた情報をダイレクトに感覚に訴えて伝えることになったし、映画やテレビの動画は、状況の映像と同時に時間的経由をも共有させることとなった。
これにより促進されたのは、大衆社会そのものである。

それにも増して革命的なのは、20世紀後半に端を発するデジタル技術であった。あらゆる情報の0・1という数字への還元は、途方も無い情報の量とあらゆる分野を埋め尽くし、計算は愚か、それ自体の自己言及化的進化により、いまや人工頭脳=AI を産み出すに至った。
これが、2045年頃に想定されるシンギュラリティにより、人智を上回り、人類を支配下に置くか、あるいは人のありようを劇的に変えるであろうと考えられていることは初めの方で観たとおりだ。

この書は、それらが具体的に述べられているのだが、その時代、時代のメディアのあり方と、哲学そのものの相互関係が主要な哲学的動向、キーとなる哲学者やその思想とともに述べられている。
そこには、とても面白い考察もある。
周知のように、ソクラテスは自分の書というものは残さなかった。文字として固定化されることによる知の形骸化、それによって失われるものを恐れたからだといわれている。だから、ソクラテスの思想というものは、今日、その弟子のプラトンの書によって間接的に知られるのみである。
要するに、文字による知を否定したソクラテスの知を、プラトンは文字で表すのだからそれ自身が矛盾を孕んでいるが、ダイレクトな音声メディアが文字メディアへと変遷するその時点の推移をも反映している。
加えて面白いのは、そうした時期にあって、ソクラテスは「書かなかった」のではなく「書けなかった」、すなわち文字を使えなかったのではないかという推察も成り立つということだ。
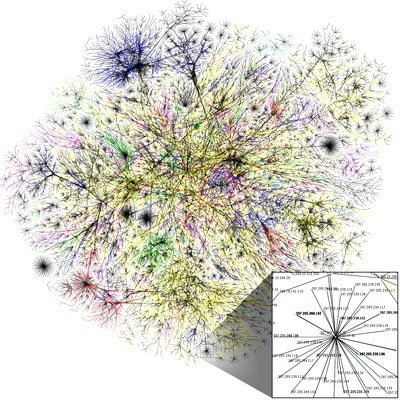
その他、主要な哲学者をメディアとの関連で論じていて面白い。
この書が、「哲学」と「人間」ではなく、『哲学と人類』であることがおわかりいただけたであろうか。
そして、そこには、「人類の終焉」というか、少なくとも人類はここ数千年の歴史とは異なる段階を迎えようとしている近未来が見通せるのである。
若い人たちはその辺のところを真剣に考えなければならないだろうと思うのだが、一方、80歳過ぎた私は、その頃にはとっくにオサラバしているのだが、生来のおせっかい癖で、「さあ、若い人たちよ、いったいどうするんだい?」と尋ねてみたいのだ。
この書は、あまり哲学の素養がなくとも読めるのではないだろうか。


















