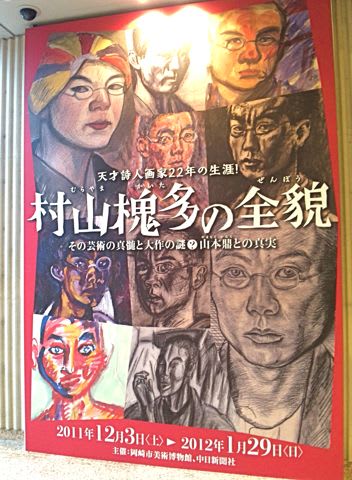*以下は私の友人のブログにコメントとしてつけたものですが、こちらへも転載させて頂きます。

ノーベル文学賞は中国の莫言氏に決まりましたね。
しかし、その略歴を読んで驚きました。なんということでしょう。このひとの原作で映画化されたものを全部観ているのです。「紅いコーリャン」、「至福のとき」はチャン・イーモウ。そして「故郷の香り」は「山の郵便配達」のフォ・ジェンチイ監督によるものでした。
この最後の作品には香川照之がスナフキンのようなアヒル使いの役で好演していました。
偶然といえば、昨日読んでいた水村美苗の「日本語が亡びるとき」という本の中に、アメリカのアイオワで開かれたIWPという文学学校のような催しに各国の作家が参加する話があり、そのメンバーのひとりでほとんど英語を話さない中国から来た「田舎のあんちゃん」(水村)が実はカンヌで特別賞をとった「活きる」(監督はチャン・イーモウ)の原作者と知って驚くシーンがあるのですが、それを読んだあとで上の事実を知って私も驚いたわけです。
もちろん、この「活きる」も観ています。
いずれも、チャン・イーモウらがハリウッド資本に絡め取られる前の中国映画の良き時代の作品ですね。

ノーベル文学賞は中国の莫言氏に決まりましたね。
しかし、その略歴を読んで驚きました。なんということでしょう。このひとの原作で映画化されたものを全部観ているのです。「紅いコーリャン」、「至福のとき」はチャン・イーモウ。そして「故郷の香り」は「山の郵便配達」のフォ・ジェンチイ監督によるものでした。
この最後の作品には香川照之がスナフキンのようなアヒル使いの役で好演していました。
偶然といえば、昨日読んでいた水村美苗の「日本語が亡びるとき」という本の中に、アメリカのアイオワで開かれたIWPという文学学校のような催しに各国の作家が参加する話があり、そのメンバーのひとりでほとんど英語を話さない中国から来た「田舎のあんちゃん」(水村)が実はカンヌで特別賞をとった「活きる」(監督はチャン・イーモウ)の原作者と知って驚くシーンがあるのですが、それを読んだあとで上の事実を知って私も驚いたわけです。
もちろん、この「活きる」も観ています。
いずれも、チャン・イーモウらがハリウッド資本に絡め取られる前の中国映画の良き時代の作品ですね。