知人から「義姫」というタイトルのDVDをいただきました。それで、約10年ほど以前に当ブログで連載していたタイトルのシリーズをまとめて再投稿します。最後までご覧ください。

◆伊達政宗は強し、されど母も強し◆
手前には建設機械、上部には送電線、右手には鉄塔も見えるなど、全体として決して麗しい景観だとは言えないが、部分的にトリミングすれば、鎮守の森が見えるなど麗しい農村景観となろう。[須川沿岸の山形市西公園見晴らし塔より]
後方には丘陵が連なっているが、建設機械と鉄塔のすぐの前方の集落があるあたりは概して平地であると申すべきであろう。
その集落こそ天下人の秀吉や家康にまで怖れられた奥羽の暴れん坊で戦国末期の武将の中でも一際強烈な個性を天下に知らしめた伊達政宗の母が隠れ住んだと伝えられている村である。
否、隠れ住んだというよりは、兄の最上義光の命により「押し込められた」里と申すべきなのかもしれない。
その集落は悪戸と称する山形市村木沢地区の一小字であるが、山形盆地の真ん中の低地を南北に流れる須川の川縁に位置し、須川西部の他の集落からは多少の距離がある「離れ里」でもある。
しかし、慶長五年(1600)この里にも大きな戦火が迫っていた。 続く

何の変哲もない盆地の集落だが、その集落に迷い込むと何とはなしに一瞬タイムスリップしたような感じがするから不思議だ。
なんと、その集落は伊達政宗の母にして最上義光の妹の義姫が政宗のもとを離れて長年住まい続けたと伝えられている集落であるためか、歴史ある地域としての風格を感じてしまうからかもしれない。
集落の真ん中に至るとかなり広い農地が開けているのも意外である。
この土蔵のある屋敷のごく近くに義姫は住んでいたようである。
なぜ彼女が山形城内や城のすぐ近くの城下町ではなく、城からかなり隔絶した離れ里のような所に住まわせられたのかはよくわからない。

この道はいつか来た道。
義姫がよみがえってこの道を歩けば、きっとそう感じるに違いない。
むろん、彼女がこの地に住んでいた時代は屋根が赤いペンキで塗られていたはずはないし、こんな豪壮な土蔵が建つほど土地の者が豊かであったわけはない。
だが、この地で彼女の警護の責任を担っていた山形城主最上義光の家臣加藤掃部左衛門はむろん武士で、その後代々この集落の名主をつとめた家系の祖であり、彼の分家がこの集落を中心に散在している。
直江兼続率いる2万の上杉軍が山形盆地になだれ込んで、この集落のすぐ近くが戦場になったがために掃部左衛門は戦死している。
上杉軍の山形盆地侵入の報を聞いた掃部左衛門は当然すぐに義姫をこの地から出して山形城に逃れさせたはずである。
兄の義光は伊達家の仙台城から少しでも遠いこの地に妹を住まわせたものの、まさかこの地が戦場のすぐそばになるとは思いもよらなかったであろう。
だが、この地が上杉兵に荒らされたことはなかったようである。

政宗の母である義姫が政宗のもとを離れて山形に出奔した時期は彼女が政宗の毒殺計画に失敗し、かつ彼女が溺愛していたとされる次男の小次郎が政宗により惨殺された直後(1590)と考えられていたが(仙台藩の正史である「貞山公治家記録」に記述)、その当時は政宗の居城が会津黒川城(後の会津若松城)と米沢城の二つであったが、平成になって発見された史料(※注)によると4年後の文禄3年であったことが記述され、これが現在では彼女が山形に出奔した年代を知る有力な史料とされている。[※注:政宗の幼少からの学問の師、虎哉禅師の手紙]
つまりこの文禄3年における政宗の居城は岩出山城であり、彼女が政宗の居城から出奔したのは会津黒川城からでもなければ米沢城でもなく、岩出山城からということになる。
それではどうして彼女(義姫)が岩出山から出奔したのであろうか。
義姫が岩出山まで政宗と一緒だったということは政宗毒殺未遂事件の史実性を疑わせることにもなる。政宗のもとから身を隠すには事件の直後しか考えられないから、4年も後となると、毒殺未遂事件とは別の理由を推察するしかなくなる。続く
◆写真は義姫が住んだ悪戸集落内を流れる小河川 現在この集落にはかなりの数の豪壮な土蔵や母屋を構える旧家が多く目にとまり、歴史の里であることがうかがえる

政宗毒殺未遂事件を史実とした場合、その事件の直後に義姫が会津黒川(現在の会津若松)から実家の兄最上義光のもとに逃れ、南館を経てここに匿われたという話は納得しやすい。
だが、新資料の発見により実際に政宗のもとから出奔して山形にやってきたのはその数年後、政宗の新居城の岩出山からであるとの説が現在有力になっているものの、彼女の山形への出奔の動機が何であるのかは不明としか言いようがない。
その推測はまたもや次回以降で行うこととして、今回は彼女が山形の地で落ち着いた悪戸の里で今なお優美にたたずむ小さな「鎮守社」を紹介したい。
この神社は「白山権現」と称するが、これまた彼女を匿って護った加藤掃部左衛門が大きく関わった伝承が残されている。

義姫が政宗毒殺未遂事件と小次郎惨殺の直後に政宗のもとから山形に向けて出奔したのではなく、その約4年後に岩出山から出奔したとする説が有力になっていることは既に述べた。
その彼女の子である伊達政宗の居城は米沢から会津黒川(若松)へ移ったかと思えば、程なくして再び米沢へ戻ったが、それもほんの束の間で、ほとんど秀吉により強制的に岩出山に移転を余儀なくされた。
それは天正19年(1591)の8月であったが、落ち着く間もなく、翌年の1月には京都に向かい、3月には文禄の役(朝鮮出兵)のために肥前名護屋に出陣し、さらにその翌年の文禄2年(1593)には渡海して朝鮮で戦っている。その年のうちに帰国してはいるが、翌年は京都に滞在し、岩出山に帰ったのは文禄4年の夏のことで、それもほんの束の間で、8月にはまた上洛した(関白秀次追放事件の関係)。
だから、母である義姫(お東の方)も政宗の居城の移転に伴い岩出山に転居したわけであるが、頼りにしていた政宗は岩出山をほとんど留守にしており、しかも慣れない土地での居住に途惑うことが多かったのではないか。
一方、同じ頃、実家である山形の最上家においても兄の義光は政宗同様に京都や肥前名護屋に出掛けておったが、義光夫妻が留守の最上家では「一大事」が迫っており、岩出山の義姫は城主夫妻が長期に留守の山形のことが気がかりでならなかったに違いない。

政宗の母である義姫(お東の方)が政宗が朝鮮出陣などで長期に留守の岩出山城から出奔して山形までやってきた動機はいったい何であったのであろうか。
むろん、息子の政宗の不在ゆえに生じる伊達家や城内での人間関係や岩出山という慣れない土地での居心地の悪さがあったとしても不思議ではない。
兄の最上義光も夫人ともども山形を留守にして京都に滞在していたばかりでなく、朝鮮出陣を控えて肥前名護屋まで出かけていたのである。
それでは山形での「一大事」とは何なのか。
むろん、城主である義光夫妻が留守であること自体も「一大事」である。
兄の義光が留守の間に山形では何が起きるかわかったものでない。
さらにそれに加えてもう一つ最上家にとっての「一大事」が控えていたのである。
おそらくは実家思いの義姫はそれらの「一大事」のことが気にかかって仕方がなかったから山形までかけつけたのであろう。
山形では義光の愛娘で義姫の可愛い姪である駒姫が関白豊臣秀次への輿入れを目前にしていた頃である。
義光夫妻が留守の間に駒姫の「嫁入り仕度」などの婚礼の準備をしっかりとしておくには叔母である自分が出向く必要があると考えていたに違いない。
また、豊臣家に嫁ぐための心得なども伝えておきたかったのかもしれない。
しかし、その後、義光が山形に、また政宗が岩出山に帰ってからも義姫が政宗のもとに帰らずに山形にとどまり、郊外の寒村に住まわせられるようになったのも謎と言うべきであろう。
※写真は義姫が厚い信仰を捧げた阿弥陀堂(山形城郊外 村木沢悪戸)

政宗の母義姫は岩出山から離れて(以前は会津黒川もしくは米沢からと伝えられていた)ここ村木沢の地に守護役の者のもとに長年住まい続けたわけだが、阿弥陀仏に帰依する念仏三昧の信仰の毎日だったと伝えられている。
彼女は山形に戻ったものの、兄の居る山形城内にではなく、当初は南館に住んでいたが、やがてここ村木沢悪戸に移っている。
彼女が信仰する阿弥陀仏像も彼女とともに移ったようである。
つまり彼女の信仰は阿弥陀仏を崇拝する念仏宗系の信仰だから、浄土宗、時宗、浄土真宗のいずれかのはずだが、彼女の墓のある仙台市内北山の覚範寺もまた位牌がある若林区の保春院(彼女の法名と同一)もともに臨済宗の禅寺である。
禅宗系の寺院では阿弥陀仏が信仰されることはほとんどないから、息子の政宗は母の信仰を尊重した上で死後の供養を行ったわけではないことがわかる。

伊達政宗の母が政宗の居城から出奔して郷里の山形に住むようになった動機はむろん、晩年の前年になってようやく仙台の政宗の膝元に呼び寄せられるまで、かくも長年山形に滞在した理由も不明であるが、やはり興味深いところであり、今後の研究に期待するところ大である。
母である義姫が山形への出奔以来子の政宗との関係がまったく疎遠であったかと言えば決してそうではなく、親子としての情愛あふれる手紙の遣り取りがあったことはよく知られているし、とりわけ直江兼続の大軍が山形盆地に押し寄せてきた時、彼女は政宗に対して援軍を大至急差し向けるよう激越な懇願状を送り、政宗もそれに応えて援軍を派遣している。その援軍はさほどの人数ではなかったが、山形勢の士気を大いに高めことは確かである。
むろん、長谷堂合戦の際は彼女は戦火を避けて山形城に避難しているが、戦後はたぶんここ悪戸に戻り、阿弥陀像に祈るなどのひっそりとした生活をおくっていたように思える。
彼女が岩出山城から出奔したのは文禄3年(1594)で45歳か46歳の時であり、仙台の政宗のもとに戻ったのが元和8年(1622)で74歳か75歳の時であった。
この間はなんと28年もの長い年月であるが、たぶんやはり一度も岩出山や仙台に戻ったことはなかったと考えるのが妥当であろう。
実際にここ悪戸の里に彼女が住んだ年月が延べで20年以上だとすれば、それこそ立派な史跡と呼ぶべきであろう。 終わり。
※写真は西側から望む悪戸集落 集落の背後には蔵王連山や奥羽の山並みが望まれる。 この山並みは山形城や城下に住む場合よりも眺望が効き、政宗が住む仙台領に想いをはせるには格好の地であった。当時、彼女が日参した阿弥陀堂も集落からやや離れた農地にあり、参詣を兼ねて仙台領を偲んでいたことであろう。

◆伊達政宗は強し、されど母も強し◆
手前には建設機械、上部には送電線、右手には鉄塔も見えるなど、全体として決して麗しい景観だとは言えないが、部分的にトリミングすれば、鎮守の森が見えるなど麗しい農村景観となろう。[須川沿岸の山形市西公園見晴らし塔より]
後方には丘陵が連なっているが、建設機械と鉄塔のすぐの前方の集落があるあたりは概して平地であると申すべきであろう。
その集落こそ天下人の秀吉や家康にまで怖れられた奥羽の暴れん坊で戦国末期の武将の中でも一際強烈な個性を天下に知らしめた伊達政宗の母が隠れ住んだと伝えられている村である。
否、隠れ住んだというよりは、兄の最上義光の命により「押し込められた」里と申すべきなのかもしれない。
その集落は悪戸と称する山形市村木沢地区の一小字であるが、山形盆地の真ん中の低地を南北に流れる須川の川縁に位置し、須川西部の他の集落からは多少の距離がある「離れ里」でもある。
しかし、慶長五年(1600)この里にも大きな戦火が迫っていた。 続く

何の変哲もない盆地の集落だが、その集落に迷い込むと何とはなしに一瞬タイムスリップしたような感じがするから不思議だ。
なんと、その集落は伊達政宗の母にして最上義光の妹の義姫が政宗のもとを離れて長年住まい続けたと伝えられている集落であるためか、歴史ある地域としての風格を感じてしまうからかもしれない。
集落の真ん中に至るとかなり広い農地が開けているのも意外である。
この土蔵のある屋敷のごく近くに義姫は住んでいたようである。
なぜ彼女が山形城内や城のすぐ近くの城下町ではなく、城からかなり隔絶した離れ里のような所に住まわせられたのかはよくわからない。

この道はいつか来た道。
義姫がよみがえってこの道を歩けば、きっとそう感じるに違いない。
むろん、彼女がこの地に住んでいた時代は屋根が赤いペンキで塗られていたはずはないし、こんな豪壮な土蔵が建つほど土地の者が豊かであったわけはない。
だが、この地で彼女の警護の責任を担っていた山形城主最上義光の家臣加藤掃部左衛門はむろん武士で、その後代々この集落の名主をつとめた家系の祖であり、彼の分家がこの集落を中心に散在している。
直江兼続率いる2万の上杉軍が山形盆地になだれ込んで、この集落のすぐ近くが戦場になったがために掃部左衛門は戦死している。
上杉軍の山形盆地侵入の報を聞いた掃部左衛門は当然すぐに義姫をこの地から出して山形城に逃れさせたはずである。
兄の義光は伊達家の仙台城から少しでも遠いこの地に妹を住まわせたものの、まさかこの地が戦場のすぐそばになるとは思いもよらなかったであろう。
だが、この地が上杉兵に荒らされたことはなかったようである。

政宗の母である義姫が政宗のもとを離れて山形に出奔した時期は彼女が政宗の毒殺計画に失敗し、かつ彼女が溺愛していたとされる次男の小次郎が政宗により惨殺された直後(1590)と考えられていたが(仙台藩の正史である「貞山公治家記録」に記述)、その当時は政宗の居城が会津黒川城(後の会津若松城)と米沢城の二つであったが、平成になって発見された史料(※注)によると4年後の文禄3年であったことが記述され、これが現在では彼女が山形に出奔した年代を知る有力な史料とされている。[※注:政宗の幼少からの学問の師、虎哉禅師の手紙]
つまりこの文禄3年における政宗の居城は岩出山城であり、彼女が政宗の居城から出奔したのは会津黒川城からでもなければ米沢城でもなく、岩出山城からということになる。
それではどうして彼女(義姫)が岩出山から出奔したのであろうか。
義姫が岩出山まで政宗と一緒だったということは政宗毒殺未遂事件の史実性を疑わせることにもなる。政宗のもとから身を隠すには事件の直後しか考えられないから、4年も後となると、毒殺未遂事件とは別の理由を推察するしかなくなる。続く
◆写真は義姫が住んだ悪戸集落内を流れる小河川 現在この集落にはかなりの数の豪壮な土蔵や母屋を構える旧家が多く目にとまり、歴史の里であることがうかがえる

政宗毒殺未遂事件を史実とした場合、その事件の直後に義姫が会津黒川(現在の会津若松)から実家の兄最上義光のもとに逃れ、南館を経てここに匿われたという話は納得しやすい。
だが、新資料の発見により実際に政宗のもとから出奔して山形にやってきたのはその数年後、政宗の新居城の岩出山からであるとの説が現在有力になっているものの、彼女の山形への出奔の動機が何であるのかは不明としか言いようがない。
その推測はまたもや次回以降で行うこととして、今回は彼女が山形の地で落ち着いた悪戸の里で今なお優美にたたずむ小さな「鎮守社」を紹介したい。
この神社は「白山権現」と称するが、これまた彼女を匿って護った加藤掃部左衛門が大きく関わった伝承が残されている。

義姫が政宗毒殺未遂事件と小次郎惨殺の直後に政宗のもとから山形に向けて出奔したのではなく、その約4年後に岩出山から出奔したとする説が有力になっていることは既に述べた。
その彼女の子である伊達政宗の居城は米沢から会津黒川(若松)へ移ったかと思えば、程なくして再び米沢へ戻ったが、それもほんの束の間で、ほとんど秀吉により強制的に岩出山に移転を余儀なくされた。
それは天正19年(1591)の8月であったが、落ち着く間もなく、翌年の1月には京都に向かい、3月には文禄の役(朝鮮出兵)のために肥前名護屋に出陣し、さらにその翌年の文禄2年(1593)には渡海して朝鮮で戦っている。その年のうちに帰国してはいるが、翌年は京都に滞在し、岩出山に帰ったのは文禄4年の夏のことで、それもほんの束の間で、8月にはまた上洛した(関白秀次追放事件の関係)。
だから、母である義姫(お東の方)も政宗の居城の移転に伴い岩出山に転居したわけであるが、頼りにしていた政宗は岩出山をほとんど留守にしており、しかも慣れない土地での居住に途惑うことが多かったのではないか。
一方、同じ頃、実家である山形の最上家においても兄の義光は政宗同様に京都や肥前名護屋に出掛けておったが、義光夫妻が留守の最上家では「一大事」が迫っており、岩出山の義姫は城主夫妻が長期に留守の山形のことが気がかりでならなかったに違いない。

政宗の母である義姫(お東の方)が政宗が朝鮮出陣などで長期に留守の岩出山城から出奔して山形までやってきた動機はいったい何であったのであろうか。
むろん、息子の政宗の不在ゆえに生じる伊達家や城内での人間関係や岩出山という慣れない土地での居心地の悪さがあったとしても不思議ではない。
兄の最上義光も夫人ともども山形を留守にして京都に滞在していたばかりでなく、朝鮮出陣を控えて肥前名護屋まで出かけていたのである。
それでは山形での「一大事」とは何なのか。
むろん、城主である義光夫妻が留守であること自体も「一大事」である。
兄の義光が留守の間に山形では何が起きるかわかったものでない。
さらにそれに加えてもう一つ最上家にとっての「一大事」が控えていたのである。
おそらくは実家思いの義姫はそれらの「一大事」のことが気にかかって仕方がなかったから山形までかけつけたのであろう。
山形では義光の愛娘で義姫の可愛い姪である駒姫が関白豊臣秀次への輿入れを目前にしていた頃である。
義光夫妻が留守の間に駒姫の「嫁入り仕度」などの婚礼の準備をしっかりとしておくには叔母である自分が出向く必要があると考えていたに違いない。
また、豊臣家に嫁ぐための心得なども伝えておきたかったのかもしれない。
しかし、その後、義光が山形に、また政宗が岩出山に帰ってからも義姫が政宗のもとに帰らずに山形にとどまり、郊外の寒村に住まわせられるようになったのも謎と言うべきであろう。
※写真は義姫が厚い信仰を捧げた阿弥陀堂(山形城郊外 村木沢悪戸)

政宗の母義姫は岩出山から離れて(以前は会津黒川もしくは米沢からと伝えられていた)ここ村木沢の地に守護役の者のもとに長年住まい続けたわけだが、阿弥陀仏に帰依する念仏三昧の信仰の毎日だったと伝えられている。
彼女は山形に戻ったものの、兄の居る山形城内にではなく、当初は南館に住んでいたが、やがてここ村木沢悪戸に移っている。
彼女が信仰する阿弥陀仏像も彼女とともに移ったようである。
つまり彼女の信仰は阿弥陀仏を崇拝する念仏宗系の信仰だから、浄土宗、時宗、浄土真宗のいずれかのはずだが、彼女の墓のある仙台市内北山の覚範寺もまた位牌がある若林区の保春院(彼女の法名と同一)もともに臨済宗の禅寺である。
禅宗系の寺院では阿弥陀仏が信仰されることはほとんどないから、息子の政宗は母の信仰を尊重した上で死後の供養を行ったわけではないことがわかる。

伊達政宗の母が政宗の居城から出奔して郷里の山形に住むようになった動機はむろん、晩年の前年になってようやく仙台の政宗の膝元に呼び寄せられるまで、かくも長年山形に滞在した理由も不明であるが、やはり興味深いところであり、今後の研究に期待するところ大である。
母である義姫が山形への出奔以来子の政宗との関係がまったく疎遠であったかと言えば決してそうではなく、親子としての情愛あふれる手紙の遣り取りがあったことはよく知られているし、とりわけ直江兼続の大軍が山形盆地に押し寄せてきた時、彼女は政宗に対して援軍を大至急差し向けるよう激越な懇願状を送り、政宗もそれに応えて援軍を派遣している。その援軍はさほどの人数ではなかったが、山形勢の士気を大いに高めことは確かである。
むろん、長谷堂合戦の際は彼女は戦火を避けて山形城に避難しているが、戦後はたぶんここ悪戸に戻り、阿弥陀像に祈るなどのひっそりとした生活をおくっていたように思える。
彼女が岩出山城から出奔したのは文禄3年(1594)で45歳か46歳の時であり、仙台の政宗のもとに戻ったのが元和8年(1622)で74歳か75歳の時であった。
この間はなんと28年もの長い年月であるが、たぶんやはり一度も岩出山や仙台に戻ったことはなかったと考えるのが妥当であろう。
実際にここ悪戸の里に彼女が住んだ年月が延べで20年以上だとすれば、それこそ立派な史跡と呼ぶべきであろう。 終わり。
※写真は西側から望む悪戸集落 集落の背後には蔵王連山や奥羽の山並みが望まれる。 この山並みは山形城や城下に住む場合よりも眺望が効き、政宗が住む仙台領に想いをはせるには格好の地であった。当時、彼女が日参した阿弥陀堂も集落からやや離れた農地にあり、参詣を兼ねて仙台領を偲んでいたことであろう。










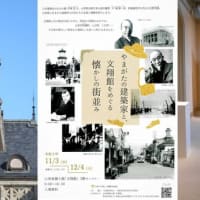


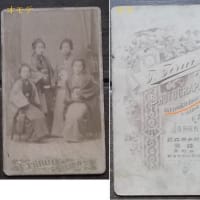












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます