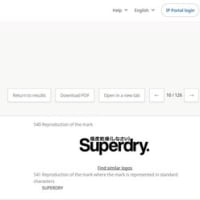一応、専門家らしいブログも書いてみます。
ここ数日、商標について知財構成で重要な判決が連続で出ているので、
ちょっとコメント。
今日は「喜多方ラーメン」。
【事案の概要】
「協同組合蔵のまち喜多方老麺会」が商標「喜多方ラーメン」(標準文字)を
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」を指定役務として出願するも、
拒絶査定⇒拒絶審決。んで審決取消訴訟。原告敗訴。
【判決より一部抜粋】
===============================================
<原告の主張>
地域団体商標(7条の2)の制度は地域振興等を目的として創設されたもので,
3条2項の登録要件を緩和したものであるから,7条の2第1項にいう
「使用をされた結果自己又はその構成員に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識された」
は,需要者において,当該商標が使用された商品ないし役務が,誰の業務に係るものか
全く判然としないものではないという意味で,一定の団体又はその構成員の業務に係る
ものであることが広く認識されていれば足り,当該商標から生産・提供される地域(産地)
の識別ができる程度であれば十分であって,特定の者である出願人又はその構成員の業務
に係る商品ないし役務に係るものであることまで広く認識されている必要はない。
<裁判所の判断>
7条の2が定める地域団体商標の制度が設けられたのは,その立法経緯にかんがみると,
地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り,地域ブランドの保護による
我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として,いわゆる「地域ブランド」
として用いられることが多い地域の名称及び商品ないし役務の名称等からなる文字商標
について,登録要件を緩和する趣旨に出たものである。
すなわち,上記のとおり地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標については,
従前,3条1項各号に該当するとして,使用による識別力を獲得し,3条2項の要件を
満たさない限り登録が認められず,全国的に相当程度知られるようになるまでは他人の
便乗使用を排除できず,また図形入りの商標の登録を受けるのみでは他人による文字部分の
便乗使用を有効に排除できないという不都合等があったのを,これらの不都合を解消して
上記のとおりの地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標の登録を許容して,
地域の産品等についての事業者の信用の維持等を実現する趣旨のものである。
そして,1項柱書で,当該
「商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品
又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」ことが要求されて
いるのは,上記のとおり地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標である
地域団体商標の登録をすると,構成員でない第三者による自由な商標(表示,名称)
の使用が制限されることになるので,かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで,
出願人たる団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためであり,
あるいは構成員でない第三者による便乗使用のおそれが生じ得る程度に,出願人たる
団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためである
と解することができる。
(中略)
なるほど,3条2項で同条1項各号で登録できないとされている商標が,使用に
より登録が認められるとしても,「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認
識することができるもの」との要件,すなわち識別力を発揮できるまでの程度の要
件を充たさなければならないのに対し,7条の2第1項柱書では,使用により「自
己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広
く認識されている」との要件を充たすことを要件としており,前記の地域団体商標
の立法経緯を踏まえてみると,後者の要件は前者の要件を緩やかにしたものと解す
るのが相当ということになる。
しかし,この要件緩和は,識別力の程度(需要者の広がりないし範囲と,質的な
ものすなわち認知度)についてのものであり,当然のことながら,構成員の業務と
の結び付きでも足りるとした点において3条2項よりも登録が認められる範囲が広
くなったのは別としても,後者の登録要件について,需要者(及び取引者)からの
当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係る商品ないし役務との結び付きの
認識の要件まで緩和したものではない。
この登録要件は法律の解釈上導かれるものであり,立法経過や立法趣旨にも反するものではない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(判決引用終わり)
==================================================
恥ずかしながら、疑問点が2つ。
(1)そもそも3条2項において、
「需要者(及び取引者)からの当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係る
商品ないし役務との結び付きの認識の要件」
って、要求されてたっけ??
条文上は、
「…使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」
とあるのみで、ここでいう「何人か」は特定の出所(=典型的にはメーカー)を具体的に想起する「結びつき」ではなく、仮に具体的な企業名等は想起できなくとも、出所としての同一性を認識しうる抽象的な「結びつき」で足りるものだと理解していたが(実際そのような立証で登録に至った例もある)…。
(2)誰の「信用」?
「かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで~」のくだりについて。
確かに、要件緩和してまでも保護するためには、それ相応の理由(これが代替的な要件に繋がって行く)
は必要であることは理解できる。
しかし、それは「商標に化体した信用保護の枠組み」として必要なのであって、
その信用の客体(具体的な“誰”に対する信用なのか)の特定は不要なはず。
このあたり、同様の趣旨説明は青本の1208~1209ページに記載がある。
青本では
「~保護すべきであるといえる程度に当該商標に信用が蓄積されていること」
との表現にとどまり、「“出願人たる団体の”信用」などとは説明されていない。
冷静に考えて、
需要者(消費者)が商標に信用を化体「させていく」過程において、
その客体(つまり「誰」に対する信用か)をはっきりと意識して化体させていくことは、
むしろ稀だと思われる。
青本の上記記載は、そのあたりを踏まえての説明と理解しているし、小職も同意見である。
つまり、商標に化体している「信用」は、誰のものでもなく、
あえて言えば、それは化体させた需要者のものだ。
単なる品質表示ではなく、誰だかは知らないが特定の誰かが製造した商品(あるいは提供した役務)であると
認識させる標識、として機能している限り、それは保護対象になりうるのではないか?と思う。
この点で、今般の判決には大いに違和感を感じる。
一般的に、どこの団体、地方においてもいわゆる「アウトサイダー」は存在するし、
その状況が“好ましくない”というわけでもない。
法上、32条の2で先使用を認めていることもその表れと理解することが可能だ。
組合加入の是非は、地域ブランドの振興の仕方に対する各事業者の捉え方に依存するところだし、
全ての事業者に“全体主義”的に組合加入を促すことは自然ではない。
にもかかわらず、このような解釈をおこなっている限り、
権利化のためにいたずらに組合加入を促す結果となり、
各事業者が個々に行う「地域おこし」を全面否定することにもつながりかねない。
導入来、必ずしも問題なしとはしなかった「地域団体商標制度」だが、
ここへきてその扱いにくさが浮き彫りになった印象。
なんにしろ、本判決においては「信用」の解釈につき大いに疑問。
ここ数日、商標について知財構成で重要な判決が連続で出ているので、
ちょっとコメント。
今日は「喜多方ラーメン」。
【事案の概要】
「協同組合蔵のまち喜多方老麺会」が商標「喜多方ラーメン」(標準文字)を
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」を指定役務として出願するも、
拒絶査定⇒拒絶審決。んで審決取消訴訟。原告敗訴。
【判決より一部抜粋】
===============================================
<原告の主張>
地域団体商標(7条の2)の制度は地域振興等を目的として創設されたもので,
3条2項の登録要件を緩和したものであるから,7条の2第1項にいう
「使用をされた結果自己又はその構成員に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識された」
は,需要者において,当該商標が使用された商品ないし役務が,誰の業務に係るものか
全く判然としないものではないという意味で,一定の団体又はその構成員の業務に係る
ものであることが広く認識されていれば足り,当該商標から生産・提供される地域(産地)
の識別ができる程度であれば十分であって,特定の者である出願人又はその構成員の業務
に係る商品ないし役務に係るものであることまで広く認識されている必要はない。
<裁判所の判断>
7条の2が定める地域団体商標の制度が設けられたのは,その立法経緯にかんがみると,
地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り,地域ブランドの保護による
我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として,いわゆる「地域ブランド」
として用いられることが多い地域の名称及び商品ないし役務の名称等からなる文字商標
について,登録要件を緩和する趣旨に出たものである。
すなわち,上記のとおり地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標については,
従前,3条1項各号に該当するとして,使用による識別力を獲得し,3条2項の要件を
満たさない限り登録が認められず,全国的に相当程度知られるようになるまでは他人の
便乗使用を排除できず,また図形入りの商標の登録を受けるのみでは他人による文字部分の
便乗使用を有効に排除できないという不都合等があったのを,これらの不都合を解消して
上記のとおりの地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標の登録を許容して,
地域の産品等についての事業者の信用の維持等を実現する趣旨のものである。
そして,1項柱書で,当該
「商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品
又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」ことが要求されて
いるのは,上記のとおり地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標である
地域団体商標の登録をすると,構成員でない第三者による自由な商標(表示,名称)
の使用が制限されることになるので,かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで,
出願人たる団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためであり,
あるいは構成員でない第三者による便乗使用のおそれが生じ得る程度に,出願人たる
団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためである
と解することができる。
(中略)
なるほど,3条2項で同条1項各号で登録できないとされている商標が,使用に
より登録が認められるとしても,「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認
識することができるもの」との要件,すなわち識別力を発揮できるまでの程度の要
件を充たさなければならないのに対し,7条の2第1項柱書では,使用により「自
己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広
く認識されている」との要件を充たすことを要件としており,前記の地域団体商標
の立法経緯を踏まえてみると,後者の要件は前者の要件を緩やかにしたものと解す
るのが相当ということになる。
しかし,この要件緩和は,識別力の程度(需要者の広がりないし範囲と,質的な
ものすなわち認知度)についてのものであり,当然のことながら,構成員の業務と
の結び付きでも足りるとした点において3条2項よりも登録が認められる範囲が広
くなったのは別としても,後者の登録要件について,需要者(及び取引者)からの
当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係る商品ないし役務との結び付きの
認識の要件まで緩和したものではない。
この登録要件は法律の解釈上導かれるものであり,立法経過や立法趣旨にも反するものではない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(判決引用終わり)
==================================================
恥ずかしながら、疑問点が2つ。
(1)そもそも3条2項において、
「需要者(及び取引者)からの当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係る
商品ないし役務との結び付きの認識の要件」
って、要求されてたっけ??
条文上は、
「…使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」
とあるのみで、ここでいう「何人か」は特定の出所(=典型的にはメーカー)を具体的に想起する「結びつき」ではなく、仮に具体的な企業名等は想起できなくとも、出所としての同一性を認識しうる抽象的な「結びつき」で足りるものだと理解していたが(実際そのような立証で登録に至った例もある)…。
(2)誰の「信用」?
「かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで~」のくだりについて。
確かに、要件緩和してまでも保護するためには、それ相応の理由(これが代替的な要件に繋がって行く)
は必要であることは理解できる。
しかし、それは「商標に化体した信用保護の枠組み」として必要なのであって、
その信用の客体(具体的な“誰”に対する信用なのか)の特定は不要なはず。
このあたり、同様の趣旨説明は青本の1208~1209ページに記載がある。
青本では
「~保護すべきであるといえる程度に当該商標に信用が蓄積されていること」
との表現にとどまり、「“出願人たる団体の”信用」などとは説明されていない。
冷静に考えて、
需要者(消費者)が商標に信用を化体「させていく」過程において、
その客体(つまり「誰」に対する信用か)をはっきりと意識して化体させていくことは、
むしろ稀だと思われる。
青本の上記記載は、そのあたりを踏まえての説明と理解しているし、小職も同意見である。
つまり、商標に化体している「信用」は、誰のものでもなく、
あえて言えば、それは化体させた需要者のものだ。
単なる品質表示ではなく、誰だかは知らないが特定の誰かが製造した商品(あるいは提供した役務)であると
認識させる標識、として機能している限り、それは保護対象になりうるのではないか?と思う。
この点で、今般の判決には大いに違和感を感じる。
一般的に、どこの団体、地方においてもいわゆる「アウトサイダー」は存在するし、
その状況が“好ましくない”というわけでもない。
法上、32条の2で先使用を認めていることもその表れと理解することが可能だ。
組合加入の是非は、地域ブランドの振興の仕方に対する各事業者の捉え方に依存するところだし、
全ての事業者に“全体主義”的に組合加入を促すことは自然ではない。
にもかかわらず、このような解釈をおこなっている限り、
権利化のためにいたずらに組合加入を促す結果となり、
各事業者が個々に行う「地域おこし」を全面否定することにもつながりかねない。
導入来、必ずしも問題なしとはしなかった「地域団体商標制度」だが、
ここへきてその扱いにくさが浮き彫りになった印象。
なんにしろ、本判決においては「信用」の解釈につき大いに疑問。