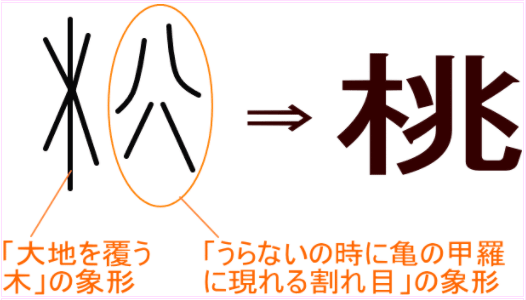高齢者の方で車を運転している皆さん、車に「高齢者マーク」をつけていますか?
私は以前、免許証の更新の時、自動車教習所の方から、70歳以上になったら「高齢者マーク」をつけるように言われた記憶がありますが、後期高齢者になって久しい現在もまだつけていません。
近所の70歳以上の人でも、つけていない人を多く見かけます。
「高齢者マーク」をつけるのは義務なのでしょうか?
また、つけないと違反になり、罰則があるのでしょうか?
今日は「高齢者マーク」について調べました。
「高齢者マーク」
高齢者マークとは、正式名称を「高齢運転者標識」と言い、「もみじマーク」と「四つ葉マーク」の2種類があります。
現在では70歳以上のドライバーが車を運転する場合はいかなるときも、高齢者マークを車に貼りつけて走行することが求められています。
高齢者マークは1997年(平成9年)、75歳以上のドライバーを対象に、道路交通法の改正によって導入されたものですが、2002年(平成14年)に対象が70歳以上のドライバーに引き下げられました。
そして現在に至るまで70歳以上の高齢者が車を運転する場合は、車に高齢者マークを貼りつけることを推奨しています。
ただし、すべての70歳以上のドライバーに高齢者マークを付けることが求められているわけではありません。
・「70歳以上75歳未満」(道路交通法第七十一条の五 第3項)
70歳以上75歳未満の場合は「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」のみに高齢者マークを付けることが求められています。
・「75歳以上」(道路交通法第七十一条の五 第4項)
そして75歳以上の高齢者が車を運転する際は、「普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない」とし、高齢者マークを付けることを義務化しています。
「当面は努力義務」
但し、2009(平成21年)年4月の道路交通法改正により「75歳以上の高齢者ドライバーの義務を定めた道路交通法第七十一条の五 第2項」と「70歳以上75歳未満の努力義務を定めた道路交通法第七十一条の五 第3項」は当分の間適用しないこととなり、「高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置」として、
・75歳以上の高齢者マークの義務化は当分適用せず努力義務となり、
・加齢により体の機能が低下し、車の運転に影響を及ぼす恐れのある70歳以上のドライバーも努力義務となっています。
「罰則」
高齢者マークを貼ることは、現状においては努力義務なので、高齢者マークを貼らなくても罰則に問われることはありません。
・「高齢運転者標識」の「四つ葉マーク(新)」と「もみじマーク(旧)」です。
「取付位置」
なお、高齢者マークを取り付ける場合は、道路交通法ではその位置が決められています。
その位置は、「地上0.4m以上1.2m以下の位置で、前面に1枚、後面に1枚貼ること」となっています。
「高齢者マーク取付のメリット」
高齢者マークをつけるメリットは、他の車に高齢者が運転していることを知らせることができ、高齢者に配慮した運転をしてもらいやすくなること。
高齢者マークをつけている車に対しては、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みをしてはならないこととなる、などのメリットがあります。
「高齢者マークを貼っている車への禁止事項」
高齢者マークを貼っている車には初心者マークを貼っている車と同様に、周りの車は安全に走行するための配慮をしなくてはいけません。
このため、危険を防止するためにやむを得ない場合を除いては、高齢者マークの車に幅寄せしたり、無理な割込みをした場合は道路交通法違反となり、その場合の反則金は以下の通りです。
・罰金 運転者に 5万円以下の罰金
もしくは
・反則金 中型車を含む大型車は 7000円
普通車や二輪車は 6000円、
小型特赦は 5000円が課せられます。
・違反点数 1点
「結論」
以上のように、高齢者マークを貼ることは、現状においては努力義務なので、高齢者マークを貼らなくても罰則に問われることはありません。