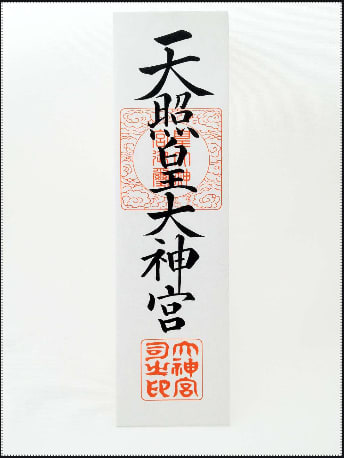春の七草
一昨日の弊ブログで春の七草の覚え方を記しましたが、今日は春の七草とは一体どのような草なのか、その画像をご紹介することにしました。
先ず、春の七草とは、一般的には「芹(せり)」、「薺(なずな)」、「御形(ごぎょう)」、「繁縷(はこべら)」、「仏の座(ホトケノザ)」、「菘月(すずな)」、「蘿蔔(すずしろ)」の七種類を言います。
この七草の内、菘月(すずな)はカブのことであり、蘿蔔(すずしろ)は大根です。
この2種類を除いた5種類はいずれも野草で、畑やあぜ道などにはたくさん生えています。
以下、その野草である春の七草を画像でご紹介します。
1.「芹(せり)」
セリ科の多年草で、湿地や田んぼの周辺水路などに生育しています。
一箇所に競り(せり)合って生えていることから、この名称がつけられたと言われています。
2.「薺(なずな)」
アブラナ科の越年草で、別名を「ぺんぺん草」と言います。
「ペンペン草」の名前は、花後につける逆三角形の実を三味線の撥(ばち)に見立てて付けられたと言われています。
3.「御形(ごぎょう)」
菊(きく)科の越年草です。
本来は「ハハコグサ(母子草)」と呼ばれている野草です。
「御形(ごぎょう)」は春の七草での呼び名となっています。
4.「繁縷(はこべら)」
ナデシコ科の越年草で、道端や庭先など、どこにでも生える雑草です。
私の故郷、岡山ではヒズルと言って雛(ひよこ)の餌にしていました。
花期は3月~9月で白い小さな五弁の花を次々に咲かせます。
5-1.キク科の「仏の座」
キク科の越年草で、和名は「コオニタビラコ(小鬼田平子)」といい、田やあぜ道に生えるタンポポに似た小形の雑草です。
5-2.シソ科の「仏の座」
仏の座にはキク科の他にシソ科の種類もあり、下の画像がそれです。
こちらは「オドリコグサ(踊子草)」の仲間で上記とは別の種類です。
6.「菘月(すずな)」
アブラナ科の一年草で「蕪(かぶ・かぶら)」のことです。
蕪(かぶ)は頭の意味で、根が頭状の塊になるのでそう呼ばれています。
7.蘿蔔(すずしろ)
アブラナ科の越年草で、大根のことです。
たくさんの品種があり、最も大きいものは「桜島大根」で直径30㎝以上にもなります。
以上が春の七草の画像です。
名前は知っていても実際に野草をご覧になることは少ないのではないでしょうか?
「春の七草」はいずれも薬用効果があって食用になりますが、その実態は、蕪と大根を除けば田やあぜ道、道端などに生えている雑草です。