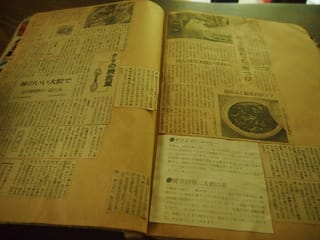先日、友人達を夕食に招く機会があったので、せっかくならと、いつもと違うパンを焼いてみたくなりました。
で、焼いてみたのは、料理の本「クチーナ・ベジターレ」のなかで紹介されている全粒粉のパンです。
この本に載っているイタリアの野菜料理はいくつか作ったことがあるのですが、パンは初めて。おいしそうだな、とおもっただけでよく読んでいなかったのですが、ちゃんとみて、驚きました。ホシノ天然酵母を使ったパンなのに、なんと、粉1キロに対して10gしか入れないのです。

一般のドライイーストは、粉1キロに対して20g。ホシノの酵母だと、80g入れるというのが普通のつくり方です。アンティマキのこねないで作るパンは、この半分量の40g。ただし、水は1割以上多めに入れて、発酵を促します。
それが、その4分の1の10gとは! 半信半疑、ほぼレシピにしたがって、粉を用意し、仕込みました。

本に書いてあった材料は、中力粉400g、全粒粉150g、薄力粉450gに対して、塩18g、ホシノ天然酵母元種10g、水510g。強力粉は入っていません。たまたま薄力粉がなかったので、ほとんど中力粉、そこにすこしだけ強力粉をくわえて、まず指示にしたがって、混ぜました。
ざっとまぜてまとまったところで大きな容器に入れ、ふたをします。そのまま10分ほど放置。そのあと、かるくちょっとだけこね、表面がなめらかになってきたら丸くして、またふたをします。そのまま、12時間から14時間ほど寝かせます。2倍ほどになったら、1次発酵完了です。

分割し、継ぎ目がみえないよう、1個ずつまるめます。そして1時間ほど乾燥させないようにしながらまた放置。ふっくらしてきたら、成型します。

表面に油を塗ってバンジュウに入れ、ふたをしておいておきます。だいたい約30分から1時間。ようすをみて取り出し、クープを入れます。高温に熱したオーブンに入れ、25分ほど焼成。完了です。

できました! クープがうまく入っていないとか、形がいびつ、とか難点はありますが、おおむね良好な仕上がりです。味も、かなりよいものでした、
酵母もと種8分の1、水は通常とほぼ同じかそれ以下、ほとんどこねずに、ここまでできました。たぶん、少ない酵母を最大限に粉が利用し、無駄なくつかったのでしょう。

さて、この日のメインディッシュは、昨年クリスマスの頃、生活クラブで売っていた鶏まるごと1羽。ひさびさに丸焼きをしました。パンもこの鳥も好評でした。ホッ。
昨日、2回目のこの方法でのパン作りの試みをしました。今度はレシピどおり、薄力粉と中力粉。間には、ドライのレーズンとイチジクを入れました。
1次発酵は順調に。ついで2次、3次と行こうとしたのですが、時間が足らなかったため、あまり膨れないのに焼いてしまいました。
おそらくそのせいで、焼きあがったパンはカチカチ。わずかだけれど、苦みもあります。酵母少なめなのに、なぜ苦いのか不思議です。
1回めは、少ない酵母が十分に活動してうまく膨れてくれたのでしょう。今回は、発酵時間が短かったため、活動が途中でとめられてしまった、ということなのかしら。過発酵だとすっぱくなることがありそうですが、発酵不足だと苦くなる、ということなのでしょうか?
近々、また挑戦してみます。
で、焼いてみたのは、料理の本「クチーナ・ベジターレ」のなかで紹介されている全粒粉のパンです。
この本に載っているイタリアの野菜料理はいくつか作ったことがあるのですが、パンは初めて。おいしそうだな、とおもっただけでよく読んでいなかったのですが、ちゃんとみて、驚きました。ホシノ天然酵母を使ったパンなのに、なんと、粉1キロに対して10gしか入れないのです。

一般のドライイーストは、粉1キロに対して20g。ホシノの酵母だと、80g入れるというのが普通のつくり方です。アンティマキのこねないで作るパンは、この半分量の40g。ただし、水は1割以上多めに入れて、発酵を促します。
それが、その4分の1の10gとは! 半信半疑、ほぼレシピにしたがって、粉を用意し、仕込みました。

本に書いてあった材料は、中力粉400g、全粒粉150g、薄力粉450gに対して、塩18g、ホシノ天然酵母元種10g、水510g。強力粉は入っていません。たまたま薄力粉がなかったので、ほとんど中力粉、そこにすこしだけ強力粉をくわえて、まず指示にしたがって、混ぜました。
ざっとまぜてまとまったところで大きな容器に入れ、ふたをします。そのまま10分ほど放置。そのあと、かるくちょっとだけこね、表面がなめらかになってきたら丸くして、またふたをします。そのまま、12時間から14時間ほど寝かせます。2倍ほどになったら、1次発酵完了です。

分割し、継ぎ目がみえないよう、1個ずつまるめます。そして1時間ほど乾燥させないようにしながらまた放置。ふっくらしてきたら、成型します。

表面に油を塗ってバンジュウに入れ、ふたをしておいておきます。だいたい約30分から1時間。ようすをみて取り出し、クープを入れます。高温に熱したオーブンに入れ、25分ほど焼成。完了です。

できました! クープがうまく入っていないとか、形がいびつ、とか難点はありますが、おおむね良好な仕上がりです。味も、かなりよいものでした、
酵母もと種8分の1、水は通常とほぼ同じかそれ以下、ほとんどこねずに、ここまでできました。たぶん、少ない酵母を最大限に粉が利用し、無駄なくつかったのでしょう。

さて、この日のメインディッシュは、昨年クリスマスの頃、生活クラブで売っていた鶏まるごと1羽。ひさびさに丸焼きをしました。パンもこの鳥も好評でした。ホッ。
昨日、2回目のこの方法でのパン作りの試みをしました。今度はレシピどおり、薄力粉と中力粉。間には、ドライのレーズンとイチジクを入れました。
1次発酵は順調に。ついで2次、3次と行こうとしたのですが、時間が足らなかったため、あまり膨れないのに焼いてしまいました。
おそらくそのせいで、焼きあがったパンはカチカチ。わずかだけれど、苦みもあります。酵母少なめなのに、なぜ苦いのか不思議です。
1回めは、少ない酵母が十分に活動してうまく膨れてくれたのでしょう。今回は、発酵時間が短かったため、活動が途中でとめられてしまった、ということなのかしら。過発酵だとすっぱくなることがありそうですが、発酵不足だと苦くなる、ということなのでしょうか?
近々、また挑戦してみます。