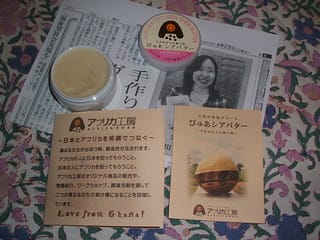昨年暮れ、納屋を整理したら、数年前知人を介してもらった古い陶器の山が出てきました。そのおりもらったのは、文机、壊れかけた糸車、和裁の裁ち台、織り機の部品などなど、私にとっては宝のような古道具でした。そのなかに、木箱にはいった古い食器があったのです。ほかの道具はみんな家のどこかにところを得てそれなりに収まっているのですが、食器だけは始末に困り、そのままになっていました。古いといっても時代物というほどのものではなく、多くは色あせて薄汚れていたし、格別立派そうなものもなかったので、ほったらかしにしていたのでした。
ダンボールに6箱ほどの食器類を運び出し、日の下にさらしました。最初に思ったとおり、いいものはありません。ふたつだけ、面白い形のものがあったので取り除け、小皿の何枚かはクラフトに使えそうなのでそれも除外して、後はすべて処分することにしました。


でも、ちゃんと形があって使えるものを捨てるのはもったいないなあと思っていたとき、以前、岐阜県の多治見か土岐で陶器のリサイクルをやっていると聞いたことがあるのを思い出し、調べてみたら、やっていました。ときたま行く事のある土岐の道の駅・どんぶり会館でも回収していると分かったのです。
さっそく持っていきました。受付でその旨告げると、係の人がやってきて端から箱に入れ直し、引き取ってくれました。会館の前にはちゃんとボックスがおいてあります。これからも、ちょっとでも持ってきてここに捨てればいいのだなとわかりました。

どんぶり会館にちかい、多治見の道の駅・志野・織部にも、同じようなボックスが入り口に置かれ、持参した器を箱に入れている人を見かけました。
どんぶり会館の職員は、回収した食器は陶器タイルに再生するらしいと言っていましたが、再生陶器で作られた食器もあるらしく、どんなものになるか、いつか見てみたいものです。再生陶器のサイトはこちら(→)。
捨てるものが生き返ると聞くと、ほっとします。捨てるときの後ろめたさが減ります。ただし、回収してもらえるのは食器だけ。花瓶、置物、土鍋、植木鉢、ガラス製品は引き取ってもらえません。陶磁器のリサイクル活動に関してはこちらをご覧ください。
ダンボールに6箱ほどの食器類を運び出し、日の下にさらしました。最初に思ったとおり、いいものはありません。ふたつだけ、面白い形のものがあったので取り除け、小皿の何枚かはクラフトに使えそうなのでそれも除外して、後はすべて処分することにしました。


でも、ちゃんと形があって使えるものを捨てるのはもったいないなあと思っていたとき、以前、岐阜県の多治見か土岐で陶器のリサイクルをやっていると聞いたことがあるのを思い出し、調べてみたら、やっていました。ときたま行く事のある土岐の道の駅・どんぶり会館でも回収していると分かったのです。
さっそく持っていきました。受付でその旨告げると、係の人がやってきて端から箱に入れ直し、引き取ってくれました。会館の前にはちゃんとボックスがおいてあります。これからも、ちょっとでも持ってきてここに捨てればいいのだなとわかりました。

どんぶり会館にちかい、多治見の道の駅・志野・織部にも、同じようなボックスが入り口に置かれ、持参した器を箱に入れている人を見かけました。
どんぶり会館の職員は、回収した食器は陶器タイルに再生するらしいと言っていましたが、再生陶器で作られた食器もあるらしく、どんなものになるか、いつか見てみたいものです。再生陶器のサイトはこちら(→)。
捨てるものが生き返ると聞くと、ほっとします。捨てるときの後ろめたさが減ります。ただし、回収してもらえるのは食器だけ。花瓶、置物、土鍋、植木鉢、ガラス製品は引き取ってもらえません。陶磁器のリサイクル活動に関してはこちらをご覧ください。