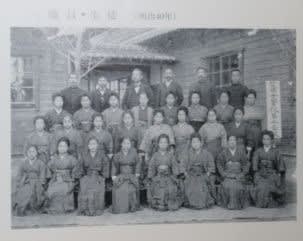備中松山藩水谷家
改易日・寛永18年(1641)
江戸時代の武士は”お家断絶”となると、藩の武士全員が無職となり、
地位も禄も家屋敷もなくしてしまう。
しかも、ほとんどの場合が予測不能な急な出来事。
武士はけっこう辛いところがある。イヤ辛すぎる。
吉備の国では、
①備中の水谷家、
②美作の森家、
③備後の水野家、
がお家断絶になった。(早い順、森家と水野家はほぼ同時)
ちょっとだけ調べてみた。

備中松山藩は水谷家が廃絶の際、赤穂藩が城の受け取り大名になり、今も登城道のほぼ中間点に「大石内蔵助の休み石」がある。
管理人も松山城に行くときは、その石に座り、ひと休みする。
水谷家は城の処理が終わってから、領民がたいへんだったようで
検地をしたら5万石から11万国になり、農民は”生かさぬように、殺さぬように”を地で行く状態になった。
。。。。。。
「江戸大名のお引っ越し」 白峰旬 新人物ブックス 2010年発行
改易大名の居城を受け取るのは、
その居城を軍事的に接収して武装解除することを意味している。
具体的には、
上使を派遣して監督業務にあたらせる、
城取り大名を派遣して臨戦体制下で城を受け取り、
次の城主が来るまで在番大名に城の在番をさせる。
「高梁市史上巻」 高梁市 平成16年発行
水谷氏の改易
勝隆・勝宗の2代47年間は、近世大名として藩政の基礎が完成し、領内の経済体制も確立した時期であり、
勝宗の晩年は財政的にも経済的にも非常に豊かな時代であったといわれる。
3代勝美の治世はわずか5年に過ぎなかったが、土木事業を大いに興し民政に心を用いた。
元禄6年(1693)勝美は大病にのぞみ、一族の勝晴を養子と定めて死去したが、
勝美もまた痘瘡を病んで翌11月、家督相続をしないうちに13歳で早世した。
そこで勝美の弟をと幕府に願い出たが許されず、徐封となり水谷家は断絶した。
水谷家は、祖先の勲功により勝美の弟が備中国川上郡のうちに3.000石を与えられて寄合に列せられ、
布賀に陣屋を置いて幕末にいたっている。
元禄6年12月松山収城使を命ぜられた播州赤穂藩主浅野長矩は、老中土屋正直の指図を仰ぎ、
掘利安・駒井正春の両目付と諸事打ち合わせ、翌7年1月22日赤穂から松山へ先発させた。
2月18日家老大石内蔵助は赤穂を出発、翌日松山へ到着。
浅野長矩は自ら本隊を率いて翌19日、赤穂を出発。
水谷家から役向きの者が出迎えた。
到着した翌日高札を建てた。
一、家中のやから今日より30日以内に引き払うべきこと。
城引き渡しは23日午後と決定されている。
大石内蔵助は水谷藩家老と会見、折衝、昼時には城地の授受が完全に終わった。
内蔵助は名代として、約1年半在番した。
この収城に、赤穂藩から繰り出された人数は大変なもので、その中には後年赤穂義士とうたわれた
不破和衛門、武林唯七、神崎弥五郎らがある。
旧水谷領を収公した幕府は、赤穂藩主浅野長矩を在番として松山の城地を守備させ、
代官を領内の民政をさせ、
姫路藩主本多忠国に松山領の検地を命じた。

この検地は旧水谷領の農民にとっては、その浮沈に関する大事件であった。
松山領から7~8人の庄屋を姫路に招き、領内の事情を、特に土地台帳について詳細に問いただした。
姫路藩では検地総奉行以下諸役人が姫路を出発。
庄屋・組頭に
村々から検地の案内人を選定して差し出させ、そのうちから姫路藩で人物を選び、
その案内人から誓紙を取って、各村一切の田畑の位付をした帳面と田畑の反別・位付などの従前のものの書付を差し出させた。
検地前に田の水を干しておくこと、
検地現場へは案内人と地主以外の者は出て騒がぬよう村中で堅く申し合わせをしておくこと。
検地は総奉行1人、元締2人、大横目2人、検地奉行3人、竿先の役人侍35人、位付役侍3人、領内庄屋3人、
勘定頭2人、勘定の者19人、医師3人、右筆3人、大工頭1人、納戸役1人、勝手方賄人4人、
徒目付16人、絵師1人、足軽150人ほど、中間200人ほど、総計約450人があたった。
検地の組は2手に分けた。12月には大体終わった。
田・畑は上々田・上田・中田・下田・下々田と5段階に等位を付けられた。
旧水谷領新検の結果に関し、ある哲多郡庄屋覚書によると、
元禄七年、御検地年の事なり、
松山領分御検地を始め、播州姫路本多中務大輔様仰せつけらる。
古高5万石の所
新高11万619石に成り候。
検地結果を知った農民代表は姫路に出かけ、検地再検討を陳情した。
翻意を幕府に取り次ぐよう訴訟を起こしたが、取次ぎをことわられた。
代官にも嘆願したが、
「百姓どもの願意もっともに思う、委細口上書を差し、そのうえで下知を待つように」
さっそく口上書を差し出したが音沙汰がない。
このうえは「とかく乞食仕りながらも御江戸に罷り下り」と嘆願するほかないと決心し、
領内の庄屋が総代となって江戸に下り、直訴に及ぼうと決心した。
その江戸下りを新任の藩主安藤重博に嘆願した。
「恐れながら」に始まる長文の嘆訴状は、当時における松山領民の悲惨な生活と苦哀を知ることができる貴重な資料である。

撮影日・2019年5月15日
・・・・・・・・・
【つづく】お家断絶②作州津山藩森家
改易日・寛永18年(1641)
江戸時代の武士は”お家断絶”となると、藩の武士全員が無職となり、
地位も禄も家屋敷もなくしてしまう。
しかも、ほとんどの場合が予測不能な急な出来事。
武士はけっこう辛いところがある。イヤ辛すぎる。
吉備の国では、
①備中の水谷家、
②美作の森家、
③備後の水野家、
がお家断絶になった。(早い順、森家と水野家はほぼ同時)
ちょっとだけ調べてみた。

備中松山藩は水谷家が廃絶の際、赤穂藩が城の受け取り大名になり、今も登城道のほぼ中間点に「大石内蔵助の休み石」がある。
管理人も松山城に行くときは、その石に座り、ひと休みする。
水谷家は城の処理が終わってから、領民がたいへんだったようで
検地をしたら5万石から11万国になり、農民は”生かさぬように、殺さぬように”を地で行く状態になった。
。。。。。。
「江戸大名のお引っ越し」 白峰旬 新人物ブックス 2010年発行
改易大名の居城を受け取るのは、
その居城を軍事的に接収して武装解除することを意味している。
具体的には、
上使を派遣して監督業務にあたらせる、
城取り大名を派遣して臨戦体制下で城を受け取り、
次の城主が来るまで在番大名に城の在番をさせる。
「高梁市史上巻」 高梁市 平成16年発行
水谷氏の改易
勝隆・勝宗の2代47年間は、近世大名として藩政の基礎が完成し、領内の経済体制も確立した時期であり、
勝宗の晩年は財政的にも経済的にも非常に豊かな時代であったといわれる。
3代勝美の治世はわずか5年に過ぎなかったが、土木事業を大いに興し民政に心を用いた。
元禄6年(1693)勝美は大病にのぞみ、一族の勝晴を養子と定めて死去したが、
勝美もまた痘瘡を病んで翌11月、家督相続をしないうちに13歳で早世した。
そこで勝美の弟をと幕府に願い出たが許されず、徐封となり水谷家は断絶した。
水谷家は、祖先の勲功により勝美の弟が備中国川上郡のうちに3.000石を与えられて寄合に列せられ、
布賀に陣屋を置いて幕末にいたっている。
元禄6年12月松山収城使を命ぜられた播州赤穂藩主浅野長矩は、老中土屋正直の指図を仰ぎ、
掘利安・駒井正春の両目付と諸事打ち合わせ、翌7年1月22日赤穂から松山へ先発させた。
2月18日家老大石内蔵助は赤穂を出発、翌日松山へ到着。
浅野長矩は自ら本隊を率いて翌19日、赤穂を出発。
水谷家から役向きの者が出迎えた。
到着した翌日高札を建てた。
一、家中のやから今日より30日以内に引き払うべきこと。
城引き渡しは23日午後と決定されている。
大石内蔵助は水谷藩家老と会見、折衝、昼時には城地の授受が完全に終わった。
内蔵助は名代として、約1年半在番した。
この収城に、赤穂藩から繰り出された人数は大変なもので、その中には後年赤穂義士とうたわれた
不破和衛門、武林唯七、神崎弥五郎らがある。
旧水谷領を収公した幕府は、赤穂藩主浅野長矩を在番として松山の城地を守備させ、
代官を領内の民政をさせ、
姫路藩主本多忠国に松山領の検地を命じた。

この検地は旧水谷領の農民にとっては、その浮沈に関する大事件であった。
松山領から7~8人の庄屋を姫路に招き、領内の事情を、特に土地台帳について詳細に問いただした。
姫路藩では検地総奉行以下諸役人が姫路を出発。
庄屋・組頭に
村々から検地の案内人を選定して差し出させ、そのうちから姫路藩で人物を選び、
その案内人から誓紙を取って、各村一切の田畑の位付をした帳面と田畑の反別・位付などの従前のものの書付を差し出させた。
検地前に田の水を干しておくこと、
検地現場へは案内人と地主以外の者は出て騒がぬよう村中で堅く申し合わせをしておくこと。
検地は総奉行1人、元締2人、大横目2人、検地奉行3人、竿先の役人侍35人、位付役侍3人、領内庄屋3人、
勘定頭2人、勘定の者19人、医師3人、右筆3人、大工頭1人、納戸役1人、勝手方賄人4人、
徒目付16人、絵師1人、足軽150人ほど、中間200人ほど、総計約450人があたった。
検地の組は2手に分けた。12月には大体終わった。
田・畑は上々田・上田・中田・下田・下々田と5段階に等位を付けられた。
旧水谷領新検の結果に関し、ある哲多郡庄屋覚書によると、
元禄七年、御検地年の事なり、
松山領分御検地を始め、播州姫路本多中務大輔様仰せつけらる。
古高5万石の所
新高11万619石に成り候。
検地結果を知った農民代表は姫路に出かけ、検地再検討を陳情した。
翻意を幕府に取り次ぐよう訴訟を起こしたが、取次ぎをことわられた。
代官にも嘆願したが、
「百姓どもの願意もっともに思う、委細口上書を差し、そのうえで下知を待つように」
さっそく口上書を差し出したが音沙汰がない。
このうえは「とかく乞食仕りながらも御江戸に罷り下り」と嘆願するほかないと決心し、
領内の庄屋が総代となって江戸に下り、直訴に及ぼうと決心した。
その江戸下りを新任の藩主安藤重博に嘆願した。
「恐れながら」に始まる長文の嘆訴状は、当時における松山領民の悲惨な生活と苦哀を知ることができる貴重な資料である。

撮影日・2019年5月15日
・・・・・・・・・
【つづく】お家断絶②作州津山藩森家