長崎の大光寺に明治十七年五月、旧会津藩家老保科頼母近悳の養子となり、
同二十一年西郷家再興により保科四郎から改姓した西郷四郎の墓所を訪ねた。
この大光寺は慶長十九年、僧慶了が創建、万治三年(1660)現在地の
鍛冶屋町にうつり、一度の火災にも合わなかったが1913年に新しく建て
なおされている。墓地には日本印刷の祖本木昌造の墓がある。





長崎のお寺の墓域に入って驚いた。多くの墓は塀で囲まれ大きな墓域には門扉
まである。文字が金色で象られた墓碑の横に小さな「土神」(つちがみさま)と
刻みこまれた石碑が祀られ、お寺の墓域でいやに金文字の墓石が目立つと思ったら
卒塔婆をまったく見かけなかった。


講道館四天王の一人で富田常雄の小説『姿三四郎』のモデルと云われる志田四郎は
明治十二年保科有鄰が病死した後すぐ保科家の養子になったことになっているが、
その時期や養子にした理由についてはハッキリしていない。
明治二十三年、嘉納治五郎の洋行中に講道館を任せられていた四郎は「支那渡航意見書」
を残して講道館を去り長崎に赴いた。大陸志向の強かった四郎だが講道館を出奔した理由も
大陸に渡った西郷頼母の妹幾与子二男の一瀬熊鉄や妹八代子三男の井深彦三郎らに大きく
影響を受けたと思われるが、ハッキリしていない。
(青山墓園にある井深彦三郎之墓)

明治三十三年、四郎は長崎市長だった北原雅長の弟神保岩之助の四男孝之を
養子に迎え、同三十五年、生涯の友となる二本松藩出身の鈴木天眼が長崎で
創刊した東洋日の出新聞に編集責任者として参加する。なお神保岩之助は、
福岡豊津の育徳館に留学中、切腹自刃した郡長正を介錯している。
日露戦争が始まった明治三十七年五月十三日、西郷四郎は東洋日の出新聞社員、
福島熊之助、安永東之助及び玄洋社社員、萱野長知、真藤慎太郎、小野鴻之助、
柴田鱗次郎、福住克己ら八名は特別任務のため陸軍通訳に奏仕官待遇で採用されたが、
鈴木天眼の強い阻止にあって当該辞令書を返却している。のち福島熊之助以下7名は
花田中佐率いる満州義軍に参加している。このとき井深彦三郎は満州軍総司令部で
通訳として特別任務に就いてる。
①右から2人目西郷四郎 ②右から5人目井深彦三郎
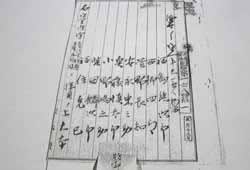

①JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. C09122006300
陸軍通訳に採用の上大本営付被命度移牒(防衛省防衛研究所)
②JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. C06040984500、
満州軍総司令部管区軍政署職員表(防衛省防衛研究所)
大正十一年(1922)十二月、尾道にて病死、妻チカの実家菩提寺長崎大光寺の
中川家墓地に納骨された。浜口家はチカの母親中川キンの養女ミネの嫁先。
墓域中央にある山田家というのはどうゆう関係なのだろうか。


長崎思案橋郵便局近く、「孫文先生故縁の地」説明、写真左から孫文、鈴木天眼、西郷四郎


同二十一年西郷家再興により保科四郎から改姓した西郷四郎の墓所を訪ねた。
この大光寺は慶長十九年、僧慶了が創建、万治三年(1660)現在地の
鍛冶屋町にうつり、一度の火災にも合わなかったが1913年に新しく建て
なおされている。墓地には日本印刷の祖本木昌造の墓がある。





長崎のお寺の墓域に入って驚いた。多くの墓は塀で囲まれ大きな墓域には門扉
まである。文字が金色で象られた墓碑の横に小さな「土神」(つちがみさま)と
刻みこまれた石碑が祀られ、お寺の墓域でいやに金文字の墓石が目立つと思ったら
卒塔婆をまったく見かけなかった。


講道館四天王の一人で富田常雄の小説『姿三四郎』のモデルと云われる志田四郎は
明治十二年保科有鄰が病死した後すぐ保科家の養子になったことになっているが、
その時期や養子にした理由についてはハッキリしていない。
明治二十三年、嘉納治五郎の洋行中に講道館を任せられていた四郎は「支那渡航意見書」
を残して講道館を去り長崎に赴いた。大陸志向の強かった四郎だが講道館を出奔した理由も
大陸に渡った西郷頼母の妹幾与子二男の一瀬熊鉄や妹八代子三男の井深彦三郎らに大きく
影響を受けたと思われるが、ハッキリしていない。
(青山墓園にある井深彦三郎之墓)

明治三十三年、四郎は長崎市長だった北原雅長の弟神保岩之助の四男孝之を
養子に迎え、同三十五年、生涯の友となる二本松藩出身の鈴木天眼が長崎で
創刊した東洋日の出新聞に編集責任者として参加する。なお神保岩之助は、
福岡豊津の育徳館に留学中、切腹自刃した郡長正を介錯している。
日露戦争が始まった明治三十七年五月十三日、西郷四郎は東洋日の出新聞社員、
福島熊之助、安永東之助及び玄洋社社員、萱野長知、真藤慎太郎、小野鴻之助、
柴田鱗次郎、福住克己ら八名は特別任務のため陸軍通訳に奏仕官待遇で採用されたが、
鈴木天眼の強い阻止にあって当該辞令書を返却している。のち福島熊之助以下7名は
花田中佐率いる満州義軍に参加している。このとき井深彦三郎は満州軍総司令部で
通訳として特別任務に就いてる。
①右から2人目西郷四郎 ②右から5人目井深彦三郎
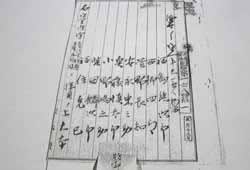

①JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. C09122006300
陸軍通訳に採用の上大本営付被命度移牒(防衛省防衛研究所)
②JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. C06040984500、
満州軍総司令部管区軍政署職員表(防衛省防衛研究所)
大正十一年(1922)十二月、尾道にて病死、妻チカの実家菩提寺長崎大光寺の
中川家墓地に納骨された。浜口家はチカの母親中川キンの養女ミネの嫁先。
墓域中央にある山田家というのはどうゆう関係なのだろうか。


長崎思案橋郵便局近く、「孫文先生故縁の地」説明、写真左から孫文、鈴木天眼、西郷四郎




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます