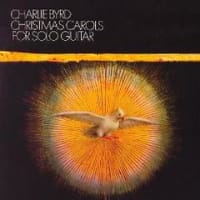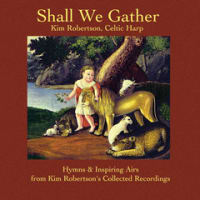”AUTUMN '66”by THE SPENCER DAVIS GROUP
何しろタイトルに秋とあるので、いかにも秋、と言った季節に聴こうなんて考えていたら、毎度お馴染み、「せっかく買ったのにいつまで放置しておくつもりだ」の状態になってしまい、何年か前に買ったこのアルバムを、本日やっと聴取に成功した次第。
音楽ファンとしての第一歩を当方は、60年代イギリスのビートグループの崇拝者として踏み出したのだった。はじめはストーンズやアニマルズに夢中だったのだが、あれこれ聴き進みそれなりに生意気になりだした頃には、このスペンサー・デイビスグループが大のゴヒイキとなっていた。グループというより、ご多分に漏れずこのバンドの擁する天才少年、スティービー・ウィンウッドの大ファンだった。
こいつは何者だ。まだこの当時、高校生そこそこの年齢のくせに、まるで黒人みたいなむちゃくちゃ濃厚な喉を聴かせる。そのうえギターやオルガンの腕も達者だ。手がつけられないじゃないか。
このアルバムは、そんな天才少年スティービーがいよいよその才能を縦横に発揮し、グループをさらにディープな境地に連れて行った記録だ。この後、スティービーは、自分の戦場としては、このバンドは狭過ぎるとでも言うようにバンドを脱退して行くことになる。
いやその前に、「ギミ・サム・ラビン」というとんでもないかっこ良いナンバーを炸裂させて行くのだが、とりあえずスペンサー・デイビスグループのアルバムとしては、これがスティービーの最後の参加作品となる。
などと言っているが、かって現役ファンだった頃の私は小遣いをかき集めてやっとシングル盤を買っていたチューボーだったのであって、アルバム作品としての”秋66”を聴くのはこれが初めてなのだけれど。
ずいぶん堅牢な出来上がりだな、というのが最初の感想。何だかこげ茶色に煮しめられた古い家具みたいな鈍い光沢を放って、音が存在している。スティービーがガキのくせしてドンと重心を落として歌う渋いスローバラードなどが要所を締めているせいもあるだろう。
一方、ブルースロックやらアメリカのフォークソングのカバーなど、もう無効となってしまったジャンルも、スティービーの歌唱のリアルさにより、それなりに聴けてしまうのだった。
そして、このアルバムからはみ出した前出、「ギミ・サム・ラビン」などの、ボーナストラックとして収められている作品群に漲る、新しいロックのページを開こうとするスティービーの気迫は、それから何が起こるのか知っている、21世紀に生きるこの身にも、なにやら身を切るような切迫感を伝えて来る。
この1966年秋の英国ロック最前線からの便りは、間近かにやって来ているロックの革命の予感を孕み、今だ生々しい光を放っているのだった。
何しろタイトルに秋とあるので、いかにも秋、と言った季節に聴こうなんて考えていたら、毎度お馴染み、「せっかく買ったのにいつまで放置しておくつもりだ」の状態になってしまい、何年か前に買ったこのアルバムを、本日やっと聴取に成功した次第。
音楽ファンとしての第一歩を当方は、60年代イギリスのビートグループの崇拝者として踏み出したのだった。はじめはストーンズやアニマルズに夢中だったのだが、あれこれ聴き進みそれなりに生意気になりだした頃には、このスペンサー・デイビスグループが大のゴヒイキとなっていた。グループというより、ご多分に漏れずこのバンドの擁する天才少年、スティービー・ウィンウッドの大ファンだった。
こいつは何者だ。まだこの当時、高校生そこそこの年齢のくせに、まるで黒人みたいなむちゃくちゃ濃厚な喉を聴かせる。そのうえギターやオルガンの腕も達者だ。手がつけられないじゃないか。
このアルバムは、そんな天才少年スティービーがいよいよその才能を縦横に発揮し、グループをさらにディープな境地に連れて行った記録だ。この後、スティービーは、自分の戦場としては、このバンドは狭過ぎるとでも言うようにバンドを脱退して行くことになる。
いやその前に、「ギミ・サム・ラビン」というとんでもないかっこ良いナンバーを炸裂させて行くのだが、とりあえずスペンサー・デイビスグループのアルバムとしては、これがスティービーの最後の参加作品となる。
などと言っているが、かって現役ファンだった頃の私は小遣いをかき集めてやっとシングル盤を買っていたチューボーだったのであって、アルバム作品としての”秋66”を聴くのはこれが初めてなのだけれど。
ずいぶん堅牢な出来上がりだな、というのが最初の感想。何だかこげ茶色に煮しめられた古い家具みたいな鈍い光沢を放って、音が存在している。スティービーがガキのくせしてドンと重心を落として歌う渋いスローバラードなどが要所を締めているせいもあるだろう。
一方、ブルースロックやらアメリカのフォークソングのカバーなど、もう無効となってしまったジャンルも、スティービーの歌唱のリアルさにより、それなりに聴けてしまうのだった。
そして、このアルバムからはみ出した前出、「ギミ・サム・ラビン」などの、ボーナストラックとして収められている作品群に漲る、新しいロックのページを開こうとするスティービーの気迫は、それから何が起こるのか知っている、21世紀に生きるこの身にも、なにやら身を切るような切迫感を伝えて来る。
この1966年秋の英国ロック最前線からの便りは、間近かにやって来ているロックの革命の予感を孕み、今だ生々しい光を放っているのだった。