何かを思い描いたり、誰かのことを想ったり、遠い場所を夢みたりするのは
頭の中での作業だと、理屈では分かっていても、重ねた両手は自然に胸の前で
組まれるし、ずきんと鳴ったり、きゅんとするのも胸の内側ではないですか?
この本。
そっと覚えて、いつでも自分の「内側」で、繰り返し唱えた短い詩が、
安野さんの美しい挿絵とともに、50篇も入っています。
 『ソナチネの木』
『ソナチネの木』
岸田 衿子 作 安野 光雅 絵
詩っていうか、ひとりごとみたいな短い文は、すべてがたったの4行でできていますが、
一旦自分の中に入ってくると、それはどこまでもどこまでも広がっていく感じです。
たとえばこんなふう。
わたしはえのぐをといた
昼をとっておくために
窓をみがいた
夜をとっておくために
ソナチネの木。
タイトルからして、すごく素敵。
小鳥が一つずつ
音をくわえて とまった木
その木を
ソナチネの木 という
rの14歳の誕生日に、と贈った本ですが、彼女の胸に届く日が来るまでは
(こういう詩が響くようになるのは、好きな人がいてこそですから)
私が何度も何度もページを繰るでしょう。
*今年もまた誕生日がやってきました。
奇数の年より、なぜか偶数の年(年齢)になるほうが、好きだなと思います。
今朝、昇る朝日をみたのです。
12年前の、8月28日を覚えているように、12年後も、今日のことを思い出すことが
できるでしょうか。
強い日差し、夏の庭、友とのおしゃべり、家族の祝福‥ソナチネの木。
頭の中での作業だと、理屈では分かっていても、重ねた両手は自然に胸の前で
組まれるし、ずきんと鳴ったり、きゅんとするのも胸の内側ではないですか?
この本。
そっと覚えて、いつでも自分の「内側」で、繰り返し唱えた短い詩が、
安野さんの美しい挿絵とともに、50篇も入っています。
 『ソナチネの木』
『ソナチネの木』岸田 衿子 作 安野 光雅 絵
詩っていうか、ひとりごとみたいな短い文は、すべてがたったの4行でできていますが、
一旦自分の中に入ってくると、それはどこまでもどこまでも広がっていく感じです。
たとえばこんなふう。
わたしはえのぐをといた
昼をとっておくために
窓をみがいた
夜をとっておくために
ソナチネの木。
タイトルからして、すごく素敵。
小鳥が一つずつ
音をくわえて とまった木
その木を
ソナチネの木 という
rの14歳の誕生日に、と贈った本ですが、彼女の胸に届く日が来るまでは
(こういう詩が響くようになるのは、好きな人がいてこそですから)
私が何度も何度もページを繰るでしょう。
*今年もまた誕生日がやってきました。
奇数の年より、なぜか偶数の年(年齢)になるほうが、好きだなと思います。
今朝、昇る朝日をみたのです。
12年前の、8月28日を覚えているように、12年後も、今日のことを思い出すことが
できるでしょうか。
強い日差し、夏の庭、友とのおしゃべり、家族の祝福‥ソナチネの木。











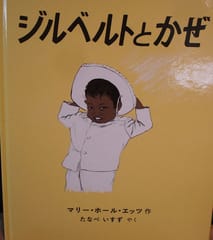 『
『 『
『 『
『 『
『 『
『 『
『 『
『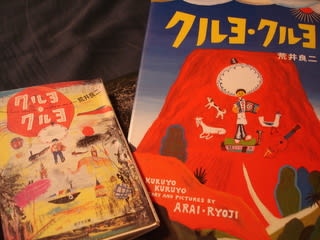
 『
『 『
『 『
『



 『ハンバーグーチョキパー』
『ハンバーグーチョキパー』

 『
『