
「時の海」に生き続ける村の人たち
★※Sea of Time '98宮島達夫氏の作品について、もう少し詳しく書いた別ブログにリンクします

「現代アート」はわからない?
好きなように感じればよい?

いや、適切な解説があってこそ、その意味が理解できる。
今回案内していただいたKさんのおかげではっきりそう思うようになった。
ありがとうございます(^^)
※ベネッセの「家プロジェクト」解説ページにリンクします
★護王神社 杉本博司作品

「伊勢神宮など初期の神社建築の様式を念頭に、さらに作家自身の美意識に基づく」とパンフレットで解説されている。
見てすぐに、日本最古の神社建築とされる国宝「神魂(かもす)神社」(島根県)を思い出した↓

↑※2019年10月小松撮影↑これは天正11年(1583年=本能寺の変の翌年)に建築されたもの。
拝殿と、本殿への斜めの階段は古代神社建築の雰囲気を感じる。
出雲大社本殿は平安時代まで巨大な柱に支えられた高さ五十メートルにも達するもので、地上からの長い斜めの階段が本殿へ導いていたとされている。近年の発掘調査でそれが見えてきた。
※國學院大學の復元ページにリンクします
直島の作品のおもしろいのは、古代の古墳を神社と重ねているところ。

横から、地下へ入ることができる。

一人が通るのにやっとの通路を抜け、真っ暗な玄室にはいると

地上のガラスの階段が地下にも続いていたではないか。

天井を照らすと、石舞台古墳のような巨石があらわれた。
政教一致の古代では、支配者は神でありその墓は崇拝の対象になっただろう。
古墳と社がリンクするのは自然だ。

表に出ると瀬戸内が穏やかにひろがっていた。
後から訪れたベネッセ・ハウスで、同じ杉本博司の水平線写真を並べた作品に出会った。
そうか、あの「古墳」から出て見えた水平線も作者の見せたかったモノだったのか。
以前にあった神社がどのようなものかは分からないけれど、
この現代アート作品もまた充分祈りの場に相応しいと感じる。
実際に村の人はここでお参りもするのだそうだ。
どんな「作品」も、お金がなくては実現できない。

↑「社殿一式」を奉納した福武総一郎さん、よい仕事されました(^^)

社殿前の玉砂利だが、以前はもっと細かいモノだったそうだ。
作家の希望で大きさに敷き換えられた。

↑よく見ると小さな砂利が下にある。

昔のままだろう鳥居。

この門も一見そのままに見えるが、新しく建築されたのだとか。


***
★ANDOミュージアム

のれんをくぐると
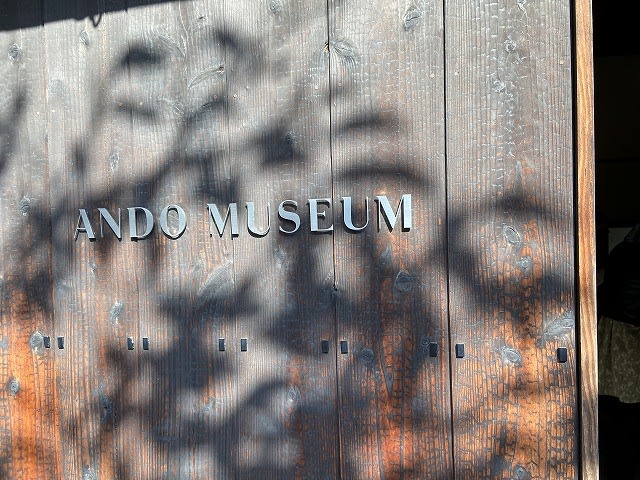
焼杉板の壁が迎えてくれるが、

内部はまごうことなき安藤建築のコンクリート壁(^^)
この壁が光と織りなす幾何学的な空間自体が見るべきもの↓この部屋は1989年に建設された通称「光の教会」を解説してある↓※「光の教会」関連のHPへ

↑こちら「光の教会」の模型
↓こちらコンクリートと古民家構造の融合

一角に、現場で施工した人々の名前があった↓

「光の教会」の建設顛末を書いた本を読んでよくわかったが、建築家のこだわりは現場泣かせ。
施工する人々の協力があってはじめて建築家が成り立つ(^^)
★※Sea of Time '98宮島達夫氏の作品について、もう少し詳しく書いた別ブログにリンクします

「現代アート」はわからない?
好きなように感じればよい?

いや、適切な解説があってこそ、その意味が理解できる。
今回案内していただいたKさんのおかげではっきりそう思うようになった。
ありがとうございます(^^)
※ベネッセの「家プロジェクト」解説ページにリンクします
★護王神社 杉本博司作品

「伊勢神宮など初期の神社建築の様式を念頭に、さらに作家自身の美意識に基づく」とパンフレットで解説されている。
見てすぐに、日本最古の神社建築とされる国宝「神魂(かもす)神社」(島根県)を思い出した↓

↑※2019年10月小松撮影↑これは天正11年(1583年=本能寺の変の翌年)に建築されたもの。
拝殿と、本殿への斜めの階段は古代神社建築の雰囲気を感じる。
出雲大社本殿は平安時代まで巨大な柱に支えられた高さ五十メートルにも達するもので、地上からの長い斜めの階段が本殿へ導いていたとされている。近年の発掘調査でそれが見えてきた。
※國學院大學の復元ページにリンクします
直島の作品のおもしろいのは、古代の古墳を神社と重ねているところ。

横から、地下へ入ることができる。

一人が通るのにやっとの通路を抜け、真っ暗な玄室にはいると

地上のガラスの階段が地下にも続いていたではないか。

天井を照らすと、石舞台古墳のような巨石があらわれた。
政教一致の古代では、支配者は神でありその墓は崇拝の対象になっただろう。
古墳と社がリンクするのは自然だ。

表に出ると瀬戸内が穏やかにひろがっていた。
後から訪れたベネッセ・ハウスで、同じ杉本博司の水平線写真を並べた作品に出会った。
そうか、あの「古墳」から出て見えた水平線も作者の見せたかったモノだったのか。
以前にあった神社がどのようなものかは分からないけれど、
この現代アート作品もまた充分祈りの場に相応しいと感じる。
実際に村の人はここでお参りもするのだそうだ。
どんな「作品」も、お金がなくては実現できない。

↑「社殿一式」を奉納した福武総一郎さん、よい仕事されました(^^)

社殿前の玉砂利だが、以前はもっと細かいモノだったそうだ。
作家の希望で大きさに敷き換えられた。

↑よく見ると小さな砂利が下にある。

昔のままだろう鳥居。

この門も一見そのままに見えるが、新しく建築されたのだとか。


***
★ANDOミュージアム

のれんをくぐると
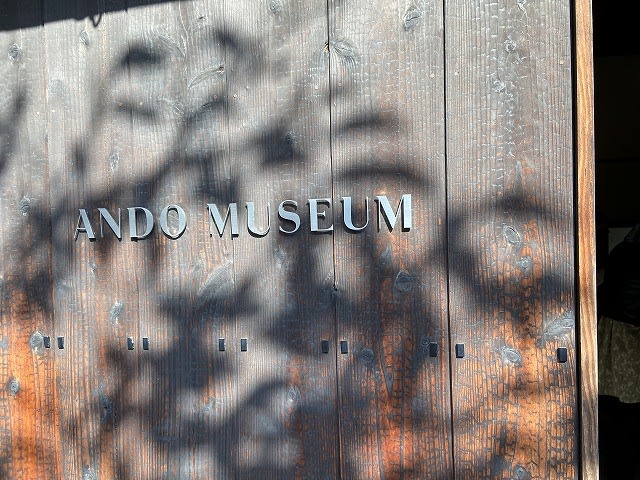
焼杉板の壁が迎えてくれるが、

内部はまごうことなき安藤建築のコンクリート壁(^^)
この壁が光と織りなす幾何学的な空間自体が見るべきもの↓この部屋は1989年に建設された通称「光の教会」を解説してある↓※「光の教会」関連のHPへ

↑こちら「光の教会」の模型
↓こちらコンクリートと古民家構造の融合

一角に、現場で施工した人々の名前があった↓

「光の教会」の建設顛末を書いた本を読んでよくわかったが、建築家のこだわりは現場泣かせ。
施工する人々の協力があってはじめて建築家が成り立つ(^^)















