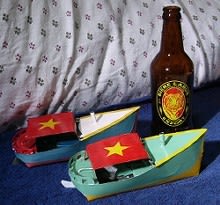○ロナルド・ドーア『働くということ:グローバル化と労働の新しい意味』(中公新書) 中央公論新社 2005.4
雇用と労働を考えるマイブームに乗って、また1冊、新しい本を読んでみた。著者のロナルド・ドーア氏は、日本ふうに言えば大正生まれの、日本研究の大御所。いわゆる「日本型」社会・経済システムの研究者として定評がある。
本書は、現在、日本経済が直面している問題(市場のグローバル化と不平等の加速)について述べるとともに、過去半世紀にわたる著者の日本研究を回想・総括したものでもある。その中には、いろいろ知らなかった事実が含まれていて、興味深い。たとえば、古い話では、日清戦争まで、工場では職工も書記も、夏は6時半、冬は7時に出勤する規則だったという。早いな~。まあ、夜も早く帰ったんだろうけど。大正9年の不景気で、7時半出勤となり、昭和14年、工員が7時半か8時、事務員が8時半出勤となったそうだ。
それから、最近は低賃金層の長時間労働が話題になっているけれど、2000年までの調査によれば、日本では(アメリカと同様)所得階層と労働時間に正の相関関係があるそうだ。つまり、一般職員よりも管理職のほうが長く働いているのである。いずれもトリビア的な知識に過ぎないけれど、日本人の労働実態に全く無知であった私には、素朴にびっくりしたり、感心したりする事実だった。
年功制度は、日本の専売特許のように言われるが、決してそうではなく、イギリスの官庁・警察・軍隊でも行われているという。ただし、英米の民間企業は職務給制度で、同じポストに留まっている限り、昇給は上司の任意に頼るしかない。一方、ドイツの工場は今も出来高払い(成果主義)が多い。このように、ひとくちに「日本型システム」と言っても、それに対峙する、唯一の非日本型システムがあるわけではなく、欧米諸国も、国によってさまざまである、というのも、本書によって知ったことだ。
しかし、全体として著者が懸念するのは、世界中が、アングロ・サクソン諸国の牽引する方向に進んでいることである。株主の利益を最大限に実現する経営が「公正」であるという考え方を、経営者ばかりでなく、多くの人が支持するようになっている。従業員の福祉や社会的連帯は犠牲にされてもやむを得ない。有能なCEOが、莫大な報酬を独占し、一般従業員との格差が拡大するのは正当なことだ。このような考え方を、市場個人主義と呼ぶ。
この流れを押し留める要因があるとすれば、ひとつは資本主義の多様性である。大陸ヨーロッパ型、日本型、あるいは中国型資本主義には、アングロ・サクソン型資本主義(対立のゼロサム関係)に再考を促す可能性があるのではないか。
もうひとつの手がかりは、「あなたの不安は私の平和を脅かす」という箴言である。行き過ぎた格差は、対立や怨嗟の種となり、社会に不安を撒き散らす。どんなに監視や統制を強めても、見えない不安を完全に解消するのは難しい。だとすれば、我々が安心して生活するためには、できるだけ多くの人が納得する「公正」を実現するよう、努力するしかないのではないか。新年このかた、凶悪事件のニュースの連続に付き合っていると、迂遠なようで、これは真実と思われてくる。
雇用と労働を考えるマイブームに乗って、また1冊、新しい本を読んでみた。著者のロナルド・ドーア氏は、日本ふうに言えば大正生まれの、日本研究の大御所。いわゆる「日本型」社会・経済システムの研究者として定評がある。
本書は、現在、日本経済が直面している問題(市場のグローバル化と不平等の加速)について述べるとともに、過去半世紀にわたる著者の日本研究を回想・総括したものでもある。その中には、いろいろ知らなかった事実が含まれていて、興味深い。たとえば、古い話では、日清戦争まで、工場では職工も書記も、夏は6時半、冬は7時に出勤する規則だったという。早いな~。まあ、夜も早く帰ったんだろうけど。大正9年の不景気で、7時半出勤となり、昭和14年、工員が7時半か8時、事務員が8時半出勤となったそうだ。
それから、最近は低賃金層の長時間労働が話題になっているけれど、2000年までの調査によれば、日本では(アメリカと同様)所得階層と労働時間に正の相関関係があるそうだ。つまり、一般職員よりも管理職のほうが長く働いているのである。いずれもトリビア的な知識に過ぎないけれど、日本人の労働実態に全く無知であった私には、素朴にびっくりしたり、感心したりする事実だった。
年功制度は、日本の専売特許のように言われるが、決してそうではなく、イギリスの官庁・警察・軍隊でも行われているという。ただし、英米の民間企業は職務給制度で、同じポストに留まっている限り、昇給は上司の任意に頼るしかない。一方、ドイツの工場は今も出来高払い(成果主義)が多い。このように、ひとくちに「日本型システム」と言っても、それに対峙する、唯一の非日本型システムがあるわけではなく、欧米諸国も、国によってさまざまである、というのも、本書によって知ったことだ。
しかし、全体として著者が懸念するのは、世界中が、アングロ・サクソン諸国の牽引する方向に進んでいることである。株主の利益を最大限に実現する経営が「公正」であるという考え方を、経営者ばかりでなく、多くの人が支持するようになっている。従業員の福祉や社会的連帯は犠牲にされてもやむを得ない。有能なCEOが、莫大な報酬を独占し、一般従業員との格差が拡大するのは正当なことだ。このような考え方を、市場個人主義と呼ぶ。
この流れを押し留める要因があるとすれば、ひとつは資本主義の多様性である。大陸ヨーロッパ型、日本型、あるいは中国型資本主義には、アングロ・サクソン型資本主義(対立のゼロサム関係)に再考を促す可能性があるのではないか。
もうひとつの手がかりは、「あなたの不安は私の平和を脅かす」という箴言である。行き過ぎた格差は、対立や怨嗟の種となり、社会に不安を撒き散らす。どんなに監視や統制を強めても、見えない不安を完全に解消するのは難しい。だとすれば、我々が安心して生活するためには、できるだけ多くの人が納得する「公正」を実現するよう、努力するしかないのではないか。新年このかた、凶悪事件のニュースの連続に付き合っていると、迂遠なようで、これは真実と思われてくる。