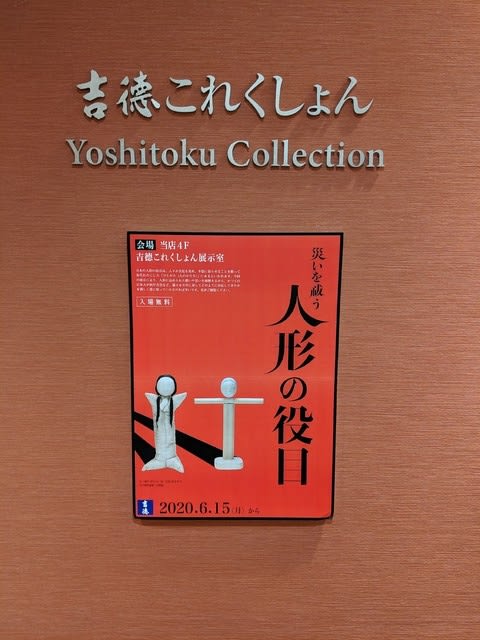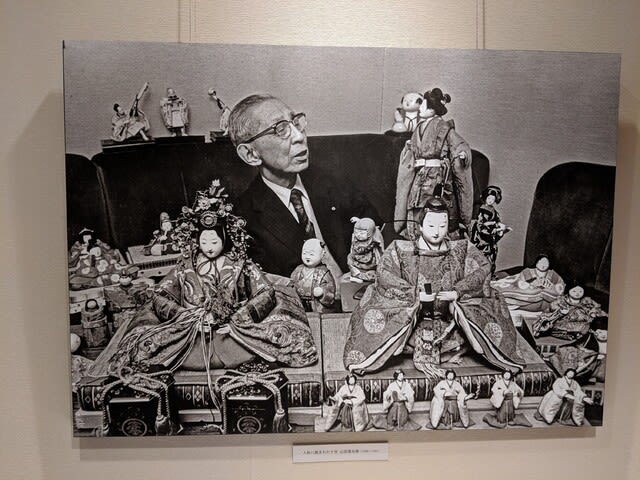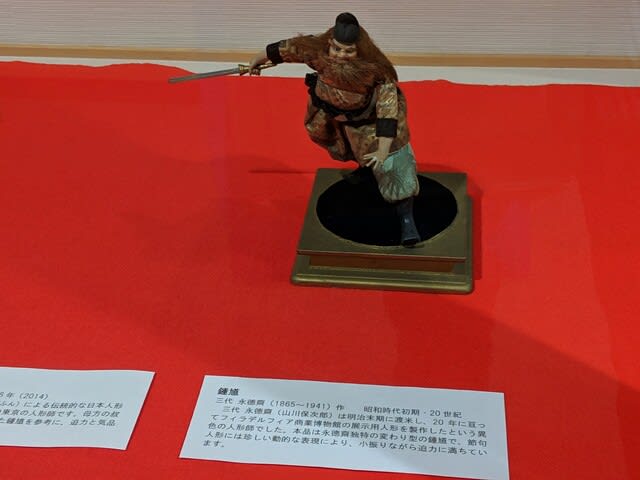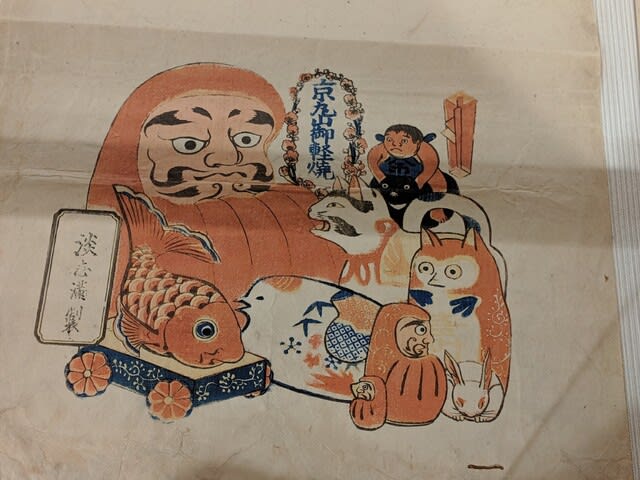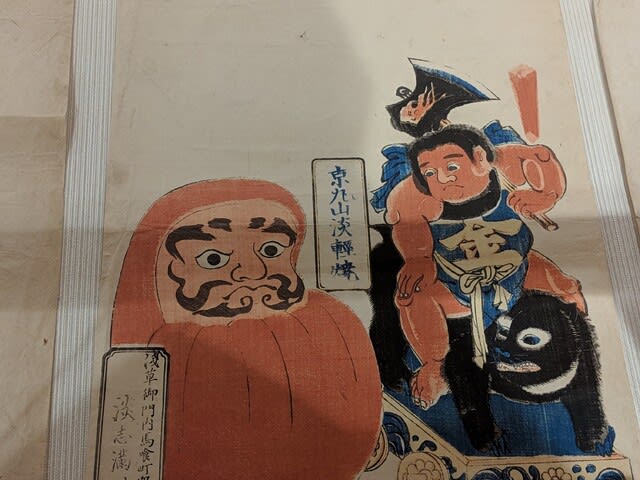結論を言えば、もっと早く出かけるべきだったと思いました。会期が煮詰まってきているので当然平日でも混んでいます。この夏、前半は宮城県大崎市内の稲荷神社への半堤式の稲荷の納で手一杯だったのと、この暑さで自転車で出かけるのが心配でした。それと深夜の作業のほうが少しでもしやすいので夜型生活になって日中眠気に苛まれていた。幸い今日はは照っていないので幾分ひりつくような暑さでもなく、雨が心配ではあったものの展示を観終わるまで天気が持ってくれさえすれば帰りはずぶ濡れでもいいかと思って自転車で出かけました。

平成館の建物入口のテントのところで入場規制をしていました。せいぜい5分10分くらいの待ちだったですが混んでいます。会場内撮影OKではあったのですが、カメラを携帯するのを忘れたのと、ケースが黒山の人だかりで展示品が見えず、しぶとく並ぶのも体力が必要なので無理と思うところは流して近づけるところだけ観て帰ってきました。(これが会期はじめの頃だったら見直しに出かける考えも湧いたかも、、。)
第一展示室、第二展示室とも集まったという感じの豪華さでしたね。この勢揃いも空前絶後のサミット的な感じで、ひとつひとつを現地に追いかけて観に行くというのは無理でしょう。すべてをじっくり味わったと言えないのですが、第一展示室のはじめのほうにあった尖底土器の単独ケースに入っていたものに何だかわかりませんが粘土紐を編んだような細長い装飾がありすごいと思いました。何を表しているのだろう?、、と。これまであんまり気を入れて眺めることをしなかったので今回改めて驚いたのですが、土器でも土偶でもどうやって作っていたのだろう、、信じられないということを感じました。火焔土器でも尖底土器でもひもづくりで底から積み上げていったのでしょうが、大きさに比べそんなに厚みがないという印象。乾燥させて焼き上げてあの大きさなので成形するときはもっと大きいはずなのと積み上げながら下のほうがへたることがありそうなのに、、。当時の特別な職の人が作ったのでしょうが、地面を掘って土を採取することから始めて、当時は水簸(すいひ)などしなかっただろうから、不純物を取り除きながら練り込むところから始まりますね。
縄目で文様をつける前に装飾の凹凸をつける道具として2本平行に爪を持つへらのようなもので平行曲線をつけるんでしょうね。NHK特集で紹介されていたように火焔風の装飾に空いている孔がトローチの笛のように入口と出口の孔の間に空間があるようで、観る方向から二つの孔のずれによって月の満ち欠けを感じさせるというのもすごいです。基本的にシンメトリーに展開する文様と「ねじれシンメトリーとも」いうべき配置を持つものもありました。土色もそれぞれ微妙に異なり、当然焼具合も異なるのでしょうが、発掘された遺跡=作られたところ とは限らないのでしょうね。例えば身びいきになりますが、山形県舟形町西の前遺跡出土の土偶が舟形の土なのかということです。ヒップの表現の感じが長野出土のものに感じが似ていますし、群馬出土のハート顔土偶の足腰にも似ています。
びっくりしたのはまた土器に赤漆が塗られたいるものがあったこと。縄文で既に漆の技術があった?漆って耐熱性があるとかいいますが、塗り終わって乾くまでは傷んだり扱いが難しいとか聞いたような、、。
第二室の後半から出てくる容器に顔がついている式のものは確かに縄文ではあるのに何か牧歌的な感じがして面白いと思います。どこの何かは思いつきませんが、同じような印象を持ったものが海外にあったような気がします。
会場では心行くまでじっくりということができず、同時に早くここから脱出したいという気持ちとで葛藤しましたが、これから図録でじっくり味わいたいと思います。(本当なら図録を観てからもう一度観るのが贅沢。)
本館の仏像や陶磁なども観たかったのですが体力の限界で、そそくさと自転車で帰路につきました。


博物館を離れ、谷中の裏道の静けさの中で持参のお茶で一息。

旧・藍染川の流れだった道沿いに北上して田端のお不動様前。可愛い箱庭っぽくて楽しいと思いませんか。


霜降橋近辺の路地裏で見かけたおしろい花。黄色の花が混じっておらず、ピンクも淡い。あまり観たことがことがないので撮ってみました。昼抜きでお腹が空いていたので急いで赤羽まで戻って最近お気に入りの麻婆豆腐麺とハイボールで一杯やりました。