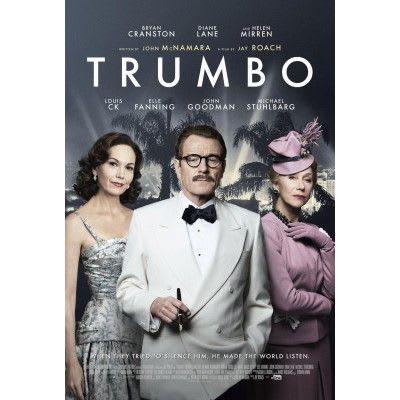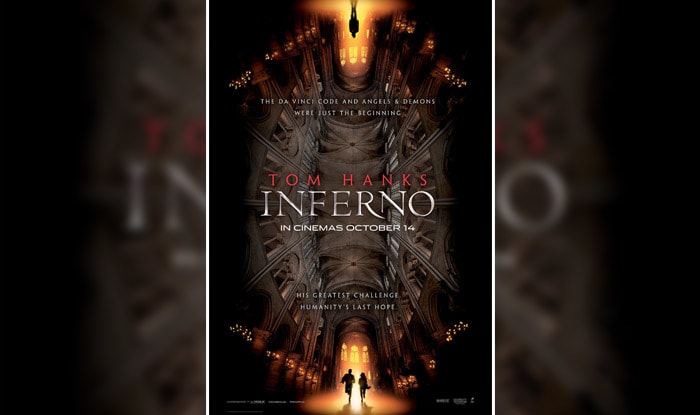
2015年版はこちら。
さあ年末調整。去年の今ごろは扶養控除申告書にマイナンバーをどう記載するかでおおもめでした。前任校でも収集にはそりゃあ苦労した。スマホにLINEで送られた画像を見せられもしたし(笑)。さて、それでは今年はどうなるかというと、基本的に
『マイナンバーの記載は必要ありません』
これはどういうことか。当初のイメージでは平成28年分の保険料控除申告書と住宅借入金等特別控除申告書については、今年からマイナンバーを記入する予定でした。実際に、平成26年に確定申告して住宅取得控除をうける人の申告書には、マイナンバーを記載する欄がちゃんともうけられています。それでも、記入しなくてかまいません。
扶養控除等申告書についてはきちんと記入する建前ですが、平成29年分からは、給与の支払者(わたしたちの場合は吉村美栄子さんです)が本人および扶養親族のナンバーをきちんと記録していれば書かなくてもいいことになったのです。吉村さんはどうやらちゃんと記録しています。
ぶっちゃけた話、マイナンバーについてはその管理がとてもたいへんなので批判が殺到したのでしょう。このままだと秘密を要する書類が年々増えていくところでしたから。
でも総務省の渋い顔が目に浮かびます。だって、霞が関が最も恐れているのは、この制度が住基ネットのように国民から忘れ去られてしまうことだからです。まるで鬼っ子のようなあつかいになっているマイナンバーの、明日はどっちだ。
ということであなたにやっていただくのは
◆去年記入した平成28年分扶養控除申告書の内容をチェックする。
◆平成28年分保険料控除申告書を記入する(証明書を忘れずに)。
◆住宅ローンがある人は、住宅借入金控除申告書を記入する。
◆平成29年分扶養控除申告書を記入する(マイナンバーは書かなくてもいい)。
事務室に11月25日(金)まで提出を。わかんなくなったら事務室で書け!
画像は「インフェルノ」(2016 SONY)主演:トム・ハンクス
ヨーロッパの名所旧跡をこれでもかと走り回るラングトン教授シリーズ第三弾。にしてもあんた抜け道とか隠れ扉とかを知りすぎてない?
「わたしは何も忘れない。」
たいへんですねえ。
2017年版につづく。