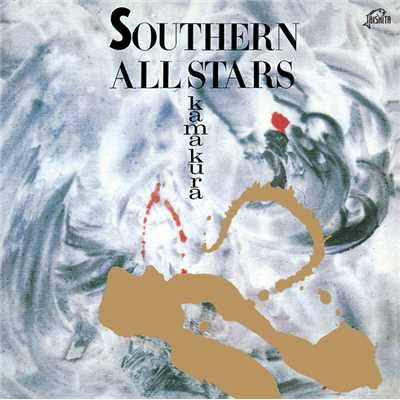夜のヒットスタジオ 1980年6月2日 YMO TECHNOPOLIS~RYDEEN (雷電)
その2はこちら。
さて、デビューアルバムは市場でどう評価されたか。
初回枚数は2800枚。当時でさえこの数字は、かなり控えめに言っても、あまり芳しいものではなかった。ちなみに同じ日にリリースされた坂本龍一のファースト・ソロ・アルバム「千のナイフ」の初回枚数は400枚。セールスの数字だけを見れば、彼らはいばらの道を歩き出した、と言ってもいい。
……確かに、リスナーにとってほとんどなじみのない、カテゴライズするとすれば現代音楽に近い音は業界人たちをも戸惑わせた。アルファはけっこう力を入れて広告をうっていたけどな。しかし、78年12月に紀伊國屋ホールで行われたアルファ・ミュージック・フェスティバルに“人数合わせ”で登場した彼らに来日したアメリカのプロデューサーは
「この中で売れるのはイエロー・マジック・オーケストラだけだ、このバンドはすごい」
と言い放った。その予言は的中。2枚目のアルバム「SOLID STATE SURVIVOR」は爆発的に売れることになった。A面の1曲目はこのようにして始まる。
♪TOKIO~♪
「テクノポリス」「ライディーン」「ビハインド・ザ・マスク」「デイ・トリッパー」などが含まれたこのアルバムは1979年9月25日リリース。幼稚園児までライディーンのメロディを口ずさんでいたものな。
藤井:(「テクノポリス」について)細野さんは坂本さんに、欧陽菲菲みたいな曲を書いてとオーダーしたそうです。ベンチャーズが作曲した(「雨の御堂筋」)みたいなことなんでしょうか。
……オーヤンフィフィ!お若い方たち、ついて来てね。しかしYMOの怖いところは、商業的に大成功したソリッド・ステイト・サバイバーと同傾向のアルバムを出すことはもうなかったということだ。以下次号。
本日は夜のヒットスタジオバージョン。うわー橋本一子さんなつかしー。