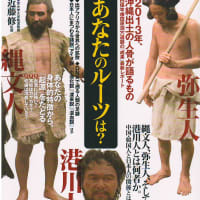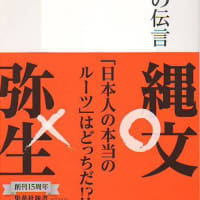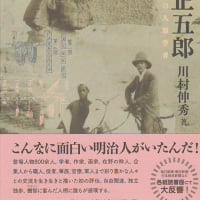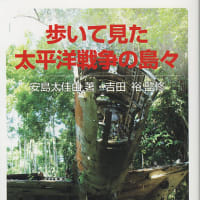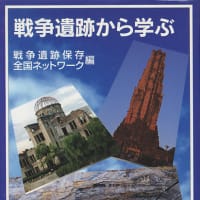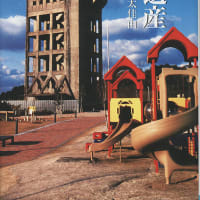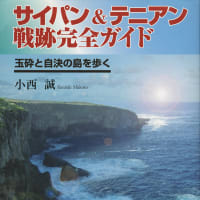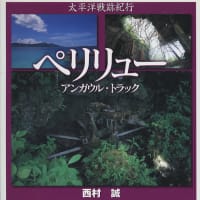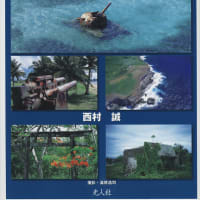アクア説は、別名アクア・エイプ説あるいは水生類人猿説とも呼ばれます。この学説は、ドイツのマックス・ヴェシュテンヘーファー(Max WESTENHOFER)[1871-1957]が1942年に唱え、1960年にイギリスのアリスター・ハーディー(Alister HARDY)[1896-1985]が唱え、1972年に作家のエレイン・モーガン(Elaine MORGAN)[1920-2013]が一般向けの本を書いたことで有名になった説です。
このアクア説は、初期人類の段階で海や川で進化したというものです。
マックス・ヴェシュテンヘーファー(Max WESTENHOFER)[1871-1957]
(経歴)
マックス・ヴェシュテンヘーファーは、1871年2月9日にドイツのニュールンベルグ近郊のアンスバッハで生まれました。やがて、ベルリン大学に入学し、著名な病理学者兼人類学者のルドルフ・ウィルヒョウ(Rudolf VIRCHOW)[1821-1902]に学び、1894年に卒業します。その後、1908年に南米のチリ大学医学部で病理学を教える機会があり、1911年までその地位に留まりました。この時、チリ政府はかなりの高額な報酬を払ったと言われています。ところが、1911年にチリの劣悪な健康状態や公衆衛生についてドイツの医学誌に論文を発表したため、チリから国外退去の宣告を受けました。
1911年にドイツに帰国すると陸軍で働き、1914年から1918年の第一次世界大戦では陸軍少佐として鉄十字勲章も受章しました。戦後、1922年、母校のベルリン大学の病理学教授に就任します。1929年には、再びチリに赴き、チリ大学医学部の病理学教授として活躍しました。チリ滞在中は、梅毒の研究も行っています。
1932年にドイツに帰国すると、一線からは引退します。その後、1939年から1945年の第二次世界大戦はヨーロッパを戦渦に巻き込みました。しかし、この時代に、ヴェシュテンヘーファーは次々と人類進化に関する本や論文を発表します。人類学への興味は、恐らく、ベルリン大学での師のルドルフ・ウィルヒョウの影響を受けたのでしょう。ところが、第二次世界大戦中に子供3人の内、2人までもが死亡してしまいます。
第二次世界大戦後の1948年、三度チリに渡り、病理学アドヴァイザーに就任します。1957年9月25日、ヴェシュテンヘーファーは、第二の故郷とも呼んだチリで86歳で死去しました。
(理論)
マックス・ヴェシュテンヘーファーは、1942年に『Der Eigenweg des Menschen』を出版しました。この本で、以下のように記載しています。
・人類の骨や内臓の構造は、樹上に適応した霊長類よりも哺乳類の原型に近い。恐らく、両生類のサンショウウオに近いと思われる。
・人類の耳の構造は、地中や水中に適応した哺乳類に似ており、特に水中生活をしているものに似ている。
・人類の脾臓や腎臓の構造は、クジラ・イルカ・アザラシ・ラッコ・クマに似ている。











![日本の人類学者51.小金井良精(Ryosei KOGANEI)[1859-1944]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0a/97/46d972234646556faff44f0f58d1bae6.jpg)