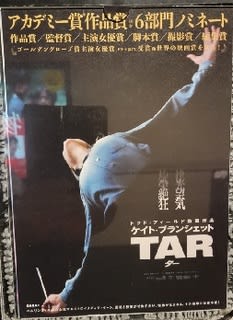(原題:Oromtriali)86年ソビエト作品。日本では劇場での一般封切りはされておらず、私は第2回の東京国際映画祭で観ている。グルジア共和国(現ジョージア)の映画人同盟書記であった女流監督ラナ・ゴゴベリーゼの手によるヒューマンドラマで、彼女はこの映画祭で最優秀監督賞を獲得。それを裏付けるように、作劇の密度は高い。
グルジアの首都トビリシで、かつての映画スターであるマナナと学者のルスダンの初老の女性2人が何十年かぶりで会うところから映画は始まる。別れた数分後、ルスダンは交通事故に遭い病院に担ぎ込まれる。マナナは予定していた撮影の仕事がキャンセルになり、金に困った彼女は昔からのファンであるゼネコン社長のアンドロから大金を借りる。
マナナの19歳の娘サロメは浪費癖のある母親を心配してその金を取り上げてアンドロに返そうとするが、チンピラのバドレに金を盗まれてしまう。一方ルスダンの入院先ではアンドロの若い愛人ナナが幼い娘アンナを残して世を去る。ルスダンを見舞いに来たマナナは病院でアンドロに再会。そしてアンナをめぐってルスダンとマナナ、アンドロとその妻ラウラの思惑が交錯する。
上映前の舞台挨拶でゴゴベリーゼ監督が“人の運命、性格、行為がもつれ合って織りなす人生というもの、そして各人の行為が他者に与える影響について、いつも興味を持っていた”と述べていたが、その言葉通り本作は各キャラクターの行為が他人と関わって別のエピソードを生み出すというような、鎖のような構成の上に成り立っている。しかも単なるオムニバス・ドラマではなく、各パートが互いに入り組んでいるため観客側でも想像力を働かせないと付いていけない。
この映画の大きなモチーフとも言えるのが、冒頭のルスダンでの研究室で映写されるフィルムだ。若い女がカメラに向かって何か切実に訴えている。しかし故意に音声を消しているのでしゃべっている内容は分からない。ルスダンはこの映像を同僚や学生に見せて、何を言っているのか予想してもらう。するとそれぞれ“求愛だろう”とか“相手の不実に対して怒っている”とか、勝手な見解を下す。
この画像は劇中で何度も繰り返されるが、ラスト近くにその内容が明かされる。すると画面の中の女性は、大方の見方とまったく異なることを訴えていたことが分かる。人と人とのコミュニケーションがいかにアテにならないものか、後半に無理解な大人たちに振り回される少女アンナを通じて作者が主張したかったことはこれだろう。だからこそコミュニケーションを積み上げる重要性がクローズアップされる。
ゴゴベリーゼの演出は観る者を完全に突き放したストイックなもの。愛想は無いが求心力は大きい。寒色系を活かした映像が場を盛り上げる。レイア・アバシゼにリア・エリアバ、グラム・ピルチュカラーバ、オター・メグビネトゥクチェシといったキャストも良い仕事をしている。




グルジアの首都トビリシで、かつての映画スターであるマナナと学者のルスダンの初老の女性2人が何十年かぶりで会うところから映画は始まる。別れた数分後、ルスダンは交通事故に遭い病院に担ぎ込まれる。マナナは予定していた撮影の仕事がキャンセルになり、金に困った彼女は昔からのファンであるゼネコン社長のアンドロから大金を借りる。
マナナの19歳の娘サロメは浪費癖のある母親を心配してその金を取り上げてアンドロに返そうとするが、チンピラのバドレに金を盗まれてしまう。一方ルスダンの入院先ではアンドロの若い愛人ナナが幼い娘アンナを残して世を去る。ルスダンを見舞いに来たマナナは病院でアンドロに再会。そしてアンナをめぐってルスダンとマナナ、アンドロとその妻ラウラの思惑が交錯する。
上映前の舞台挨拶でゴゴベリーゼ監督が“人の運命、性格、行為がもつれ合って織りなす人生というもの、そして各人の行為が他者に与える影響について、いつも興味を持っていた”と述べていたが、その言葉通り本作は各キャラクターの行為が他人と関わって別のエピソードを生み出すというような、鎖のような構成の上に成り立っている。しかも単なるオムニバス・ドラマではなく、各パートが互いに入り組んでいるため観客側でも想像力を働かせないと付いていけない。
この映画の大きなモチーフとも言えるのが、冒頭のルスダンでの研究室で映写されるフィルムだ。若い女がカメラに向かって何か切実に訴えている。しかし故意に音声を消しているのでしゃべっている内容は分からない。ルスダンはこの映像を同僚や学生に見せて、何を言っているのか予想してもらう。するとそれぞれ“求愛だろう”とか“相手の不実に対して怒っている”とか、勝手な見解を下す。
この画像は劇中で何度も繰り返されるが、ラスト近くにその内容が明かされる。すると画面の中の女性は、大方の見方とまったく異なることを訴えていたことが分かる。人と人とのコミュニケーションがいかにアテにならないものか、後半に無理解な大人たちに振り回される少女アンナを通じて作者が主張したかったことはこれだろう。だからこそコミュニケーションを積み上げる重要性がクローズアップされる。
ゴゴベリーゼの演出は観る者を完全に突き放したストイックなもの。愛想は無いが求心力は大きい。寒色系を活かした映像が場を盛り上げる。レイア・アバシゼにリア・エリアバ、グラム・ピルチュカラーバ、オター・メグビネトゥクチェシといったキャストも良い仕事をしている。