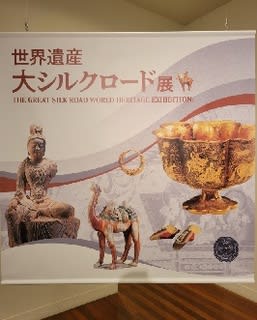2024年8月末をもって、鹿児島市鴨池2丁目にある大型商業施設“イオン鹿児島鴨池店”が閉店した。私は十代の頃に鹿児島市に何年か住んでいたことがあるが、この店に対しては個人的にちょっと思い入れがあり、今回営業を終えてしまったのは寂しさを感じる。たぶん私だけではなく、ある年代から上の鹿児島市民であれば何らかの感慨を抱くことだろう。
イオン鹿児島鴨池店の前身であるダイエー鹿児島ショッパーズ・プラザ(通称:鴨池ダイエー)がオープンしたのは1975年。それまで当地には大手ショッピングモールが無く、開店当時は大変な騒ぎだったという。我が家が鹿児島市に引っ越してきたのはそれから後の話だが、大きな吹き抜けが特徴のその店の垢抜けた出で立ちには驚いたものだ。

日曜日の午前中には、我が家では父親が運転する車で鴨池まで出掛けて行き、この店で食料品や日用品をまとめて仕入れることがルーティンになっていた。時には日用品等だけではなく、家電品やちょっとした外出着なども購入した。もちろん、鹿児島市は天文館などの中心地に行けば大抵のものは揃えられるのだが、この鴨池ダイエーでは店内だけで買い物が“完結”してしまうのが有り難かった。
そういえば、高校卒業時に大学の入学式に着るためのジャケットを親に買ってもらったのも、この鴨池ダイエーだった。また、クラスメートたちとの待ち合わせ場所にもよく利用したものだ。本当に懐かしい。
店の経営がダイエーからイオンに移ったのは2015年だが、その後も多くの市民の間では鴨池ダイエーという呼び名が一般的だったらしい。だが、近年は鹿児島市には別にショッピングモールが次々とオープンし、加えて建物の経年劣化も避けられず、このたび49年の歴史に幕を閉じた。跡地の利用は未定とのことだが、また新たな商業施設が建つのだろう。だが、その際にはエンタテインメントの要素もフィーチャーして、他店との差別化を図った仕様にして欲しいものだ。
イオン鹿児島鴨池店の前身であるダイエー鹿児島ショッパーズ・プラザ(通称:鴨池ダイエー)がオープンしたのは1975年。それまで当地には大手ショッピングモールが無く、開店当時は大変な騒ぎだったという。我が家が鹿児島市に引っ越してきたのはそれから後の話だが、大きな吹き抜けが特徴のその店の垢抜けた出で立ちには驚いたものだ。

日曜日の午前中には、我が家では父親が運転する車で鴨池まで出掛けて行き、この店で食料品や日用品をまとめて仕入れることがルーティンになっていた。時には日用品等だけではなく、家電品やちょっとした外出着なども購入した。もちろん、鹿児島市は天文館などの中心地に行けば大抵のものは揃えられるのだが、この鴨池ダイエーでは店内だけで買い物が“完結”してしまうのが有り難かった。
そういえば、高校卒業時に大学の入学式に着るためのジャケットを親に買ってもらったのも、この鴨池ダイエーだった。また、クラスメートたちとの待ち合わせ場所にもよく利用したものだ。本当に懐かしい。
店の経営がダイエーからイオンに移ったのは2015年だが、その後も多くの市民の間では鴨池ダイエーという呼び名が一般的だったらしい。だが、近年は鹿児島市には別にショッピングモールが次々とオープンし、加えて建物の経年劣化も避けられず、このたび49年の歴史に幕を閉じた。跡地の利用は未定とのことだが、また新たな商業施設が建つのだろう。だが、その際にはエンタテインメントの要素もフィーチャーして、他店との差別化を図った仕様にして欲しいものだ。