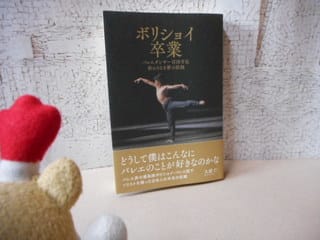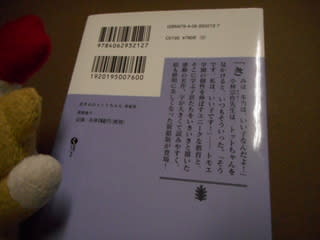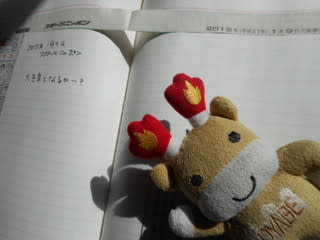時々、ふっと、胸の中に現れる存在。
人それぞれに、あるでしょうけども、
ミツコにとってのそれは、
小説「夢をかなえるゾウ」の「ガネーシャ」でっす。

豪放磊落で、いかなる場合でもユーモアを追求、
泣き虫な一面もあり、お供え物のあんみつに喜ぶ、「神様」。
キャラクターは、強烈ですが、
教えは、至極まっとう。
毎回の「課題」と、その根拠には、
うなずくばかりです。

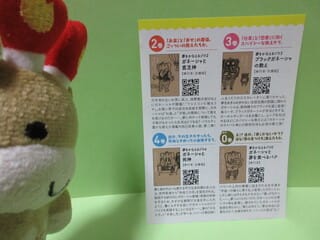
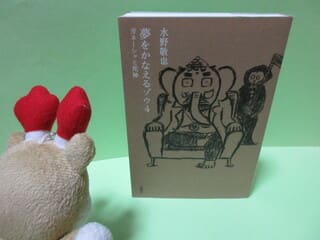
「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」
著者は、水野敬也さん。
挿画は、矢野信一郎さん。
サブタイトルにもあるように、
「死神」も登場。
今作のテーマは、重く、シビアなのですが、
不思議と、怖さはありません。
むしろ、あたたかみを感じさせてくれます。
そりもこりも、「死神」さんの、お人柄、
いや、お神柄によるところかしら。
「ガネーシャ」との力関係も、
なんともいえず、可笑しいのでっす。
登場人物(神々含む)を、近くに感じられる一冊。

ところで~。
ずうっと前、某所で購入した、
ガネーシャのステッカーでっす。


「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」
著:水野敬也
挿画:矢野信一郎
装丁:池田進吾(next door design)
ぜひ、手に取ってくださいますよう、お願いしますガネ
明日もがんばるぞ!
人それぞれに、あるでしょうけども、
ミツコにとってのそれは、
小説「夢をかなえるゾウ」の「ガネーシャ」でっす。

豪放磊落で、いかなる場合でもユーモアを追求、
泣き虫な一面もあり、お供え物のあんみつに喜ぶ、「神様」。
キャラクターは、強烈ですが、
教えは、至極まっとう。
毎回の「課題」と、その根拠には、
うなずくばかりです。

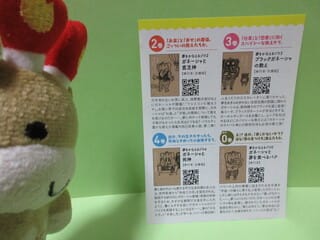
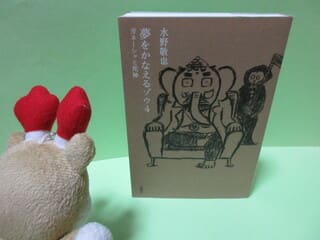
「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」
著者は、水野敬也さん。
挿画は、矢野信一郎さん。
サブタイトルにもあるように、
「死神」も登場。
今作のテーマは、重く、シビアなのですが、
不思議と、怖さはありません。
むしろ、あたたかみを感じさせてくれます。
そりもこりも、「死神」さんの、お人柄、
いや、お神柄によるところかしら。
「ガネーシャ」との力関係も、
なんともいえず、可笑しいのでっす。
登場人物(神々含む)を、近くに感じられる一冊。

ところで~。
ずうっと前、某所で購入した、
ガネーシャのステッカーでっす。


「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」
著:水野敬也
挿画:矢野信一郎
装丁:池田進吾(next door design)
ぜひ、手に取ってくださいますよう、お願いしますガネ
明日もがんばるぞ!