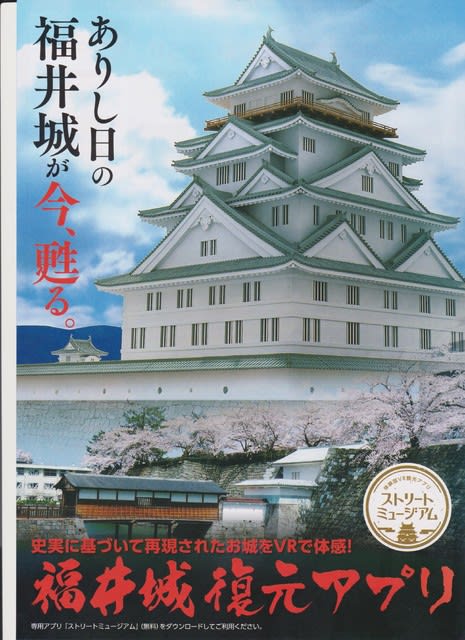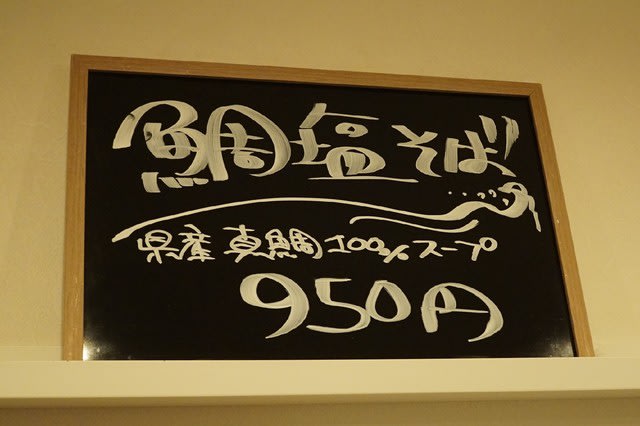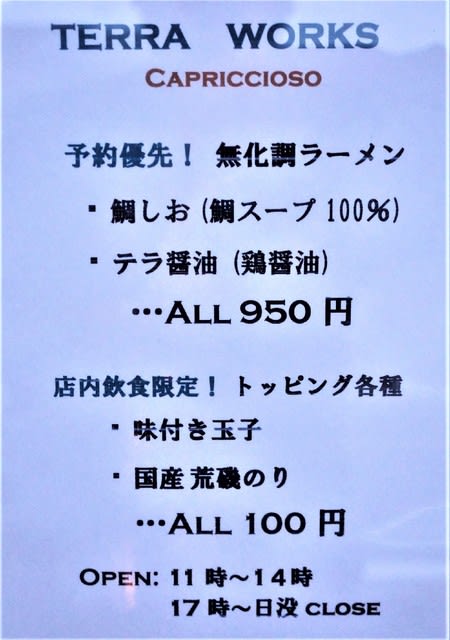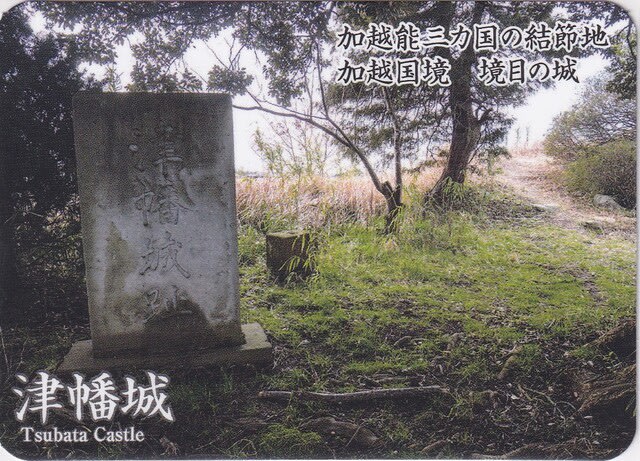お城検索→
こちら
いしかわ城郭カード→
こちら
石川県史跡【末森城】
歴史上「末森」の名前が現れるのは、上杉謙信が七尾城攻めの時に「春日山にあてた手紙」の中に書かれているものが最も古い記録です。江戸末期から明治時代に書かれた書物には、上杉謙信より前の時代にも城があったとする記録も見受けられますが証明できる文書は見つかっていません。
末森山を含む周辺での発掘調査から、旧石器時代から近世までの遺物が出土しており、古くから人々の活動の場であったことが伺われます。
山城としての活動時期は、出土品から14世紀から16世紀初めころ推定されています。全国の中世期の山城と同じく「一国一城令」で破却されたと考えられています。
この城に足を踏み入れた加賀藩主は、前田利家公・利長公の父子と、幕末の第13代前田斉泰公だけです。
、、、宝達志水町教育委員会、同埋蔵文化センター
金沢から羽咋へ延びるR159から「末森城跡」の標識と「駐車場」の案内通り脇道へ入ると「第1駐車場」がある。
ここには貨車を改造した奇麗なトイレとイラストマップの案内看板が設置されています。

ここから徒歩で進みます。

ところがこの先「第2駐車場」があったりして、車で来ればよかったと後悔してはいけません(笑)
ここにはパンフレット置き場と、俯瞰イラストの案内板が設置されています。

この先R159に架かる陸橋を渡り、登城口に向かいます。

陸橋の下を走るR159金沢方向

橋詰には「末森城跡」の大きな看板と「史跡末森山古戦場碑」、「NHK大河放映記念碑」、「前田家当主の碑文」が設置されています。

ここからは曲輪跡などの遺構を訪ねる訳ですが、
第1駐車場に設置してある「イラストマップ」
(※矢印、〇印、黒色の文字は筆者記入)

第2駐車場に設置してある「俯瞰図」

同じく宝達志水町作成のパンフレットにある「縄張り図」
(※矢印、〇印、黒色の文字は筆者記入)

これら3点の資料中「曲輪の名称」「位置表示」に統一性がなく、また現地における説明・案内看板が無いに等しく、初心者の自分には分かりにくかったのが非常に残念でした。
一番信頼度の高い町作成の「縄張り図」を頼りに歩きましたが
「大手門」の場所が分かりません。
現地に案内板がなく、イラストマップでは「三の丸」手前となっているし、、、(;^ω^)
やはりイノシシの被害が多いようで途中罠が仕掛けられていました。

大手道でしょうか?城跡までの遊歩道は整備され凄く歩きやすいです。
◆この辺りが「大手門」でしょうか?

◆「ササラ城戸」
これも現地に案内板が無く確信はありません。
両脇が切り立ち道幅が狭いので敵の侵入を抑制する工夫のようにも感じます。

◆「武家屋敷跡」
イラストマップにはあるが縄張り図には記載されていない曲輪
明らかに人工的な平坦面が数段にわたって広がっています。

最上段から下段部を見下ろした全体図
現在は植林地となっており、周囲は害獣の侵入を防ぐ竹笹の柵が巡らされている。

土塁?

空堀でしょうか?

◆武家屋敷から若宮に至る歩道を軽トラ軍団が占拠!
町からの以来でしょうか?除草作業が行われていました。
夏草の伸びるのは早く除草作業は大変ですが、そのおかげで遺構が見やすく歩きやすく、しっかり管理されているのがありがたいですね。

◆「若宮丸」
本丸方向から下ってきた町の職員。史跡紹介のTVクルーと鉢合わせとなったので一旦回避します。

◆「大手大門跡」
縄張り図には無く、イラストマップに記載アリ。但し現地に案内板が無いので詳細不明。
若宮丸から三の丸に至る土塁で挟まれた大手道辺りにあったのでしょうか? 確信はありません。

◆「三の丸」
どちらの資料もピンポイントで示されていないうえ、現地案内板が無いので非常に曖昧です。
大手道を挟んで左右に分かれた曲輪と、本丸に向かって数段に渡って広がる曲輪が混在し、明確な区分けが付きにくかったです。
本丸に向かって右手にある平坦地。左手の「二の丸下段」と思われる台地から見たところ。
これが三の丸と思われますが現地案内板が無いので確信はありません。

同平坦地

◆「二の丸」
大手道、本丸に向かって左手の平坦地、下段

同平坦地
ここにも現地案内板が無いので、二の丸下段なのか三の丸なのか確信がありません。

同空堀

二の丸上段への登り口(土橋?)

二の丸標識

二の丸平坦地、
西側に日本海が広がる

◆「本丸」
前田家第18代当主前田利祐記念植樹
古戦場石碑脇にある碑文と一体のもの

金属プレートの説明版と千畳敷平坦地

西側の端からは城下町と日本海が一望できる。

本丸北側の先端部
主郭から一段下がっており搦手門に至るはずだが

先端部は崖となっており、一旦迂回すると脇道があるものの整備されていないので危険。

◆ここから先へは進めないと判断し帰路に就く
途中三の丸から若宮丸に至る道で「本丸へ」という標識の脇に小路を発見!
これ、絶対見逃します!

搦手門に至る路と思い進んでみました。
するとどうでしょう♪
その先には平坦地が広がっているではありませんか♪

◆「馬掛場」
これもイラストマップにはあるが縄張り図には記載されていない曲輪。現地案内板が無いですが確信はあります。

三の丸の下辺りに隠れるように配置された曲輪
軍事施設なのか居住空間なのかは不明
見上げる方向に三の丸の高台

◆「若宮丸」
往路で一旦回避したので復路で立ち入りました。
若宮丸の標識

大手道から若宮丸平坦地に至る土橋
狭くて急な登り、脇は崖となっている。

土橋を上り詰めると平坦地が広がる

反対側から

曲輪先端部からは「若宮」が連なるそうだが、下におりる道は整備されていない。

◆末森城の戦い
押水の地は能登の中でも最大の荘園でした。
この「大泉庄」は宝達山系と海岸線が最もせばまった地形にあり、古くから加賀・能登・越中へ通じる交通の要となっていました。
越中の佐々成征は加賀と能登を分断し、前田氏の戦力を弱めるのに最も適した末森城を手にしようとしたのです。
、、、中略
前田軍の奇襲により佐々軍は退却
、、、中略
個の戦い以降、前田利家は勢力を越中にまで伸ばしますが、末森合戦こそ前田方が加賀・能登・越中三国を支配するきっかけとなったのです。
、、、宝達志水町教育委員会

※2022年6月12日 お城検索、いしかわ城郭カードリンク、写真追加
【末森城】
《末森城の戦い以降成政は守勢に転じ、前田利家は領国の防衛に成功し小牧・長久手の戦いで政治的勝利を収めた羽柴秀吉と協力し攻勢を強めていく》


名称(別名);末盛城、末守城
所在地;石川県羽咋群宝達志水町竹生野
城地種類;連郭式山城
築城年代;不明
築城者;土肥親真?
主な城主;土肥氏、斎藤氏(上杉)奥村氏(前田)
文化財区分;石川県指定史跡
近年の主な復元等;
天守の現状、形態;なし、土塁、曲輪跡
地図;
※出典、、、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


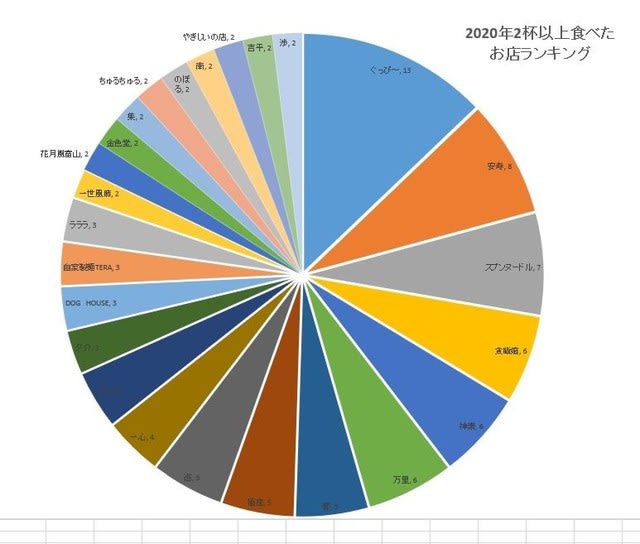


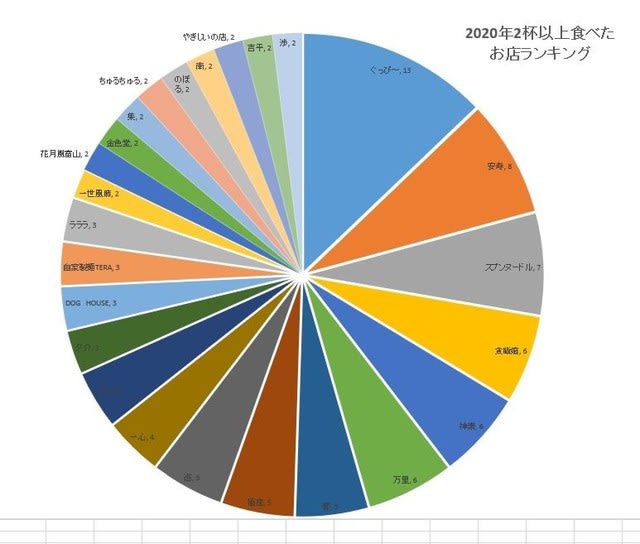











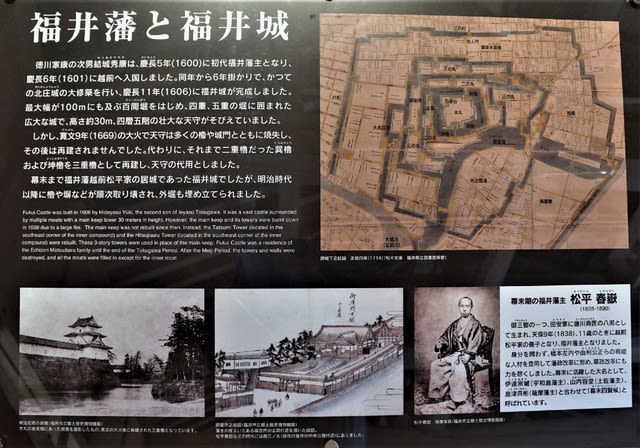 、、、櫓門資料館展示
、、、櫓門資料館展示