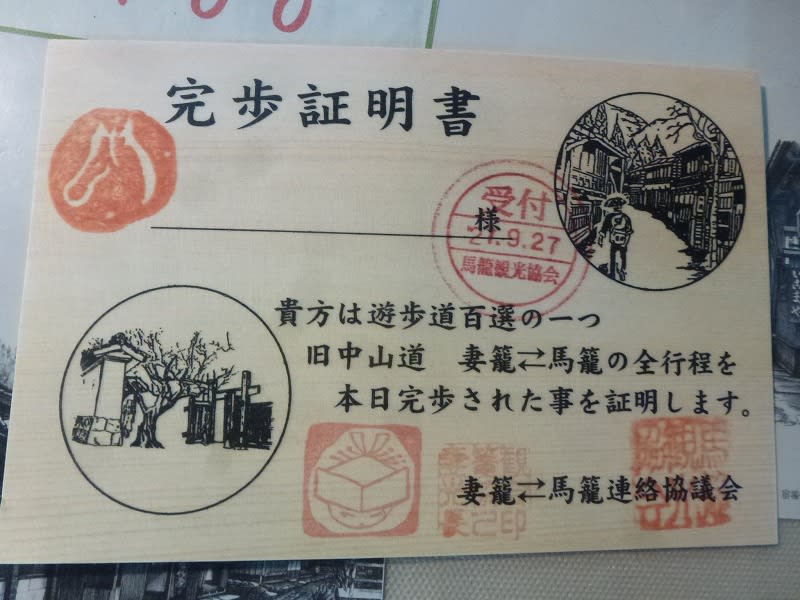2016年2月28日(日)
ある旧街道全ての区間を歩くのは、時間的にも資金的にも厳しいため、
昨年から、旧街道の中でも交通の便が良く、見所が比較的多いとされる宿場間を選んで歩いている。
ある街道の中から気に入った宿場間を選んで歩くというものである。
「旧街道を歩く」第十回目は、中山道の板橋宿~蕨宿間(約9.6Km)を歩いた。
日本橋~板橋宿間は、第一回目の2015年1月25日に歩いているので、その続きとなる。
この日のスタートは、板橋宿のため、日暮里から山手線に乗り換え、
さらに巣鴨から都営三田線に乗り換え、板橋区役所前で下車。
この日の参加者は5名とやや寂しい人数だ。

都営三田線板橋区役所前駅

首都高中央環状線に沿って少し戻り、板橋宿入口(江戸寄り)へ向かう。

9時10分、見覚えのある板橋宿平尾宿入口に到着。
板橋宿は江戸寄りから平尾宿・仲宿、「板橋」から京寄りを上宿と云う。
ここがこの日のスタート地だ。

不動通り商店街を進む。

9時13分、如意山観明寺に到着
観明寺は、真言宗豊山派の寺院で室町時代の創建と伝わる。

寺の境内に入って直ぐ左手に寛文元年(1661)の庚申塔がある。
青面金剛像が彫られたものとしては、都内最古だそうで、
昭和58年度に板橋区の指定有形文化財となっている。

観明寺の赤門
加賀藩下屋敷から遷されたと云われる。
もと加賀屋敷の通用門だった。

この稲荷神社は、もと加賀藩下屋敷内に祀られていた三稲荷の内の一社で、
明治になって陸軍造幣廠が建設された際、観明寺に遷座された。

観明寺の本尊は正観世音菩薩
脇本尊は不動明王で、通称「出世不動」と呼ばれ親しまれている。

本堂前に聳える桜の大木は、板橋区の保存樹木である。
『桜が咲くと見事だろうなぁ』
あと1か月もすれば見頃になるだろう。

まん丸い顔をした六地蔵が目を引く。
『可愛らしいけど何だかお地蔵さまのありがたみが感じられないよねっ』

平尾町脇本陣の入口表示

細い路地を50mほど入って行くと、

「板橋宿平尾町脇本陣」の碑があった。
板橋平尾宿の脇本陣豊田家の屋敷跡で、豊田家は代々市右衛門を世襲し、名主も兼ねていた。
近藤勇が処刑されるまでの間ここに幽閉され、また、江戸時代に見世物となったペルシャ産のラクダが
逗留したこともある、とのこと。

「板橋三丁目の縁宿広場」の中山道の宿場情報に見入る。
『中山道を全部歩くのは大変だよねっ』

「いたばし観光センター」で何か情報が得られるかも・・・

係の方が親切・丁寧に教えてくれた。
また、板橋のパンフをたくさんいただいた。

江戸時代から板橋宿の名所として名高かった初代の「縁切り榎」
榎は本来、縁結びの木として知られていたものが、板橋の榎は縁を切る木として、
特に離縁を願う女性たちの信仰対象となったのだと云う。

縁切り榎の図
『随分でかい木だったんだぁ』

前田家下屋敷の図
江戸時代に成立した参勤交代制度により、各大名に対しては、将軍より屋敷地が下賜された。
加賀藩前田家は本郷邸を上屋敷、駒込邸を中屋敷、板橋宿に面する平尾邸を下屋敷に定めている。
上屋敷は藩主と家族が住む公邸に、中屋敷は隠居した藩主などの住居に利用された。
下屋敷の平尾邸は、約21万8千坪に及ぶ広大な敷地があり、尾張・紀伊・水戸の徳川御三家を含めて、
江戸に所在する大名屋敷では最大の広さを持つ屋敷だった。
邸内には石神井川が流れ、その水流と千川用水の配水を利用した大池が設けられ、
築山や立石、滝などが各所に配された池泉回遊式庭園が展開していた。
その規模は本国金沢にある有名な大名庭園兼六園の約7倍の広さがある。
現在、平尾邸の面影は、わずかに加賀公園に残る築山の一部だけとなっている、とのこと。

王子新道で平尾宿が終わるが、その先には仲宿が続いている。

案内には、
これより仲宿商店街、日本橋より二里二十九町九間(十粁五十二米)と書かれていた。

仲宿商店街には、古い家も残っており、昔を偲ぶことが出来る。

日本橋からの距離を尺貫法で表示している和菓子屋。
なかなか粋で趣がある。

板橋宿本陣跡
旧中山道の板橋宿本陣跡の碑が、スーパー「ライフストア」手前の民家脇に立てられていた。
代々新左衛門を世襲した本陣飯田家の屋敷跡である。
(うっかり見落としてしまい、「板橋」から引き返して撮った)

その向かいには、幕末の異国船打ち払い令を批判し、弾圧を受けた幕末の蘭学者、
高野長英をかくまったという彼の門人水村玄洞宅(現在は石神医院)がある。

10時13分、「板橋」に到着
「板橋」という地名の由来となった旧石神井川に架かる橋。
江戸時代の板橋は木造の太鼓橋で、長さは9間(16.2m)、幅3間(5.4m)だった。

鎌倉から室町時代の古文書にすでにこの名が見え、江戸時代になると宿場の名となった。
板橋宿は江戸寄りから平尾宿・仲宿、そしてこの橋から京寄りを上宿と云い、
地誌「江戸名所図絵」ではこの橋の周辺が最も賑っていたらしい。

かつての石神井川は、南側に大きくV字状に回り込んでいたため、
昭和47年(1972)の河川改修で直線化し、新しい石神井川に造り替えられ、
現在は遊歩公園になっている。

新石神井川に架かる新しい「板橋」

現在の石神井川

交番の脇の角地に上宿の碑が建てられている。

板橋宿上宿の碑

旧中山道上宿を進む。

縁切り榎
嫁入りの際には縁が短くなることを恐れて、この木の下を通らなかったとか。
幕末、皇女和宮が中山道を下って将軍家茂に降嫁する折もこの榎を避けるように迂回路が造られた。
近代以降は難病との縁切という信仰も広がり、板橋宿の名所となっている。
現在の榎は三代目

榎の一部がコンクリで固められて保存されている。

縁切り榎の神様も祀られている。

10時24分、環七通りを通過。

環七通りを過ぎると商店街も終わり、高層マンションが目立つようになってきた。

首都高5号池袋線と合流し、

しばらく中山道(国道17号)を進むと、

10時44分、南蔵院に到着した。
南蔵院は、江戸時代初期に創建されたと伝わる真言宗智山派の寺院で、
八代将軍徳川吉宗の鷹狩りの際の御膳所(休憩所)だった。

境内には、六地蔵の他に、地蔵菩薩や、

地蔵堂がある。

境内の地蔵には、承応二年(1653)に旧蓮沼村の庚申講中の十人によって建立された、
板橋区内で確認されている203基の庚申塔の中でも二番目に古いとされる、
丸彫り地蔵の庚申地蔵(庚申塔)がある。
江戸時代に地蔵が庚申信仰の礼拝対象であったことを示す代表的な例としても貴重、
ということで、板橋区登録有形民俗文化財(信仰)に指定されている。

南蔵院は、真言宗智山派で、寶勝山蓮光寺と号する。(本尊は十一面観音)
たび重なる荒川の洪水のために、江戸期に坂下二丁目より現在地に移ったと伝えられている。

10時55分、中山道(国道17号)小豆沢バス停を通過。

11時3分、志村一里塚に到着
徳川家康は慶長九年(1604)に諸国の街道に一里塚の設置を命じた。
志村一里塚は、日本橋から数えて3番目の一里塚で、5間(約9m)四方、
高さ1丈(約4m)の塚が道を挟んで2基ずつ築かれた。

志村一里塚は、新中山道整備の際、周囲に石組がなされて保全され、今日に至っている。
都内で現存する一里塚は日光御成道にある西ヶ原一里塚とここだけ、だそうだ。
道路反対側の一里塚

志村一里塚を後にしてさらに進むと、清水坂の手前に富士大山道標と庚申塔がある。
中山道と富士大山道の分岐点に立ち、道標は寛政四年(1792)、庚申塔は安政七年(1860)に
それぞれ志村講中によって建立されたもの。

富士大山道標と庚申塔の先から中山道で最初の難所とされた急勾配である清水坂に入る。

日本橋を発って最初の難関がこの清水坂と云われた。
中山道で唯一富士山の姿を右手に一望できる名所でもあった。

今でもきれいに舗装されたこの板を上るのは息が切れるが、
荷駄を引く牛馬は大変な思いをしたと思われる。

坂の下には板橋と蕨を繫ぐ合の宿があり、茶屋などがあって、この先、
荒川を渡る戸田の渡しが増水で利用できない場合の溜まりの場所としていた。

埼京線線路を潜った先辺りが、合の宿があった所だ。
合の宿は、宿場と宿場のほぼ真ん中に位置する休憩を目的とする施設で、旅籠などの宿泊施設はなかった。、

埼京線線路の先で再び中山道(国道17号)へ合流。

中山道(国道17号)を横断し、反対側へ。

11時46分、三軒屋バス停を通過

11時51分、新河岸川を通過

荒川手前の船渡交差点を右折し、

埼京線・東北上越新幹線の下を通り抜け、150mほど先を左折すると、荒川土手が見える。

荒川土手に上がると・・・

12時6分、荒川だ。
戸田橋を渡ると埼玉県(戸田市)である。

右手の高層ビル群は川口市か?

土手に腰を下して一休み。
『いやぁ 天気が良くて気持ちが良いねぇ』

荒川土手に「戸田の渡し場」の碑が立っている。
荒川には、明治八年(1875)まで橋が無く、舟によって人や物資の運搬を行っていた。
洪水で利用できない時には、合の宿で待機したり、下流の奥州道中の千住大橋へ迂回することもあった。

「戸田の渡し場」は、戸田河岸と呼ばれ、荒川下流から塩・砂糖・雑貨がここで降ろされ、
大根や漬物などこの地の特産物などがここから積み込まれて下っていった物流の基地だった。
対岸の戸田村の名前をとって「戸田の渡し場」と呼ばれた。

12時27分、戸田橋を渡る。

新幹線・埼京線が頻繁に走り抜ける。

橋を渡り切った橋の袂に「歴史のみち 中山道」の案内があった。

案内に従って「歴史のみち」へ行ってみると、

案内されていた地蔵堂があった。
創立は不明だが、戸田市内最古の木造建造物とのこと。

地蔵堂の前に享保十六年(1731)銘が入った青面金剛像の庚申塔がある。
板橋宿の観明寺にあった庚申塔とよく似ている。

「歴史のみち」を進むと、

菖蒲川に突き当たった。
『うわっ 随分濁ってるねぇ』
『気分が悪くなりそうっ』
上流側は戸田競艇場に繋がっていると思われるが・・・

菖蒲川に架かる川岸橋を渡る。

中山道(国道17号)を一つ入った裏通りを歩いていたが、食べ物屋が見つからないので、

中山道(国道17号)に出てみると、幸楽苑があった。
時刻は間もなく13時になろうとしている。
『ラーメンでも食べて行こうっ!』で意見が一致。

この店のラーメンは早くて安いし、こういう時にはうってつけだ。

食事も終わり、再び蕨宿を目指す。

14時8分、蕨市に入った。

14時12分、木戸風の蕨宿標柱が現れた。
戸田の渡しで荒川を渡ってからの旧道は、大半が失われてしまっているが、
ここから先の蕨宿本陣までは、旧街道の面影が残されている。

日本橋から中山道全69宿場の浮世絵図が道の両側に描かれていた。

蕨市立歴史民俗資料館分館
かつて蕨市長だった金子吉衛夫妻没後、蕨市が譲り受け、2003年より一般公開された家屋敷。
(入館無料)

金子家は、明治時代に織物の買継商をしていた。
旧中山道と国道17号の間にあり、敷地面積は516坪と広い。

国道側は庭園になっている。

蕨市立歴史民俗資料館
蕨市の歴史と文化の特色である宿場および織物に関する情報を中心に展示している。
常設コーナー「街道と宿場」は見ておきたい。
(入館無料)

この庚申塔は、寛政四年(1792)に建てられたもので、
正面には青面金剛像・邪鬼・三猿が浮き彫りにされている。
板橋宿の観明寺と戸田の渡しの地蔵堂で見たものと同じだ。

旅籠の様子

江戸時代後期の蕨宿中心部の町並みを再現した模型。
本陣2軒と脇本陣1軒からなる宿場の様子が手に取るように分かる。
(手前が板橋宿方面)

本陣(岡田加兵衛家)の模型
蕨宿本陣は、岡田加兵衛家と岡田五郎兵衛家の2家が代々勤め、
宿場の中央に中山道を挟むように向かい合わせで建っていた。
両家とも門構え・玄関付の屋敷で、加兵衛家跡に蕨宿本陣跡の碑が立っている。

織物
江戸時代末期から、蕨では綿織物業が盛んになり、文政年間(1818~1830)塚越村の5代目高橋新五郎は、
青縞を織って江戸に売り出した。(以下略)

蕨市立歴史民俗資料館の隣に蕨宿本陣跡があった。

蕨宿本陣は、公家・大名などが休泊し、文久元年(1861)皇女和宮が御降嫁の折には、御休息の場となり、
ついで、明治元年(1868)同三年には、明治天皇の大宮氷川神社御親拝の際の御小休所となった。

蕨宿を利用した藩と禄高が展示されていた。
102万石の加賀金沢藩を筆頭に、尾張名古屋藩61万石、紀伊和歌山藩59万石と続き、
下野足利藩1万石まで、20の藩が利用したことになっている。

この日のゴールは、蕨宿本陣までのため、この後京浜東北線の蕨駅へ向かうことにした。
14時56分、蕨市役所前を通過。

JR蕨駅を目指す。

和楽備神社があったので、立寄ってみることに。

和楽備神社本殿
社伝によると、室町時代に蕨を所領とした足利将軍家の一族、
渋川氏が蕨城築城の折、八幡神を祀ったのが最初とされる。

江戸時代には蕨八幡と呼ばれ、明治44年に町内18社を合祀して和楽備神社と改称した。
合祀後の神社名に、祭神名(八幡神)を取ることは、各集落とも承服しない状況であり、
蕨一字では尊厳味がないので、岡田健次郎元町長の知人本居豊穎に依頼し、
万葉仮名から取って、和樂備神社と命名した、とのこと。
本殿にお参りし、この日の無事を報告した。

JR京浜東北線蕨駅

15時23分、蕨駅改札口に到着
『今日は大変お疲れさまでしたぁ』

中山道の板橋宿~蕨宿間約9.6Kmを歩き終わった。
道中見どころもたくさんあり、良い天気に恵まれて一日楽しく歩くことが出来た。
今回でいったん中山道は終わるが、今後も面白そうな宿場を見つけて歩いてみたい。
この日の万歩計は、23,000歩を越えていた。
ウマさんの「旧街道(特選)を歩く」目次に戻る。
ある旧街道全ての区間を歩くのは、時間的にも資金的にも厳しいため、
昨年から、旧街道の中でも交通の便が良く、見所が比較的多いとされる宿場間を選んで歩いている。
ある街道の中から気に入った宿場間を選んで歩くというものである。
「旧街道を歩く」第十回目は、中山道の板橋宿~蕨宿間(約9.6Km)を歩いた。
日本橋~板橋宿間は、第一回目の2015年1月25日に歩いているので、その続きとなる。
この日のスタートは、板橋宿のため、日暮里から山手線に乗り換え、
さらに巣鴨から都営三田線に乗り換え、板橋区役所前で下車。
この日の参加者は5名とやや寂しい人数だ。

都営三田線板橋区役所前駅

首都高中央環状線に沿って少し戻り、板橋宿入口(江戸寄り)へ向かう。

9時10分、見覚えのある板橋宿平尾宿入口に到着。
板橋宿は江戸寄りから平尾宿・仲宿、「板橋」から京寄りを上宿と云う。
ここがこの日のスタート地だ。

不動通り商店街を進む。

9時13分、如意山観明寺に到着
観明寺は、真言宗豊山派の寺院で室町時代の創建と伝わる。

寺の境内に入って直ぐ左手に寛文元年(1661)の庚申塔がある。
青面金剛像が彫られたものとしては、都内最古だそうで、
昭和58年度に板橋区の指定有形文化財となっている。

観明寺の赤門
加賀藩下屋敷から遷されたと云われる。
もと加賀屋敷の通用門だった。

この稲荷神社は、もと加賀藩下屋敷内に祀られていた三稲荷の内の一社で、
明治になって陸軍造幣廠が建設された際、観明寺に遷座された。

観明寺の本尊は正観世音菩薩
脇本尊は不動明王で、通称「出世不動」と呼ばれ親しまれている。

本堂前に聳える桜の大木は、板橋区の保存樹木である。
『桜が咲くと見事だろうなぁ』
あと1か月もすれば見頃になるだろう。

まん丸い顔をした六地蔵が目を引く。
『可愛らしいけど何だかお地蔵さまのありがたみが感じられないよねっ』

平尾町脇本陣の入口表示

細い路地を50mほど入って行くと、

「板橋宿平尾町脇本陣」の碑があった。
板橋平尾宿の脇本陣豊田家の屋敷跡で、豊田家は代々市右衛門を世襲し、名主も兼ねていた。
近藤勇が処刑されるまでの間ここに幽閉され、また、江戸時代に見世物となったペルシャ産のラクダが
逗留したこともある、とのこと。

「板橋三丁目の縁宿広場」の中山道の宿場情報に見入る。
『中山道を全部歩くのは大変だよねっ』

「いたばし観光センター」で何か情報が得られるかも・・・

係の方が親切・丁寧に教えてくれた。
また、板橋のパンフをたくさんいただいた。

江戸時代から板橋宿の名所として名高かった初代の「縁切り榎」
榎は本来、縁結びの木として知られていたものが、板橋の榎は縁を切る木として、
特に離縁を願う女性たちの信仰対象となったのだと云う。

縁切り榎の図
『随分でかい木だったんだぁ』

前田家下屋敷の図
江戸時代に成立した参勤交代制度により、各大名に対しては、将軍より屋敷地が下賜された。
加賀藩前田家は本郷邸を上屋敷、駒込邸を中屋敷、板橋宿に面する平尾邸を下屋敷に定めている。
上屋敷は藩主と家族が住む公邸に、中屋敷は隠居した藩主などの住居に利用された。
下屋敷の平尾邸は、約21万8千坪に及ぶ広大な敷地があり、尾張・紀伊・水戸の徳川御三家を含めて、
江戸に所在する大名屋敷では最大の広さを持つ屋敷だった。
邸内には石神井川が流れ、その水流と千川用水の配水を利用した大池が設けられ、
築山や立石、滝などが各所に配された池泉回遊式庭園が展開していた。
その規模は本国金沢にある有名な大名庭園兼六園の約7倍の広さがある。
現在、平尾邸の面影は、わずかに加賀公園に残る築山の一部だけとなっている、とのこと。

王子新道で平尾宿が終わるが、その先には仲宿が続いている。

案内には、
これより仲宿商店街、日本橋より二里二十九町九間(十粁五十二米)と書かれていた。

仲宿商店街には、古い家も残っており、昔を偲ぶことが出来る。

日本橋からの距離を尺貫法で表示している和菓子屋。
なかなか粋で趣がある。

板橋宿本陣跡
旧中山道の板橋宿本陣跡の碑が、スーパー「ライフストア」手前の民家脇に立てられていた。
代々新左衛門を世襲した本陣飯田家の屋敷跡である。
(うっかり見落としてしまい、「板橋」から引き返して撮った)

その向かいには、幕末の異国船打ち払い令を批判し、弾圧を受けた幕末の蘭学者、
高野長英をかくまったという彼の門人水村玄洞宅(現在は石神医院)がある。

10時13分、「板橋」に到着
「板橋」という地名の由来となった旧石神井川に架かる橋。
江戸時代の板橋は木造の太鼓橋で、長さは9間(16.2m)、幅3間(5.4m)だった。

鎌倉から室町時代の古文書にすでにこの名が見え、江戸時代になると宿場の名となった。
板橋宿は江戸寄りから平尾宿・仲宿、そしてこの橋から京寄りを上宿と云い、
地誌「江戸名所図絵」ではこの橋の周辺が最も賑っていたらしい。

かつての石神井川は、南側に大きくV字状に回り込んでいたため、
昭和47年(1972)の河川改修で直線化し、新しい石神井川に造り替えられ、
現在は遊歩公園になっている。

新石神井川に架かる新しい「板橋」

現在の石神井川

交番の脇の角地に上宿の碑が建てられている。

板橋宿上宿の碑

旧中山道上宿を進む。

縁切り榎
嫁入りの際には縁が短くなることを恐れて、この木の下を通らなかったとか。
幕末、皇女和宮が中山道を下って将軍家茂に降嫁する折もこの榎を避けるように迂回路が造られた。
近代以降は難病との縁切という信仰も広がり、板橋宿の名所となっている。
現在の榎は三代目

榎の一部がコンクリで固められて保存されている。

縁切り榎の神様も祀られている。

10時24分、環七通りを通過。

環七通りを過ぎると商店街も終わり、高層マンションが目立つようになってきた。

首都高5号池袋線と合流し、

しばらく中山道(国道17号)を進むと、

10時44分、南蔵院に到着した。
南蔵院は、江戸時代初期に創建されたと伝わる真言宗智山派の寺院で、
八代将軍徳川吉宗の鷹狩りの際の御膳所(休憩所)だった。

境内には、六地蔵の他に、地蔵菩薩や、

地蔵堂がある。

境内の地蔵には、承応二年(1653)に旧蓮沼村の庚申講中の十人によって建立された、
板橋区内で確認されている203基の庚申塔の中でも二番目に古いとされる、
丸彫り地蔵の庚申地蔵(庚申塔)がある。
江戸時代に地蔵が庚申信仰の礼拝対象であったことを示す代表的な例としても貴重、
ということで、板橋区登録有形民俗文化財(信仰)に指定されている。

南蔵院は、真言宗智山派で、寶勝山蓮光寺と号する。(本尊は十一面観音)
たび重なる荒川の洪水のために、江戸期に坂下二丁目より現在地に移ったと伝えられている。

10時55分、中山道(国道17号)小豆沢バス停を通過。

11時3分、志村一里塚に到着
徳川家康は慶長九年(1604)に諸国の街道に一里塚の設置を命じた。
志村一里塚は、日本橋から数えて3番目の一里塚で、5間(約9m)四方、
高さ1丈(約4m)の塚が道を挟んで2基ずつ築かれた。

志村一里塚は、新中山道整備の際、周囲に石組がなされて保全され、今日に至っている。
都内で現存する一里塚は日光御成道にある西ヶ原一里塚とここだけ、だそうだ。
道路反対側の一里塚

志村一里塚を後にしてさらに進むと、清水坂の手前に富士大山道標と庚申塔がある。
中山道と富士大山道の分岐点に立ち、道標は寛政四年(1792)、庚申塔は安政七年(1860)に
それぞれ志村講中によって建立されたもの。

富士大山道標と庚申塔の先から中山道で最初の難所とされた急勾配である清水坂に入る。

日本橋を発って最初の難関がこの清水坂と云われた。
中山道で唯一富士山の姿を右手に一望できる名所でもあった。

今でもきれいに舗装されたこの板を上るのは息が切れるが、
荷駄を引く牛馬は大変な思いをしたと思われる。

坂の下には板橋と蕨を繫ぐ合の宿があり、茶屋などがあって、この先、
荒川を渡る戸田の渡しが増水で利用できない場合の溜まりの場所としていた。

埼京線線路を潜った先辺りが、合の宿があった所だ。
合の宿は、宿場と宿場のほぼ真ん中に位置する休憩を目的とする施設で、旅籠などの宿泊施設はなかった。、

埼京線線路の先で再び中山道(国道17号)へ合流。

中山道(国道17号)を横断し、反対側へ。

11時46分、三軒屋バス停を通過

11時51分、新河岸川を通過

荒川手前の船渡交差点を右折し、

埼京線・東北上越新幹線の下を通り抜け、150mほど先を左折すると、荒川土手が見える。

荒川土手に上がると・・・

12時6分、荒川だ。
戸田橋を渡ると埼玉県(戸田市)である。

右手の高層ビル群は川口市か?

土手に腰を下して一休み。
『いやぁ 天気が良くて気持ちが良いねぇ』

荒川土手に「戸田の渡し場」の碑が立っている。
荒川には、明治八年(1875)まで橋が無く、舟によって人や物資の運搬を行っていた。
洪水で利用できない時には、合の宿で待機したり、下流の奥州道中の千住大橋へ迂回することもあった。

「戸田の渡し場」は、戸田河岸と呼ばれ、荒川下流から塩・砂糖・雑貨がここで降ろされ、
大根や漬物などこの地の特産物などがここから積み込まれて下っていった物流の基地だった。
対岸の戸田村の名前をとって「戸田の渡し場」と呼ばれた。

12時27分、戸田橋を渡る。

新幹線・埼京線が頻繁に走り抜ける。

橋を渡り切った橋の袂に「歴史のみち 中山道」の案内があった。

案内に従って「歴史のみち」へ行ってみると、

案内されていた地蔵堂があった。
創立は不明だが、戸田市内最古の木造建造物とのこと。

地蔵堂の前に享保十六年(1731)銘が入った青面金剛像の庚申塔がある。
板橋宿の観明寺にあった庚申塔とよく似ている。

「歴史のみち」を進むと、

菖蒲川に突き当たった。
『うわっ 随分濁ってるねぇ』
『気分が悪くなりそうっ』
上流側は戸田競艇場に繋がっていると思われるが・・・

菖蒲川に架かる川岸橋を渡る。

中山道(国道17号)を一つ入った裏通りを歩いていたが、食べ物屋が見つからないので、

中山道(国道17号)に出てみると、幸楽苑があった。
時刻は間もなく13時になろうとしている。
『ラーメンでも食べて行こうっ!』で意見が一致。

この店のラーメンは早くて安いし、こういう時にはうってつけだ。

食事も終わり、再び蕨宿を目指す。

14時8分、蕨市に入った。

14時12分、木戸風の蕨宿標柱が現れた。
戸田の渡しで荒川を渡ってからの旧道は、大半が失われてしまっているが、
ここから先の蕨宿本陣までは、旧街道の面影が残されている。

日本橋から中山道全69宿場の浮世絵図が道の両側に描かれていた。

蕨市立歴史民俗資料館分館
かつて蕨市長だった金子吉衛夫妻没後、蕨市が譲り受け、2003年より一般公開された家屋敷。
(入館無料)

金子家は、明治時代に織物の買継商をしていた。
旧中山道と国道17号の間にあり、敷地面積は516坪と広い。

国道側は庭園になっている。

蕨市立歴史民俗資料館
蕨市の歴史と文化の特色である宿場および織物に関する情報を中心に展示している。
常設コーナー「街道と宿場」は見ておきたい。
(入館無料)

この庚申塔は、寛政四年(1792)に建てられたもので、
正面には青面金剛像・邪鬼・三猿が浮き彫りにされている。
板橋宿の観明寺と戸田の渡しの地蔵堂で見たものと同じだ。

旅籠の様子

江戸時代後期の蕨宿中心部の町並みを再現した模型。
本陣2軒と脇本陣1軒からなる宿場の様子が手に取るように分かる。
(手前が板橋宿方面)

本陣(岡田加兵衛家)の模型
蕨宿本陣は、岡田加兵衛家と岡田五郎兵衛家の2家が代々勤め、
宿場の中央に中山道を挟むように向かい合わせで建っていた。
両家とも門構え・玄関付の屋敷で、加兵衛家跡に蕨宿本陣跡の碑が立っている。

織物
江戸時代末期から、蕨では綿織物業が盛んになり、文政年間(1818~1830)塚越村の5代目高橋新五郎は、
青縞を織って江戸に売り出した。(以下略)

蕨市立歴史民俗資料館の隣に蕨宿本陣跡があった。

蕨宿本陣は、公家・大名などが休泊し、文久元年(1861)皇女和宮が御降嫁の折には、御休息の場となり、
ついで、明治元年(1868)同三年には、明治天皇の大宮氷川神社御親拝の際の御小休所となった。

蕨宿を利用した藩と禄高が展示されていた。
102万石の加賀金沢藩を筆頭に、尾張名古屋藩61万石、紀伊和歌山藩59万石と続き、
下野足利藩1万石まで、20の藩が利用したことになっている。

この日のゴールは、蕨宿本陣までのため、この後京浜東北線の蕨駅へ向かうことにした。
14時56分、蕨市役所前を通過。

JR蕨駅を目指す。

和楽備神社があったので、立寄ってみることに。

和楽備神社本殿
社伝によると、室町時代に蕨を所領とした足利将軍家の一族、
渋川氏が蕨城築城の折、八幡神を祀ったのが最初とされる。

江戸時代には蕨八幡と呼ばれ、明治44年に町内18社を合祀して和楽備神社と改称した。
合祀後の神社名に、祭神名(八幡神)を取ることは、各集落とも承服しない状況であり、
蕨一字では尊厳味がないので、岡田健次郎元町長の知人本居豊穎に依頼し、
万葉仮名から取って、和樂備神社と命名した、とのこと。
本殿にお参りし、この日の無事を報告した。

JR京浜東北線蕨駅

15時23分、蕨駅改札口に到着
『今日は大変お疲れさまでしたぁ』

中山道の板橋宿~蕨宿間約9.6Kmを歩き終わった。
道中見どころもたくさんあり、良い天気に恵まれて一日楽しく歩くことが出来た。
今回でいったん中山道は終わるが、今後も面白そうな宿場を見つけて歩いてみたい。
この日の万歩計は、23,000歩を越えていた。
ウマさんの「旧街道(特選)を歩く」目次に戻る。