雫石鉄也の
とつぜんブログ
甲賀忍法帖
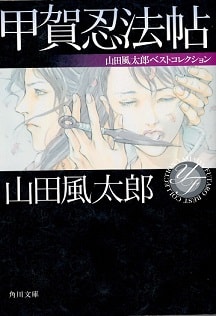
山田風太郎 角川書店
風太郎忍法帳の第1作である。映画、漫画、小説などの日本のエンタティメントの定番ともいえる集団バトルものの原点ともいうべき小説といってもいいだろう。
甲賀10人VS伊賀10人の団体戦である。甲賀と伊賀、おたがい憎しみあっている。服部半蔵の命によって、なんとか戦いをがまんしていた。それが、このたび半蔵によって、その禁が解かれた。竹千代か国千代か。三代将軍をどっちにするか決めかねている。それを伊賀、甲賀の戦いで決めようというわけ。三代将軍家光の幼名は竹千代だから、勝敗は判っているが、この小説の興味は伊賀、甲賀の勝敗ではない。
10人VS10人。20人の忍者が登場するが、一人一つづつ忍法を持っている。20の忍法。問題はこれをどう見せるかだ。このあたりはプロレスといっしょ。プロレスラーは一人一つづつ必殺技を持っている。力道山の空手チョップ、ジャイアント馬場の16文キック、アントニオ猪木の卍固めなどなど。これらの技が出れば試合は終わる。で、双方の必殺技をいかに見せるかが大切だ。梶原一騎原作の漫画「紅の挑戦者」では、間違ってレフリーに技をかけてしまうという反則をやっていたが。
忍法帳も同じ。忍法を出せば必ず相手は死ぬ。だったら、その相手の忍法は見れない。20人の忍者が出ているのに、10の忍法しか見られないわけ。これでは、読者としては不満が残り。山田はこのあたりの処理は見事なもので、きっちり20の忍法を見せてくれた。中には掟破り的な忍者もいたが、どいう具合にそれぞれの忍法を見せてくれたかは、もちろん、ここではいえない。どうか本書をお読みいただきたい。
風太郎忍法帳としては最適の入門書である。さて、これを読んで、奇奇怪怪、奇想天外、奇絶怪絶、玄妙幽玄、法悦快楽な風太郎忍法帳の世界に遊びにいこうではないか。
コメント ( 17 ) | Trackback ( 0 )
| « 三代目桂春団... | そんなことを... » |




実は初期の探偵小説というかミステリも悪くないんですが「太陽黒点」とか。
「甲賀忍法帳」は原点というか入門書ですね。
カート・ボォガネットの短編に「人間チェス」の話があって秀逸でしたが、似たような話は多数あれど、長編でやり抜いたらのは山田爺だけなような…
一つのシーンとしてやる作家は多いんですけどね。長編の中で。
丸ごと長編にしたのはこれだけ?
まぁ…山田正紀氏の「謀殺のチェスゲーム」が唯一くらいか…
ダブル山田は二人ともゲーム性というものと、そのバカバカしさをよく心得た作家なのだろうと思います。
後は安能務という歴史家・作家が、その有名にした翻訳の「封神演義」か…
理知的かつシニカルな作風の作家でないと、この種の「代理ゲーム」ものは難しいのですかね。
これは古代中国の商(殷)→周の易姓革命を舞台にしてますが、どう見てもSFです。
天界と現世を繋ぐ存在に仙界があるのですが、仙人たちは神となる過程で「殺戮本能」を抑えているため、1500年に一回、殺戮ゲームを許し、殺し会う。
殺された仙人は封神塚に封印されてしまう。その1500年ぶりが訪れた時に、
数百年~1000年の齢を経た「非人間型の仙人」と人類仙人の争いが激化していた。
仙人たちはそれぞれの宝貝という呪術兵器を用いて、殷と周のそれぞれについて殺しあいをする。
この宝貝が、熱線追尾ミサイル、毒ガス、
細菌兵器、ロボットにサイボーグ、音響爆弾…と近代兵器そっくりで。
まるでSFです。
後はどれだけ沢山の兵士を喰わせる事ができるか?
でないすか?
田舎で村を襲う野盗は、ある段階で1000人を喰わせるボスの下に走る。すると官の穀物輸送隊を襲撃できる。
それが行き詰まると、数万を養うボスに走る。すると官の物資集積基地を襲える。
あの国は北京から南京あたりまで山らしい山のない平坦な土地が続いてまして、まあまっ平ら。
日本みたいに山岳で分断された複雑な地形を持つと、桶狭間だの鵯越の奇襲作戦が評価されますが、平らな土地で数千万人が争う中国では、「喰わせる」ことが出来て、
相手より沢山の兵を集めて、包囲するのが王道なのだと思います。
なんか英雄豪傑入り乱れ、かーっと熱いぜ男一匹ガキ大将っ!
みたいなノリですよね、小説、マンガ、映画!ゲームと。
私はこの時代は熱気のない、人心の荒みきった 侘しい時代と思うのですよ。
一つは人口っね。
中国は国民の半数が餓死するよな苛烈な歴を繰り返してるのですが、この時代は最悪。後漢のAD157年実施国勢調査に5648万6856人の人口が、三国鼎立時代には全部合わせて768万2881人でした。
AD220年に後漢が滅亡してから、僅か数十年で人口が14%まで減った事になる。
ついで言えば、三国の主の誰を取ってみても、次の王朝というか、支配体制への夢というかビジョンを語る者がいない。
急速に8割以上も民が消えたので、遊牧民を長城の内側に入れたりして、南北分裂の禍根を残すわけてすが、
勢い政策は「より大きなパイを造る」のでなく、「小さなパイの奪い合い」に終始する。中国の王朝交代劇には、新しく成立したパイの分け前に預かろうとする豪傑達の
野望、欲望が熱気を与えるものなのですが、それがからきし観られない。
一言で言うと「やる気のない乱世」なのですね。
乱世か治世かを問わず、ビジョンを未来に向けて知識層が発信できんと、こうなる…というか。
まあ知識層は彼らも食わねばならないので、江南に逃れていたから仕方ないげど。
これって春秋戦国のキングダム並みなんですよ。だいたい人口が100万単位で王国、
1000万人単位でエンパイアですが、
戦力は人口による生産力で決まりますから。この人口で大艦隊や大軍団を組織して、長駆するなど不可能だと思うのですね。
ゲーム三国志然り、歴史をロマンチックに捉える向きがあるのは、何故か戦国が多いですよね。中華思想は、秦代から続く武力による統治だと思いますので、赤壁で存外、呉蜀も戦えると知ってしまった事は、当人、孫権や劉備にはサプライズだったと思います。不慣れな水軍や地域の風土病に負けただけだと言っても。恐らく、侘しい時代だったのは、戦国で、権力者だけが、三国鼎立による夢を見られたからでしょうね。権力の夢は、個人の夢とは対立すると。呉蜀も軍閥ではなく、魏のように学問や詩文をたしなむ文化の無い後身国だったであろう事や、文学の徒を曹操が招聘したのは、江南に逃げてしまった儒者や学習の空位を収めただけで、実際には、曹操の多才さというのは、歴史の裁断に対する、警戒心もあったのでは、と思います。だから、最終的には曹家は儒教に屈服したと。曹植に継がせられなかったのは、そういう文学は儒教のニッチだったという理由があって、それは後生の文学者達の人生を見ても、理解出来ると思います。時代は文学の暖かい日差し、心の安らぎではなく
、実務者を求めたと。だから、逆に言えば、当世は曹操でも良かったと。
>中国は国民の半数が餓死するよな苛烈な歴を繰り返してるのですが、この時代は最悪
結局、異民族の侵入を防げなかったのですね。董卓の悪行は筆舌に尽くしがたいですが、改革者を時代が求めたのも事実。李郭ら、董軍の残党達の政治は酷いですが、帝位にあるから、君主だから尊いというわけでは無いと。むしろ、漢民族の利害から離れたところに、当世の政治はあったと。三国鼎立による、三皇帝の即位には、そうした多極化への対応、つまり、後世の九品官人法に連なる、士太夫との合意形成との連関も見えますね。だから、根なし草ではない、名士こそが、郷里を基礎として、中国化に最も貢献したと思います。
>三国の主の誰を取ってみても、次の王朝というか、支配体制への夢というかビジョンを語る者がいない。
曹操も、儒教への反発という意味では、確たる政策は持っておらず、ネトウヨの曲解ではなく、左翼的な役割だったと思います。最もまともな改革者でしょう。取り敢えず、反曹、乱世の終息、それしか無かったのは、呉蜀こそが顕著だったでしょうが、魏がもっと頑張らないといけないですよね。名士は郷里の仕業を見て、局地的な安定をもたらしますが、所詮、国政にとっては漢代の反動であって、仁義を省みれば省みる程に、国政のダイナミズムは損なわれる、という(笑)。
>勢い政策は「より大きなパイを造る」のでなく、「小さなパイの奪い合い」に終始する。
曹操の屯田制とか、評価は高いですが、中華の領土、無辺の土地を切り開くのは、異民族統治という意味で困難であって、魏蜀は頑張りましたが、中華圏の流動は呉に示唆があると思います。つまり、海洋国家として、近隣から諸外国に懸けて、市場を広げれば良いと。日本の戦国の九州の大名達も同じような事をしてますよね。薩摩は武力による侵略でしたが。
>まあ知識層は彼らも食わねばならないので、江南に逃れていたから仕方ないげど。
知識人が、戦国とはいえ、人物評とか歴史評、ひいては政策の評価に向いていた事を思えば、江南の成長には、彼ら名士の力量を得た国が強いという事なのでは。魏も蜀も北伐と南征で得られたものはあった。だけど、辺境には名士は居なかった、という事だと思います。呉は南方の士キの懐柔に腐心して、経済圏を任せていましたが、名士の価値とは地域を抑え込む仕事をする事。だから、士キが死ぬと、呉は自治を解消していますね。あれには、単に直轄したがっただけでは無いと思います。
>キングダム
面白い漫画ですよね。順を追って揃えるつもりですが、春秋戦国の、軍政に秦の勝ち残りの秘密があった、という、血みどろの戦はあったとして、様々な荷を抱える人間に本物のドラマがあるという…。春秋戦国をスポ根視点で描きながら、国家の体制や軍序列ではなく、ソフトパワーに愛や感情の拠所があって、だから、政は一般的な家庭を持つぐらいの欲望は無いし、国家ではなく、家庭の単位の幸福度を競うというのは、今までの始皇帝ものには全然無いですね。信も下僕から、国家からすれば「無」から立ち上がって来るわけですし。これは、確かアメトークだったか、メディアからの評価も高いし、注目ですw
「徹夜城」という塾の歴史教師の方のサイトがあります。その中に「史劇的伝言板」という掲示板があり、ここ数日のログを見ていただけば、貴兄の学識と思想を見込んで援軍を頼む理由がお分かり頂ける筈です。また、同様の事を願えるような、貴兄のWeb活動上の盟友がおられましたら、是非とも同様の事をお願いしたいのです。
お願いいたします。
本格的な方が多そうなので、オブザーバーとしての立場で、読ませて頂きます。後学なので、議論の主導は勘弁してください。
>貴兄のWeb活動上の盟友がおられましたら
居ませんねえ。映画関係の方は勘弁願います。
と、別なサイトで脱落を宣言してました。
私は諸事情で派手に暴れられないので、外部に義勇兵を募って揺さぶったんですけどね。そんなわけで、今回はお疲れ様でした。
感想として「フェミニズム」を持ってくるとは思わなかったです。
でも、その側面を切り口にしてゆけば、
謝罪も時間の経過も効果を成さないんですよね。あれは上手い手です。
そっちから論じてないし。
私は彼処から手を引こうと思ってます。
歴史を軸にすると言いながら、大河ドラマや史劇映画のファンサイトになってますから。そこに一石投じてやろうと、私が問題提示した前後の週間とかは、結構、活発化してたりしますよ(笑)
でも、全員がドラマに映画の歴史者だから、疎んじられてね。B氏なんざ、連続投稿するなと来てましたよ。
この辺りが引き際かなと。
でも、付き合ってくれて有り難う。
テルマエの返事はまた書かせていただきますね。では。
だから隆さんが指摘されてないことで、まあこんなのも…みたいのを。
一つは中国の中原と違って、ヨーロッパ・アルプスちゅう邪魔くさいもんがイタリア半島の付け根からフランス・ドイツ方面に延びていることでないすか?
ローマってイタリア半島の都市国家で、地中海方向に植民地も延びているてしょう?
カエサルよりポンペイウスの方がはるかに資金潤沢だったのを見ても、後に東ローマが帝国の主体となるのを見ても、ガリアとかアルプスの向こうは付け足しだったんだと思うのですね。
フランク王国以後は、海側のイタリア半島から地中海にかけてが主舞台となるから、
アルプスか邪魔くさくて、統合なんかする気になろなかったんと違います?
あと「割拠=悪」でもなかったのでは?
国が帝国としてデカイ方が、寄らば大樹のナントカで良いじゃろう…てのは、近代以後の価値観なんと違います?
基本的に「有能」で実力、軍事的な動員力を持つ領主は、帝国なんか有り難がらないのでは?自分に領地を護るだけの力があれば、皇帝だろが何だろうが頭の上に乗られるのは気に入らないと思うのですよ。
まー、アメリカでは有能な学生ほど起業するてのと似てますね。
だから割拠がいかんというのは、少なくとも中世の価値観ではなくったと思うのですよ。
経済も、国家の風貌からしても、イベリア半島は欧州からしても、随分個性的ですよね。イスラム教の影響も受けていますし、レコンキスタが半島で起きたのは、北アフリカから自在に侵入して来るイスラム軍に対して、欧州から援軍を送りづらい、という事情もあったのでしょう。宗教融和といっても、武力を梃子にして、入植や布教、そして戦争、を繰り返したのが、イスラム教との関係であると思います。これは、多神教が、民間伝承の下に、平時に受容されていったのとは異なると思います。多神教の戦争とは、権力に対抗するテロですよね。
>ローマってイタリア半島の都市国家で、地中海方向に植民地も延びている
地中海のほうが、大陸を併呑するより、遥かに経済的意義があると思います。海賊が居た事も、陸路よりも交通が活発からだったからではないですか。なぜ、地中海、あるいは、海上交通、つまりシーレーンが延びたかといえば、交易路としての需要があったからでしょう。つまり、アフリカ地方、エジプトの存在、そして、地中海を仲介とした、中東、パルミュラなどの方がガリアなどより、遥かに豊かで重要な協商国であり、同盟相手であったと思います。どうでしょうか、カエサルとポンペイウスとの金脈の差異とは、統帥時代、制圧した地域の利権、その掌握課程と成果に大きな格差があったのではないでしょうかね。
>後に東ローマが帝国の主体となるのを見ても、ガリアとかアルプスの向こうは付け足しだった
やはり、僻地である西と比べて、圧倒したのが東であり、それは、半島を抑えた異文化との窓口でもあり、また、異民族の移動の圧力を最初に受ける緩衝地帯としての難しさもあったと思いますが、異民族の侵入とは、暫時的であったとしても、第一撃は戦争であったと思いますので、東はそれに対抗し得る精強な軍隊を持っていたのでしょうね。つまり、ローマ時代からして、帝国とはその版図が広い事もあり、また、経済の集約地としての、国際地域としての欧州の重要性が、東の繁栄にみられると思います。
>あと「割拠=悪」でもなかったのでは?
>国が帝国としてデカイ方が、寄らば大樹のナントカで良いじゃろう…てのは、近代以後の価値観なんと違います?
戦国時代などはまさにそうですね。軍隊があって、政治機構は独立し、地方に割拠する武士達がいて、政権の意向よりも、自家の権利を重しと見た事でしょう。国としてまとまりがあることには、それだけの実力が必要だったのが、国家主義以前の時代であり、ローマの解体というのは、自主的なものであったとしても、それだけの人材を循環させる事が出来なくなった、ということでしょうね。ローマ時代もまた、都市国家連合という、独立性の強い国家体であって、戦争の野心は、軍隊によって達成されていたと思います。フン族の侵入が、漢による匈奴の弾圧によって、起こされた大移動であったことからして、帝国とは、当時から連動して、国際政府の命運を共有していたと思います。
どんな国も内憂と外患がセットで滅びますからねえ…
経済的に恵まれた東ローマ(ビザンチン)は
皇帝が宗教的権威を兼ねる東洋的な専制こっなっちまいますから、西とはやはり別物だろうと。
ウイットフオーゲルが中国共産党は、東洋的な専制政治の復活だと発言してますよね? そのまま「オリエンタルディスポニズム」て本の中で、ローマも中国も「水力文明」であり、水を管理する国は専制国家にならざるえないのだと書いてます。
確かに乾燥した地域での灌漑農業を行う国は、水の管理の為に強烈な強制力を持たざるを得ず、ローマがオリエントに遷都した途端に、東ローマがペルシァ帝国みたくなっちまうのを見ても、ウイットフオーゲルの論は当たってる気がする。
だから儒教と共産主義は相性が良いという貴兄の弁は外れてない気がするんですよね。中国も主流である黄河地域は、日本なんかに比べれば、はるかに乾燥した気候ですしね。日本に天智天皇、天武天皇の律令国家が出来ても、直ぐに形骸化してゆくのは、灌漑を大規模に管理する必要がなかったからではないですかね?
これが必要だったら、荘園が栄えて、やがて武士が台頭して割拠に至るなんて歴史はなかったかもしれない。
ローマ人にしたって、別に風呂に入るために水道橋とか建築したわけではありますまい?
都市が巨大化する過程で、上水の必要性に迫られたのは事実でしょうが、そもそもは農業用水の確保だったと考えるのが現実的ですね。
実際、オリエントやイベリア半島、北アフリカの元カルタゴ領地などからの物資の流入で、つい商業国家みたく錯覚し勝ちですが、元老院への参政資格に、一定規模の農地(荘園)所有が定められているのを見ても、ローマは農業国だったでしょうから。
まあ、領土から入ってくる安い小麦の為に、重装歩兵となる市民階級(自営農民)は没落しちまいますけどね。
数世代すると元老院階級の奴隷の方が、市民より教養があるようになる。
それが回りめぐって、隆さんの言われる人材の循環を果たせなくなったのと違いますかね?
>人材の循環が利かなくなってローマが滅んだって説はリアルですね。
>どんな国も内憂と外患がセットで滅びますからねえ…
ローマは、戦争で奴隷を得て、経済基盤たる労働力や、華麗なコロシアムでの戦いの兵力にしたものの、宗教を超えるイデオロギーを発明する事が出来なかった。これが、指導層の純粋な視野を弱め、それは、政策上の不備につながっていったのではないでしょうか。アッピア水道とか、インフラ整備が出来なくなった事は、版図の維持を危うくして、それ以上の拡張は無理、ということになりました。経済圏の不活性が、結局、国策を縮小させた、ということだと思います。そして、属領然り、エジプトから入ってきた食料、貿易としての物産というのは、経済競争というよりは、国策の下に、運搬されてきた、上納金に過ぎず、ローマの経済思想とは、自由市場ではなく、巨大な序列階級思想であったと思うのですよ。だから、強力過ぎる軍団の存在が、ローマの頭脳を安楽にむさぼらせて、テクノクラートが育たなかった理由があると思います。
>ローマも中国も「水力文明」であり、水を管理する国は専制国家にならざるえないのだと書いてます。
つまりは、農業国であり、その版図拡張は、大陸国家としての宿命でしょうね。水脈といえば、山岳部に位置するものですが、巨大な山岳を制覇する事に、ローマも中国も国境を超える根拠があったと思います。このへんは、四大文明の筆頭格であるエジプトが、大河を抑えているがゆえに、地盤を固めて、農業国として安定し、それが、ローマの属領となっても、衰退しなかった根拠ではないかと思います。
>ローマがオリエントに遷都した途端に、東ローマがペルシァ帝国みたくなっちまうのを見ても、ウイットフオーゲルの論は当たってる気がする。
ローマの中心地は、イタリアではなく、中東と欧州の交差点であるオリエントでもあるのではないでしょうか。先のコメントで、触れられていましたが、欧州には中原はないと。では、地域の輪郭を広げて、欧州と中東をミックスしてしまえばどうか。それは、コンスタンチノープル、すなわち、ビザンティンを中心とした中世のローマ帝国の栄光が見えるように思います。東ローマが繁栄を続けたのは、交易の中心路を抑え、双方の文明にシフト出来る地の利にあったからで、それは、体制にも影響を与えていないですか?
>儒教と共産主義は相性が良いという貴兄の弁は外れてない気がするんですよね。
儒教も、有徳者による革命は肯定していますから、道徳の根源といっても、日本の儒教と中国とでは、質と歴史が違い過ぎると思います。ですが、日本の幕末などは、欧米とのミックスを踏まえて、儒教が先鋭化した時代にあったのではないでしょうか。吉田松陰などは、その過激派の主席でしょう。共産主義革命は日本では起こらない理由は、武士階級という、政治に責任を有した官僚層が、決然たる覚悟と資格を持って、政治に関与していたからだと思います。そこで思うのは、権力のダウンサイズにおいて、左翼主導の地域主権では、武士特有の独立意識を気風に保ちえない、のではないでしょうか。時代錯誤と言われても、それは譲れません。日本の左翼主導の政治に、独立意識は見当たりませんから。
>日本に天智天皇、天武天皇の律令国家が出来ても、直ぐに形骸化してゆくのは、灌漑を大規模に管理する必要がなかったからではないですかね?
日本の荘園制度の確立においては、某所でも盛り上がっているのを一読しましたが、鎌倉期の悪党とか自営武士の芽生えが、早期に起きた事からしても、土地が豊かさの一つの指標であったからでしょう。土地がなければ、日本の武士として認められないのは、血脈を重視して来た日本においても顕著だと思います。足利義昭とか、落ち武者などはそうでしょう。彼は、謀略家としては一流かもしれませんが、その武才や威儀が認められた事はないと思います。明智光秀も、なぜクーデターに失敗したかといえば、基盤となる領土を召し上げられ、態勢の立て直し様もないし、正統性において、秀吉に全く敵わなかったからではないですかね。秀吉は、中国からの退路において、大名の支持を取り付ける事に余念がなかったですよね。その視点の差が、「決戦」に大きく出他のだと思います。
>オリエントやイベリア半島、北アフリカの元カルタゴ領地などからの物資の流入で、つい商業国家みたく錯覚し勝ちですが、元老院への参政資格に、一定規模の農地(荘園)所有が定められているのを見ても、ローマは農業国だったでしょうから。
カルタゴに脅威を覚えたのは、その軍事力というよりは、経済力ですよね。軍隊では、ローマに遠く及ばないカルタゴは、ハンニバルという軍事的天才に頼らざるを得なかったと。戦争が争点になっていますけど、あれは、カルタゴとローマはいずれ雌雄を決する運命にあったと思います。大陸国家と海洋国家で、領土の占領の是非が、重要視されず、自由経済による国境の解体が進むことは何としても避けたかった筈です。大陸国家は、先人が血を流して、得た重要な財産で、そこには土地があり住民がいる限り、必ず、戦争が起こるもの。対するに、海洋世界は余りに自由であって、ローマの統制とは、都市国家連合で緩かった、といいますが、それは、官僚統治が無い代わりに、貴族や名士の影響力が強かったわけで、だからこそ、カルタゴ軍がアルプス越えをしてやって来ても、十分な備えを持った都市国家は一つも門戸を開けなかったのでしょう。都市単位で、軍隊や警察の独立が必要だというのは、十分な独立意識があるがためであって、ポエニ戦争でこそ、カルタゴは、ローマの強さの秘密を知ったのではないでしょうか。つまり、ローマとカルタゴの戦いとは、原理原則の対立でもあって、重要な隣国にカルタゴがあり、ローマがあったのは、皮肉としか言いようがありません。
>人材の循環が利かなくなってローマが滅んだって説はリアルですね。
>どんな国も内憂と外患がセットで滅びますからねえ…
ローマは、戦争で奴隷を得て、経済基盤たる労働力や、華麗なコロシアムでの戦いの兵力にしたものの、宗教を超えるイデオロギーを発明する事が出来なかった。これが、指導層の純粋な視野を弱め、それは、政策上の不備につながっていったのではないでしょうか。アッピア水道とか、インフラ整備が出来なくなった事は、版図の維持を危うくして、それ以上の拡張は無理、ということになりました。経済圏の不活性が、結局、国策を縮小させた、ということだと思います。そして、属領然り、エジプトから入ってきた食料、貿易としての物産というのは、経済競争というよりは、国策の下に、運搬されてきた、上納金に過ぎず、ローマの経済思想とは、自由市場ではなく、巨大な序列階級思想であったと思うのですよ。だから、強力過ぎる軍団の存在が、ローマの頭脳を安楽にむさぼらせて、テクノクラートが育たなかった理由があると思います。
>ローマも中国も「水力文明」であり、水を管理する国は専制国家にならざるえないのだと書いてます。
つまりは、農業国であり、その版図拡張は、大陸国家としての宿命でしょうね。水脈といえば、山岳部に位置するものですが、巨大な山岳を制覇する事に、ローマも中国も国境を超える根拠があったと思います。このへんは、四大文明の筆頭格であるエジプトが、大河を抑えているがゆえに、地盤を固めて、農業国として安定し、それが、ローマの属領となっても、衰退しなかった根拠ではないかと思います。
>ローマがオリエントに遷都した途端に、東ローマがペルシァ帝国みたくなっちまうのを見ても、ウイットフオーゲルの論は当たってる気がする。
ローマの中心地は、イタリアではなく、中東と欧州の交差点であるオリエントでもあるのではないでしょうか。先のコメントで、触れられていましたが、欧州には中原はないと。では、地域の輪郭を広げて、欧州と中東をミックスしてしまえばどうか。それは、コンスタンチノープル、すなわち、ビザンティンを中心とした中世のローマ帝国の栄光が見えるように思います。東ローマが繁栄を続けたのは、交易の中心路を抑え、双方の文明にシフト出来る地の利にあったからで、それは、体制にも影響を与えていないですか?
>儒教と共産主義は相性が良いという貴兄の弁は外れてない気がするんですよね。
儒教も、有徳者による革命は肯定していますから、道徳の根源といっても、日本の儒教と中国とでは、質と歴史が違い過ぎると思います。ですが、日本の幕末などは、欧米とのミックスを踏まえて、儒教が先鋭化した時代にあったのではないでしょうか。吉田松陰などは、その過激派の主席でしょう。共産主義革命は日本では起こらない理由は、武士階級という、政治に責任を有した官僚層が、決然たる覚悟と資格を持って、政治に関与していたからだと思います。そこで思うのは、権力のダウンサイズにおいて、左翼主導の地域主権では、武士特有の独立意識を気風に保ちえない、のではないでしょうか。時代錯誤と言われても、それは譲れません。日本の左翼主導の政治に、独立意識は見当たりませんから。
>日本に天智天皇、天武天皇の律令国家が出来ても、直ぐに形骸化してゆくのは、灌漑を大規模に管理する必要がなかったからではないですかね?
日本の荘園制度の確立においては、某所でも盛り上がっているのを一読しましたが、鎌倉期の悪党とか自営武士の芽生えが、早期に起きた事からしても、土地が豊かさの一つの指標であったからでしょう。土地がなければ、日本の武士として認められないのは、血脈を重視して来た日本においても顕著だと思います。足利義昭とか、落ち武者などはそうでしょう。彼は、謀略家としては一流かもしれませんが、その武才や威儀が認められた事はないと思います。明智光秀も、なぜクーデターに失敗したかといえば、基盤となる領土を召し上げられ、態勢の立て直し様もないし、正統性において、秀吉に全く敵わなかったからではないですかね。秀吉は、中国からの退路において、大名の支持を取り付ける事に余念がなかったですよね。その視点の差が、「決戦」に大きく出他のだと思います。
>オリエントやイベリア半島、北アフリカの元カルタゴ領地などからの物資の流入で、つい商業国家みたく錯覚し勝ちですが、元老院への参政資格に、一定規模の農地(荘園)所有が定められているのを見ても、ローマは農業国だったでしょうから。
カルタゴに脅威を覚えたのは、その軍事力というよりは、経済力ですよね。軍隊では、ローマに遠く及ばないカルタゴは、ハンニバルという軍事的天才に頼らざるを得なかったと。戦争が争点になっていますけど、あれは、カルタゴとローマはいずれ雌雄を決する運命にあったと思います。大陸国家と海洋国家で、領土の占領の是非が、重要視されず、自由経済による国境の解体が進むことは何としても避けたかった筈です。大陸国家は、先人が血を流して、得た重要な財産で、そこには土地があり住民がいる限り、必ず、戦争が起こるもの。対するに、海洋世界は余りに自由であって、ローマの統制とは、都市国家連合で緩かった、といいますが、それは、官僚統治が無い代わりに、貴族や名士の影響力が強かったわけで、だからこそ、カルタゴ軍がアルプス越えをしてやって来ても、十分な備えを持った都市国家は一つも門戸を開けなかったのでしょう。都市単位で、軍隊や警察の独立が必要だというのは、十分な独立意識があるがためであって、ポエニ戦争でこそ、カルタゴは、ローマの強さの秘密を知ったのではないでしょうか。つまり、ローマとカルタゴの戦いとは、原理原則の対立でもあって、重要な隣国にカルタゴがあり、ローマがあったのは、皮肉としか言いようがありません。
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。