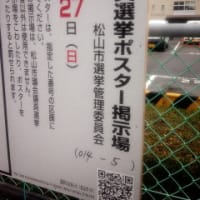米百俵の精神
米百俵の精神今日ある先輩から、「最近、お前のブログ優しくなったなあ。」と指摘されました。
自分としては、何も意識していなかったのですが、自分の中の意識の変化とともに変わってきたのでしょうか。
その変化について自己分析をすると、一時もてはやされた「米百俵」の話に行き着くのです。
この話は「米百俵の精神」という言葉になり、小泉純一郎内閣総理大臣が第一次内閣を組閣した後の国会での所信表明演説で引用し有名になりました。
当時は経済関係の部署にいましたから、「教育」の重要性を今ほど実感をもって理解していなかったと思うのです。
この話は、司馬遼太郎氏の「峠」という話よりも後の話であります。
そこでどのような内容だったかフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から以下のとおり引用させていただきます。
戊辰戦争で敗れた長岡藩は7万4000石から2万4000石に減知され、実収にして6割を失って財政が窮乏し、藩士たちはその日の食にも苦慮する状態であった。
このため窮状を見かねた長岡藩の支藩三根山藩から百俵の米が贈られることとなった。
藩士たちは、これで生活が少しでも楽になると喜んだが、藩の大参事小林虎三郎は、贈られた米を藩士に分け与えず、売却の上で学校設立の費用(学校設備の費用とも)とすることを決定する。
藩士たちはこの通達に驚き反発して虎三郎のもとへと押しかけ抗議するが、それに対し虎三郎は、
「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」
と諭し、自らの政策を押しきった。
この米百俵の売却金によって開校したのが「国漢学校」であった。
また、この学校は士族によって建てられた学校であるが、一定の学力に達した庶民の入学も許可された。
洋学局と医学局が設置され、洋学局が現在の長岡市立阪之上小学校と新潟県立長岡高等学校、医学局が長岡市内にある長岡赤十字病院とその付属の看護学校が後身となっている。
[小林虎三郎とは?]
文政11年(1828年)、現在の新潟県に長岡藩士小林又兵衛の三男として誕生。
長岡藩校崇徳館で学び、若くして藩校の助教を務めるほどの学識深い俊英だった。
23歳の時に藩命で江戸に遊学をし、当時兵学や砲学、洋学で有名な佐久間象山の門下に入り、長州藩士の吉田寅次郎(吉田松陰)と「象門の二虎」と称せられるほどに学問に秀でていた。
また、象山に「天下、国の政治を行う者は、吉田であるが、わが子を託して教育してもらう者は小林のみである」と言わせるほど、虎三郎は教育者だった。
戊辰戦争が始まり、新政府軍が越後高田藩に至るという報が入ると、長岡藩では小林が起草した嘆願書を提出することを決定する。
この嘆願書の内容は、当時としては珍しく法学の理論から徳川慶喜の赦免を訴えたものである。すなわち、新政府の「王政復古(=天皇親政)」のスローガンを逆手に取り、(天皇親政時の法規範である)律令に照らせば、慶喜の罪は八虐のうちの「反」にも「叛」にも当たらず、むしろこれまでの徳川氏の功績も含めて考えると六議のうちの「議功」に当たるので、律令に沿って慶喜を寛典に処してほしいというものである。
しかし、往来の騒擾のため使者をなかなか出立させることができず、そのうち江戸より河井継之助が帰藩し、嘆願の無意味を主張して取り消させたため、結局この嘆願書が提出されることはなかった。
明治元年(1868年)長岡藩大参事となる。
官軍との開戦を反対していたのが、抜擢の理由の一つだともいわれる。開戦に反対したことだけであれば、長岡藩の家老首座の地位を連綿としてきた稲垣平助も同様であるが、稲垣は、合戦の直前に、逃亡して長岡城をめぐる北越戦争には参加せず、終戦後になって、また長岡に戻ってきたため、藩内に信望がまったくなく、彼や彼の惣領を大参事に推す空気はなかったという。
家老次席の山本帯刀は、開戦派であり刑死していた。
虎三郎は明治4年(1871年)、「病翁」と自ら名を改めているが、リウマチ、腎臓病、肝臓病などさまざまな病を患っていた。しかし廃藩置県後も、情熱が失せることなく郡役所に対して、教育行政をはじめとする諸案件について、陳情・嘆願を繰り返しおこなったが、郡役所から疎まれたらしく、静養に専念するよう命じられた。
明治10年(1877年)、湯治先の伊香保で熱病に罹り、8月24日に東京府東京市内にあった弟の雄七郎宅で死去。享年50歳。
本当にすごい人がいたものであります。
目の前の経済も大事なのですが、その基盤を築くためにはしっかりとした教育が何よりも大切であると説いた小林虎三郎のような人に近づけるよう、がんばらないといけないと冬の夜長を過ごしながら改めて思ったのであります。