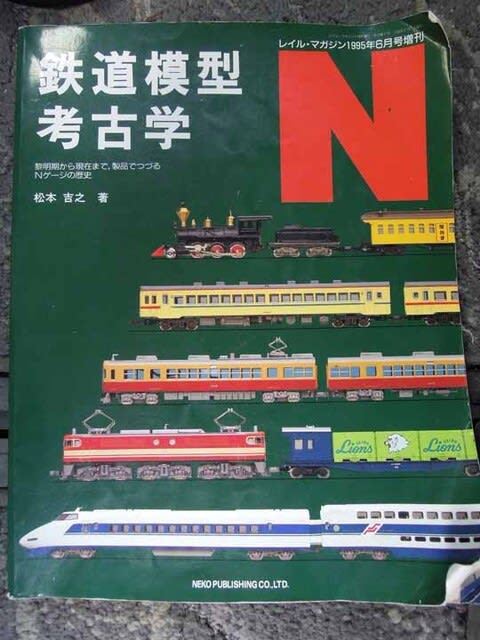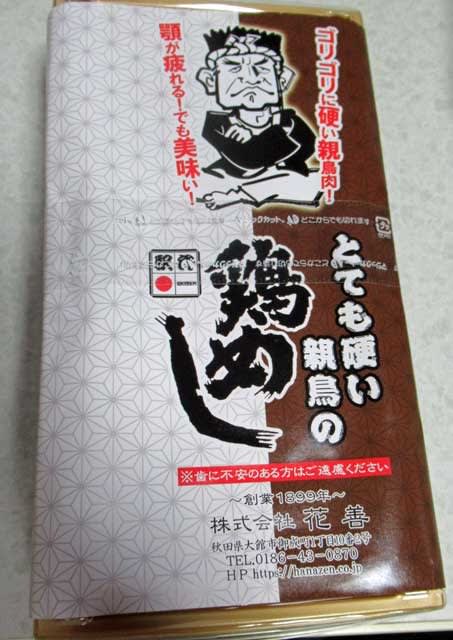帰省途中の悪魔の散財で得た戦利品から。

今回はしなのマイクロ製のED42です。
ED42自体は現在のマイクロエースからも出ていますが、今回のは最初期の金属ボディのモデル。
同じく金属製のワールド工芸はボディの細密さでは今回のモデルを上回るものの「動輪のロッドがジャック軸に連動しないのでロッドの動きが安っぽく見える」弱点(あとカプラーポケットが無粋なボックス形状なのもマイナス点)があり旧製品のしなの製もそう悪いモデルではありません。

実はしなののED42は以前から入線させていたモデルだったのですが、今回また入線させた理由は「これで実物通りの4重連が可能になる」からでした(爆笑)
最初にED42を入れたのは2012年の事で、その後順次増備を進めてきたのですが、今回の入線で12年目にして夢が実現したことになります(それまでは3重連プラスED41で対応していた)
随分と気の長い話でしたが、諦めないで待っていればこういう事もある、という事でしょうか。
走行性は走りはじめで幾分ロッドがぎくしゃくしますが、ある程度当たりが付いてくると割合ちゃんと走る印象でした。

むしろこの個体の問題はエージングが進んだようなボディの質感(笑)
表面に粉を吹いた様に見える前面はやや薄汚く見えるのも確かなので洗浄かリペイントは必須と思われます。
でもこれを始めたらほかの3両にも同じ事をしないといけない様な気が(汗)

あと、無動力の仕様がない(旧製品の一部にはトレーラーが、後のプラ製リニューアル品は無動力機を交えたセットです)ので電気はかなり食いそうですし、第一、この4重連がきちんと走れるのかはいまだに未知数です。
しなの製のED42の特徴はもう一つ、エッチングのメリットを生かし「4種類のナンバーの仕様が製品化されている」のですが、帰宅後チェックしてみたら手持ちの1両と同じ「18号機」でした(他は5号機、7号機、15号機および戦時型の28号機)

今回はしなのマイクロ製のED42です。
ED42自体は現在のマイクロエースからも出ていますが、今回のは最初期の金属ボディのモデル。
同じく金属製のワールド工芸はボディの細密さでは今回のモデルを上回るものの「動輪のロッドがジャック軸に連動しないのでロッドの動きが安っぽく見える」弱点(あとカプラーポケットが無粋なボックス形状なのもマイナス点)があり旧製品のしなの製もそう悪いモデルではありません。

実はしなののED42は以前から入線させていたモデルだったのですが、今回また入線させた理由は「これで実物通りの4重連が可能になる」からでした(爆笑)
最初にED42を入れたのは2012年の事で、その後順次増備を進めてきたのですが、今回の入線で12年目にして夢が実現したことになります(それまでは3重連プラスED41で対応していた)
随分と気の長い話でしたが、諦めないで待っていればこういう事もある、という事でしょうか。
走行性は走りはじめで幾分ロッドがぎくしゃくしますが、ある程度当たりが付いてくると割合ちゃんと走る印象でした。

むしろこの個体の問題はエージングが進んだようなボディの質感(笑)
表面に粉を吹いた様に見える前面はやや薄汚く見えるのも確かなので洗浄かリペイントは必須と思われます。
でもこれを始めたらほかの3両にも同じ事をしないといけない様な気が(汗)

あと、無動力の仕様がない(旧製品の一部にはトレーラーが、後のプラ製リニューアル品は無動力機を交えたセットです)ので電気はかなり食いそうですし、第一、この4重連がきちんと走れるのかはいまだに未知数です。
しなの製のED42の特徴はもう一つ、エッチングのメリットを生かし「4種類のナンバーの仕様が製品化されている」のですが、帰宅後チェックしてみたら手持ちの1両と同じ「18号機」でした(他は5号機、7号機、15号機および戦時型の28号機)