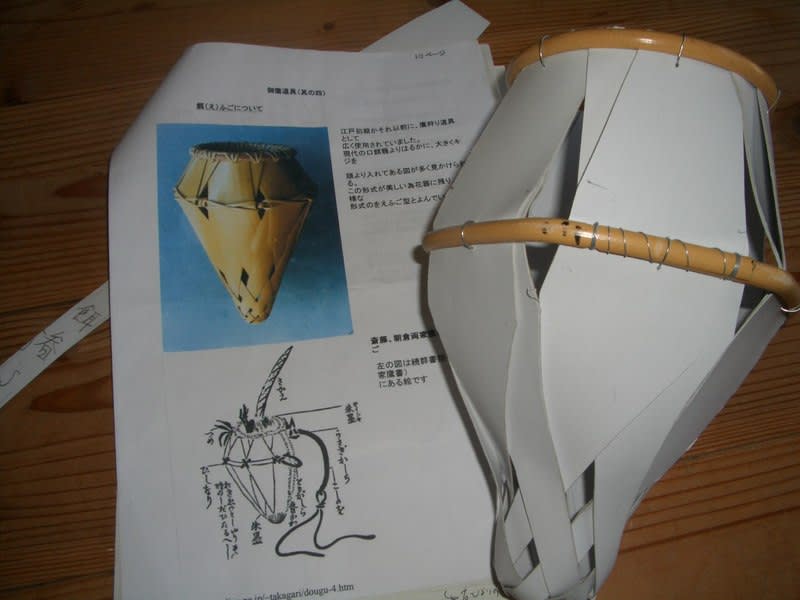「マイ箸運動」 が少しずつ見直されている。自分のお箸を持って、割り箸を使わない、自分の小さな主張、お洒落として!この「マイ箸運動」にも、賛否両論あって、人の意見はホントさまざまだなーと、思ってしまう。ネットで検索してみると
「マイ箸運動」 が少しずつ見直されている。自分のお箸を持って、割り箸を使わない、自分の小さな主張、お洒落として!この「マイ箸運動」にも、賛否両論あって、人の意見はホントさまざまだなーと、思ってしまう。ネットで検索してみると
《マイ箸を持ち歩いて、<wbr></wbr>さも自分がエコロジカ<wbr></wbr>ルな意識が高いかのよ<wbr></wbr>うに装うためだけに利<wbr></wbr>用されては堪りません<wbr></wbr>。
そんな人が、建築資材<wbr></wbr>としてどれだけの量の<wbr></wbr>木材が消費されている<wbr></wbr>か、また、その消費量<wbr></wbr>と比べて、割り箸とし<wbr></wbr>ての消費量がどれだけ<wbr></wbr>僅かなものに過ぎない<wbr></wbr>かを知れば、そんなこ<wbr></wbr>とで満足している自分<wbr></wbr>が恥ずかしくなると思<wbr></wbr>います。》
《 中国からの木材の流通<wbr></wbr>を阻止しようとする、<wbr></wbr>日本の製材業者の意図<wbr></wbr>があるのかも知れませ<wbr></wbr>んし、今後の中国の木<wbr></wbr>材利権を狙って、日本<wbr></wbr>の商社が駆け引きの材<wbr></wbr>料に使っているのかも<wbr></wbr>知れません。》
また、《 現在流通<wbr></wbr>している割り箸の90<wbr></wbr>%以上は外国産で、割<wbr></wbr>り箸作りのために伐採<wbr></wbr>しているケースがほと<wbr></wbr>んどです。間伐のために切られて<wbr></wbr>いるものではないため<wbr></wbr>、森を育てるどころか<wbr></wbr>、緑を奪い、生態系を<wbr></wbr>崩し、砂漠化を加速さ<wbr></wbr>せています。
そういう点においては<wbr></wbr>外国産の割り箸は環境<wbr></wbr>負荷の高い商品である<wbr></wbr>といえます。ただ、多くの割り箸は<wbr></wbr>「割り箸のために伐採<wbr></wbr>された木」によって作<wbr></wbr>られていることは、ど<wbr></wbr>うか知ってください。<wbr></wbr>》
など等、いろんな意見が飛び交っています。自分の意見を押し付けようとすると、いやらしくなるから、私は「自分の楽しみとして、自分の気に入った使い易いお箸を持ち歩いてみたい!」こんな所でやってます。
 ネット販売で一番人気の「名入れ箸」を購入された方から、「箸袋を作って欲しい!」という要望が結構あります。以前にも、参考のために数点「箸袋」を買って来ていた。作りはいたってシンプルで三角形状に縫い合わせた布に頂点に結び紐を付けるだけである。
ネット販売で一番人気の「名入れ箸」を購入された方から、「箸袋を作って欲しい!」という要望が結構あります。以前にも、参考のために数点「箸袋」を買って来ていた。作りはいたってシンプルで三角形状に縫い合わせた布に頂点に結び紐を付けるだけである。
工房ではハンドバッグに取り付けている布の余り布が沢山ある。その布を活用して試作を始めた。余った布をパッチワークのように繋ぎ合わせて!花の模様を可愛くワンポイントに!リバーシブルにしては?飾り紐の先にこの玉を付けよう?あーだ、こーだ、と女性陣の話は盛り上がっている。私が考えると、「そこまで小さな布を張り合わせずに、もう少し効率良く、沢山作れる方法は無いの?」と思ってしまうが、この考えが男の考え?経営者の考え?どうもこの考えでは、女性心をくすぐる可愛い作品が出来無いようである。機能的で効率的より、無駄があっても、作るのに大変でも「まず、可愛い物!」
取り合えず、200個ほど作ってみよう、余り布自体はタダでも、製品化していく内には、余り布でなくなって原価計算しなくてはいけないし、手間が掛かりすぎて単価が高くなりすぎても商品としては問題がある。「まー、お客様の反応を見てみよう」と言うことで落ち着いた。
竹工房オンセ
 滋賀県、信楽焼きの陶芸家「上田光春 作品展」のDMが届いた。「オーソドックスな作陶ながら微妙に崩されたフォルムのバランスや手肌に触れた時の土の厚み」とある。誠実な人柄そのままの作風だ。もう一つの写真はその茶碗を入れる、古布で作られた巾着。奥様の作った巾着であろう。
滋賀県、信楽焼きの陶芸家「上田光春 作品展」のDMが届いた。「オーソドックスな作陶ながら微妙に崩されたフォルムのバランスや手肌に触れた時の土の厚み」とある。誠実な人柄そのままの作風だ。もう一つの写真はその茶碗を入れる、古布で作られた巾着。奥様の作った巾着であろう。 楕円の茶篭と四角い茶篭、もう一つは古布の巾着を付けた底だけの篭、3種類違うタイプでのサンプルである。この茶篭の中に上田さんの抹茶椀を入れて、茶筅や茶杓、棗も上田さんの知り合いの作家に作ってもらうそうだ。こんな、依頼は受けても楽しいモノだ。
楕円の茶篭と四角い茶篭、もう一つは古布の巾着を付けた底だけの篭、3種類違うタイプでのサンプルである。この茶篭の中に上田さんの抹茶椀を入れて、茶筅や茶杓、棗も上田さんの知り合いの作家に作ってもらうそうだ。こんな、依頼は受けても楽しいモノだ。