
「人生の王道 西郷南洲の教えに学ぶ」 稲盛和夫・著、日経BP社、2007年9月25日
p.28 トップに立つ人間には、いささかの私心も許されないのです。基本的に個人という立場はあり得ないのです。トップの「私心」が露わになったとき、組織はダメになってしまうのです。
p.43 辱めを受けて、それに耐えることは人にとって最も難しいことであるが、それでもなお耐え忍んだとき、人は悟りに近づくことができるというものです。
p.53-4 「己を足れりとする」、つまり自分に自信があるというところから一歩退いて、謙虚さを持つことが大事です。部下を含め、いろんな人から意見を聞き、自分の考えをまとめていく、そういう謙虚さが必要であるといっているのです。
p.56 (リーダーは)強烈なリーダーシップを持つと同時に、一方ではそれを否定するような謙虚さを兼ね備えていかなければならないのです。いわば「独裁と協調」「強さと弱さ」「非情と温情」という相矛盾する画面を、トップである社長は持ち合わせていなければならないのです。
p.64 「欲を離れること」
一人ひとりが過剰な欲を捨てさえすれば、すべてうまくいく。
p.98 「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」
p.106 金や地位、権力、策略は、一点の曇りもない心、誠心誠意の志の前に歯が立たないということは歴史が証明しています。
p.150 国家公務員とは国家に対するサーバントではなく、あくまで国民に対するサーバントであるべきなのです。行政官は、法案や制度の整備、運用にあたっても、「国民にとってよいことかどうか」という唯一の基準に従って、仕事を進めなくてはなりません。
薬局も公共性のある組織であるのなら、運営にあたり、患者さんにとってよいことかどうか、患者目線で考えたらどうすべきか、国民に対して果たすべき役割は何か、などを根底にすえて判断をすべきなのだろう。
p.151 もし為政者が国民大衆を大切にするかどころか、それをないがしろにして苦しい目に遭わせれば、その結果は為政者自信に及び、やがて自分が倒れることになるといっているのです。
p.177 「うそ」をつき「策」をめぐらせることが、結局は功を奏さないということは、現代においても通じる真理です。
p.186 人格こそが、才覚をコントロールすることができるのです。もし、その人格に歪みがあれば、才覚や熱意を正しい方向へと発揮させることができず、結果として誤った方向に経営の舵取りを行ってしまうのです。
もちろん、多くの経営者も、人格が大切だということくらいは知っています。しかし、その人格とはどのようなものであり、どうすればそれを高め、維持できるのかということを理解してはいません。
では、「人格」とは何なのでしょう。人格とは、人間が生まれながらに持っている性格と、その後の人生を歩む過程で、その人が学び身につけていった哲学から成り立っている、と私は考えています。
p.204 万難を排し何としてもやり抜くという勇気がなければ、どんな知識も役立つことはありません。
「人から謗られはしないだろうか」「人から嫌われはしないだろうか」などと考え、自分を守ろうとすることで実行できないのです。自分を大事にしようとする、そんな気持ちを放り出してしまい、「馬鹿にされようが、軽蔑されようが何とも構わない」となれば、どんな困難なことでも必ず実行できるはずなのです。
p.225 人生の目的とは、お金儲けや立身出世など、いわゆる成功を収めることではなく、美しい魂をつくることにあり、人生とはそのように魂を磨くために与えられた、ある一定の時間と場所なのだと私は思うのです。
p.237 「六つの精進」
1.誰にも負けない努力を日々続ける。
2.謙虚にして驕らず。
3.反省のある毎日を送る。
4.生きていることに感謝する。
5.善行、利他を積む。
6.感覚・感性を伴うような悩み、心配事はしない。
p.28 トップに立つ人間には、いささかの私心も許されないのです。基本的に個人という立場はあり得ないのです。トップの「私心」が露わになったとき、組織はダメになってしまうのです。
p.43 辱めを受けて、それに耐えることは人にとって最も難しいことであるが、それでもなお耐え忍んだとき、人は悟りに近づくことができるというものです。
p.53-4 「己を足れりとする」、つまり自分に自信があるというところから一歩退いて、謙虚さを持つことが大事です。部下を含め、いろんな人から意見を聞き、自分の考えをまとめていく、そういう謙虚さが必要であるといっているのです。
p.56 (リーダーは)強烈なリーダーシップを持つと同時に、一方ではそれを否定するような謙虚さを兼ね備えていかなければならないのです。いわば「独裁と協調」「強さと弱さ」「非情と温情」という相矛盾する画面を、トップである社長は持ち合わせていなければならないのです。
p.64 「欲を離れること」
一人ひとりが過剰な欲を捨てさえすれば、すべてうまくいく。
p.98 「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」
p.106 金や地位、権力、策略は、一点の曇りもない心、誠心誠意の志の前に歯が立たないということは歴史が証明しています。
p.150 国家公務員とは国家に対するサーバントではなく、あくまで国民に対するサーバントであるべきなのです。行政官は、法案や制度の整備、運用にあたっても、「国民にとってよいことかどうか」という唯一の基準に従って、仕事を進めなくてはなりません。
薬局も公共性のある組織であるのなら、運営にあたり、患者さんにとってよいことかどうか、患者目線で考えたらどうすべきか、国民に対して果たすべき役割は何か、などを根底にすえて判断をすべきなのだろう。
p.151 もし為政者が国民大衆を大切にするかどころか、それをないがしろにして苦しい目に遭わせれば、その結果は為政者自信に及び、やがて自分が倒れることになるといっているのです。
p.177 「うそ」をつき「策」をめぐらせることが、結局は功を奏さないということは、現代においても通じる真理です。
p.186 人格こそが、才覚をコントロールすることができるのです。もし、その人格に歪みがあれば、才覚や熱意を正しい方向へと発揮させることができず、結果として誤った方向に経営の舵取りを行ってしまうのです。
もちろん、多くの経営者も、人格が大切だということくらいは知っています。しかし、その人格とはどのようなものであり、どうすればそれを高め、維持できるのかということを理解してはいません。
では、「人格」とは何なのでしょう。人格とは、人間が生まれながらに持っている性格と、その後の人生を歩む過程で、その人が学び身につけていった哲学から成り立っている、と私は考えています。
p.204 万難を排し何としてもやり抜くという勇気がなければ、どんな知識も役立つことはありません。
「人から謗られはしないだろうか」「人から嫌われはしないだろうか」などと考え、自分を守ろうとすることで実行できないのです。自分を大事にしようとする、そんな気持ちを放り出してしまい、「馬鹿にされようが、軽蔑されようが何とも構わない」となれば、どんな困難なことでも必ず実行できるはずなのです。
p.225 人生の目的とは、お金儲けや立身出世など、いわゆる成功を収めることではなく、美しい魂をつくることにあり、人生とはそのように魂を磨くために与えられた、ある一定の時間と場所なのだと私は思うのです。
p.237 「六つの精進」
1.誰にも負けない努力を日々続ける。
2.謙虚にして驕らず。
3.反省のある毎日を送る。
4.生きていることに感謝する。
5.善行、利他を積む。
6.感覚・感性を伴うような悩み、心配事はしない。










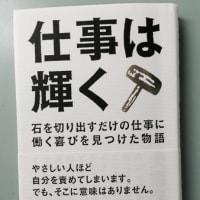
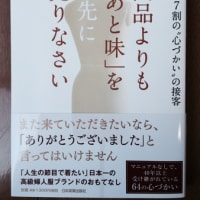
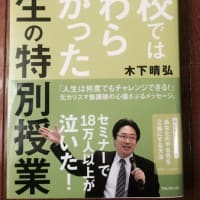
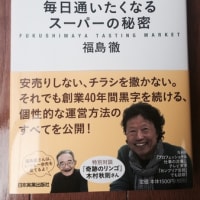
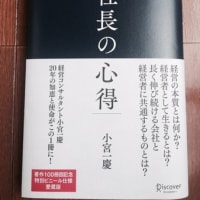
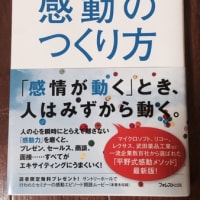
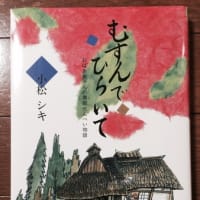
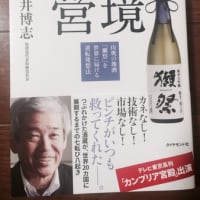
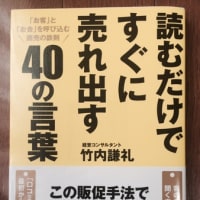
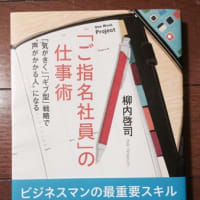





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます