身近な統計の一周目が見終わりました。
なかなか濃い感じ。
事前に「マンガでわかる統計学」を読んでいたのですが、多少は役に立ったかな。
でも放送授業の方がはるかに濃い感じでした。
一部は駆け足で通り過ぎた感じがありますが、印刷教材には書いてあるのかもしれませんね。
印刷教材が届かない状態での受講でしたので、理解できない部分などはネットで調べました。
この方が理解が深まりますね。
やはり受動的な姿勢ではなく能動的な姿勢の方が学びにはいいのでしょう。
授業の後半には社会と統計というテーマで、実際に統計を活用している企業などを紹介するコーナーがあります。
ここまで来ると、あとは今日習ったことのexcelでの使い方と全体のまとめ程度ですから、なんだかホッとします。
数学系の授業は1回の授業を何回かに分けて学ばないとついていけないことが多く、この科目もそうでした。
まして印刷教材なしですから時々止めてはノートを取って、しばらく考えたり調べたりして続きを見るという感じなので、結構時間がかかりました。
このあたりは数学の素養の有無や、どこまで理解したいかによって大きく差が出そうです。
ノートを見直してから過去問に挑戦です。
終わったら、次は心理統計法かな。
授業とネットで調べたことで腑に落ちたことが一つ。
それは、帰無仮説とはなにかということ。
帰無仮説は無に帰する仮説、最後は棄却されるであろう仮説なんですね。
わざと反対の説を唱え、それが棄却されたらその反対が採択される。
例えば新薬が効くかどうかを検証するとき、新薬は効かないと反対のことを唱えるのが帰無仮説。
最終的には無に帰する・棄却されるであろう仮説をまず立てる。
次に、帰無仮説の反対を立てる。
帰無仮説に対立するので対立仮説と呼ぶが、証明したいと思った内容そのもの。
そして統計処理によって帰無仮説が棄却されたら新薬は効くということになり、反対に帰無仮説が棄却できなかった場合は(帰無仮説が正しいとはいわずに)帰無仮説は棄却できない、となる。
これは本当に帰無仮説が正しい場合もあるが、標本数が少なすぎて帰無仮説が正しくなってしまった場合もあるから。
と、いう感じでしょうか・・・。
合っているかな。
帰無仮説を立てるのは、正しいであろう仮説(対立仮説)を証明するために、あえて反対の仮説を立て、反対の仮説が棄却されれば「仮説は正しい可能性が高い」となる。
敵の敵は味方という発想でしょうか。
新薬は効く、という仮説を考えます。
帰無仮説は、新薬は効かない。
対立仮説は、新薬は効く。
新薬が効くということを想定しての検定ですから、調査対象の多くが「効いた」となるはずです。
ですから、効いた人を調べるよりも効かない人を調べて、その割合が一定数以上いたら「この薬は効果ないんじゃないか?」となります。
検定の結果、帰無仮説が棄却されたら「新薬は効く」となります。
(100%効くという意味ではなく、条件付きでですが)
反対に、帰無仮説が棄却できない場合は「新薬は効かない」とはなりません。
「新薬は効かない」という説は棄却できない、となります。
この場合、本当に効かない可能性だけでなく、今回の調査対象者がたまたま効かない体質の人が多かっただけで一般的には効く薬かもしれないのです。
ですから「新薬は効かない」とはならないのです。
・・・間違っていたらごめんなさい。
私の今の理解ではこんな感じです。
なかなか濃い感じ。
事前に「マンガでわかる統計学」を読んでいたのですが、多少は役に立ったかな。
でも放送授業の方がはるかに濃い感じでした。
一部は駆け足で通り過ぎた感じがありますが、印刷教材には書いてあるのかもしれませんね。
印刷教材が届かない状態での受講でしたので、理解できない部分などはネットで調べました。
この方が理解が深まりますね。
やはり受動的な姿勢ではなく能動的な姿勢の方が学びにはいいのでしょう。
授業の後半には社会と統計というテーマで、実際に統計を活用している企業などを紹介するコーナーがあります。
ここまで来ると、あとは今日習ったことのexcelでの使い方と全体のまとめ程度ですから、なんだかホッとします。
数学系の授業は1回の授業を何回かに分けて学ばないとついていけないことが多く、この科目もそうでした。
まして印刷教材なしですから時々止めてはノートを取って、しばらく考えたり調べたりして続きを見るという感じなので、結構時間がかかりました。
このあたりは数学の素養の有無や、どこまで理解したいかによって大きく差が出そうです。
ノートを見直してから過去問に挑戦です。
終わったら、次は心理統計法かな。
授業とネットで調べたことで腑に落ちたことが一つ。
それは、帰無仮説とはなにかということ。
帰無仮説は無に帰する仮説、最後は棄却されるであろう仮説なんですね。
わざと反対の説を唱え、それが棄却されたらその反対が採択される。
例えば新薬が効くかどうかを検証するとき、新薬は効かないと反対のことを唱えるのが帰無仮説。
最終的には無に帰する・棄却されるであろう仮説をまず立てる。
次に、帰無仮説の反対を立てる。
帰無仮説に対立するので対立仮説と呼ぶが、証明したいと思った内容そのもの。
そして統計処理によって帰無仮説が棄却されたら新薬は効くということになり、反対に帰無仮説が棄却できなかった場合は(帰無仮説が正しいとはいわずに)帰無仮説は棄却できない、となる。
これは本当に帰無仮説が正しい場合もあるが、標本数が少なすぎて帰無仮説が正しくなってしまった場合もあるから。
と、いう感じでしょうか・・・。
合っているかな。
帰無仮説を立てるのは、正しいであろう仮説(対立仮説)を証明するために、あえて反対の仮説を立て、反対の仮説が棄却されれば「仮説は正しい可能性が高い」となる。
敵の敵は味方という発想でしょうか。
新薬は効く、という仮説を考えます。
帰無仮説は、新薬は効かない。
対立仮説は、新薬は効く。
新薬が効くということを想定しての検定ですから、調査対象の多くが「効いた」となるはずです。
ですから、効いた人を調べるよりも効かない人を調べて、その割合が一定数以上いたら「この薬は効果ないんじゃないか?」となります。
検定の結果、帰無仮説が棄却されたら「新薬は効く」となります。
(100%効くという意味ではなく、条件付きでですが)
反対に、帰無仮説が棄却できない場合は「新薬は効かない」とはなりません。
「新薬は効かない」という説は棄却できない、となります。
この場合、本当に効かない可能性だけでなく、今回の調査対象者がたまたま効かない体質の人が多かっただけで一般的には効く薬かもしれないのです。
ですから「新薬は効かない」とはならないのです。
・・・間違っていたらごめんなさい。
私の今の理解ではこんな感じです。

















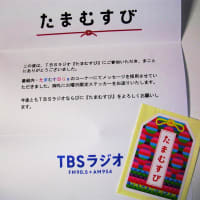
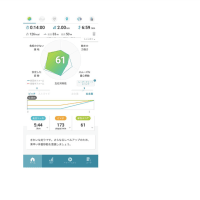

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます