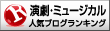谷町ビルというのだろうか……。
下駄履きの公団住宅の、下駄の部分に、劇団大阪の谷町劇場がある。一階のそのドアを開けると、フラットな黒で統一された夢の空間が、そこにある。
三十坪ほどの黒の空間は、入り口を入った右側が演技空間。左側が五段のひな壇になった、100席ほどの観客席。一番遠い席でも、役者との距離が八メートル以上になることが無く、とても集中して芝居の世界に入れる小劇場になっている。
さて、『イノセントピープル』である。
この芝居は、ロスアラモスの女子高生、シェリル・ウッドがポップスにあわせてノリノリで踊っているシーンで始まり、そのシェリルが日本人のタカハシと結婚し、シェリル・タカハシとしての彼女の広島での葬儀で終わる。
その五十年あまりの、シェリルの家族、知人の人生が、前後しながら描写される。
ちなみにイノセントとは、無実の、潔白、潔癖な、無邪気な、などを現す形容動詞である。
このイノセントな人々は、みな人生のどこかで、原爆(核)に関わっている。
ロスアラモスは、ご存じの方も多いと思うが、戦時中から、アメリカが核兵器の開発、実験、製造を行った街である。
シェリルの父は、この原爆の開発に携わった、科学者の一人である。友人や知人もみなそうで、彼らを指してイノセントピープルと、作者は呼んでいるようだ。日本語にせず英語のイノセントの方が多義的で、タイトルとしての含蓄が深く、さすがだなと思った。
登場人物のあるものは、核兵器に罪悪感を持ち、あるものは、正当な武器使用であったと思い。正当であったと思った海兵隊の退役准将は、息子をイラクとの戦争で、米軍が使用した劣化ウラン弾の影響で若死にさせてしまう。
シェリルは、大学でタカハシという日本人と平和活動を通じて知り合い結婚、親や身内の大変な反対を受けながら、結婚、生涯を広島で過ごし、六十代で短い生涯を閉じる。
この芝居、一見シェリルの身の回りの人々の戦後史で、部分的にはドラマとして成立している。シェリルの父や、その同僚たちの苦悩、シエリルの兄が海兵隊を志願し、ベトナム戦争で、下半身マヒの傷痍軍人として帰国、聴衆の前でスピーチするが、おりからのベトナム反戦に出会い、苦悩。彼の身の回りの世話をするヘルパーは、ナバホ族の血が混じっていて、彼女の祖父の世代は硫黄島の戦いで勇戦したこと(たしか映画であった) また、彼女の祖父、父は、居住地からウランが発見され、その放射線で若死にしたこと、などなど盛りだくさん。しかし、後述するが、この芝居の主軸に絡むことがなく、ご都合で持ってきたエピソードでしかない。
そして、肝心のシェリルの人生が描写されていない。
1960年代に日本人と結婚することがどれだけ困難なことであったか。「愛してるの」を数回言わせるだけでスルーしてしまっている。婚約者のタカハシは、仮面を被り、台詞が終盤まで、まるでない。
平和運動への参加への動機も分からない。母の葬儀に顔を出すが、母が入院する最後の日まで自分の部屋の手入れをしてくれたことに涙する描写があって、あとは印象としては、広島での病死になってしまう。
やはり、シェリルの人生、その苦悩と葛藤、自分の人生への誇り、喜びなどがドラマの主軸として表現されなければ完成された戯曲とは言えない。また、シェリルの身内のドラマが、シェリルの人生にほとんど絡んでこないことにも、ドラマ構造の弱さを感じてしまう。
日本人が、アメリカ人を演じることは難しい。表情や、ちょっとした身体表現が日本人とはまるで違う。特に上半身(それも肩の使い方)の動きが、また、顔の表情筋の使い方が違う(例えば、日本人の大半はウィンクができない) 全員がアメリカ人ならばそれでもいいが、日本人が出てくるので、その差別化はやっておかなければならないだろう。
また、日本人が、後半タカハシの例外を除いて仮面というのも異様である。アメリカ人から見た日本人という表現なのだろうけども、もっと日本人を人間として表現して欲しかった。仮面を被っている間は台詞が無い。不気味さが先になって、シェリルが好きになった人間として共感が持てない。それ以上に、日本人の人間としての描き方に共感できない。
シェルリの葬儀で、タカハシが仮面をとって喋る言葉が、ほとんどシェリルの父への、ほとんど糾弾といっていい台詞なのには、思わずうつむいてしまった。こういう糾弾調の言葉は、実生活でも、舞台表現としても、わたしは前世紀で食傷気味である。同席している無言の日本人たち、体を使っての感情表現はできているのだが、どうも非人間的な印象が拭いきれない。黒澤明の『八月の狂詩曲』のような、井上ひさしの『父と暮らせば』などと比べると、知識先行でドラマ性希薄な糾弾劇になってしまったことが惜しまれる。
わたし個人の趣味かもしれないが、シェリルは炒りたてのポップコーンのように元気で、かつクレバーな女性だと思う。最初のポップスで踊っているところなど、まさにポップコーンになっていなければならない。タカハシとの結婚の決意や、平和運動に身を挺するところなど、もっと力強いクレバーさが欲しかった。しかし、けして元気が無く、バカに見えたということではない。いささか日本人的情緒表現になってしまったことが惜しまれるのである。アン・ハサウェーなど、いい見本になると思う。
ラストで、シェリルの娘はるかが、明るい笑顔で臨月に近いお腹を抱えて現れる。これで、未来への希望と和解のシンボルとしたことはよく分かったが、それ以前のタカハシの糾弾(お願い)の始末がつかないままの登場であったのが、フィナーレとしては、やや唐突であった。
原爆の死者を20万人としているが、これは日本側の数字で、アメリカは、この数字をとっているのだろうか。日本の記録でも、一度の爆撃で、最大の死者を出したのは東京大空襲の8万3793人であると思う。
宴曲な表現では通じないので、あからさまになって申し訳ないが、本が、プロットの段階で、未整理なままカタチにしてしまっていることに最大の問題を感じた。
しかし、作家も演出も、原爆とロスアラモスをよく勉強されていて、その博識ぶりはよく分かる。
ロスアラモスについて、とっておきの情報を紹介。
ロスアラモスの研究施設と工場は、空から見ても分からないようにカモフラージュ。そのカモフラージュがふるっている。ディズニープロダクションのスタッフの指導で、屋根の上に街のセットを作った。いかにもアメリカらしく、わたしがロスアラモスを取り上げるなら、この線から迫る。『天空の街・ロスアラモス』なんかどうだろう。
ホリゾントの、グラフィックの作りは、さすがに劇団大阪さんのセンスと技術の高さを感じた。在阪のアマチュア劇団で、これほどの人的、技術的財産をお持ちの劇団は、ちょっと見あたらない。