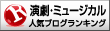誤訳日本の神話・1
『天地のはじめ(アメツチノハジメ)』 
※ 始まりにあたって
わたしは、かつて日本史の教師でした。
わたしが生徒であったころは、日本史の教師はずっと日本史で、古いノート一冊あれば事足りました。気楽な商売でした。一年生の担任になっても日本史とか世界史が自分の持ち教科であれば、一年の地理などは持たずに、二三年生の授業だけを持っていて、自分のクラスにはホームルーム以外は顔を見せない、どうかするとホームルームも生徒任せで、月に数回しかクラスに顔を見せない先生もおられました。
自分が教師になると大違い。たいてい、複数の小教科を兼ね、ノートも、その年その年の教科書に合ったものを作り(教育基本法だったか指導要領だったかに、授業は教科書によらねばならないとあります。それ以上に教科書を大切にさせる=授業に教科書を持ってこさせるため)、なんとか授業のカタチと水準を維持していました。
そのため、自分の専門と思っていた日本史は手薄なものでした。
それで、この歳になって、ちょっと振り返ってみようと思い立ちました。
振り返ってみるにあたっては、記紀神話から始めようかと思います。
地震などの災害で避難した時に、日本人の行儀の良さは有名です。戦後の学校教育の成果……いえ、もっと昔、日本書紀には中国に渡った日本人がリーダーの指示に従い、行儀よく並んでいたという記述があります。
『倭』という日本の古名は中国が付けました。背の低いやつらという意味ですが、もう一つの意味は――従順な奴ら――という意味です。集まれと言えば集まり、待っていろと言われれば大人しく、いつまでも待っています。列に並べと指示があれば世話を焼かすこともなく並んで次の指示を待ちます。こういうことを知っていると、日本人や日本の歴史への親近感が違います。明治以降の悪い教育のせいとは思いません。日本と日本人の祖型というか原風景を感じるには良い方法だと思うのです。しかし、一年間三単位~四単位の時間配当で神話は、せいぜい一時間ほどしか割けません。高校生活でたったの一時間、つまり一生で神話に思いを巡らすのは一時間しか持ちようがないのです。
で、長ったらしい前説を言い訳にして、好き放題に神話を騙って……語ってみようと思った次第であります。
天地(あめつち)のはじめ
その昔、世界の一番始めの時、天界で御出現になった神さまは、お名前をアメノミナカヌシの神といいました。
次の神さまはタカミムスビの神、その次の神さまはカムムスビの神、この三人の神様さまは皆お一人で現れて、すぐに居なくなりました。
次に国ができたてで水に浮いたサラダオイルのように、またクラゲのようにふわふわ漂つている時に、泥の中から葦が芽を出してくるようなスピードで現れた神さまは、ウマシアシカビヒコヂの神、次にアメノトコタチの神でありました。この神さまがたも皆お一人で御出現になつて、すぐに居なくなってしまいました。
それから続々と現われ出た神さまは、クニノトコタチの神、トヨクモノの神、ウヒヂニの神、スヒヂニの女神、ツノグヒの神、イクグヒの女神、オホトノヂの神、オホトノベの女神、オモダルの神、アヤカシコネの女神、それからイザナギの神とイザナミの女神とでした。このクニノトコタチの神からイザナミの神までで、神代七代と言います。
最後のイザナミにいたる神さままでは実体がありません。ただ名前が出てくるだけです。
いろんな面倒くさい解釈がありますが、わたしはハッタリだと思っています。いわばイザナギ・イザナミの出現にモッタイを付けるためのイントロの役割にすぎません。映画や舞台でも、主役がいきなり出てくることはありませんよね。
このイントロにあたる部分は、たいていの神話や宗教の伝記にはあり、聖書などノアが出てくるまでアダムとイブから何十人も出てきて、箱舟のあとノアの子孫からキリストが出現するまで、長編小説が二冊書けるほどの人物とストーリーがあります。
まあ、キリスト教はユダヤ教という土壌を持っているせいもありますが、日本の神話は、わずか神代七代に過ぎません。スカートで言えば膝上5センチ程度で、シンデレラほどの長さはありません。まあ、女子高生のスカートほどの軽やかさです。無ければ上着だけのスッポンポンで、どうにもなりませんが、ベルばらのマリーアントワネットほどの仰々しさでもありません。
寝っ転がってポテチを齧りながら読んでいける軽さでやっていこうと思います。自分のイメージに合わない所は、好き放題に付け加えたり、膨らましたりしようと思います。最後まで行きつけるかどうか分かりませんが、とりあえず、始まりでした。