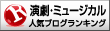ボク(ケンジ)は二十歳になった今も十歳の時の自分が心の中にわだかまっていた。 十歳のときに両親は離婚、作家である父には新しい彼女(カオルさん)ができる。 カヌーに興味のあるボクは、カヌーのパドルを持って父を訪れ、カオルさんに出会う。 そんな大人の状況を受け入れることができず、心の中では、カオルさんに好意的な気持ちを持ちながら、 素直に状況を受け入れることができず、 一人神田川にカヌーを浮かべ、海にまで漕ぎ出てしまうボク。 心配する大人達。 ボクの心を知って身を引くカオルさん。 そのボクに二十歳のボクが寄り添い、過去を取り戻そうとする。 多感なな少年時代のボクの心を中心に物語は、ホンワカとやさしく、 少し切なく流れていく。 カヌーとともに……
キャラメルボックスの成井豊さんの、 温かく人間を描いた秀作でありました。 二百ちょっとぐらいのキャパのA&Hホールは満席の盛況ぶりでした。客席と同じ高さの平土間に、淡いエンジ色の地がすり。 白くうねった簀の子状の切り出しが、上下と中央に。 中央の切り出しは二枚の切り出しが重なっており、芝居の場に合わせて、 開かれたり、 閉じられたり。 開かれた時も上下が逆になって、 川のうねりを上手く表していました。 そして芝居の優しい流れにきちんとマッチしていて、 簡素ではありましたが、実に効果的に作られ、 使われていました。 過去わたしが観た芝居の中でも秀逸な装置であったと思いました。 昨年の『法王庁の避妊法』は、 リアルな田舎の医院を見事に見せていただき、 今回の詩的な道具は、 いい意味で意表をつかれました。
開場したときから、 中央の机の上の砂時計がトップサスに照らされ、 何事かを暗示しているように思いましたが、 二十歳のボクが砂時計を逆さにすることで、 時間を十歳のボクの時代に戻すことが分かり、 観客は自然に十年の時を登場人物と共にさかのぼることができました。 原作にない表現だとしたら演出と美術は、 いいセンスを持っていらっしゃると感じました。
さて、 芝居は二十歳のボクのモノローグからはじまりました。 舞台の折々に二十歳のボクは姿を現し語ります。 ここ難しいですね、 状況を説明するだけに終わって、 観客の関心をそいでしまいます。 最初のモノローグで「いけるかなあ」と、 正直思いましたが、 なんとか持ちこたえていました。 わたしの悪い癖で、台詞をしゃべっていない役者さんを見てしまいます。 リアクションが弱かったり、カタチだけで終わってしまっていたりしたところがありました。 例えば、 十歳のボクが家庭教師のコーキチくんから、カヌーのパドルをもらったときの喜び などは少し苦しかったように感じました。 しかし、 この芝居は、 どこか優しく爽やかなのです。 それは若い役者さんたちの芝居に取り組む姿勢の良さだと感じました。 無理な表現はせず、 自分たちの力の中で溌剌と演じていらっしゃるのが、 この作品が持っている人間への優しい視線とあいまって舞台の空気を柔らかくも、 力強く見せてくれました。 ラストのキャスト八人の歌とダンスも、 自然な盛り上がりの中で良かったと思いました。 観客のみなさんの拍手はカーテンコールを温かく求めていました。
ただ一つ不満に思うのは、 小屋が大阪の中心からやや遠いのと、 初めてきた観客は場所が分かりづらいことです。 まあ、 わたしの方向音痴のせいもありますが。
一度、 もう少し大きなホールで、 若手とベテランの役者さんで芝居を見せてもらいたいと思いました。 大阪放送劇団は、 今は貴重になった自然で豊かな芝居のできる劇団です。 次回作も期待しています。
大橋むつお