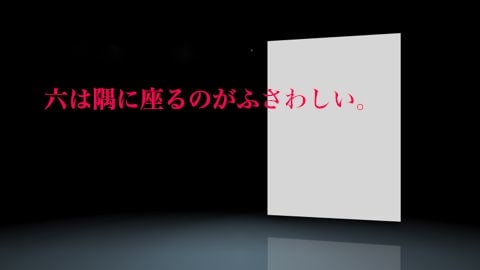*写真は本文には関係ありません。雪の稲沢操車場です。
戦中戦後、疎開先での風呂は母屋でのもらい風呂で、しかもその母屋が大家族ときて、母や私が入るのは十人以上が入った最後であった。
20Wの裸電球しかない五右衛門風呂であったが、私たちの入る頃にはすでに湯は汚れきっていて、どろどろした感さえあった。農作業を終えた人たちの後だから致し方なく、それでも入れるだけましだった。
父がシベリアから復員し、何やかやあって岐阜へ戻れたのは昭和25年(1950年)であった。嬉しかったのは、借家ではあったが風呂付きであったことだ。
40W程の明るい電球のもと(蛍光灯というものはまだなかった)、きれいな湯に入ることができた。
しかしである、内湯がありながらも毎日風呂を沸かすことはなかった。水道代、ガス代などからしてそれは贅沢極まりないことだったのだ。風呂を沸かす日は週にニ、三回だったと思う。
しかし、私はそのころ小学校の高学年で、育ち盛りの遊び盛りとあってよく汗をかき、またどろんこになって帰ったりした。
そんな時は「風呂屋へ行っといで」という母の言葉を背に小銭をもらって銭湯へ出かけた。

うちの風呂も良かったが、銭湯もまた楽しかった。
広々としていて、当時の木桶がタイルに当たる音かカラカラ~ンとこだまして独特の雰囲気を醸しだしていた。
「とおちゃん、石鹸投げるよっ」と女湯から声がかかり、「よっしゃ」と亭主が答えると白い塊が(その頃は白しかなかった)境の壁越しに飛んで来るのだが、無事キャッチということはほとんどなく、タイルの上を滑る石鹸を亭主が追いかけたりする姿が面白かった。
石鹸も貴重品だったから、庶民の家では一家にひとつだったのだ。
風呂からあがると、たしか一本5円だった「みかん水」を飲むのが楽しみだった。これは今では見かけることはないが、駄菓子屋などでも売っていて、当時の清涼飲料水の代表格であったサイダーやラムネより安かったせいで私たち子供がよく飲んだ。
みかん水を味わいながら脱衣場にいると、よく見かける初老のおっさんが上がってきて、その人に視線が吸い寄せられるのだった。
というのは、その人の湯上り後の仕草が実に粋で絵になっていたからだ。
まず体中を手拭いでくまなく拭き上げる。
当時、銭湯へ持参するのは手拭いであった。
タオルや、バスタオルなどという派手なものが登場するのはもっと後のことだ。

さて、そのおっさんだが、からだを拭き上げると必ず行う儀式があった。
それがこの文章のタイトルにした「股間をパシッ!」である。
絞り上げた手拭いで最後の仕上げとして股間を打つのである。
そのパシッという音の響きが素晴らしく惚れぼれとするほどであった。
おっさんはそれを終えるとダボシャツにステテコ(通販で売っている今様のカラーのものではなく純白のもの)、それに腹巻というスタイルでさっそうとのれんを肩で分けて出てゆくのであった。
とにかく、かっこ良かった。
あるとき、私も真似をしてみた。
からだを拭き上げてから手拭いを振りかざし、エイッとばかりに股間に打ち下ろした。
トンガラシのようなオチンチンを刺激するには充分な効果はあったが、とてもパシッと言う渇いた音は出なかった。
バサッ、あるいはズタッという音にもならない情けない音が申し訳程度にするのみだった。
実に多くのの銭湯が消えてゆくなか、その銭湯はいろいろ趣向を凝らして今も残っている。そして時折私はその前を通りかかる。
その都度、みかん水を飲みながら眺めていた「股間をパシッ!」を思い出すのである。60年前に目を丸くしてそれを眺めていたあの可憐な少年はどこへ行ったのだろうといぶかしく思いながら・・・。
戦中戦後、疎開先での風呂は母屋でのもらい風呂で、しかもその母屋が大家族ときて、母や私が入るのは十人以上が入った最後であった。
20Wの裸電球しかない五右衛門風呂であったが、私たちの入る頃にはすでに湯は汚れきっていて、どろどろした感さえあった。農作業を終えた人たちの後だから致し方なく、それでも入れるだけましだった。
父がシベリアから復員し、何やかやあって岐阜へ戻れたのは昭和25年(1950年)であった。嬉しかったのは、借家ではあったが風呂付きであったことだ。
40W程の明るい電球のもと(蛍光灯というものはまだなかった)、きれいな湯に入ることができた。
しかしである、内湯がありながらも毎日風呂を沸かすことはなかった。水道代、ガス代などからしてそれは贅沢極まりないことだったのだ。風呂を沸かす日は週にニ、三回だったと思う。
しかし、私はそのころ小学校の高学年で、育ち盛りの遊び盛りとあってよく汗をかき、またどろんこになって帰ったりした。
そんな時は「風呂屋へ行っといで」という母の言葉を背に小銭をもらって銭湯へ出かけた。

うちの風呂も良かったが、銭湯もまた楽しかった。
広々としていて、当時の木桶がタイルに当たる音かカラカラ~ンとこだまして独特の雰囲気を醸しだしていた。
「とおちゃん、石鹸投げるよっ」と女湯から声がかかり、「よっしゃ」と亭主が答えると白い塊が(その頃は白しかなかった)境の壁越しに飛んで来るのだが、無事キャッチということはほとんどなく、タイルの上を滑る石鹸を亭主が追いかけたりする姿が面白かった。
石鹸も貴重品だったから、庶民の家では一家にひとつだったのだ。
風呂からあがると、たしか一本5円だった「みかん水」を飲むのが楽しみだった。これは今では見かけることはないが、駄菓子屋などでも売っていて、当時の清涼飲料水の代表格であったサイダーやラムネより安かったせいで私たち子供がよく飲んだ。
みかん水を味わいながら脱衣場にいると、よく見かける初老のおっさんが上がってきて、その人に視線が吸い寄せられるのだった。
というのは、その人の湯上り後の仕草が実に粋で絵になっていたからだ。
まず体中を手拭いでくまなく拭き上げる。
当時、銭湯へ持参するのは手拭いであった。
タオルや、バスタオルなどという派手なものが登場するのはもっと後のことだ。

さて、そのおっさんだが、からだを拭き上げると必ず行う儀式があった。
それがこの文章のタイトルにした「股間をパシッ!」である。
絞り上げた手拭いで最後の仕上げとして股間を打つのである。
そのパシッという音の響きが素晴らしく惚れぼれとするほどであった。
おっさんはそれを終えるとダボシャツにステテコ(通販で売っている今様のカラーのものではなく純白のもの)、それに腹巻というスタイルでさっそうとのれんを肩で分けて出てゆくのであった。
とにかく、かっこ良かった。
あるとき、私も真似をしてみた。
からだを拭き上げてから手拭いを振りかざし、エイッとばかりに股間に打ち下ろした。
トンガラシのようなオチンチンを刺激するには充分な効果はあったが、とてもパシッと言う渇いた音は出なかった。
バサッ、あるいはズタッという音にもならない情けない音が申し訳程度にするのみだった。
実に多くのの銭湯が消えてゆくなか、その銭湯はいろいろ趣向を凝らして今も残っている。そして時折私はその前を通りかかる。
その都度、みかん水を飲みながら眺めていた「股間をパシッ!」を思い出すのである。60年前に目を丸くしてそれを眺めていたあの可憐な少年はどこへ行ったのだろうといぶかしく思いながら・・・。