カウンターの隅フェチという客がいるようだ。通いつめた店っへいっても、隅が空いてないと帰ってきてしまうというぐらいなのだ。しかし、そこはよくしたもので迎え撃つ客どもも常連、したがって相互の癖もわきまえていて隅に座っているのがいても、彼が行くと「オッ、隅さんが来た」といってサッと席を代わってくれたりする。
ときおり気のきかないドシロウトが隅に座っていて退こうとしなかったりすると、隅さんはプイと踵を返し、何やら呪いの言葉をつぶやきながら店を出るのであった。
その退こうとしなかった客が店を出た途端、車にはねられたとか、野良犬にガブリとやられたという話がまことしやかに伝わると、もはやそれは完全な都市伝説ともいえる。
何を隠そうかくいう私もカウンターに座る場合隅のほうが好きだ。上に述べた隅フェチさんほどではないし、別に謙虚でいっているわけでもない。そのほうが落ち着くし、ひとさまに干渉されることも少ないからだ。
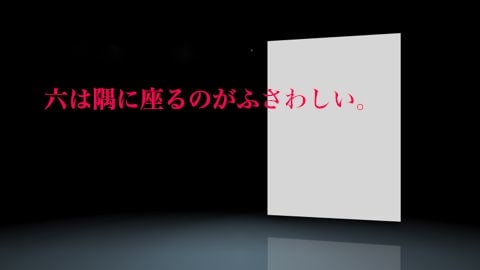
かつて、といってももう何十年も前の話だが、直ぐに目を通したいような本を買って、ときどき立ち寄る居酒屋に入った。カウンターだけのその店はあいにく真ん中のひと席しか空いていなかった。ちょっと悪い予感がしたが、そこで踵を返すほどの隅フェチではない私は、そこに座を占めてしかるべく注文をし、早速入手した本を読み始めた。店主にとっては手のかからない客であるといってもよい。
しばらくするとフイに横から罵声が飛んだ。
「こんなところで本なんか読みやがって、カッコつけるんじゃないよ!」
声の主はいかにもその筋のおにいさんで、さっきから連れの女性と何か口論めいたおしゃべりをしていたのだが、どうやら言い負けてその腹いせがこちらへ回ってきたらしい。あわせて居酒屋で本を読むという私の習慣がなにか気障なものに見えたのだろう。
困惑して店主の方を見ると、自分には関わりのないことのようにそっぽを向いている。この店で本を開くのは初めてではなく、それまでしばしばあったことだった。ただし、いつもはカウンターの隅でのことであった。
私は本を閉じた。そしてそのおにいさんにいった。
「お気に触りましたか。こうして飲みながら本を開くのは私の癖でしてね。でもまあせっかくのお楽しみを邪魔しては何ですから、今日はやめさせて頂きます。大将、お勘定はいくらでしょうか」
私はできるだけ卑屈にならないように語気もはっきりと述べて席を立った。
もちろん注文したばかりの酒肴はまだ残っていた。
「いや、別に帰らんでも・・・」とおにいさんは口ごもった。
店主はまごまごしている。
「これでいいですか?」
と私はしかるべき金額をカウンターに置いた。
「あ、お釣りが・・・」
といって店主は慌ててレジからそれをもってきた。
その間、一切、私と目を合わそうとしない。
外の空気は爽快であった。
以来、その店には一度も足を運んだことはない。
しばらく前に偶然通りかかったら、携帯のショップか何かになっていた。
やはり、カウンターは隅のほうが無難なようだ。
ときおり気のきかないドシロウトが隅に座っていて退こうとしなかったりすると、隅さんはプイと踵を返し、何やら呪いの言葉をつぶやきながら店を出るのであった。
その退こうとしなかった客が店を出た途端、車にはねられたとか、野良犬にガブリとやられたという話がまことしやかに伝わると、もはやそれは完全な都市伝説ともいえる。
何を隠そうかくいう私もカウンターに座る場合隅のほうが好きだ。上に述べた隅フェチさんほどではないし、別に謙虚でいっているわけでもない。そのほうが落ち着くし、ひとさまに干渉されることも少ないからだ。
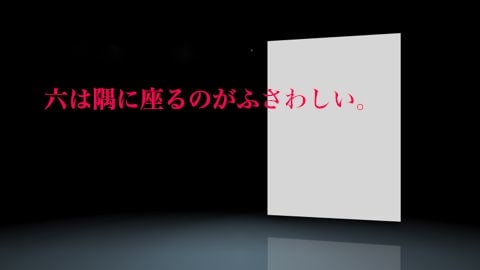
かつて、といってももう何十年も前の話だが、直ぐに目を通したいような本を買って、ときどき立ち寄る居酒屋に入った。カウンターだけのその店はあいにく真ん中のひと席しか空いていなかった。ちょっと悪い予感がしたが、そこで踵を返すほどの隅フェチではない私は、そこに座を占めてしかるべく注文をし、早速入手した本を読み始めた。店主にとっては手のかからない客であるといってもよい。
しばらくするとフイに横から罵声が飛んだ。
「こんなところで本なんか読みやがって、カッコつけるんじゃないよ!」
声の主はいかにもその筋のおにいさんで、さっきから連れの女性と何か口論めいたおしゃべりをしていたのだが、どうやら言い負けてその腹いせがこちらへ回ってきたらしい。あわせて居酒屋で本を読むという私の習慣がなにか気障なものに見えたのだろう。
困惑して店主の方を見ると、自分には関わりのないことのようにそっぽを向いている。この店で本を開くのは初めてではなく、それまでしばしばあったことだった。ただし、いつもはカウンターの隅でのことであった。
私は本を閉じた。そしてそのおにいさんにいった。
「お気に触りましたか。こうして飲みながら本を開くのは私の癖でしてね。でもまあせっかくのお楽しみを邪魔しては何ですから、今日はやめさせて頂きます。大将、お勘定はいくらでしょうか」
私はできるだけ卑屈にならないように語気もはっきりと述べて席を立った。
もちろん注文したばかりの酒肴はまだ残っていた。
「いや、別に帰らんでも・・・」とおにいさんは口ごもった。
店主はまごまごしている。
「これでいいですか?」
と私はしかるべき金額をカウンターに置いた。
「あ、お釣りが・・・」
といって店主は慌ててレジからそれをもってきた。
その間、一切、私と目を合わそうとしない。
外の空気は爽快であった。
以来、その店には一度も足を運んだことはない。
しばらく前に偶然通りかかったら、携帯のショップか何かになっていた。
やはり、カウンターは隅のほうが無難なようだ。




























面白く拝読致しました。 いま大寒は禅庭は大変ストイックな表情をしています。 機会があれば行かれては?
jien