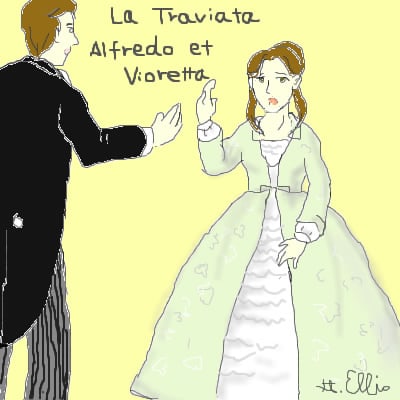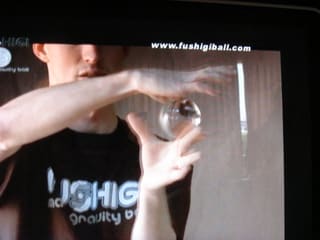毎朝毎朝ニュースを見て怒り心頭の今、ある意味一番話を聴きたかった人に会えました。
金美鈴さん。
御存じ、日本人より日本を愛する、日台のマドンナ。
TОの所属する某会で話を伺う機会があると聞き、駆け付けました。
金さんはご存知のように日本に帰化した台湾人。
留学で在日中、台湾独立運動に参加したため、長い間台湾に帰ることを許されませんでした。
2006年まで台湾総督府で政策顧問の仕事に携わっていましたが、現在もメディアで子育て、教育、社会、政治などへの提言を行っています。
この日の金さんは秋らしい紫色のベルベットのジャケットにロングスカート、
足許はなんとネイビーブルーのスニーカー。
76歳とは思えない美しさです。
小柄でほっそりした体で登壇するや、ハリのある声で一言。
「私の講演では私語は許しません」
多忙を極める金さんが今回異例ともいえるこの会でのスピーチを引き受けたのは、紹介者Y氏の亡くなった兄上の縁だそうです。
Y氏の兄上は昔台湾に留学していたころ、国際文化会館で館長秘書だった金さんに日本で勉強するように勧めていたのですが、記者として乗り込んでいた船が金門島の砲撃に巻き込まれ客死してしまいます。
親しい友人であり、留学の手引きをしてくれるはずたった人を亡くしたショックで打ちひしがれる金さんの前に現れたのがY氏の母上でした。
「息子があなたとした約束を果たすために来ました」
金さんは母上の尽力で早稲田大学に留学します。
この何より日本人らしい日本人との出会いが、金さんを「日本人より日本を愛している台湾人」たらしめる最初のきっかけだったのです。
さて、御存じのように日本は1945年までの50年間、台湾を統治していました。
韓国と違って、台湾の7割以上の人は,現在も日本統治を評価しています。
もちろん、統治という体制の中に光があれば影もあったわけで、喰いつめ者や、権力をかさに着る程度の悪い日本人がいたことも事実ですが、日本は初めて得た統治領土をあくまでも正しいルールに則って経営し、心血を注いで本土並みにしようと、惜しげもなく金や人を送り込みました。
この統治のときに台湾に植え付けられた
「約束を守ること」
「向上心」
「清潔観念」
などの美点は、いまだに台湾社会の規範となっており、それを以て光の部分を台湾人は公平に評価しているのだということです。
日本が敗け、去った後の台湾に蒋介石がやってきました。
台湾の人々は、日本統治時代の清潔で公平な社会を懐かしむようになります。
その後、李登輝総統のもと、自由と民主を旗印に独立運動が起こり、現在に至るわけですが、台湾人と言っても中国本土から来た台湾人は台湾の独立を認めず、なおかつ日本に対して反日を続けています。
ですから尖閣諸島で台湾からの船が出ていくようなことがあるとき、それはほぼ100パーセントの確率で「本土出身台湾人」なのだということです。
「尖閣諸島」
先週、バカミンスがやくざ国家中国が放った当たり屋船長を釈放してしまいました。
日頃民主ヨイショに余念のないコメンテーターさえ不満を口に出し、
日頃全く政治問題に興味を持たないそのへんの主婦ですら「おかしい」といい、
あの選挙で民主に入れた『自民お灸派』『やらせてみよう派』でさえも「何をやっている!」
海軍搭乗員の会で元大尉が言われた
「いやなニュース」
の最たるものが、これだったのではないでしょうか。
国士、金美鈴が尖閣問題について何をしゃべるのか。
この言葉が出たとき会場は(最初からですが)静まり返りました。
「途中で折れるなら、最初からしないほうがまし。
中国という国は日本とは全く違います。
彼らはどんなカードを使ってでも、卑怯と言われようが何と言われようが自国の国益とプライドしか守るつもりはありません。
お人よしの日本人が「落とし所」
などと甘いことを言い、「釈放したからフジタの4人返して」などといっても、
「それとこれとは別、釈放するなら悪かったって認めたんだから賠償と謝罪よこせ」
とにべもありません。
取れる利益は取る、自分が悪いなどとは決して思っていない。
しかし、ある意味それは国家として当然のことなのです」
甘いのは、愚かなのは、あの中国に対してあのような外交しかできないアマチュア政権をマスコミに煽られて選んでしまった日本人なのだ、と金さんは憤懣やるかたない様子で語りました。
そして、経済という「目先の金」欲しさにふらふらした外交をしているうちに、国体は無茶苦茶になってしまう。
しかしながら、国益を守らずして、長期的に経済的な安定などはありえないのだと。
(確かに昨日時点で経団連がさっそくこれ以上の土下座を要求しているようです)
そして、もっとも重要なのは、この問題は日中の間だけのものではない、ということ。
中国は、南沙諸島、東沙諸島でいろんな国と領土問題を起こしています。
先進国であり、アジアの発言力が大きい日本が中国に対してどう対応するかは、世界中が、とりわけこの当事国などは息をを飲んで見ていたはず。
しかしこのていたらくです。
「ノーと言えない日本に皆がっかりしています」
と金さん。
ある雑誌が「中国にモノ申す」というタイトルでコメントをいただきたい、と言ってきたそうです。
金さんはそれに対して
「中国は法治国家ではない、人治国家です。
そんな国に言うことなど何もないし、言っても無駄です。
言いたいことがあるとすればそれは日本人に対してです。
はっきりものを言え、途中で節を曲げるな、国を愛せと」
と答えたそうです。
65年もの間、中国と言うブラックホールに飲み込まれずに、いまだ台湾が国体を維持している理由の一つに「台湾人の愛国心」があります。
かつて「朝まで生テレビ」に出演した金さんは、そこで福島瑞穂の信じられない発言を耳にしたそうです。
「そんなこと言って、けっこう福島さんも愛国心あるんですね」
出演者の一人の揶揄に対し、福島瑞穂は顔の前で手を振り、
「ありませんありません!」
と大慌てで否定したというのです。
「こんな国会議員が大臣をやり、北朝鮮の代弁者でしかない辻本清美のようなものが議員に当選する。
一体日本はどういう国なんですか!」
この日、金さんが登壇した壇上には日の丸が掲揚されていました。
登壇前金さんは国旗に丁重に一礼。
公演後席に戻る前に今一度一礼。
講演後、御挨拶に伺いました。
間近に見る金さんのチャーミングな笑顔に魅了されてしまいましたが、金さんの方でも、おじさんばかりのこの会にわざわざゲスト参加で話を聴きに来たエリス中尉に少し興味を持たれたらしく、「ぜひ○○の方にも遊びにいらっしゃい」と言っていただきました。
金さんが言った、
「昔の日本人が持っていたもので失われたものがある。
今こそそれを問われているのではないですか。
日本は、台湾のために日本であってほしい。
台湾は日本のために台湾でいたいと思っています」
という言葉と、国旗に礼をする金さんの姿を見て、思わず感極まってしまったのに・・・
最後に挨拶した人が言った、
「(言いたいことを言ってくれて)なにか胸がすっとしたような」
という言葉にずっこけました。
違うでしょそれ。
金さんは「あなたたちのような方にちゃんと声をあげていただきたい」
って最後に言ったんだぞ。
すっとしている場合じゃないってば。











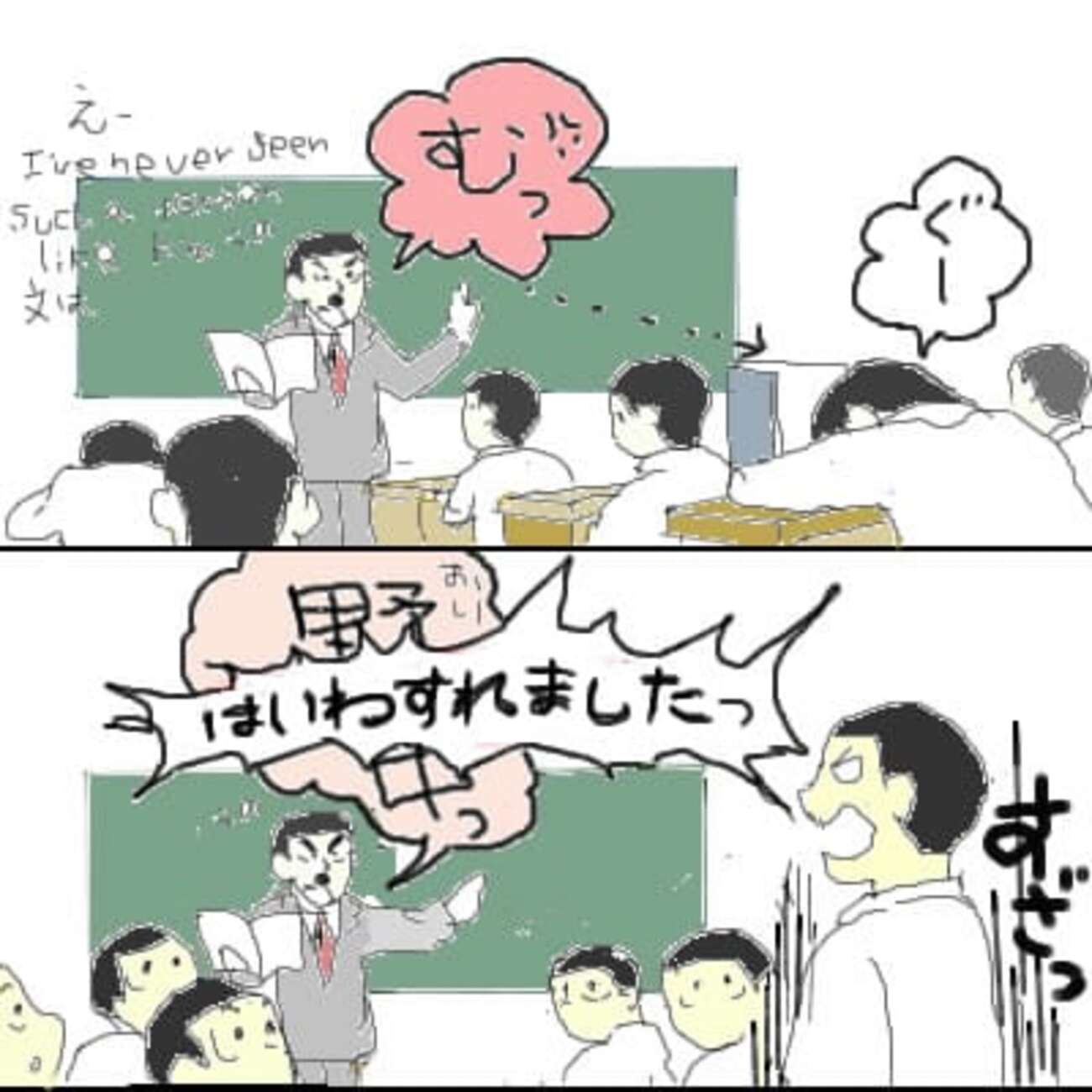







 フランス料理そのものが今日本ではあまりありがたがられず、特に「重い感じ」が避けられる傾向にあるので、メインダイニングはここもイタリアンのようですが、一階はカフェ風フレンチ。
フランス料理そのものが今日本ではあまりありがたがられず、特に「重い感じ」が避けられる傾向にあるので、メインダイニングはここもイタリアンのようですが、一階はカフェ風フレンチ。