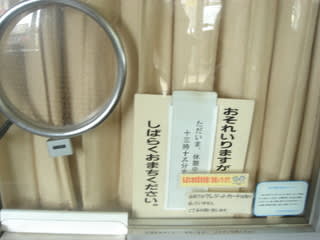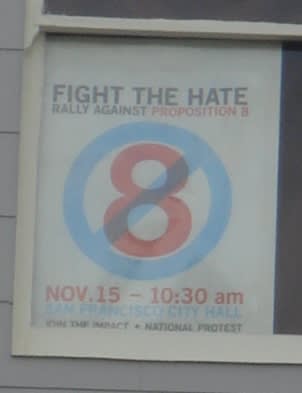この画像を見て「和製スパイ映画の主人公みたい」と思った方。
あなたは正しい。
イアン・フレミングのスパイ映画007シリーズは、この映画公開時の1966年、
すで12作目の「黄金銃を持つ男」の公開を終えていました。
この映画が、このシリーズの人気にあやかって作られたのかも、
となんとなくこの写真から推測しているのですが・・・・・。
この「和製ジェームズ・ボンド」(と呼ばれていたのかどうかは知りませんが)、
映画「陸軍中野学校」で、主人公椎名(三好)次郎を演じる市川雷蔵。
時代劇で大人気だった役者が現代ものに挑戦した異色作です。
フィリピンのルバング島で密林に暮らし、終戦を知りつつ30年日本兵として戦っていた
小野田寛郎氏が陸軍中野学校出身の情報将校であったことはご存知でしょうか。
小野田氏は「諜報諜略の科学化」を目的に陸軍省が1938年設立した軍学校
「陸軍中野学校二俣分校」の「退校命令」(卒業とは言わない)を受けています。
この大映映画「陸軍中野学校」は、
その創設時、第一期生徒となり「軍のスパイ」となった青年の成長と苦悩を描きます。
主人公三好次郎は、東京帝大を出た陸軍少尉。
ある日草薙中佐と名乗る男(加東大介)に風変りな質問を浴びせかけられる。
机の上にいきなり地図を広げ
「チモール島はどこにある?」
「この地図にはチモール島は書いてありません」
「地図の下、机の上には何と何があった」
「軍帽、カバン、万年筆、湯呑茶碗、煙草」
「煙草はなんだ?」
「チェリーです。・・・・マッチ、灰皿」
「灰皿の中には?」
「吸殻が二本ありました」
この試験に合格した三好は、やはり有名校を卒業した選ばれし陸軍士官18人と共に
国家のスパイとなるために中野学校の訓練を受ける。
名前を捨て、過去を捨て、母も、恋人も、将来の夢さえも捨てて。
と、映画の予告風に説明してみましたが、この陸軍中野学校出身の元軍人は、
「功を語らず、語られず」
「サイレント・ネイビー」に相当する理念をまず教育されました。
中野学校について語る出身者がほとんど現れず、秘められた歴史のようになっているのも、
彼らが戦後口を閉ざし続けた所為であるといわれています。
「名誉や地位を求めず、日本の捨て石となって朽ち果てること」
が信条であったというのは戦時の軍人としてごく自然なことであったと思われますが、
その一方で一般の陸軍的な常識とは一線を画した
「生きて虜囚の辱めを受けても生き残り、二重スパイとなっても敵を混乱させるなど、
あくまでも任務を遂行するように」
という教育をされていました。
ルバング島で小野田少尉が終戦を知っていながら30年を投降せず生き抜いたその精神力の源には、
この「生き続けてそのうち任務を遂行せよ」という命令に対する忠誠があったと言われています。
日本に帰国せよという説得に肯んじなかった小野田少尉がそれを承諾するのには、
かつての上官であった谷口義美元少佐の任務解除、帰国命令の下命を待たねばなりませんでした。
この映画では、この中野学校の「スパイ訓練」が描かれます。
武道はもちろんのこと、思想学、統計学、戦争論、兵器学などの一般教養、
飛行機や自動車操縦、射撃に始まり、諜報に必要な海外情勢、
語学、心理学や薬物学(毒殺法含む)など。
おっと、スパイには変装術や手紙の偽装などの通信術、手品の手法や金庫破りも必須。
身をやつすためにコックや仕立て屋などの特殊技能を身につける授業も。
ダンスを巧みにこなし、女性をたぶらかすためのジゴロのようなテクニックも伝授されます。
一般世間に紛れ込むために生徒は髪を伸ばし、背広がユニフォーム。
彼らが主に一般大学の出身者から選ばれたというのも「世間慣れしているかどうか」が重視されたためです。
映画では「六大学勢ぞろいだな」と笑いあうシーンがありましたが、東大出身が一番多かったそうです。
実際は、士官姿に憧れて任官した一部の訓練生などが、軍服が着られないことに不満を持ったり、
この映画の主人公のように知人の前から全く姿を消すというわけでもなかった若い諜報将校たちは、
何故髪を伸ばすかとか、背広を着るかなどという説明が家族にできないので大変困ったという話です。
(浦安にある某鼠施設では、そこで働いていることを友人知人は勿論、家族にも言わないように
というマニュアルがあると聞いたことがありますが、これをふと思い出してしまった・・・)
この映画は、秘められた陸軍史の奔流に身を投じられた一青年が、
愛する人をも犠牲にしながらその使命に向かって突き進む姿をサスペンス風に描いて、
非常に質の高いエンターテイメント作品となっています。
タイトルから「戦争もの」だと思って観た人は、おそらくかなり驚くのではないでしょうか。
(例えばわたしとかですね)
この第一作は好評だったと見え、「陸軍中野学校シリーズ」は、この後続編が四つ製作されています。
拾い物といっては失礼ですが、思いもよらず面白い映画を見つけた、という軽い興奮を感じました。
なので、この後もこのシリーズ、ウォッチングを続けてみます。
その時にまた、市川雷蔵に対するコメントなども織り込んでいくつもりですが、
今日はこの映画の予告編をシナリオ風に掲載しますので、
もし興味をお持ちになった方は観てみてくださいね。
草薙少佐「戦争においてスパイがいかに重要な働きをするか諸君も知っているはずだ。
日本のため、身を捨ててスパイになってくれ。この草薙と一緒に働いてくれ!」
ナレーター 教科は、殺人、誘拐、盗み、女の・・・・あらゆる実地訓練!
生徒「手塚!中野学校の名誉のために死んでくれ!」
手塚「よし、みんながそんなに俺を殺したいなら、見事に死んでやる!」
みんな「よし、行け!」
手塚「うわあああああああ!」
(級友の持つ刀に自ら突っ込んでいく手塚)
ナレーター スパイには失敗は許されない
草薙中佐「じゃ俺の中野学校で盗んでやろうか。英国のコードブックを」
仕立て屋に変装した椎名「この間の情報、いかがでした?」
E・H・エリック「領事に相談したら、買うと言っていた」
中野学校に敵意を持つ陸軍少佐
「暗号本部から漏れた?貴様ぁ、参謀本部を侮辱すると許さんぞ!
ここは日本陸軍最高の機関だ」
ナレーター 親を捨て戸籍を消し 今また 最愛の女を毒殺する
陸軍スパイ学校の全貌を、初めて描いた
衝撃の異色大作!
陸軍中野学校! (クラシック風の重厚なBGM)
・・・・ところで、この映画に描かれていること、元陸軍中野学校の方のお話によると
80パーセントが実話
だそうですよ。
・・・。(絶句)