
マンション・デベロッパー大手の穴吹工務店が24日、会社更生法を申請し実質倒産しました。穴吹工務店と言えば愛媛県の地方都市の一建設業が全国区にのしあがり、マンション供給ナンバーワンにまで上り詰めたいわば“地方の星”的企業でした。1905創業の100年企業でもあったものがなぜ倒産の憂き目にあったのか、その経営者からは学ぶべき教訓が大いにあるように思います。
その前に、穴吹工務店の発展と今回の倒産劇に至った経緯です。穴吹工務店が成長軌道に乗ったのは、先代がマンション施工・販売に本格参入した80年代後半。後を継いだ創業家の穴吹英隆社長は、若い発想を存分に活かしてブランド化を進めました。マンション・ブランド「サーパス」の立ち上げと野球、バスケットボールなどスポーツ支援によるイメージ戦略が功を奏し知名度は一躍全国区になり、安価でありながらそのブランド力にものを言わせて売上は右肩上がりに上昇しました。ところが、昨年のリーマン・ショック以降の不景気と不動産価格の下落が状況を一変させました。そして、再建方針を巡っての社長と他の役員との対立。10月には社長以外の全取締役を全員解任するための株主総会が召集される動きにまで至りました。結局、総会開催は見送られ解任は撤回。事態は収拾に向かいますが、この一件が及ぼした信用失墜のダメージはことの他大きく、結局信用収縮が今回の倒産を招いたと言えます。
問題は、倒産の引き金となった、社長はなぜ役員全員を解任すると公表するような事態を招いたかです。私が思うところを一言で言えば、こんな異常事態に陥った原因は「経営者の驕り(おごり)」以外にないと考えます。しかも想像するに英隆社長の「驕り」には、経営者が最も注意すべき3つの「驕り」が勢揃いしてたように思うのです。3つ「驕り」とは、「自身の成功に対する驕り」「社長の地位誤認による驕り」「同族経営者の会社所有意識の驕り」です。この点の再認識こそ、企業経営に対する今回一番の教訓であると思いました。3つを順を追ってご説明いたします。
まずは「自身の成功に対する驕り」です。英隆社長は自身が描いた新事業プラン、「サーパス」ブランドによる低価格マンション供給全国展開の大成功によって、会社を一段と飛躍させました。そして遂には、マンション供給数全国一位にまで上り詰めます。結果として、社長は自身の経営手腕に自信過剰気味になってしまったではないでしょうか。すなわち、「私は役員の中でも別格」「結局は私の判断が正しい」という自信です(この自信のベースとして、若い時代に上場企業で修行を積んだ後継経営者は、その後自社に入って人材のレベルの差に愕然として、妙な自信を持ちやすいこともあります)。そして、周囲の言葉に耳を貸さなくなる…。昨年のリーマン・ショック以降の急激な経営環境の変化に対し、その対応を巡って役員間で議論となった時に他の役員を全員解任するという異常事態に至るほどにまで他の取締役たちと相容れない状況が生じていた背景には、間違いなくそんな“驕り”があったのでしょう。
では、この手の「驕り」を事前回避するためにはどうするかですが、まずは経営者が「どんな成功にも偶然の後押しがある」と言うことを知ることです。そして「成功」こそその要因分析をしっかりおこなうことなのです。こと「失敗」には口うるさく「原因分析」を求める経営者も、「成功」は手放しで受け入れるのみというケースが多いのではないでしょうか。「成功」の要因分析をすることで、景気の後押しやトレンドの後押しなど、計画時には想定していなかった偶然の要因が必ずや出てくるものです。すなわち、どこまでが実力でどこからが「運」だったのかが明確になります。さらに、偶然の要因が分かれば、この先どのようなリスク管理をしなくてはいけないのか、最悪のケースも想定しながらどうコンティンジェンシー・プランを立てるべきなのか等を冷静に検討することができるのです。穴吹工務店も、「成功分析」をしてそこができていれば、こんな悲劇には至らなかったのではないかと思われるのです。
残り2つは明日説明します。
「つづく」ということで…。
その前に、穴吹工務店の発展と今回の倒産劇に至った経緯です。穴吹工務店が成長軌道に乗ったのは、先代がマンション施工・販売に本格参入した80年代後半。後を継いだ創業家の穴吹英隆社長は、若い発想を存分に活かしてブランド化を進めました。マンション・ブランド「サーパス」の立ち上げと野球、バスケットボールなどスポーツ支援によるイメージ戦略が功を奏し知名度は一躍全国区になり、安価でありながらそのブランド力にものを言わせて売上は右肩上がりに上昇しました。ところが、昨年のリーマン・ショック以降の不景気と不動産価格の下落が状況を一変させました。そして、再建方針を巡っての社長と他の役員との対立。10月には社長以外の全取締役を全員解任するための株主総会が召集される動きにまで至りました。結局、総会開催は見送られ解任は撤回。事態は収拾に向かいますが、この一件が及ぼした信用失墜のダメージはことの他大きく、結局信用収縮が今回の倒産を招いたと言えます。
問題は、倒産の引き金となった、社長はなぜ役員全員を解任すると公表するような事態を招いたかです。私が思うところを一言で言えば、こんな異常事態に陥った原因は「経営者の驕り(おごり)」以外にないと考えます。しかも想像するに英隆社長の「驕り」には、経営者が最も注意すべき3つの「驕り」が勢揃いしてたように思うのです。3つ「驕り」とは、「自身の成功に対する驕り」「社長の地位誤認による驕り」「同族経営者の会社所有意識の驕り」です。この点の再認識こそ、企業経営に対する今回一番の教訓であると思いました。3つを順を追ってご説明いたします。
まずは「自身の成功に対する驕り」です。英隆社長は自身が描いた新事業プラン、「サーパス」ブランドによる低価格マンション供給全国展開の大成功によって、会社を一段と飛躍させました。そして遂には、マンション供給数全国一位にまで上り詰めます。結果として、社長は自身の経営手腕に自信過剰気味になってしまったではないでしょうか。すなわち、「私は役員の中でも別格」「結局は私の判断が正しい」という自信です(この自信のベースとして、若い時代に上場企業で修行を積んだ後継経営者は、その後自社に入って人材のレベルの差に愕然として、妙な自信を持ちやすいこともあります)。そして、周囲の言葉に耳を貸さなくなる…。昨年のリーマン・ショック以降の急激な経営環境の変化に対し、その対応を巡って役員間で議論となった時に他の役員を全員解任するという異常事態に至るほどにまで他の取締役たちと相容れない状況が生じていた背景には、間違いなくそんな“驕り”があったのでしょう。
では、この手の「驕り」を事前回避するためにはどうするかですが、まずは経営者が「どんな成功にも偶然の後押しがある」と言うことを知ることです。そして「成功」こそその要因分析をしっかりおこなうことなのです。こと「失敗」には口うるさく「原因分析」を求める経営者も、「成功」は手放しで受け入れるのみというケースが多いのではないでしょうか。「成功」の要因分析をすることで、景気の後押しやトレンドの後押しなど、計画時には想定していなかった偶然の要因が必ずや出てくるものです。すなわち、どこまでが実力でどこからが「運」だったのかが明確になります。さらに、偶然の要因が分かれば、この先どのようなリスク管理をしなくてはいけないのか、最悪のケースも想定しながらどうコンティンジェンシー・プランを立てるべきなのか等を冷静に検討することができるのです。穴吹工務店も、「成功分析」をしてそこができていれば、こんな悲劇には至らなかったのではないかと思われるのです。
残り2つは明日説明します。
「つづく」ということで…。











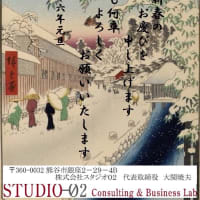
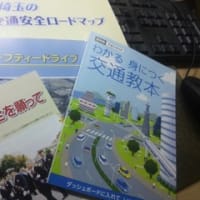
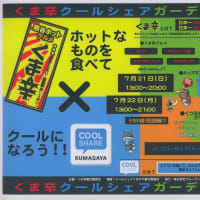
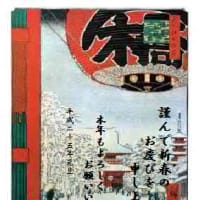


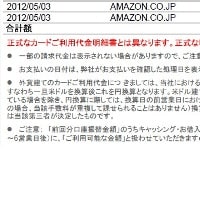

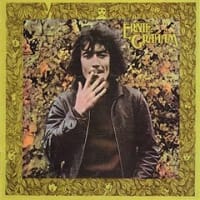
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます