音楽ソフト販売の大手HMVの渋谷店が昨日をもって閉店し、20年の歴史に幕を下ろしました。
そもそも渋谷は、81年のタワーレコード東京初出店以降急激に市民権を得た輸入音楽ソフト販売業のメッカであり、HMVは90年出店の後発でありながら輸入ソフト販売だけでなく、国内の音楽においても“渋谷系”と言われる独自の流行を作り出すなど、“流行文化を発信するCDショップ”として新らしい音楽関連産業のあり方を提示した“カリスマ店舗”でもありました。特に若者の聖地であるセンター街に場所を移してからは、その圧倒的な売場面積に支えられた品揃えもあり、一時期は他を圧倒する勢いを持って“渋谷音楽販売の王者”として君臨していたのでした。
今回の撤退の理由を同社は具体的には公表していませんが、ipodの登場が様相を一転させた音楽データダウンロード・ビジネスの隆盛は如何ともしがたく、同店の売上に大きなダメージを与えたことは疑いのないところであります。本当にipodの登場とituneストアのオープン以降の音楽購入文化の変化にはめざましいものがあります。私のような古い音楽ファンは今でも、音楽はレコードやCDはアルバム単位で聞くモノというこだわりがあるのですが、今の若い人たちは、「欲しい曲だけ聞ければ良い」「アルバム買うといらない曲が入っている」「ジャケットなんて不要」「CDは自分の好きな曲だけ集めて作るモノ」といった考えから、1曲単位のデータダウンロードが主流になっているのです。
かく言う私も音楽購入方法において、CDに関してはここ2年ほどでリアル店舗からネット購入に完全シフトしており、さらに最近では昔懐かしいアーティストでもアルバムまでは不用というものはituneストアで曲単位でダウンロード購入といったマネまでするに至ってしまいました。私ほどの音楽ソフトのヘビーバイヤーまでもがリアル店舗購入からバーチャル店舗購入に移行している訳で、これではHMVのシンボル的旗艦店の渋谷店が閉店するのも無理からぬところでしょう。ちなみに、以前私が渋谷店と並んでよく足を運んでいた、HMV銀座店、数寄屋橋も昨年から今年にかけて相次いで閉店しており、リアルの音楽ソフト販売業はもはや存続の危機に瀕していると言っていいのかもしれません。
音楽ソフト販売業の問題だけでなく、CDという媒体自体今後どうなって行くのか分からない感じさえしています。エジソンがレコードという音楽録音再生媒体を発明して以来、約100年以上にわたり動かし難い存在であった音楽媒体の歴史を劇的に書き換えたCDが、その衝撃的な登場からすればあまりに短い20数年という天下の時代を、同じデジタル方式のデータダウンロードという予想だにしなかった後継にとって変わられてしまう、そんな勢いを感じさせる昨今なのです。音楽データ・ダウンロードがこんなに急激に業界の主導権を握ろうとは、誰が予想できたでしょう。もちろん時代の流れを大きく動かしたのは、アップルのipodを軸にした斬新なビジネスモデルの登場に他なりません。
次なる変革は書籍の世界でしょう。書籍はレコード以上に長い歴史を持っていますから、いきなり紙媒体がすべて電子データにとって変わるとは思えないですが、ipad登場はその長い歴史をも変えかねないだけのパワーと可能性を秘めているように思えます。CDショップに続いて本屋さんが街から姿を消す日は意外に早く訪れるかもしれません。
そもそも渋谷は、81年のタワーレコード東京初出店以降急激に市民権を得た輸入音楽ソフト販売業のメッカであり、HMVは90年出店の後発でありながら輸入ソフト販売だけでなく、国内の音楽においても“渋谷系”と言われる独自の流行を作り出すなど、“流行文化を発信するCDショップ”として新らしい音楽関連産業のあり方を提示した“カリスマ店舗”でもありました。特に若者の聖地であるセンター街に場所を移してからは、その圧倒的な売場面積に支えられた品揃えもあり、一時期は他を圧倒する勢いを持って“渋谷音楽販売の王者”として君臨していたのでした。
今回の撤退の理由を同社は具体的には公表していませんが、ipodの登場が様相を一転させた音楽データダウンロード・ビジネスの隆盛は如何ともしがたく、同店の売上に大きなダメージを与えたことは疑いのないところであります。本当にipodの登場とituneストアのオープン以降の音楽購入文化の変化にはめざましいものがあります。私のような古い音楽ファンは今でも、音楽はレコードやCDはアルバム単位で聞くモノというこだわりがあるのですが、今の若い人たちは、「欲しい曲だけ聞ければ良い」「アルバム買うといらない曲が入っている」「ジャケットなんて不要」「CDは自分の好きな曲だけ集めて作るモノ」といった考えから、1曲単位のデータダウンロードが主流になっているのです。
かく言う私も音楽購入方法において、CDに関してはここ2年ほどでリアル店舗からネット購入に完全シフトしており、さらに最近では昔懐かしいアーティストでもアルバムまでは不用というものはituneストアで曲単位でダウンロード購入といったマネまでするに至ってしまいました。私ほどの音楽ソフトのヘビーバイヤーまでもがリアル店舗購入からバーチャル店舗購入に移行している訳で、これではHMVのシンボル的旗艦店の渋谷店が閉店するのも無理からぬところでしょう。ちなみに、以前私が渋谷店と並んでよく足を運んでいた、HMV銀座店、数寄屋橋も昨年から今年にかけて相次いで閉店しており、リアルの音楽ソフト販売業はもはや存続の危機に瀕していると言っていいのかもしれません。
音楽ソフト販売業の問題だけでなく、CDという媒体自体今後どうなって行くのか分からない感じさえしています。エジソンがレコードという音楽録音再生媒体を発明して以来、約100年以上にわたり動かし難い存在であった音楽媒体の歴史を劇的に書き換えたCDが、その衝撃的な登場からすればあまりに短い20数年という天下の時代を、同じデジタル方式のデータダウンロードという予想だにしなかった後継にとって変わられてしまう、そんな勢いを感じさせる昨今なのです。音楽データ・ダウンロードがこんなに急激に業界の主導権を握ろうとは、誰が予想できたでしょう。もちろん時代の流れを大きく動かしたのは、アップルのipodを軸にした斬新なビジネスモデルの登場に他なりません。
次なる変革は書籍の世界でしょう。書籍はレコード以上に長い歴史を持っていますから、いきなり紙媒体がすべて電子データにとって変わるとは思えないですが、ipad登場はその長い歴史をも変えかねないだけのパワーと可能性を秘めているように思えます。CDショップに続いて本屋さんが街から姿を消す日は意外に早く訪れるかもしれません。











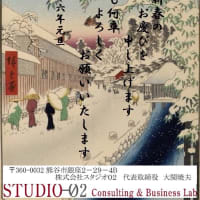
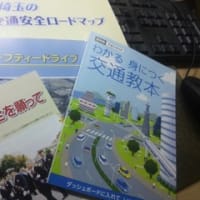
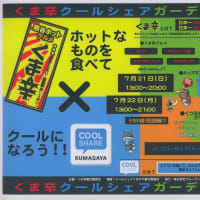
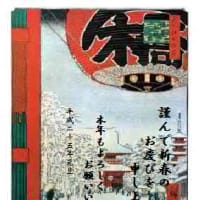


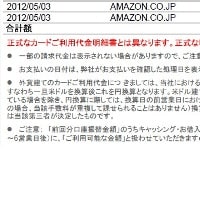

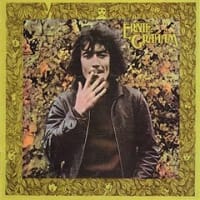
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます