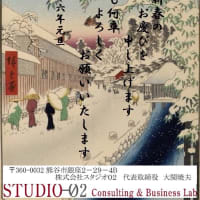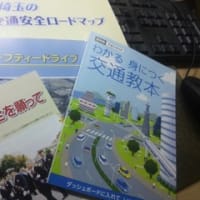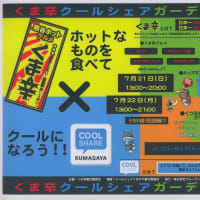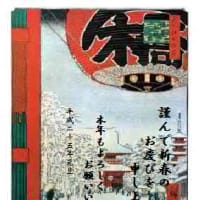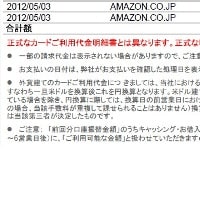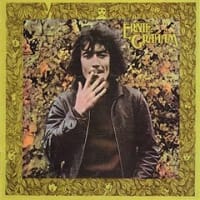日本テレビ記者の秩父取材死亡事故は、テレビ取材のあり方の根本を考えさせられる事件であったと思います。
今回の事件について、「日テレはけしからん」とか「責任問題だ」とかを問う以前の問題として、なぜ事件は起きたのかという根本的な問題を考える必要があるのではないかと思っています。その際に今一度考えなくてはいけないのは、「報道とは何か」という問いかけです。「報道」とは、政治・経済動向や世間一般に起きている事件や事故に代表される重要情報を、より客観的な立場で広く一般人に伝えることではないかと思います。その代表が新聞を中心とした活字メディアです。そもそも「報道」は、江戸時代の瓦版の時代から活字メディアとして生まれ、活字メディアとして発展してきました。その発展の過程において、挿絵が取り入れられたり、写真が取り入れられたりといった視覚面での変化はあったものの、主役が活字であると言う点では長い新聞報道の歴史において変わることなく来ているのです。
一方、今回問題の渦中にあるテレビ媒体はどうでしょう。テレビは活字媒体に比べれば圧倒的に歴史は浅く、視覚に訴えるという活字とは全く異なる媒体の特性もハッキリしています。また、新聞と異なり一般の民間テレビ局は視聴料をとらずにスポンサーに電波を切り売りするビジネスモデルで発展を遂げた結果、勢い娯楽媒体として視聴率競争を身上とする存在となったのです。すなわち、取材に基づいていかにして客観的事実を早く正確に伝えるかという新聞とはその成り立ちからして異なっており、いかに視聴率が稼げるイコール視聴者が喜ぶ映像を入手し放映するかという点こそがテレビマンの使命であるのです。報道番組と言えども、スポンサーがついている限りにおいては、視聴率争いを背負わされた“報道ショー”“報道バラエティ”であり、その番組スタッフはいかにいい映像がとれるかを常に競っている訳なのです。
そこで今回の事件で私が言いたいのは、テレビの“報道番組”は新聞等活字メディアが脈々と作り上げてきた本来の意味での「報道」とは全く違うのだということを今一度問いなおす必要があるのではないかと言う事なのです。犠牲になった二人のテレビマンは、日曜夕方の“報道番組”「バンキシャ」の取材で現地入りしたといいます。彼らの目的は、番組に必要な“絵になる映像の入手”以外になく、これはもう本来の「報道」とは全く別次元の行動であったと言わざるを得ないと思います。すなわち、ここでハッキリ認識しなくてはいけないことは、2人は“報道の正義”に倒れたのではなく、“報道ショー”という“テレビのビジネスモデルの犠牲”になったということなのです。「報道」では真実を求める“報道の正義”から、やむなく危険を冒す行動に出ざるを得ない場面があるのも事実です。しかしながら、テレビクルーの取材活動は“報道の正義”ではなく“報道ショー”のスポンサーを喜ばせるための視聴率争いに勝つ「映像入手活動」に過ぎず、そこには危険を冒す理由は全く存在しませんし、また危険を冒させてはいけないはずなのです。
テレビ局は自身の媒体の特性を今一度よく考え、テレビの発展とともにその存在感を増してきた“報道ショー”が本来の「報道」とは異なる特異なビジネスであると再認識した上で、その取材活動のあり方を根本に立ち返って検討すべき時に来ているのではないかと思うのです。“報道の正義”と“テレビのビジネスモデル”の倒錯の末、行きすぎた取材をおこないテレビ界ビジネスの犠牲になった二人のテレビマンの死。この死を無駄にしないためにも、業界全体の問題としてこの事件を真摯に受け止め、「報道」と“報道ショー”の違いを明確化し「テレビ報道取材行動指針」を作成するなどの再発防止に向けた改善策を講じるべきであると心から思って止みません。
今回の事件について、「日テレはけしからん」とか「責任問題だ」とかを問う以前の問題として、なぜ事件は起きたのかという根本的な問題を考える必要があるのではないかと思っています。その際に今一度考えなくてはいけないのは、「報道とは何か」という問いかけです。「報道」とは、政治・経済動向や世間一般に起きている事件や事故に代表される重要情報を、より客観的な立場で広く一般人に伝えることではないかと思います。その代表が新聞を中心とした活字メディアです。そもそも「報道」は、江戸時代の瓦版の時代から活字メディアとして生まれ、活字メディアとして発展してきました。その発展の過程において、挿絵が取り入れられたり、写真が取り入れられたりといった視覚面での変化はあったものの、主役が活字であると言う点では長い新聞報道の歴史において変わることなく来ているのです。
一方、今回問題の渦中にあるテレビ媒体はどうでしょう。テレビは活字媒体に比べれば圧倒的に歴史は浅く、視覚に訴えるという活字とは全く異なる媒体の特性もハッキリしています。また、新聞と異なり一般の民間テレビ局は視聴料をとらずにスポンサーに電波を切り売りするビジネスモデルで発展を遂げた結果、勢い娯楽媒体として視聴率競争を身上とする存在となったのです。すなわち、取材に基づいていかにして客観的事実を早く正確に伝えるかという新聞とはその成り立ちからして異なっており、いかに視聴率が稼げるイコール視聴者が喜ぶ映像を入手し放映するかという点こそがテレビマンの使命であるのです。報道番組と言えども、スポンサーがついている限りにおいては、視聴率争いを背負わされた“報道ショー”“報道バラエティ”であり、その番組スタッフはいかにいい映像がとれるかを常に競っている訳なのです。
そこで今回の事件で私が言いたいのは、テレビの“報道番組”は新聞等活字メディアが脈々と作り上げてきた本来の意味での「報道」とは全く違うのだということを今一度問いなおす必要があるのではないかと言う事なのです。犠牲になった二人のテレビマンは、日曜夕方の“報道番組”「バンキシャ」の取材で現地入りしたといいます。彼らの目的は、番組に必要な“絵になる映像の入手”以外になく、これはもう本来の「報道」とは全く別次元の行動であったと言わざるを得ないと思います。すなわち、ここでハッキリ認識しなくてはいけないことは、2人は“報道の正義”に倒れたのではなく、“報道ショー”という“テレビのビジネスモデルの犠牲”になったということなのです。「報道」では真実を求める“報道の正義”から、やむなく危険を冒す行動に出ざるを得ない場面があるのも事実です。しかしながら、テレビクルーの取材活動は“報道の正義”ではなく“報道ショー”のスポンサーを喜ばせるための視聴率争いに勝つ「映像入手活動」に過ぎず、そこには危険を冒す理由は全く存在しませんし、また危険を冒させてはいけないはずなのです。
テレビ局は自身の媒体の特性を今一度よく考え、テレビの発展とともにその存在感を増してきた“報道ショー”が本来の「報道」とは異なる特異なビジネスであると再認識した上で、その取材活動のあり方を根本に立ち返って検討すべき時に来ているのではないかと思うのです。“報道の正義”と“テレビのビジネスモデル”の倒錯の末、行きすぎた取材をおこないテレビ界ビジネスの犠牲になった二人のテレビマンの死。この死を無駄にしないためにも、業界全体の問題としてこの事件を真摯に受け止め、「報道」と“報道ショー”の違いを明確化し「テレビ報道取材行動指針」を作成するなどの再発防止に向けた改善策を講じるべきであると心から思って止みません。