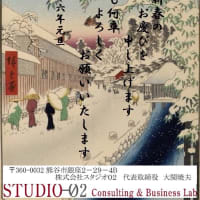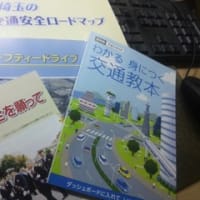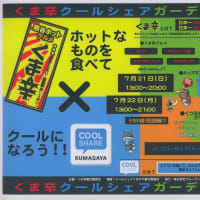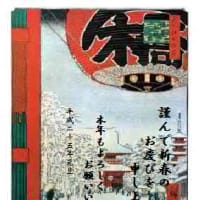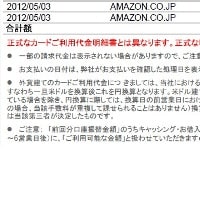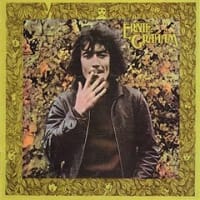地銀トップの横浜銀行と関東圏を地盤とする第二地銀東日本銀行の、持ち株会社方式による経営統合が日経新聞のスクープで報じられました。一応古巣がらみの話なので、この報道の読み方についての個人的な見解を書いておきます。
まずこの報道を聞いて、金融界を多少なりとも知る人は若干の違和感を覚えたのではないでしょうか。まず、当事者両行の統合メリットがイマイチ見えない点。それと、現時点では正式発表ではないこの報道を受けての両行の対応が妙に落ち着きはらっていること。
「発表はしていないけど、事実ですよ」と言っているのですが、まるで写真誌に熱愛場面を撮られたアイドルが「仲の良いお友達の一人です」と交際を否定するのではなく、「お付き合いさせていただいております。ファンに皆様には温かく見守っていただければと思います」と交際を認めた、みたいな感じです。
横浜銀行
http://www.boy.co.jp/news/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2014/11/04/141104.pdf
東日本銀行
http://www.higashi-nipponbank.co.jp/pdf/news_release/20141104_release_02.pdf
M&Aがらみのリークと言うのは、たいてい誰かにリークメリットがあるからされるものです。しかも、M&Aというのは通常超トップシークレットでことが進められ、トップとその周辺のごく少数のみで動くケースがほとんど。それがリークされるというのは、当事者に事前公表メリットがあるか統合話を小耳にはさんだ統合反対派関係者の統合つぶし目的であります。
特に後者は伝統のある企業に多く、リーク報道を受けてOBなんかが騒ごうものなら、事態の収拾はほとんど不可能になるのです。最近の例では、キリンとサントリーの経営統合に関するフライイング報道が思い出されます。スクープが出るや否や途端にガタガタ大騒ぎになって、結局ほどなく統合話は白紙になってしまったのは記憶に新しいところです。
では今回の情報リークの目的は何か。このリークは誰がしたのか、言いかえれば誰にメリットがあるのか、が気になるところです。両行の対応の落ち着きぶりと、正式発表もないまま判を押したような対応の同一性を見るに、リークそのものが当事者にメリットがある状況ではなく、反対派が存在するような状況でもなさそう。となると、メリットのある第三者のリークである可能性が大と言うことになります。
金融庁ですね。金融庁は景気が浮揚を続けている間に、地方人口の減少で経営が苦しくなるであろう地銀の再編を急ぎたいわけで、横浜、東日本の統合は願ってもない打ち上げ花火になるわけです。実は10月1日に、関東圏では東京都民銀行と八千代銀行が系絵統合し東京YTフィナンシャルグループを設立したのですが、この原稿を読んでいる大半の人がその事実すら知らないという線香花火程度のニュースに終わってしまっています。ならば、都民、八千代統合のほとぼりが冷めないこのタイミングで、なんとか地銀統合の流れを世間にそして関係者に強く印象付けしたい、そういう当局の思惑が容易に見て取れるのです。
地銀トップの横浜が、救済目的ではなく近隣地銀との統合に動いたとなれば、金融庁の全国各地の地銀に対する統合に向けた暗黙の圧力は強くなりますし、当局から必要以上ににらまれたくない地銀経営者としては、単独生き残りにこだわりすぎて後々貧乏クジを引くことになりたくない、という思惑を働かすことにもつながり、一気に地銀再編に突き進むという青写真が描けても来るわけなのです。
すなわち、今回の横浜、東日本の統合話自体の仕掛人そのものが金融庁なのではないかということになるわけです。新聞報道にあるように、横浜銀行の寺沢頭取、東日本銀行の石井頭取、共に金融庁の前身である旧大蔵省OBです。以前なら、横浜銀行の頭取は事務次官経験者がその席についていたのですが、寺沢頭取は石井頭取と同じく局長職で官職を終えた身。自身の出身母体である当局の現トップから命が下れば従わざるを得ないのが官僚の世界の掟でもあるわで、当局が自己の手駒として動かしやすい横浜と東日本のトップに命を下して、地銀再編ののろし役を申しつけたと考えるのが正答なのではないでしょうか(なぜ、横浜銀行の現頭取が五代続いた事務次官経験者から格下げになったのかという疑問も、今回の件で解けた気分です)。
経営内容が悪いわけでもないのに、地銀トップ行がいつまでも当局からトップをいただいているのは不思議なことだと若い頃は思ったものですが、当局OBがトップを務めているという事実は同時に金融行政の一翼を陰の部分で担ってもいることでもあるのです。90年代後半の金融危機以降、金融行政は管理の時代から各銀行自己責任の時代に移ったと言われているのですが、結局護送船団方式の時代から脈脈と続く当局の管理文化は何も変わっていないと痛感させられるわけで、個人的には地銀再編とは別の意味でニュースバリューのある報道でありました。
まずこの報道を聞いて、金融界を多少なりとも知る人は若干の違和感を覚えたのではないでしょうか。まず、当事者両行の統合メリットがイマイチ見えない点。それと、現時点では正式発表ではないこの報道を受けての両行の対応が妙に落ち着きはらっていること。
「発表はしていないけど、事実ですよ」と言っているのですが、まるで写真誌に熱愛場面を撮られたアイドルが「仲の良いお友達の一人です」と交際を否定するのではなく、「お付き合いさせていただいております。ファンに皆様には温かく見守っていただければと思います」と交際を認めた、みたいな感じです。
横浜銀行
http://www.boy.co.jp/news/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2014/11/04/141104.pdf
東日本銀行
http://www.higashi-nipponbank.co.jp/pdf/news_release/20141104_release_02.pdf
M&Aがらみのリークと言うのは、たいてい誰かにリークメリットがあるからされるものです。しかも、M&Aというのは通常超トップシークレットでことが進められ、トップとその周辺のごく少数のみで動くケースがほとんど。それがリークされるというのは、当事者に事前公表メリットがあるか統合話を小耳にはさんだ統合反対派関係者の統合つぶし目的であります。
特に後者は伝統のある企業に多く、リーク報道を受けてOBなんかが騒ごうものなら、事態の収拾はほとんど不可能になるのです。最近の例では、キリンとサントリーの経営統合に関するフライイング報道が思い出されます。スクープが出るや否や途端にガタガタ大騒ぎになって、結局ほどなく統合話は白紙になってしまったのは記憶に新しいところです。
では今回の情報リークの目的は何か。このリークは誰がしたのか、言いかえれば誰にメリットがあるのか、が気になるところです。両行の対応の落ち着きぶりと、正式発表もないまま判を押したような対応の同一性を見るに、リークそのものが当事者にメリットがある状況ではなく、反対派が存在するような状況でもなさそう。となると、メリットのある第三者のリークである可能性が大と言うことになります。
金融庁ですね。金融庁は景気が浮揚を続けている間に、地方人口の減少で経営が苦しくなるであろう地銀の再編を急ぎたいわけで、横浜、東日本の統合は願ってもない打ち上げ花火になるわけです。実は10月1日に、関東圏では東京都民銀行と八千代銀行が系絵統合し東京YTフィナンシャルグループを設立したのですが、この原稿を読んでいる大半の人がその事実すら知らないという線香花火程度のニュースに終わってしまっています。ならば、都民、八千代統合のほとぼりが冷めないこのタイミングで、なんとか地銀統合の流れを世間にそして関係者に強く印象付けしたい、そういう当局の思惑が容易に見て取れるのです。
地銀トップの横浜が、救済目的ではなく近隣地銀との統合に動いたとなれば、金融庁の全国各地の地銀に対する統合に向けた暗黙の圧力は強くなりますし、当局から必要以上ににらまれたくない地銀経営者としては、単独生き残りにこだわりすぎて後々貧乏クジを引くことになりたくない、という思惑を働かすことにもつながり、一気に地銀再編に突き進むという青写真が描けても来るわけなのです。
すなわち、今回の横浜、東日本の統合話自体の仕掛人そのものが金融庁なのではないかということになるわけです。新聞報道にあるように、横浜銀行の寺沢頭取、東日本銀行の石井頭取、共に金融庁の前身である旧大蔵省OBです。以前なら、横浜銀行の頭取は事務次官経験者がその席についていたのですが、寺沢頭取は石井頭取と同じく局長職で官職を終えた身。自身の出身母体である当局の現トップから命が下れば従わざるを得ないのが官僚の世界の掟でもあるわで、当局が自己の手駒として動かしやすい横浜と東日本のトップに命を下して、地銀再編ののろし役を申しつけたと考えるのが正答なのではないでしょうか(なぜ、横浜銀行の現頭取が五代続いた事務次官経験者から格下げになったのかという疑問も、今回の件で解けた気分です)。
経営内容が悪いわけでもないのに、地銀トップ行がいつまでも当局からトップをいただいているのは不思議なことだと若い頃は思ったものですが、当局OBがトップを務めているという事実は同時に金融行政の一翼を陰の部分で担ってもいることでもあるのです。90年代後半の金融危機以降、金融行政は管理の時代から各銀行自己責任の時代に移ったと言われているのですが、結局護送船団方式の時代から脈脈と続く当局の管理文化は何も変わっていないと痛感させられるわけで、個人的には地銀再編とは別の意味でニュースバリューのある報道でありました。