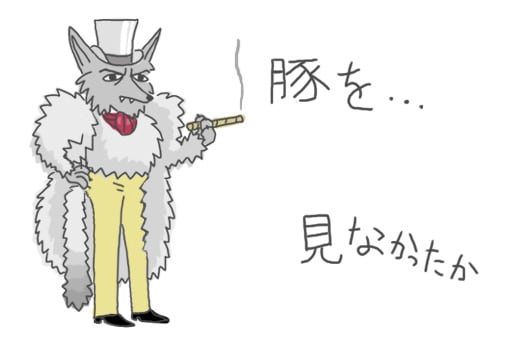ピリッと辛いおつまみをお皿にたんまり盛って、かたわらに小瓶のビールをずらりと並べて、そいつを片っ端から空けてラッパ飲みしながらつまみをむしゃむしゃやりながら、時には立ち上がって踊りながらそして「ありえね~」だの「やっちまえ~」だの大声で茶々を入れながら観るのが、クストリッツァ映画の正しい鑑賞法なのではないかと思うのでございます。
ともあれ、『ウェディング・ベルを鳴らせ!』を観てまいりました。
↑公式サイトがいろいろと楽しいつくりになっております。(昨今流行りの”婚活”なる言葉を持ち出しているのは気に食わぬ所でございますけれども)
日本で長編のクストリッツァ作品が公開されるのは『ライフ・イズ・ミラクル』以来4年ぶりでございますが、この間カントクは映画学校を設立したり、フィルムフェスティバルを開催したり、マラドーナの伝記映画を撮ったり、渋るネレを説得して『ジプシーのとき』をオペラ化したり、さらにはノー・スモーキング・オーケストラの一員としてワールドツアーに出たりもしておいでですから、ずいぶんとお忙しかったはず。にもかかわらず本作からほとばしるバイタリティときたら、例えて言うなら一杯機嫌で好き勝手に演奏しまくるジプシーバンドを満載して突っ走る蒸気機関車のごとくで、クスツ親爺もはや恐いものなし(というかやりたい放題)の感がございます。
今回はコメディに徹したようで社会風刺は少なく、そのぶんドタバタハチャメチャぶりに更に磨きがかかっているのですが、カントクのこれまでの作品と比べるとやや求心力が弱いような気はいたします。登場人物おのおののエピソードがつぶ立ちしすぎているせいなのか、はたまた動物を含め無数に登場する小道具たちを活かしきれていないせいなのか。しかし、本筋と関係のない周辺的なことがらがいやに自己主張するというのもクストリッツァ作品の魅力のひとつでございますから、ここはひとつ赤瀬川源平風に「今回の作品はいつになく拡散力がある」とでも申しておきましょう。
揃いも揃ってアクが強く血の気が多い登場人物たちが、ベタなギャグやシュールな冒険を執拗なまでに繰り広げ、その合間にストーリーと全く関係のない小ネタが当たり前な顔をして割り込んで来る、要するに甚だクストリッツァ的なコメディでございます。よって、爪の先ほども面白さが感じられないという方もいらっしゃることでしょう。これはトムヤムクンのどこが美味しいのかわからないとか、ヘビメタの何がいいんだかさっぱり、というのと同様、好みと相性の問題でございまして、合わない方にはそりゃ残念、としか言いようがございません。

そう。
牛は走り、猫は飛び、煙突は倒れ、美しい山村には至る所にメカ仕込みの落とし穴が口を空け、懲りない求婚者を何度でも呑み込むのでございます。大男の頭突きで建物は倒壊しかけ、ロケット男は(案の定)ひたすら飛び続け、血の気の多い司祭様は鉄拳を振るい、結婚式は銃撃戦と化し、それでもなおウエディングベルは鳴らされねばならないのでございます。ちなみにベルはじいちゃんのお手製。このじいちゃんの作るヘンテコな、しかし意外と実用的なメカの数々もまた見ものでございます。
じいちゃん自身もなかなか隅に置けない人で、孫をお嫁さん探しに送り出す一方、自分は街から彼を追ってきた美女に結婚を迫られる日々。でもってこの美女もまた、彼女の美貌とダイナマイトバディに一目惚れした男に結婚を迫られる日々。主人公のツァーネ君は運命の人を見つけた喜びもつかの間、牛は盗られるわ、不良にボコられるわ、植木鉢に直撃されるわと散々でございます。
そこへおじいちゃん同士の友情やらセルビアマフィアやらがからんで来て、ああもうどうすんだこりゃどっこい何とかなるわないやいやそうは言ってもとりあえずGoツァーネGo!Go!てな感じでございまして、「ボクのお嫁さん探し」というシンプルなはずのストーリーは、怒濤のごちゃごちゃを擁して突き進んで行くのでございます。
風刺は少なめとはいえ、その矛先と描き方は実に明解(というかあからさま)でございました。
例えばマフィアのボス、バヨは娼館を兼ねたストリップバーのオーナーで、昔からある工場をつぶしてセルビア初の世界貿易センタービルを建てようと画策しております。御丁寧にも例のツインタワーとそっくりのものを。貧乏人からも容赦なく金をむしり取り、性的搾取と暴力で儲けているバヨが、俺の力でツインタワー-----経済グローバリズム/アメリカニズムの象徴-----をぶっ建ててやるぞと息巻く様には、経済グローバリズムに対するカントクの皮肉な見方が伺われます。またカントクの息子ストリボール・クストリッツァが演じる大男は「世界に愛と平和を広げよう」とのたまいながら、ランボー(詩人じゃない方)が持っているようなでっかいマシンガンを粛々と撃ちまくるのでございます。
ストリボールは前作『ライフ・イズ・ミラクル』に引き続き主人公の頼れる友人役でございまして、マッチョな風貌を活かして笑わせてくれます。今回は音楽も彼が担当ということで、ノー・スモーキング・オーケストラのクレジットは無し。
現在のノースモのギタリスト、イヴィツァ・マクシモヴィッチ氏がしつこい求婚者役で出ていたということは後で知りました。サイモン・ラトルのごとき鳥の巣頭の姿しか見たことがなかったので全く気付きませんでした。そういえば劇中で弾いておりました、ギター。

このおっさんがまた、いい味出してらっしゃるのですわ。
音楽は今までと比べると若干おとなしいように感じられましたが、世間の評判は上々のようでございます。ノースモのアクの強さ、わざとらしさとゴチャゴチャ感が好きなワタクシにはちょっと物足りなませんでした。まあ、これも好みの問題でございます。
そんなわけでございまして
100点満点というわけではないものの、のろは大いに楽しませていただきました。
ウンザ・ウンザ・サウンドに乗せてドタバタ人生讃歌を歌い上げたカントク、今後もどんな作品を見せてくれるのやら、のろは楽しみにしております。そろそろまた『アンダーグラウンド』や『ジプシーのとき』のような悲劇性のある作品を撮っていただきたいなあとも思いつつ。
ともあれ、『ウェディング・ベルを鳴らせ!』を観てまいりました。
↑公式サイトがいろいろと楽しいつくりになっております。(昨今流行りの”婚活”なる言葉を持ち出しているのは気に食わぬ所でございますけれども)
日本で長編のクストリッツァ作品が公開されるのは『ライフ・イズ・ミラクル』以来4年ぶりでございますが、この間カントクは映画学校を設立したり、フィルムフェスティバルを開催したり、マラドーナの伝記映画を撮ったり、渋るネレを説得して『ジプシーのとき』をオペラ化したり、さらにはノー・スモーキング・オーケストラの一員としてワールドツアーに出たりもしておいでですから、ずいぶんとお忙しかったはず。にもかかわらず本作からほとばしるバイタリティときたら、例えて言うなら一杯機嫌で好き勝手に演奏しまくるジプシーバンドを満載して突っ走る蒸気機関車のごとくで、クスツ親爺もはや恐いものなし(というかやりたい放題)の感がございます。
今回はコメディに徹したようで社会風刺は少なく、そのぶんドタバタハチャメチャぶりに更に磨きがかかっているのですが、カントクのこれまでの作品と比べるとやや求心力が弱いような気はいたします。登場人物おのおののエピソードがつぶ立ちしすぎているせいなのか、はたまた動物を含め無数に登場する小道具たちを活かしきれていないせいなのか。しかし、本筋と関係のない周辺的なことがらがいやに自己主張するというのもクストリッツァ作品の魅力のひとつでございますから、ここはひとつ赤瀬川源平風に「今回の作品はいつになく拡散力がある」とでも申しておきましょう。
揃いも揃ってアクが強く血の気が多い登場人物たちが、ベタなギャグやシュールな冒険を執拗なまでに繰り広げ、その合間にストーリーと全く関係のない小ネタが当たり前な顔をして割り込んで来る、要するに甚だクストリッツァ的なコメディでございます。よって、爪の先ほども面白さが感じられないという方もいらっしゃることでしょう。これはトムヤムクンのどこが美味しいのかわからないとか、ヘビメタの何がいいんだかさっぱり、というのと同様、好みと相性の問題でございまして、合わない方にはそりゃ残念、としか言いようがございません。

そう。
牛は走り、猫は飛び、煙突は倒れ、美しい山村には至る所にメカ仕込みの落とし穴が口を空け、懲りない求婚者を何度でも呑み込むのでございます。大男の頭突きで建物は倒壊しかけ、ロケット男は(案の定)ひたすら飛び続け、血の気の多い司祭様は鉄拳を振るい、結婚式は銃撃戦と化し、それでもなおウエディングベルは鳴らされねばならないのでございます。ちなみにベルはじいちゃんのお手製。このじいちゃんの作るヘンテコな、しかし意外と実用的なメカの数々もまた見ものでございます。
じいちゃん自身もなかなか隅に置けない人で、孫をお嫁さん探しに送り出す一方、自分は街から彼を追ってきた美女に結婚を迫られる日々。でもってこの美女もまた、彼女の美貌とダイナマイトバディに一目惚れした男に結婚を迫られる日々。主人公のツァーネ君は運命の人を見つけた喜びもつかの間、牛は盗られるわ、不良にボコられるわ、植木鉢に直撃されるわと散々でございます。
そこへおじいちゃん同士の友情やらセルビアマフィアやらがからんで来て、ああもうどうすんだこりゃどっこい何とかなるわないやいやそうは言ってもとりあえずGoツァーネGo!Go!てな感じでございまして、「ボクのお嫁さん探し」というシンプルなはずのストーリーは、怒濤のごちゃごちゃを擁して突き進んで行くのでございます。
風刺は少なめとはいえ、その矛先と描き方は実に明解(というかあからさま)でございました。
例えばマフィアのボス、バヨは娼館を兼ねたストリップバーのオーナーで、昔からある工場をつぶしてセルビア初の世界貿易センタービルを建てようと画策しております。御丁寧にも例のツインタワーとそっくりのものを。貧乏人からも容赦なく金をむしり取り、性的搾取と暴力で儲けているバヨが、俺の力でツインタワー-----経済グローバリズム/アメリカニズムの象徴-----をぶっ建ててやるぞと息巻く様には、経済グローバリズムに対するカントクの皮肉な見方が伺われます。またカントクの息子ストリボール・クストリッツァが演じる大男は「世界に愛と平和を広げよう」とのたまいながら、ランボー(詩人じゃない方)が持っているようなでっかいマシンガンを粛々と撃ちまくるのでございます。
ストリボールは前作『ライフ・イズ・ミラクル』に引き続き主人公の頼れる友人役でございまして、マッチョな風貌を活かして笑わせてくれます。今回は音楽も彼が担当ということで、ノー・スモーキング・オーケストラのクレジットは無し。
現在のノースモのギタリスト、イヴィツァ・マクシモヴィッチ氏がしつこい求婚者役で出ていたということは後で知りました。サイモン・ラトルのごとき鳥の巣頭の姿しか見たことがなかったので全く気付きませんでした。そういえば劇中で弾いておりました、ギター。

このおっさんがまた、いい味出してらっしゃるのですわ。
音楽は今までと比べると若干おとなしいように感じられましたが、世間の評判は上々のようでございます。ノースモのアクの強さ、わざとらしさとゴチャゴチャ感が好きなワタクシにはちょっと物足りなませんでした。まあ、これも好みの問題でございます。
そんなわけでございまして
100点満点というわけではないものの、のろは大いに楽しませていただきました。
ウンザ・ウンザ・サウンドに乗せてドタバタ人生讃歌を歌い上げたカントク、今後もどんな作品を見せてくれるのやら、のろは楽しみにしております。そろそろまた『アンダーグラウンド』や『ジプシーのとき』のような悲劇性のある作品を撮っていただきたいなあとも思いつつ。