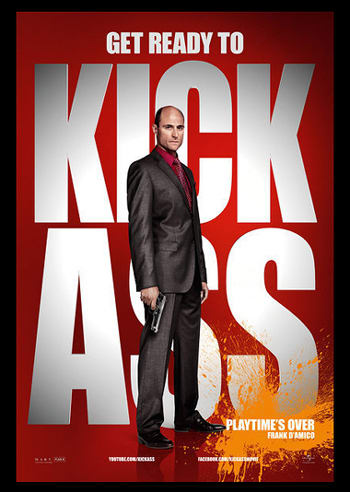秀作でございました。
レイ・ブラッドベリ作品のようなもの悲しいSFでございまして、観賞後にはしみじみとした余韻が残ります。
チラシなどの雰囲気からてっきりバッドエンドに違いないと身構えていたのろには、意外にも希望の感じられるエンディングは嬉しいものでございました。ついでに申せば作品の雰囲気と内容をよく表している邦題も、近年まれに見る秀逸さではないかと。(現題は単に”Moon”)
月に囚(とら)われた男 - オフィシャルサイト
SFといっても視覚的な派手さはなく、ほとんど密室劇のような展開。しかも出演者は実質的に主人公ひとりだけ、という超ミニマル映画でございます。舞台装置はいたって地味でありながら最後まで飽きさせないのは、求心力のある脚本と主役を演じるサム・ロックウェルの熱演のなせる技でございましょう。
出演者ひとり、とはどういうことかと申しますと。
主人公のサム・ベルはとある企業の従業員で、資源採掘のため3年の任期で月の裏側に単身赴任しております。採掘作業は機械化されているため、基地にいるのは積み込みと発送作業にあたるサムひとりっきり。会社のお偉いさんは「いや~君はわが社の誇りだよ~」なんて言ってくれるものの、通信の不具合についてはほったらかしで、なかなか直してしてくれない。そのせいでサムは地球にいる妻や娘との会話もままならず、話し相手といっては人工知能搭載のロボット、ガーティだけ。
このガーティを含め、機器や内装のデザインはいかにも実用第一といった感じの無機質なもので、心なごませるような所がちっともございません。そこに何とか人間的な空間を演出しようとして、サムがこまごまと努力しているあたりがリアルでもあり、哀しくもあるのでございます。植物を育て、写真を貼りまくり、故郷の街の模型を作る。そして今日で何日経過というカレンダーをトイレの壁に記していく。囚人がやるように。
そんな淋しく単調な3年間もあと少しで終わり、いよいよ地球に帰れるぞという時に採掘現場で事故を起こし、基地で目覚めたサム。妙な胸騒ぎに導かれて事故現場に行ってみると、そこには何と事故車両に埋もれたままの自分の姿が。
こいつは誰だ?
いやいや俺は誰だ?
・・・
「月に囚われた男」予告編
とまあこんな具合でございまして。
ふたりサムの謎はわりかしあっさりと解明されるのでございますが、謎が解けたところで、それだけではなんら解決にはならないというのがミソ。
しかも会社から派遣された船が刻一刻と近づいているのでございます。このタイムリミットがあるおかげで、初めは淡々と進むかに思えた物語は終盤へ行くに従ってずんずん緊張感を高めてまいります。のろはラスト10分ばかりは、両手を握りしめて うおーがんばれサム~ちゅーか急げ~ と心の内で声援を送っておりました。
サム・ロックウェルはたいへん好演でございまして、外界から遮断された空間で自分の分身?と付き合う、というまことにうっとうしい状況に追い込まれた男のいらだちと、真実を知ってしまったことから沸き上がる悲哀がひしひし伝わってまいります。後者については描き方が少々ウエットすぎるような気もいたしましたが、泣いている観客もいらっしたのようですので、まあ好みの問題かもしれません。
サムの唯一の話し相手である人工知能ロボット、ガーティの声を担当するのはケビン・スペイシー。何せ飄々としたくせ者を演じたら当代随一のけびんさんでございましょう。こいつ絶対何か隠してるに違いない、と初めから不信感満々で観ていたんでございますが、 ガーティ君、意外といい奴でございました、人間味があって。
人工知能に人間味もへったくれもあろうかって。いやいや、ここもまたミソなのでございまして。「サムを守る」というプログラムの指令に従って優しい選択をするガーティ、利益のためなら人を人とも思わない大企業、そして、二人のサム。彼らのありようは「人間らしさ」とは何だろうか、というシンプルな問いへと観客を導きます。
社会批判や人間性への問いを底流に据えながらも、哲学的な方向にに深入りすることはございませんので、「2001年宇宙の旅」のラストでものすごい置いてけぼり感を味わったのろでも、最後まで楽しく観ることができました。
CGによる派手なドンパチ映像が隆盛を極めております昨今、エイリアンと闘うでもなく、地球の危機を救うでもない、こんなにもヒロイックな要素の無いSF映画は珍しいのではないかしらん。とはいえ自らの運命を受け入れ、かつそれを自分の手で変えるべく一歩を踏み出すサム・ベルの行動はささやかながらも英雄的であり、このあたり、ちょっと「ガタカ」と通じるものがございます。
監督・脚本をつとめたダンカン・ジョーンズは「デヴィッド・ボウイの息子」という重たい称号を背負った人でございます。プレッシャーが無いわけはないと思いますが、それに潰されることなく、これからも創作を続けていただきたいものでございます。
レイ・ブラッドベリ作品のようなもの悲しいSFでございまして、観賞後にはしみじみとした余韻が残ります。
チラシなどの雰囲気からてっきりバッドエンドに違いないと身構えていたのろには、意外にも希望の感じられるエンディングは嬉しいものでございました。ついでに申せば作品の雰囲気と内容をよく表している邦題も、近年まれに見る秀逸さではないかと。(現題は単に”Moon”)
月に囚(とら)われた男 - オフィシャルサイト
SFといっても視覚的な派手さはなく、ほとんど密室劇のような展開。しかも出演者は実質的に主人公ひとりだけ、という超ミニマル映画でございます。舞台装置はいたって地味でありながら最後まで飽きさせないのは、求心力のある脚本と主役を演じるサム・ロックウェルの熱演のなせる技でございましょう。
出演者ひとり、とはどういうことかと申しますと。
主人公のサム・ベルはとある企業の従業員で、資源採掘のため3年の任期で月の裏側に単身赴任しております。採掘作業は機械化されているため、基地にいるのは積み込みと発送作業にあたるサムひとりっきり。会社のお偉いさんは「いや~君はわが社の誇りだよ~」なんて言ってくれるものの、通信の不具合についてはほったらかしで、なかなか直してしてくれない。そのせいでサムは地球にいる妻や娘との会話もままならず、話し相手といっては人工知能搭載のロボット、ガーティだけ。
このガーティを含め、機器や内装のデザインはいかにも実用第一といった感じの無機質なもので、心なごませるような所がちっともございません。そこに何とか人間的な空間を演出しようとして、サムがこまごまと努力しているあたりがリアルでもあり、哀しくもあるのでございます。植物を育て、写真を貼りまくり、故郷の街の模型を作る。そして今日で何日経過というカレンダーをトイレの壁に記していく。囚人がやるように。
そんな淋しく単調な3年間もあと少しで終わり、いよいよ地球に帰れるぞという時に採掘現場で事故を起こし、基地で目覚めたサム。妙な胸騒ぎに導かれて事故現場に行ってみると、そこには何と事故車両に埋もれたままの自分の姿が。
こいつは誰だ?
いやいや俺は誰だ?
・・・
「月に囚われた男」予告編
とまあこんな具合でございまして。
ふたりサムの謎はわりかしあっさりと解明されるのでございますが、謎が解けたところで、それだけではなんら解決にはならないというのがミソ。
しかも会社から派遣された船が刻一刻と近づいているのでございます。このタイムリミットがあるおかげで、初めは淡々と進むかに思えた物語は終盤へ行くに従ってずんずん緊張感を高めてまいります。のろはラスト10分ばかりは、両手を握りしめて うおーがんばれサム~ちゅーか急げ~ と心の内で声援を送っておりました。
サム・ロックウェルはたいへん好演でございまして、外界から遮断された空間で自分の分身?と付き合う、というまことにうっとうしい状況に追い込まれた男のいらだちと、真実を知ってしまったことから沸き上がる悲哀がひしひし伝わってまいります。後者については描き方が少々ウエットすぎるような気もいたしましたが、泣いている観客もいらっしたのようですので、まあ好みの問題かもしれません。
サムの唯一の話し相手である人工知能ロボット、ガーティの声を担当するのはケビン・スペイシー。何せ飄々としたくせ者を演じたら当代随一のけびんさんでございましょう。こいつ絶対何か隠してるに違いない、と初めから不信感満々で観ていたんでございますが、 ガーティ君、意外といい奴でございました、人間味があって。
人工知能に人間味もへったくれもあろうかって。いやいや、ここもまたミソなのでございまして。「サムを守る」というプログラムの指令に従って優しい選択をするガーティ、利益のためなら人を人とも思わない大企業、そして、二人のサム。彼らのありようは「人間らしさ」とは何だろうか、というシンプルな問いへと観客を導きます。
社会批判や人間性への問いを底流に据えながらも、哲学的な方向にに深入りすることはございませんので、「2001年宇宙の旅」のラストでものすごい置いてけぼり感を味わったのろでも、最後まで楽しく観ることができました。
CGによる派手なドンパチ映像が隆盛を極めております昨今、エイリアンと闘うでもなく、地球の危機を救うでもない、こんなにもヒロイックな要素の無いSF映画は珍しいのではないかしらん。とはいえ自らの運命を受け入れ、かつそれを自分の手で変えるべく一歩を踏み出すサム・ベルの行動はささやかながらも英雄的であり、このあたり、ちょっと「ガタカ」と通じるものがございます。
監督・脚本をつとめたダンカン・ジョーンズは「デヴィッド・ボウイの息子」という重たい称号を背負った人でございます。プレッシャーが無いわけはないと思いますが、それに潰されることなく、これからも創作を続けていただきたいものでございます。