「恩を喜べる自分をよろこぶ」。自分の手元で完結していく。それは不幸な出来事でも同じです。不幸が不幸を生み出していくということがあります。がんを患う、町を歩いていて「なぜあの人ではなく、この私ががんになったんだろうか」と、一日中、がんを引きずるというのが、通常のパターンです。
しかし悟りを得た人は、「第二の矢を受けない」という教えがあります。
「不幸にして、矢に打たれた人があるとしよう。ここで、次にどうするのかに関して、二種に分かれるだろう。一人は、慌てふためき、第二の矢を受けてしまう人。もう一人は、矢に打たれても痛みに耐え動揺せず、第二の矢をかわすことの出来る人である」
仏は続ける。
「仏の教えを知らない凡夫は、最初の人である。苦しさに嘆き悲しんで、混迷の心は深まるばかり。楽も、かえって迷いの心を増すばかりである。仏の教えを知る人は、第二の人である。苦しみを受けてもそれに耐え、苦しみに囚われることが無くなり、生死の束縛を脱する事が出来る」
「このことが、仏教を知らない者と知る者との違いなのである」と。(以上)
悟りに達した人であっても、生老病死の暴流の中で、その事実に対した時、悲しみや苦しみ怒りをもちます。しかし「第二の矢を受けない」とは、その次には事実を受け入れて、その事実から波紋のように広がっていく苦しみは受けないというのです。
初っ端から釈尊の言葉を出したのは、「師の恩を思える心を喜ぶ」とは、「第二の矢を受けない」ことと通ずると思うからです。
私たちは損した得したという客観的に事実に、衝撃を受けます。これが第一の矢です。悟りを得た人も同様に衝撃を受けるのです。ところが凡夫は、その事実に引きずられて、その原因を外に求めます。とこらは悟道の人は、その衝撃の原因が外界にあるのではなく、そう受けとめてしまう私の側にあると見極めます。だからその客観的に事実に引きずられることがないのです。
これは先の「思う心を喜ぶ」と同様に、私の外にある念仏を喜ぶことから、喜べる自分喜ぶという具合に心が深まっていく。それは同様に客観的な事実を悲しむとう第一の矢は即、「思う心を悲しみて」と衝撃の原因をわたしの内に見ていくので、客観的な事実にのめり込まずに済むのです。それはイコール第二の矢を受けなくて済むのです。がんが苦しみの原因ではなく、がんを苦しみだと感じている私が、苦しみの大本であることに開かれて生きることです。
しかし悟りを得た人は、「第二の矢を受けない」という教えがあります。
「不幸にして、矢に打たれた人があるとしよう。ここで、次にどうするのかに関して、二種に分かれるだろう。一人は、慌てふためき、第二の矢を受けてしまう人。もう一人は、矢に打たれても痛みに耐え動揺せず、第二の矢をかわすことの出来る人である」
仏は続ける。
「仏の教えを知らない凡夫は、最初の人である。苦しさに嘆き悲しんで、混迷の心は深まるばかり。楽も、かえって迷いの心を増すばかりである。仏の教えを知る人は、第二の人である。苦しみを受けてもそれに耐え、苦しみに囚われることが無くなり、生死の束縛を脱する事が出来る」
「このことが、仏教を知らない者と知る者との違いなのである」と。(以上)
悟りに達した人であっても、生老病死の暴流の中で、その事実に対した時、悲しみや苦しみ怒りをもちます。しかし「第二の矢を受けない」とは、その次には事実を受け入れて、その事実から波紋のように広がっていく苦しみは受けないというのです。
初っ端から釈尊の言葉を出したのは、「師の恩を思える心を喜ぶ」とは、「第二の矢を受けない」ことと通ずると思うからです。
私たちは損した得したという客観的に事実に、衝撃を受けます。これが第一の矢です。悟りを得た人も同様に衝撃を受けるのです。ところが凡夫は、その事実に引きずられて、その原因を外に求めます。とこらは悟道の人は、その衝撃の原因が外界にあるのではなく、そう受けとめてしまう私の側にあると見極めます。だからその客観的に事実に引きずられることがないのです。
これは先の「思う心を喜ぶ」と同様に、私の外にある念仏を喜ぶことから、喜べる自分喜ぶという具合に心が深まっていく。それは同様に客観的な事実を悲しむとう第一の矢は即、「思う心を悲しみて」と衝撃の原因をわたしの内に見ていくので、客観的な事実にのめり込まずに済むのです。それはイコール第二の矢を受けなくて済むのです。がんが苦しみの原因ではなく、がんを苦しみだと感じている私が、苦しみの大本であることに開かれて生きることです。












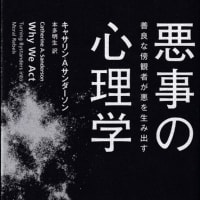
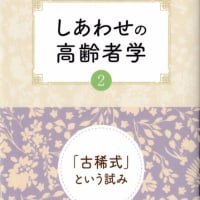


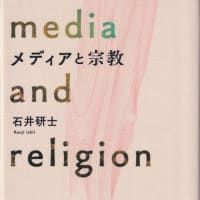

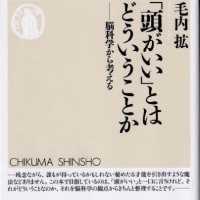
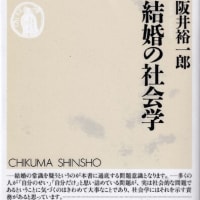
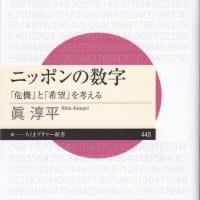







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます