大乗へ掲載と書いていましたが、会報ビハーラ52号「編集後記」へ掲載します。以下転載
性的少数者に対する理解を広げるための「LGBT理解増進法」が成立した。性の多様性に配慮し、同性カップルや友だちカップルであっても結婚を認め、異性カップルと同等の権利を与えるという動きが世界的に広がっている。
多様性といえば『阿弥陀経』にも「青色には青光が、黄色には黄光が、赤色には赤光が、白色には白光が」とあることからして、浄土真宗のみ教えから言ってもジェンダー平等社会の実現は望むべき方向だろう。
しかしここに大きな繋念がある。それは浄土真宗をはじめ既成仏教教団は、門徒(檀家)制度に支えられているという点だ。法律学者の川島武宣氏は『日本社会の家族的構成』に、「家」制度を支える意識を次の様にまとめられている。①血統連続に対する強い尊重―父系血統、女性の蔑視。②多産の尊重 子を産まない妻の蔑視。先祖の尊重。③伝統の尊重、個人に対する「家」の優位。④家の外部においても個人をその属する家(家族)によって位置づけることー家柄の尊重とある。
この家制度は「LGBT理解増進法」がめざす方向と真逆にある。これは浄土真宗ばかりではなく、世界の伝統教団の課題でもある。
旧来の家制度によって支えられる教団。個人の信心の確立によって相続される教団。両者とも重要な教団存続の課題だが、どちらにしろ、個人における信心の果たす役割を明確に提示する必要がある。
哲学用語で「限界状況」という語がある。ドイツの哲学者カール・ヤスパースの用いた哲学概念だ。『哲学入門』(1950)では、「死、苦悩、争い、偶然、罪などが限界状況として考えられ、これら限界状況の経験はわれわれを絶望のなかに突き落とすが、しかしわれわれは絶望に直面したときに初めて真の自分となることができる」とある。「真の自分となる」とは、自分の思慮分別を超えることだ。絶望は、歓迎されない状況だが、「真の自分となる」機縁だということだ。 浄土真宗で「捨機即託法」(しゃきそくたくほう)という。私の世界の絶望がそのままより質の高い阿弥陀仏の世界に開かれる起点となるということだ。自分を捨てることが、そのまま大きな世界に開かれる。この考え方は「限界状況」と同様に、質的転換をその内容としている。
今、重要なのは、家制度のなかでも、性の多様性の狭間で悩む人であっても、その苦悩に寄り添い、自分の思慮分別を超える道のあることを共有し共に歩むことだろう。(西原)
性的少数者に対する理解を広げるための「LGBT理解増進法」が成立した。性の多様性に配慮し、同性カップルや友だちカップルであっても結婚を認め、異性カップルと同等の権利を与えるという動きが世界的に広がっている。
多様性といえば『阿弥陀経』にも「青色には青光が、黄色には黄光が、赤色には赤光が、白色には白光が」とあることからして、浄土真宗のみ教えから言ってもジェンダー平等社会の実現は望むべき方向だろう。
しかしここに大きな繋念がある。それは浄土真宗をはじめ既成仏教教団は、門徒(檀家)制度に支えられているという点だ。法律学者の川島武宣氏は『日本社会の家族的構成』に、「家」制度を支える意識を次の様にまとめられている。①血統連続に対する強い尊重―父系血統、女性の蔑視。②多産の尊重 子を産まない妻の蔑視。先祖の尊重。③伝統の尊重、個人に対する「家」の優位。④家の外部においても個人をその属する家(家族)によって位置づけることー家柄の尊重とある。
この家制度は「LGBT理解増進法」がめざす方向と真逆にある。これは浄土真宗ばかりではなく、世界の伝統教団の課題でもある。
旧来の家制度によって支えられる教団。個人の信心の確立によって相続される教団。両者とも重要な教団存続の課題だが、どちらにしろ、個人における信心の果たす役割を明確に提示する必要がある。
哲学用語で「限界状況」という語がある。ドイツの哲学者カール・ヤスパースの用いた哲学概念だ。『哲学入門』(1950)では、「死、苦悩、争い、偶然、罪などが限界状況として考えられ、これら限界状況の経験はわれわれを絶望のなかに突き落とすが、しかしわれわれは絶望に直面したときに初めて真の自分となることができる」とある。「真の自分となる」とは、自分の思慮分別を超えることだ。絶望は、歓迎されない状況だが、「真の自分となる」機縁だということだ。 浄土真宗で「捨機即託法」(しゃきそくたくほう)という。私の世界の絶望がそのままより質の高い阿弥陀仏の世界に開かれる起点となるということだ。自分を捨てることが、そのまま大きな世界に開かれる。この考え方は「限界状況」と同様に、質的転換をその内容としている。
今、重要なのは、家制度のなかでも、性の多様性の狭間で悩む人であっても、その苦悩に寄り添い、自分の思慮分別を超える道のあることを共有し共に歩むことだろう。(西原)





















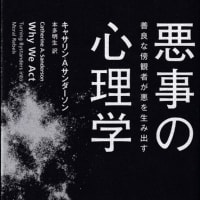






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます