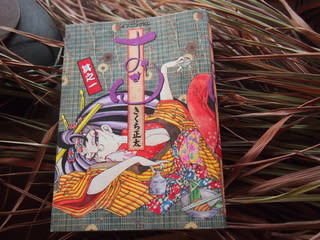昨年暮れ、西尾市の友人宅に寄ったとき、庭先になっていたミカンを、たくさんの野菜や果物と一緒にもらってきました。そのとき、彼女は、「完全無農薬のミカンだけれど、すっぱくておいしくないよ。ジュースにしてね」と言いました。
それで、いずれジュースにしようとおもいつつ、別のお宅からもらった甘いミカンばかり食べて、このミカンのことを忘れかけていました。先日ふと見たら、しわだらけ。それで、友人の言葉通りジュースにしました。

さがせば、ミキサーに付属しているジューサーがあるのですが、めんどうなので、この手動ジューサーを使いました。フリーマーケットで300円で手に入れたものです。

完熟なので、ぐっと力を入れて押さえるだけで、簡単にしぼれます。3個くらいしぼって、コップ1杯になりました。
さっそく試飲。香りがいい。味も、すばらしい! すっぱいどころか、甘い。酸味もあって、甘味もあって、これまで飲んだミカンジュースの中で、一番おいしいかもしれません。長いこと置いておいたので、甘味が凝縮したのかもしれませんが、感動的なおいしさでした。友人に知らせて、また来年もいただこう。
それで、いずれジュースにしようとおもいつつ、別のお宅からもらった甘いミカンばかり食べて、このミカンのことを忘れかけていました。先日ふと見たら、しわだらけ。それで、友人の言葉通りジュースにしました。

さがせば、ミキサーに付属しているジューサーがあるのですが、めんどうなので、この手動ジューサーを使いました。フリーマーケットで300円で手に入れたものです。

完熟なので、ぐっと力を入れて押さえるだけで、簡単にしぼれます。3個くらいしぼって、コップ1杯になりました。
さっそく試飲。香りがいい。味も、すばらしい! すっぱいどころか、甘い。酸味もあって、甘味もあって、これまで飲んだミカンジュースの中で、一番おいしいかもしれません。長いこと置いておいたので、甘味が凝縮したのかもしれませんが、感動的なおいしさでした。友人に知らせて、また来年もいただこう。