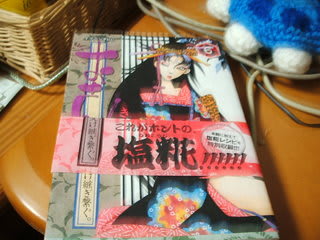きょう、若い友人Kちゃんが遊びに来ることになったので、昨夜からピザを仕込みました。私のピザは、中力粉と強力粉がほぼ半々。一割ほどの全粒粉も必ず入れます。酵母はホシノ。
彼女が到着する予定の10分前に急いで伸ばしたので、かなり厚めのピザになりました。トマトソースは夏に作って瓶詰めした自家製。なにもかも大切りで、急いで作ったさまがあらわなピザですが、おいしいといってもらえました。よかった。

前に、Kちゃんのお父さんが作ったサツマイモをたくさんいただいたので、そのサツマイモでなにか作ってお返ししたいと思って、これも今朝急遽作ったサツマイモケーキ。

先日ユズと一緒に甘く煮たサツマイモの残りをつぶし、角切りにしてオイルをかけて焼いたサツマイモと一緒に生地に混ぜ込みました。リンゴの甘煮とレーズンも入れました。味を見ながら、加減して作ってみましたが、甘酸っぱさがなかなかいけます。サツマイモの芋くささがユズで消えています。2月に豊田市の街中で開かれるイベントに、出品してみたくなりました。しばらく試作をつづけてみます。

こちらは、正月に友人たちに送ろうと思って作ったパン。クルミとレーズン入りのカンパーニュです。試作を兼ねて作ってみました。感想をきいてから、さらに試作を重ねるつもりです。
稲武はきょうも雪が降らずになんとか持ちこたえました。どんぐりの里いなぶは今日から初仕事。雪が降らないとお客さんはけっこう来て下さるようです。アンティマキは、穀物クッキーを4種納品しました。あさっては、できればスコーンも販売する予定です。そろそろオカキの仕込みも開始します。
彼女が到着する予定の10分前に急いで伸ばしたので、かなり厚めのピザになりました。トマトソースは夏に作って瓶詰めした自家製。なにもかも大切りで、急いで作ったさまがあらわなピザですが、おいしいといってもらえました。よかった。

前に、Kちゃんのお父さんが作ったサツマイモをたくさんいただいたので、そのサツマイモでなにか作ってお返ししたいと思って、これも今朝急遽作ったサツマイモケーキ。

先日ユズと一緒に甘く煮たサツマイモの残りをつぶし、角切りにしてオイルをかけて焼いたサツマイモと一緒に生地に混ぜ込みました。リンゴの甘煮とレーズンも入れました。味を見ながら、加減して作ってみましたが、甘酸っぱさがなかなかいけます。サツマイモの芋くささがユズで消えています。2月に豊田市の街中で開かれるイベントに、出品してみたくなりました。しばらく試作をつづけてみます。

こちらは、正月に友人たちに送ろうと思って作ったパン。クルミとレーズン入りのカンパーニュです。試作を兼ねて作ってみました。感想をきいてから、さらに試作を重ねるつもりです。
稲武はきょうも雪が降らずになんとか持ちこたえました。どんぐりの里いなぶは今日から初仕事。雪が降らないとお客さんはけっこう来て下さるようです。アンティマキは、穀物クッキーを4種納品しました。あさっては、できればスコーンも販売する予定です。そろそろオカキの仕込みも開始します。