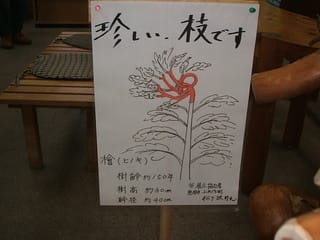ここのところ、2,3日おきに雪か雨が降り、その翌日は美しい晴天の日となることが多い。水曜日もそんな雪の合間の快晴の日だったので、用事を兼ねて久々に隣町の岐阜県恵那市と土岐市に行きました。
岐阜はなぜか道の駅が多い。稲武を出て15分ほどすると「ラフォーレ福寿の里」があります。通りすがりによく買物する場所です。家人がほしいというので、骨酒用のアマゴを買いました。前もよそで買ったことがあるのですが、私は生臭さが鼻についていただけなかった。わりと素性のいい材料でおいしいお菓子をつくっているキッチンセルプという上矢作町の共同作業所の商品です。

菌床栽培のしいたけの赤ちゃんを見つけました。これだけで350円くらいだたと思います。前に知人が、よそでこのシイタケの赤ちゃんの味噌煮が出て、とてもおいしかったといっていたのを思い出したので買ってみました。

翌日作ったのがこちらです。もっと煮詰めたら知人が言っていたようなお肉の味がしたかもしれません。でもおいしかった。

ほかに、稲庭うどんのうどんふしも買いました。こちらは、稲庭うどんのコーナーがあり、多種類の製品を売っています。遠く離れている場所なのに、どういうかかわりがあるのかわかりません。

この日の目的は土岐市のどんぶり会館にいらない食器を捨てに行くこと。山岡のおばあちゃん市は通り道なので、立ち寄りました。たびたび行く場所なのですが、周囲の景色を見たのははじめて。緑色のダム湖が美しい。

ここは、巨大な水車のモニュメントが売りなのですが、昔はこのあたりで水車による水力発電所があったということを始めて知りました。それで撤去してから記念碑として建てたらしい。だったら、せっかくだからもっと小規模な水車でいいから動くものにしてほしかった。そして米か小麦をつく小屋もあったらおもしろかったのに。

こちらは、小さい直売所があるのですが、全国の道の駅の商品もおいていて充実しています。青森のゴボウうどんを買いました。きょうのお昼に昨夜の残りのいわしのつみれ味噌汁に入れてみるつもりです。150gしか入っていないので、二人分には足りませんが。
左のお皿に乗せてあるのは、岩村にある焼き菓子の店・HALLISEのもの。前から食べてみたかったお菓子です。卵もバターも入っているふつうのお菓子ですが、甘さが押さえてあって、どれもおいしい。いいお菓子屋だと思います。

目的地のどんぶり会館で食器を「陶器リサイクルボックス」に捨てました。前に来たときはたくさんでも引き取ってくれたのですが、今度は、「ダンボール1箱程度に」と但し書きがあります。なんとかボックスに収まったのでやれやれ。捨てた陶器は、陶器レンガにするのだそう。瑞浪では、リサイクル食器も作られているそうです(こちら→)。
この道の駅は、市価よりかなり安めの陶器がたくさん売られています。陶器を捨てに来てまた買うこともしばしばあるのですが、今回は、300円のぐい飲みと小さめのおろし器を買うにとどめました。
こちらはおばあちゃん市より一段とたくさんの全国の道の駅の商品が並んでいます。こちらも来た目的のひとつ。

高知のカツオの品いろいろ。無添加で日持ちする品です。なまり節より魚臭さがなくて、おいしい。酒盗もあったので買いました。無添加の酒盗は珍しいと思う。期待して買ったのですが、保存料の代わりのつもりか砂糖の入れすぎで甘すぎる。酒の肴にはなりません。いま、塩麹を入れて、再製造中です。赤紫蘇は梅酢着け。おにぎりなどにまいたらおいしそうです。自分でも作ってみたくて参考までに買ってみました。

4つめの道の駅はソバの里・らっせいみさと。「らっせい」というのは方言で「いらっしゃい」らしい。ここに寄ったのはそばを食べるためです。地元の女性達が打っているのですが、安いわりにおいしい。新そばをたべたかったので楽しみでした。でも、そばはいいのですが、おつゆが甘い。どこに行っても、甘すぎるのが私達には難点です。

こちらで見つけた純米酒「くろくわ」。4合で1600円くらいなので、けっこう安い。精米歩合は書いてありません。箱の中に一筆箋に手書きしてコピーした文字で、こんなことが書いてあります。
「日本棚田百選のひとつ坂折棚田は、約四百年の歴史を有し、黒鍬(普請組、石工)が積んだ石垣は今なおその堅牢さを誇り、その石垣に囲まれたいくつもの田んぼが四季折々の表情を演出します。このお酒(くろくわ)は、坂折棚田で穫れたお米(坂折棚田米)、坂折川の清水で吟醸したこだわりの古里銘酒です。ご一献どうぞ。(寒のうちの水使用)」
こちらに来てから、田んぼの石垣が小さい石で細かく積まれているのをよく見かけます。長いことずっと壊れずにいたということは、やはりちゃんとした職人集団が、こんな山里にも来ていたということなのだと知りました。お米も酒も、丹精込めて作っている気分が伝わる文章です。お酒は、雑味がなくて、値段のわりにはおいしいお酒でした。これも掘り出し物です。今度行ったときも買いたいと思います。

らっせいみさとで、もう一つ知ったことがあります。それは、粗朶(そだ)沈床工法のことです。食堂でそばがゆで上がるのを待ちながら読んだ、「森林のたより」(公益社団法人・岐阜県山林協会刊)の記事で知りました。直売所にあった冊子です。

粗朶とは、柴の束のこと。「おじいさんは山へ柴刈りにいきました」の、あの柴です。広葉樹の小枝を束にして、昔から「柴漬け漁」という漁法が行われていたことは知っていました。粗朶を川に沈めておくだけで、エビや小魚が入り込むという、「濡れ手で粟」の漁法。伝統漁法だそうです。冊子には、生物のほとんど棲んでいない用水路に、この粗朶を置いたところ、モクズガニを始めとするたくさんの魚や甲殻類、水生昆虫が集まってきたのだそう。
この粗朶を河川の改修工事に使うのが、粗朶沈床工法。明治以降、ヨーロッパのこの工法が日本にはいってきて、あちこちの河川で施行されたそうです。いまでも、この工法をおこなう会社が数軒存在。現在主流になっているコンクリートブロックを用いる工法より、粗朶を使う工法のほうが、川の流れをソフトに変えるのだそう。河川の氾濫を減らすためにも良い効果が出そうです。また、ブロックを作るときからの環境負荷を考えると、CO2排出量は粗朶のほうが2744分の1だということです。
ただし、里山が荒れ、粗朶生産に携わる人つまり「柴刈りする」人が激減しているため、もし需要があったとしても供給が間に合わないだろう、とこの冊子の論者(岐阜県森林文化アカデミー・柳沢直氏)は書いています。
「もちろん昔の人は自然環境の保全を目的に暮していたわけではありません。しかし、昔の人の「森林を生かす知恵」が、結果的に日本の自然を守ってきたのです。学ぶべきことは多くあると思います」
同感です。
余談ですが、フェイスブックにこの粗朶の工法のことを書いたら、30代の何人かの方たちから、「「おじいさんは山へ芝刈りに」だとおもっていた」とのコメントをもらいました。「山で芝刈ってどうするんだろう?とおもっていた」という話も。東芝の「芝」ならぬ「柴田さん」の「柴」は、いまや死語なのだとあらためて知りました。
かまどやお風呂をくべるのに、いきなり薪に火をつけても燃えつかないから、松葉や枯葉、稲藁などに燃えつかせ、それから小枝、つまり柴に燃え移らせて薪へと火を大きくして行くのですが、その工程がいまの若い人には想定できないかもしれません。新聞紙だって、あったとしても貴重だったとおもいます。
ついでに思い出したことですが、私の母方の曾祖母は「ごかきが好きだった」と、母がよく話していました。「孫達の世話はきらいだったみたいで、よく姿を消していた。そういうときはたいてい山へごかきにいっていた」と。
「ご」というのは、方言かと思っていたのですが、辞書で調べたら、「枯松葉」とありました。母の実家は落葉松の育つ土地ではないので、たぶん焚き物にする落ち葉全部をさして「ご」と言っていたのでしょう。曾祖母にとって、騒々しくて忙しい家を出て、山の中で一人静かに時間を過ごすのに、「ごかき」はかっこうの口実だったのでしょう。
森鴎外の「山椒大夫」には、中流貴族の息子・厨子王が、山椒大夫の屋敷でなれない山仕事をさせられる場面があるのですが、そのときの彼の仕事が「柴刈り」でした。力のない子供や老人の仕事が、「ごかき」や「柴刈り」だったのでしょう。今は、こういう、小さいけれど役に立つ仕事、というのがどんどん減っているのかもしれません。
岐阜はなぜか道の駅が多い。稲武を出て15分ほどすると「ラフォーレ福寿の里」があります。通りすがりによく買物する場所です。家人がほしいというので、骨酒用のアマゴを買いました。前もよそで買ったことがあるのですが、私は生臭さが鼻についていただけなかった。わりと素性のいい材料でおいしいお菓子をつくっているキッチンセルプという上矢作町の共同作業所の商品です。

菌床栽培のしいたけの赤ちゃんを見つけました。これだけで350円くらいだたと思います。前に知人が、よそでこのシイタケの赤ちゃんの味噌煮が出て、とてもおいしかったといっていたのを思い出したので買ってみました。

翌日作ったのがこちらです。もっと煮詰めたら知人が言っていたようなお肉の味がしたかもしれません。でもおいしかった。

ほかに、稲庭うどんのうどんふしも買いました。こちらは、稲庭うどんのコーナーがあり、多種類の製品を売っています。遠く離れている場所なのに、どういうかかわりがあるのかわかりません。

この日の目的は土岐市のどんぶり会館にいらない食器を捨てに行くこと。山岡のおばあちゃん市は通り道なので、立ち寄りました。たびたび行く場所なのですが、周囲の景色を見たのははじめて。緑色のダム湖が美しい。

ここは、巨大な水車のモニュメントが売りなのですが、昔はこのあたりで水車による水力発電所があったということを始めて知りました。それで撤去してから記念碑として建てたらしい。だったら、せっかくだからもっと小規模な水車でいいから動くものにしてほしかった。そして米か小麦をつく小屋もあったらおもしろかったのに。

こちらは、小さい直売所があるのですが、全国の道の駅の商品もおいていて充実しています。青森のゴボウうどんを買いました。きょうのお昼に昨夜の残りのいわしのつみれ味噌汁に入れてみるつもりです。150gしか入っていないので、二人分には足りませんが。
左のお皿に乗せてあるのは、岩村にある焼き菓子の店・HALLISEのもの。前から食べてみたかったお菓子です。卵もバターも入っているふつうのお菓子ですが、甘さが押さえてあって、どれもおいしい。いいお菓子屋だと思います。

目的地のどんぶり会館で食器を「陶器リサイクルボックス」に捨てました。前に来たときはたくさんでも引き取ってくれたのですが、今度は、「ダンボール1箱程度に」と但し書きがあります。なんとかボックスに収まったのでやれやれ。捨てた陶器は、陶器レンガにするのだそう。瑞浪では、リサイクル食器も作られているそうです(こちら→)。

この道の駅は、市価よりかなり安めの陶器がたくさん売られています。陶器を捨てに来てまた買うこともしばしばあるのですが、今回は、300円のぐい飲みと小さめのおろし器を買うにとどめました。
こちらはおばあちゃん市より一段とたくさんの全国の道の駅の商品が並んでいます。こちらも来た目的のひとつ。

高知のカツオの品いろいろ。無添加で日持ちする品です。なまり節より魚臭さがなくて、おいしい。酒盗もあったので買いました。無添加の酒盗は珍しいと思う。期待して買ったのですが、保存料の代わりのつもりか砂糖の入れすぎで甘すぎる。酒の肴にはなりません。いま、塩麹を入れて、再製造中です。赤紫蘇は梅酢着け。おにぎりなどにまいたらおいしそうです。自分でも作ってみたくて参考までに買ってみました。

4つめの道の駅はソバの里・らっせいみさと。「らっせい」というのは方言で「いらっしゃい」らしい。ここに寄ったのはそばを食べるためです。地元の女性達が打っているのですが、安いわりにおいしい。新そばをたべたかったので楽しみでした。でも、そばはいいのですが、おつゆが甘い。どこに行っても、甘すぎるのが私達には難点です。

こちらで見つけた純米酒「くろくわ」。4合で1600円くらいなので、けっこう安い。精米歩合は書いてありません。箱の中に一筆箋に手書きしてコピーした文字で、こんなことが書いてあります。
「日本棚田百選のひとつ坂折棚田は、約四百年の歴史を有し、黒鍬(普請組、石工)が積んだ石垣は今なおその堅牢さを誇り、その石垣に囲まれたいくつもの田んぼが四季折々の表情を演出します。このお酒(くろくわ)は、坂折棚田で穫れたお米(坂折棚田米)、坂折川の清水で吟醸したこだわりの古里銘酒です。ご一献どうぞ。(寒のうちの水使用)」
こちらに来てから、田んぼの石垣が小さい石で細かく積まれているのをよく見かけます。長いことずっと壊れずにいたということは、やはりちゃんとした職人集団が、こんな山里にも来ていたということなのだと知りました。お米も酒も、丹精込めて作っている気分が伝わる文章です。お酒は、雑味がなくて、値段のわりにはおいしいお酒でした。これも掘り出し物です。今度行ったときも買いたいと思います。

らっせいみさとで、もう一つ知ったことがあります。それは、粗朶(そだ)沈床工法のことです。食堂でそばがゆで上がるのを待ちながら読んだ、「森林のたより」(公益社団法人・岐阜県山林協会刊)の記事で知りました。直売所にあった冊子です。

粗朶とは、柴の束のこと。「おじいさんは山へ柴刈りにいきました」の、あの柴です。広葉樹の小枝を束にして、昔から「柴漬け漁」という漁法が行われていたことは知っていました。粗朶を川に沈めておくだけで、エビや小魚が入り込むという、「濡れ手で粟」の漁法。伝統漁法だそうです。冊子には、生物のほとんど棲んでいない用水路に、この粗朶を置いたところ、モクズガニを始めとするたくさんの魚や甲殻類、水生昆虫が集まってきたのだそう。
この粗朶を河川の改修工事に使うのが、粗朶沈床工法。明治以降、ヨーロッパのこの工法が日本にはいってきて、あちこちの河川で施行されたそうです。いまでも、この工法をおこなう会社が数軒存在。現在主流になっているコンクリートブロックを用いる工法より、粗朶を使う工法のほうが、川の流れをソフトに変えるのだそう。河川の氾濫を減らすためにも良い効果が出そうです。また、ブロックを作るときからの環境負荷を考えると、CO2排出量は粗朶のほうが2744分の1だということです。
ただし、里山が荒れ、粗朶生産に携わる人つまり「柴刈りする」人が激減しているため、もし需要があったとしても供給が間に合わないだろう、とこの冊子の論者(岐阜県森林文化アカデミー・柳沢直氏)は書いています。
「もちろん昔の人は自然環境の保全を目的に暮していたわけではありません。しかし、昔の人の「森林を生かす知恵」が、結果的に日本の自然を守ってきたのです。学ぶべきことは多くあると思います」
同感です。
余談ですが、フェイスブックにこの粗朶の工法のことを書いたら、30代の何人かの方たちから、「「おじいさんは山へ芝刈りに」だとおもっていた」とのコメントをもらいました。「山で芝刈ってどうするんだろう?とおもっていた」という話も。東芝の「芝」ならぬ「柴田さん」の「柴」は、いまや死語なのだとあらためて知りました。
かまどやお風呂をくべるのに、いきなり薪に火をつけても燃えつかないから、松葉や枯葉、稲藁などに燃えつかせ、それから小枝、つまり柴に燃え移らせて薪へと火を大きくして行くのですが、その工程がいまの若い人には想定できないかもしれません。新聞紙だって、あったとしても貴重だったとおもいます。
ついでに思い出したことですが、私の母方の曾祖母は「ごかきが好きだった」と、母がよく話していました。「孫達の世話はきらいだったみたいで、よく姿を消していた。そういうときはたいてい山へごかきにいっていた」と。
「ご」というのは、方言かと思っていたのですが、辞書で調べたら、「枯松葉」とありました。母の実家は落葉松の育つ土地ではないので、たぶん焚き物にする落ち葉全部をさして「ご」と言っていたのでしょう。曾祖母にとって、騒々しくて忙しい家を出て、山の中で一人静かに時間を過ごすのに、「ごかき」はかっこうの口実だったのでしょう。
森鴎外の「山椒大夫」には、中流貴族の息子・厨子王が、山椒大夫の屋敷でなれない山仕事をさせられる場面があるのですが、そのときの彼の仕事が「柴刈り」でした。力のない子供や老人の仕事が、「ごかき」や「柴刈り」だったのでしょう。今は、こういう、小さいけれど役に立つ仕事、というのがどんどん減っているのかもしれません。