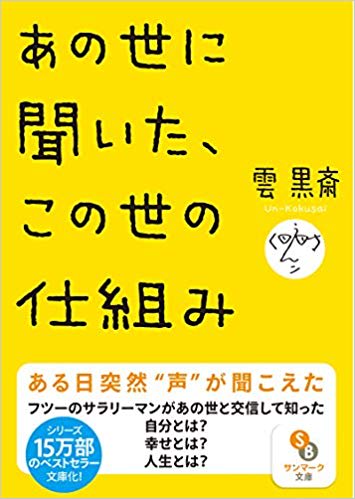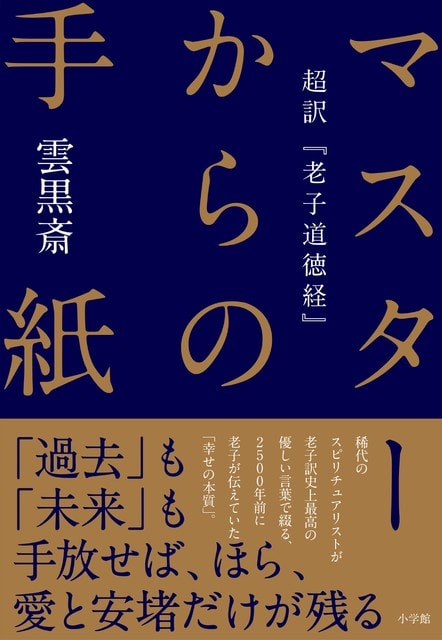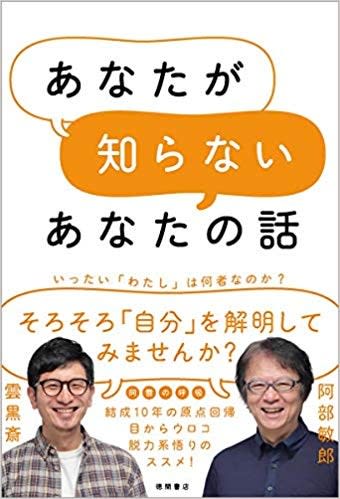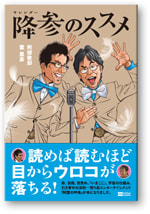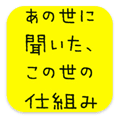いまさらながらの原点回帰
あの世に聞いた、この世の仕組み
三苦
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
さて、お待たせ致しました。『三苦』のお話です。
前回お話した「内的要因」と「外的要因」によって生まれる苦しみ。
お釈迦様は、それをさらに3つの根源にカテゴリー分けし、人間につきまとうあらゆる苦悩は、これらのいずれか、またはその複合的な組み合わせで成り立っていると説明しました。
まず、この『三苦』を辞書で調べるとこうありました。
さんく【三苦】[仏]
苦苦(くく)すなわち苦の縁から生じて受ける苦と、壊苦(えく)すなわち楽事が破れて受ける苦と、行苦(ぎょうく)すなわち無常の流転から受ける苦。
これを、少々乱暴ではありますが、平たくしていきたいと思います。
◎苦苦
サンスクリット語の「duHkha duHkhataa」を直訳すると、「苦痛を苦とする」ということだそうです。
これは、ある要因があることから受ける感覚的な苦しみ、「身体的ストレス」の事を指しています。
この説明によく用いられる例は、「暑い・寒い」という感覚とか、「腹が減った・喉が渇いた」とか。
また、もっと単純に「痛み」という感覚も含まれます。
タンスの角に足の小指をぶつけて悶絶するとかもこの「苦苦」。
「外苦」に比重の高さがある苦ですね。
◎壊苦
サンスクリット語の「vipariNaama duHkhataa」を直訳すると、「悪い方へ変化する苦」。
それがなぜ「壊れる苦」という字に訳されたかというと、この「vipariNaama(悪い方へ変化する)」という言葉が持つニュアンスの方を重視したからなんだそうです。
「快」や「楽」が壊滅(悪い方へ変化)することによって生まれる苦しみ。だから『壊苦』。
心地よいという状態や、好ましいと感じる対象が壊されていくことによって生まれる苦しみのことです。
「心地よい」とか「好ましい」という感覚・対象は人それぞれ認識の違いがありますので、『苦苦』以上に「内苦」が大きく関わってくる苦しみ。
『苦苦』の苦しみは、その外的要因が無くなれば楽に転じますが、この『壊苦』は「快」が無くなることによってストレスに転じる苦しみです。
快が得られない・続かない(欲求が満たされない・思い通りにならない)、良かれと思ってしたことが裏目に出る、正当な評価を与えてもらえない、理解してもらえないなどといった様々なことから生まれるストレス。
人間の進化(大脳新皮質が発達したこと)によって拡大された苦と言うこともできるかもしれません。
面白いですよね。
『苦苦』は苦しみ(外的要因)があることによって膨らむ苦しみ、それに対して『壊苦』は、「快」があるからこそ生まれる苦しみ。
なんだい、「苦」も「快(楽)」も、結局「苦」に転んじゃうんかい!(笑)。
でも、振り返ってみれば笑い話ではなく、お釈迦様の話はやっぱり本当のことなんですよね。
『人生とは、ストレスである』って。
で、最後の『行苦』。
これが、苦苦・壊苦が生み出される根本、「そもそも」のお話。
これについては、次回あらためて。
 ←オチが思いつかないという苦
←オチが思いつかないという苦
********************************************
さて、お待たせ致しました。『三苦』のお話です。
前回お話した「内的要因」と「外的要因」によって生まれる苦しみ。
お釈迦様は、それをさらに3つの根源にカテゴリー分けし、人間につきまとうあらゆる苦悩は、これらのいずれか、またはその複合的な組み合わせで成り立っていると説明しました。
まず、この『三苦』を辞書で調べるとこうありました。
さんく【三苦】[仏]
苦苦(くく)すなわち苦の縁から生じて受ける苦と、壊苦(えく)すなわち楽事が破れて受ける苦と、行苦(ぎょうく)すなわち無常の流転から受ける苦。
これを、少々乱暴ではありますが、平たくしていきたいと思います。
◎苦苦
サンスクリット語の「duHkha duHkhataa」を直訳すると、「苦痛を苦とする」ということだそうです。
これは、ある要因があることから受ける感覚的な苦しみ、「身体的ストレス」の事を指しています。
この説明によく用いられる例は、「暑い・寒い」という感覚とか、「腹が減った・喉が渇いた」とか。
また、もっと単純に「痛み」という感覚も含まれます。
タンスの角に足の小指をぶつけて悶絶するとかもこの「苦苦」。
「外苦」に比重の高さがある苦ですね。
◎壊苦
サンスクリット語の「vipariNaama duHkhataa」を直訳すると、「悪い方へ変化する苦」。
それがなぜ「壊れる苦」という字に訳されたかというと、この「vipariNaama(悪い方へ変化する)」という言葉が持つニュアンスの方を重視したからなんだそうです。
「快」や「楽」が壊滅(悪い方へ変化)することによって生まれる苦しみ。だから『壊苦』。
心地よいという状態や、好ましいと感じる対象が壊されていくことによって生まれる苦しみのことです。
「心地よい」とか「好ましい」という感覚・対象は人それぞれ認識の違いがありますので、『苦苦』以上に「内苦」が大きく関わってくる苦しみ。
『苦苦』の苦しみは、その外的要因が無くなれば楽に転じますが、この『壊苦』は「快」が無くなることによってストレスに転じる苦しみです。
快が得られない・続かない(欲求が満たされない・思い通りにならない)、良かれと思ってしたことが裏目に出る、正当な評価を与えてもらえない、理解してもらえないなどといった様々なことから生まれるストレス。
人間の進化(大脳新皮質が発達したこと)によって拡大された苦と言うこともできるかもしれません。
面白いですよね。
『苦苦』は苦しみ(外的要因)があることによって膨らむ苦しみ、それに対して『壊苦』は、「快」があるからこそ生まれる苦しみ。
なんだい、「苦」も「快(楽)」も、結局「苦」に転んじゃうんかい!(笑)。
でも、振り返ってみれば笑い話ではなく、お釈迦様の話はやっぱり本当のことなんですよね。
『人生とは、ストレスである』って。
で、最後の『行苦』。
これが、苦苦・壊苦が生み出される根本、「そもそも」のお話。
これについては、次回あらためて。
 ←オチが思いつかないという苦
←オチが思いつかないという苦コメント ( 65 ) | Trackback ( )