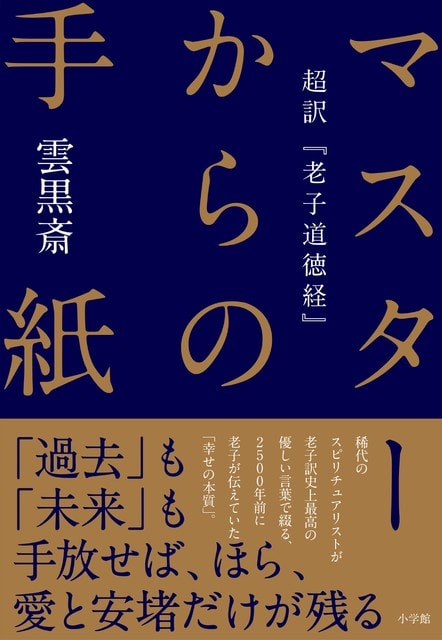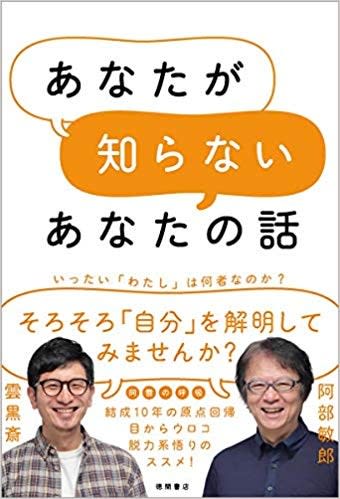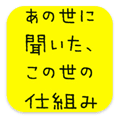いまさらながらの原点回帰
あの世に聞いた、この世の仕組み
極楽飯店.18
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
(※9月28日、ちょっとだけ加筆しました。)
翌朝、あけぼの台へ向かうバスは予定どおり七時に宿舎を出発した。
人通りのない景洛町の中を、数台のバスだけが連なって走っている。
しばらく走りバスが長いトンネルに入ると、田嶋が『ここが、景洛町と他の町を繋ぐ唯一の道です』と、後ろの座席から身を乗り出して、俺の隣に座る藪内に語りかけた。
景洛町は小高い山に囲まれた、小さな盆地になっており、この道以外から外に出ることはできない。この町に入る際も、出る際も、車は必ずここを通ることになるのだが、バスや送迎車が通る時以外は巨大なゲートでトンネルを塞がれ、出入りすることは不可能だと言う。
言われてみれば、確かに俺も案内係に連れてこられた際、このトンネルを通っている。
田嶋は続けて、「もし、失踪した人が自らの意志でこの町を出たとするなら、何らかの方法でそのゲートを開けたか、町を囲う山のどこかに抜け道を見つけたんじゃないですかね」と、自分の推測を告げていた。
トンネルを抜け緩やかな山道を過ぎると、バスは煌びやかな街に入った。
窓の外に見えるその街は、景洛町の様子とは対照的な活気に溢れ、幸せそうな人々の自由な往来がある。
曇りのない笑顔を浮かべて生活している人々のその様が恨めしかった。
この街のどこかに、あの世の入り口で出会ったあの老人も住んでいるのだろうか……。
そんな事を考えながら、ぼーっと外の景色を眺めていると、田嶋との会話を終えた藪内が小さな声で話しかけてきた。
「峰岸さん、あれから見ました?」
「え?」
「生活のしおりですよ。昨日、田嶋さんが話してた」
「いや。昨日は帰ってからすぐに寝た」
「そうですか…」
「で、何かわかったのか?」
「ええ。しおりの中に、飲食店情報っていうページがあって、そこにあの店の事も書かれていたんです」
「それで?」
俺がそう聞くと、藪内はうわさ話に花を咲かせる主婦みたいなイヤらしい目をして話を続ける。
「ヘンなんですよ。他の店は場所とか簡単な説明しか書いてないのに、あの店だけ妙に情報が多いんです。入店のための条件ってのがいくつかあって…」
「条件?」
「ええ。昨日、田嶋さん『団体客しか入れない』って言ってたじゃないですか。あれ、班単位での事前予約が必要ってことらしいんです。坂本さん、朝からずっと不機嫌そうでしょ。きっとそれを読んだからだと思うんです。坂本さんがどんなにあの店に行きたいって言っても、田嶋さんがあれじゃ、食うどころか店にも入れないですよ」
藪内が親指で示した窓側の席を見ると、口をへの字に曲げた坂本がむっすりとした表情で座っている。
と、その時。坂本の隣に座っていた白井がガバリと窓にへばりつき、いきなり「ば、ばぁちゃん!」と叫び出した。
一体何事か。突然の大声に、バスの中にいる乗客の視線が白井に集中する。
「い、いま、あそこに、僕の祖母が歩いてたんです!」
「おばあさん?」
興奮している白井に、田嶋が聞いた。
「ええ、間違いないです!祖母も、私に気づいていたみたいですから!」
白井はそう言って、再度バスが通り過ぎた道を名残惜しそうに見つめ続けた。
「くそっ、せめてこの窓を開けられたら、声をかけられたのに…」
バスから飛び降り逃げ出すのを防ぐためだろうか。俺たちを乗せたバスに、開閉機能はついていない。白井は悔しそうに、その窓を叩いている。
その様子を見ながら「おばあさんが亡くなられたのは、いつ頃です?」と、田嶋。
「三年ほど前です。まさか、こんなところで再会できるなんて…」
「ばあちゃんは、死んですぐにこの街に来たんですかね…」と藪内が興味津々な様子で話に加わると、白井は「どういう意味です?」と、目線を外から藪内に向けなおした。
「いや、ちょっと気になったんです。死んでまっすぐ天国ゲートに行けたのか、それとも、地獄ゲートを通ったのか……。こうして景洛町の外に住んでるってことは、直接天国側に案内されたか、景洛町に連れてこられたあとに、何らかの方法で町を出たかのどちらかですよね。もし地獄ゲートを通っていたのなら、当然町を出る方法を知ってるはずだと思って……」
「う~ん。直接聞かないことには、それはわからないですよね。でも、君の言うとおり、もし祖母が地獄ゲートを通ったのなら、出方を知っていることになりますね。話が出来たらなぁ…。田嶋君、このバスを途中下車する方法なんかは……」
「あるわけないでしょう!」
…つづく。
 ←ヘンなんですよ。他のブログは「クリックにご協力ください」とか簡単な説明しか書いてないのに、ここは妙に情報が多いんです。
←ヘンなんですよ。他のブログは「クリックにご協力ください」とか簡単な説明しか書いてないのに、ここは妙に情報が多いんです。
********************************************
(※9月28日、ちょっとだけ加筆しました。)
翌朝、あけぼの台へ向かうバスは予定どおり七時に宿舎を出発した。
人通りのない景洛町の中を、数台のバスだけが連なって走っている。
しばらく走りバスが長いトンネルに入ると、田嶋が『ここが、景洛町と他の町を繋ぐ唯一の道です』と、後ろの座席から身を乗り出して、俺の隣に座る藪内に語りかけた。
景洛町は小高い山に囲まれた、小さな盆地になっており、この道以外から外に出ることはできない。この町に入る際も、出る際も、車は必ずここを通ることになるのだが、バスや送迎車が通る時以外は巨大なゲートでトンネルを塞がれ、出入りすることは不可能だと言う。
言われてみれば、確かに俺も案内係に連れてこられた際、このトンネルを通っている。
田嶋は続けて、「もし、失踪した人が自らの意志でこの町を出たとするなら、何らかの方法でそのゲートを開けたか、町を囲う山のどこかに抜け道を見つけたんじゃないですかね」と、自分の推測を告げていた。
トンネルを抜け緩やかな山道を過ぎると、バスは煌びやかな街に入った。
窓の外に見えるその街は、景洛町の様子とは対照的な活気に溢れ、幸せそうな人々の自由な往来がある。
曇りのない笑顔を浮かべて生活している人々のその様が恨めしかった。
この街のどこかに、あの世の入り口で出会ったあの老人も住んでいるのだろうか……。
そんな事を考えながら、ぼーっと外の景色を眺めていると、田嶋との会話を終えた藪内が小さな声で話しかけてきた。
「峰岸さん、あれから見ました?」
「え?」
「生活のしおりですよ。昨日、田嶋さんが話してた」
「いや。昨日は帰ってからすぐに寝た」
「そうですか…」
「で、何かわかったのか?」
「ええ。しおりの中に、飲食店情報っていうページがあって、そこにあの店の事も書かれていたんです」
「それで?」
俺がそう聞くと、藪内はうわさ話に花を咲かせる主婦みたいなイヤらしい目をして話を続ける。
「ヘンなんですよ。他の店は場所とか簡単な説明しか書いてないのに、あの店だけ妙に情報が多いんです。入店のための条件ってのがいくつかあって…」
「条件?」
「ええ。昨日、田嶋さん『団体客しか入れない』って言ってたじゃないですか。あれ、班単位での事前予約が必要ってことらしいんです。坂本さん、朝からずっと不機嫌そうでしょ。きっとそれを読んだからだと思うんです。坂本さんがどんなにあの店に行きたいって言っても、田嶋さんがあれじゃ、食うどころか店にも入れないですよ」
藪内が親指で示した窓側の席を見ると、口をへの字に曲げた坂本がむっすりとした表情で座っている。
と、その時。坂本の隣に座っていた白井がガバリと窓にへばりつき、いきなり「ば、ばぁちゃん!」と叫び出した。
一体何事か。突然の大声に、バスの中にいる乗客の視線が白井に集中する。
「い、いま、あそこに、僕の祖母が歩いてたんです!」
「おばあさん?」
興奮している白井に、田嶋が聞いた。
「ええ、間違いないです!祖母も、私に気づいていたみたいですから!」
白井はそう言って、再度バスが通り過ぎた道を名残惜しそうに見つめ続けた。
「くそっ、せめてこの窓を開けられたら、声をかけられたのに…」
バスから飛び降り逃げ出すのを防ぐためだろうか。俺たちを乗せたバスに、開閉機能はついていない。白井は悔しそうに、その窓を叩いている。
その様子を見ながら「おばあさんが亡くなられたのは、いつ頃です?」と、田嶋。
「三年ほど前です。まさか、こんなところで再会できるなんて…」
「ばあちゃんは、死んですぐにこの街に来たんですかね…」と藪内が興味津々な様子で話に加わると、白井は「どういう意味です?」と、目線を外から藪内に向けなおした。
「いや、ちょっと気になったんです。死んでまっすぐ天国ゲートに行けたのか、それとも、地獄ゲートを通ったのか……。こうして景洛町の外に住んでるってことは、直接天国側に案内されたか、景洛町に連れてこられたあとに、何らかの方法で町を出たかのどちらかですよね。もし地獄ゲートを通っていたのなら、当然町を出る方法を知ってるはずだと思って……」
「う~ん。直接聞かないことには、それはわからないですよね。でも、君の言うとおり、もし祖母が地獄ゲートを通ったのなら、出方を知っていることになりますね。話が出来たらなぁ…。田嶋君、このバスを途中下車する方法なんかは……」
「あるわけないでしょう!」
…つづく。
 ←ヘンなんですよ。他のブログは「クリックにご協力ください」とか簡単な説明しか書いてないのに、ここは妙に情報が多いんです。
←ヘンなんですよ。他のブログは「クリックにご協力ください」とか簡単な説明しか書いてないのに、ここは妙に情報が多いんです。コメント ( 224 ) | Trackback ( )
極楽飯店.17
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
「いいですか。あの店には、絶対近寄っちゃいけません。…ま、どのみち皆さんが行ったところで、店に入れてもらえないですけどね」
田嶋が真剣なまなざしで説明する。
「あの人たちは、なんで血まみれで出てきたんですか?」と藪内。
「店のことを知らずに入ったからですよ…」
「どういうことだ?あの店で、一体何が起こってるっていうんだ」
坂本が出てくる客を目で追いながら聞く。
「殴られたんですよ」
「殴られた?……誰に?」
「鬼ですよ。今日の現場にもいたでしょ。あの店には、ビエルと同じような大男がいるんですよ。でも、現場と違ってあの店にいる鬼は穏やかじゃない。何かと難癖をつけては殴るんです。それも、バットみたいな棍棒で思いっきり」
「なんだそりゃ」坂本は、ワケがわからないという表情で顔を歪めている。
「あそこに行くぐらいなら、虫を食べてる方が幸せです」
「ちょ、ちょっと待て!『虫を食べる方が幸せ』って…。ってことは…、もしかしたら、あそこでは虫以外の料理が出るってことか?」
坂本が田嶋の一言にそう食いつくと、田嶋は「しまった」という顔をして話をそらそうとしたが、坂本が「待てよ、どうなんだ!あそこでは、まともな物が食えるんじゃないのか!?」と話を戻す。
「……知らない方がいいですよ」
「何か知ってるんだろ!言えよ!!」
坂本が田嶋の肩を小突いて叫ぶと、田嶋は渋々と話を続けた。
「そうですよ…。あそこは、この町で唯一まともな料理が出てくる店です。それも、とんでもなく旨そうな中華料理の数々が……」
「な、なんで早く言わねぇんだよ!」
坂本が怒りを露わにして田嶋を責めると、田嶋は顔を真っ赤にして「食えないからですよ!」と大声を上げて言い返す。
「そりゃ、凄い料理が出てきますよ。でも、それを食わせてはもらえないんです。見るだけしかできないんですよ!仕舞いにはズタボロに殴られて。それが、どんなに辛いことかわかりませんか!?」
田嶋は、声を荒げてそう言うと、一度「ふぅ」とため息をついて落ち着きを取り戻し、悲しそうな顔をして静かに語り出した。
「僕は…つい先日、あの店に行ったんです…」
「なんだって?」
「以前所属していた班のメンバーと一緒でした。噂を聞いたんです。『まともな料理が食える店があるらしい』って。それで、期待に胸を膨らませて、みんなで行ったんです。店の近くまで行くと、めちゃめちゃ旨そうな香りが漂ってて。もう、よだれが止まりませんでした。でも……。出された料理を食べようとしても、食べさせてもらえません。私語を慎めだの、テーブルマナーがなってないだのと、何かあるたび、客を囲う鬼に殴られるんです。それでも食べようとすれば、『食えるものなら食ってみろ』と、棍棒を口の中に押し込まれて……。結局、誰も料理を口にすることは出来ず、血まみれになって店を出ました。それが切っ掛けだったんです。僕以外のメンバーが景洛駅に向かったのは…」
「でも、見たところ、お前は無傷じゃないか」
俺がそう言うと、田嶋は「それは、僕がその状況を怖がって料理を口に出来なかったからです」と答えた。
「そ、それでも私は行くぞ。一口でもいい。何とかして食ってやる」
坂本が目を血走らせてそう言うと、田嶋は「無理ですよ」と鼻で笑った。
「あなたが行ったところで、店に入れてはもらえない」
「な、なんでだ。現に、さっき店から出てきたヤツがいたじゃないか!なんで私じゃダメなんだ!」
「あの店は、団体客しか入れてもらえないんですよ。一人で行っても、門前払いです」
「じゃぁ、一緒に行くヤツを募ればいい」
「だから、無理ですって」
「なんでだよ!」
「僕が行かないからですよ」
「あ?」
「そんなに知りたいなら、自分でしおりを見てみればいい」
「し、しおり?」
「ここに来たときに渡されたでしょ、『景洛町 生活のしおり』。部屋にあるはずですよ」
田嶋は「もうこの件に関しては、これ以上なにも話すつもりはありません」と言い残すと、ドタドタと足早に宿舎へ帰って行った。
…つづく。
 ←本日、一言オチが浮かびません…。こんな日もあるよね。
←本日、一言オチが浮かびません…。こんな日もあるよね。
********************************************
「いいですか。あの店には、絶対近寄っちゃいけません。…ま、どのみち皆さんが行ったところで、店に入れてもらえないですけどね」
田嶋が真剣なまなざしで説明する。
「あの人たちは、なんで血まみれで出てきたんですか?」と藪内。
「店のことを知らずに入ったからですよ…」
「どういうことだ?あの店で、一体何が起こってるっていうんだ」
坂本が出てくる客を目で追いながら聞く。
「殴られたんですよ」
「殴られた?……誰に?」
「鬼ですよ。今日の現場にもいたでしょ。あの店には、ビエルと同じような大男がいるんですよ。でも、現場と違ってあの店にいる鬼は穏やかじゃない。何かと難癖をつけては殴るんです。それも、バットみたいな棍棒で思いっきり」
「なんだそりゃ」坂本は、ワケがわからないという表情で顔を歪めている。
「あそこに行くぐらいなら、虫を食べてる方が幸せです」
「ちょ、ちょっと待て!『虫を食べる方が幸せ』って…。ってことは…、もしかしたら、あそこでは虫以外の料理が出るってことか?」
坂本が田嶋の一言にそう食いつくと、田嶋は「しまった」という顔をして話をそらそうとしたが、坂本が「待てよ、どうなんだ!あそこでは、まともな物が食えるんじゃないのか!?」と話を戻す。
「……知らない方がいいですよ」
「何か知ってるんだろ!言えよ!!」
坂本が田嶋の肩を小突いて叫ぶと、田嶋は渋々と話を続けた。
「そうですよ…。あそこは、この町で唯一まともな料理が出てくる店です。それも、とんでもなく旨そうな中華料理の数々が……」
「な、なんで早く言わねぇんだよ!」
坂本が怒りを露わにして田嶋を責めると、田嶋は顔を真っ赤にして「食えないからですよ!」と大声を上げて言い返す。
「そりゃ、凄い料理が出てきますよ。でも、それを食わせてはもらえないんです。見るだけしかできないんですよ!仕舞いにはズタボロに殴られて。それが、どんなに辛いことかわかりませんか!?」
田嶋は、声を荒げてそう言うと、一度「ふぅ」とため息をついて落ち着きを取り戻し、悲しそうな顔をして静かに語り出した。
「僕は…つい先日、あの店に行ったんです…」
「なんだって?」
「以前所属していた班のメンバーと一緒でした。噂を聞いたんです。『まともな料理が食える店があるらしい』って。それで、期待に胸を膨らませて、みんなで行ったんです。店の近くまで行くと、めちゃめちゃ旨そうな香りが漂ってて。もう、よだれが止まりませんでした。でも……。出された料理を食べようとしても、食べさせてもらえません。私語を慎めだの、テーブルマナーがなってないだのと、何かあるたび、客を囲う鬼に殴られるんです。それでも食べようとすれば、『食えるものなら食ってみろ』と、棍棒を口の中に押し込まれて……。結局、誰も料理を口にすることは出来ず、血まみれになって店を出ました。それが切っ掛けだったんです。僕以外のメンバーが景洛駅に向かったのは…」
「でも、見たところ、お前は無傷じゃないか」
俺がそう言うと、田嶋は「それは、僕がその状況を怖がって料理を口に出来なかったからです」と答えた。
「そ、それでも私は行くぞ。一口でもいい。何とかして食ってやる」
坂本が目を血走らせてそう言うと、田嶋は「無理ですよ」と鼻で笑った。
「あなたが行ったところで、店に入れてはもらえない」
「な、なんでだ。現に、さっき店から出てきたヤツがいたじゃないか!なんで私じゃダメなんだ!」
「あの店は、団体客しか入れてもらえないんですよ。一人で行っても、門前払いです」
「じゃぁ、一緒に行くヤツを募ればいい」
「だから、無理ですって」
「なんでだよ!」
「僕が行かないからですよ」
「あ?」
「そんなに知りたいなら、自分でしおりを見てみればいい」
「し、しおり?」
「ここに来たときに渡されたでしょ、『景洛町 生活のしおり』。部屋にあるはずですよ」
田嶋は「もうこの件に関しては、これ以上なにも話すつもりはありません」と言い残すと、ドタドタと足早に宿舎へ帰って行った。
…つづく。
 ←本日、一言オチが浮かびません…。こんな日もあるよね。
←本日、一言オチが浮かびません…。こんな日もあるよね。コメント ( 56 ) | Trackback ( )
極楽飯店.16
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
そんな会話が交わされている中、俺は昨日案内係と話した事を思い出していた。
たしか、俺がこれからずっとここで生活することになるのかと質問した時、女は「それはあなた次第だ」と答えていた。この町での生活は、宇宙の基本原理を学び直すための機会として機能している。その原理を理解さえすれば、自由になれると…。つまり、この町から出る方法は確実にあるはずだ。
そして、カウンターにいる男もまた「最低限の法則を知れ」と、同じような事を言っている。
宇宙の基本原理、最低限の法則…。
もしかしたら、謎の失踪をした者たちは、その何かを見つけたのかも知れない。この町を出る、何らかの方法を…。だとしたら、それはなんだ。
どうすれば地獄から抜け出せる?
考えようとしたが、猛烈な眠気のせいでうまく頭が回らない。答えを追い求めても、出てくるのはアクビばかりだった。
間近で聞こえる話し声も、「言葉」から徐々に「意味を持たない音」に変わり、さらなる眠気を誘う心地よいBGMとなっていく。
どれぐらいの間ウトウトしていたのだろう。ふと我に返ると、会話は終わり、カウンターにいた男が「したっけな」と一言残して店を出て行ったところだった。
影のある表情を浮かべているメンバーの様子からすると、その後の会話でも、特に大きな収穫は得られなかったように見える。藪内の目には、またもやうっすらと涙がにじんでいた。
「僕たちも、そろそろ帰りましょう」田嶋の一言を合図に、皆で店を出る。
何を話すわけでもなく、すっかり日の落ちた町を淡々と歩く。街灯が灯る町並みは、往路とは別な道の様に見えた。
何時間あの店にいたのだろうか。町は人通りも少なくなり、ひっそりとした静けさに包まれていた。鉄の芯が入った重い安全靴から聞こえるコツコツという足音と、光に集まる虫たちが街灯にぶつかるバチバチという音が、やけに耳に残る。
街灯を見上げて、あの虫たちも旨そうに見える日がくるのだろうかと考えていたら、ウッとゲップが上がり鼻の奥から虫籠の臭いがした。
坂本じゃないが、やはり、まともな物が食いたい。
そう思っていた矢先、その坂本が通りの向こうを指差し話し出した。
「田嶋ぁ、明日はあの店に行こうや!」
坂本が示すその先には、暗がりに煌々と光る電飾看板があった。チカチカと点滅する電球に囲まれた「極楽飯店」の文字が見える。
「極楽飯店だとよ。『地獄のゲテモノレストラン』より、あっちの方が旨そうな名前じゃねぇか!なぁ!!」
そう坂本が雄叫びを上げると、白井と藪内もウンウンと力強く頷いたが、田嶋は顔を真っ青にして拒絶している。
「ダ、ダメですよ!あそこは絶対ダメです!!」
「なんでだよぅ」と、坂本が眉間に皺をよせて言う。
「ダメなものはダメです!」
「だから、なんでだよぅ」
田嶋は、アウアウと言葉にならない声を上げて首を横に振るばかりだ。
「なんだよ。そんなに不味いのか?」
坂本がしつこく聞き続けると、田嶋は「論外です」と答える。
「論外?なんだ、虫よりひでぇもんでも出てくるのか」
「そうじゃないんです…」
「じゃぁ、何だって言うんだ?」
坂本が口を尖らせていると、田嶋は「ほら、だから、あれ…」と、ヘンな顔をして店を指差す。
皆が振り返り、店を確認し直すと、血みどろの客が出て来るのが見えた。
「なんだぁ!?」
「ああいうことなんですよ。あの店に行っても、メシなんて食べさせてもらえません」
「ど、どういうことだ?」
「僕が前に所属していたチームのメンバーが景洛駅に行ったのは、あの店に入ったのが原因なんです。この町で、唯一地獄らしい地獄が、あの店なんですよ……。近寄っちゃ…ダメです」
「地獄らしい地獄?」
…つづく。
 ←近寄ってくれなくちゃ…
←近寄ってくれなくちゃ…
********************************************
そんな会話が交わされている中、俺は昨日案内係と話した事を思い出していた。
たしか、俺がこれからずっとここで生活することになるのかと質問した時、女は「それはあなた次第だ」と答えていた。この町での生活は、宇宙の基本原理を学び直すための機会として機能している。その原理を理解さえすれば、自由になれると…。つまり、この町から出る方法は確実にあるはずだ。
そして、カウンターにいる男もまた「最低限の法則を知れ」と、同じような事を言っている。
宇宙の基本原理、最低限の法則…。
もしかしたら、謎の失踪をした者たちは、その何かを見つけたのかも知れない。この町を出る、何らかの方法を…。だとしたら、それはなんだ。
どうすれば地獄から抜け出せる?
考えようとしたが、猛烈な眠気のせいでうまく頭が回らない。答えを追い求めても、出てくるのはアクビばかりだった。
間近で聞こえる話し声も、「言葉」から徐々に「意味を持たない音」に変わり、さらなる眠気を誘う心地よいBGMとなっていく。
どれぐらいの間ウトウトしていたのだろう。ふと我に返ると、会話は終わり、カウンターにいた男が「したっけな」と一言残して店を出て行ったところだった。
影のある表情を浮かべているメンバーの様子からすると、その後の会話でも、特に大きな収穫は得られなかったように見える。藪内の目には、またもやうっすらと涙がにじんでいた。
「僕たちも、そろそろ帰りましょう」田嶋の一言を合図に、皆で店を出る。
何を話すわけでもなく、すっかり日の落ちた町を淡々と歩く。街灯が灯る町並みは、往路とは別な道の様に見えた。
何時間あの店にいたのだろうか。町は人通りも少なくなり、ひっそりとした静けさに包まれていた。鉄の芯が入った重い安全靴から聞こえるコツコツという足音と、光に集まる虫たちが街灯にぶつかるバチバチという音が、やけに耳に残る。
街灯を見上げて、あの虫たちも旨そうに見える日がくるのだろうかと考えていたら、ウッとゲップが上がり鼻の奥から虫籠の臭いがした。
坂本じゃないが、やはり、まともな物が食いたい。
そう思っていた矢先、その坂本が通りの向こうを指差し話し出した。
「田嶋ぁ、明日はあの店に行こうや!」
坂本が示すその先には、暗がりに煌々と光る電飾看板があった。チカチカと点滅する電球に囲まれた「極楽飯店」の文字が見える。
「極楽飯店だとよ。『地獄のゲテモノレストラン』より、あっちの方が旨そうな名前じゃねぇか!なぁ!!」
そう坂本が雄叫びを上げると、白井と藪内もウンウンと力強く頷いたが、田嶋は顔を真っ青にして拒絶している。
「ダ、ダメですよ!あそこは絶対ダメです!!」
「なんでだよぅ」と、坂本が眉間に皺をよせて言う。
「ダメなものはダメです!」
「だから、なんでだよぅ」
田嶋は、アウアウと言葉にならない声を上げて首を横に振るばかりだ。
「なんだよ。そんなに不味いのか?」
坂本がしつこく聞き続けると、田嶋は「論外です」と答える。
「論外?なんだ、虫よりひでぇもんでも出てくるのか」
「そうじゃないんです…」
「じゃぁ、何だって言うんだ?」
坂本が口を尖らせていると、田嶋は「ほら、だから、あれ…」と、ヘンな顔をして店を指差す。
皆が振り返り、店を確認し直すと、血みどろの客が出て来るのが見えた。
「なんだぁ!?」
「ああいうことなんですよ。あの店に行っても、メシなんて食べさせてもらえません」
「ど、どういうことだ?」
「僕が前に所属していたチームのメンバーが景洛駅に行ったのは、あの店に入ったのが原因なんです。この町で、唯一地獄らしい地獄が、あの店なんですよ……。近寄っちゃ…ダメです」
「地獄らしい地獄?」
…つづく。
 ←近寄ってくれなくちゃ…
←近寄ってくれなくちゃ…コメント ( 106 ) | Trackback ( )
極楽飯店.15
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
メシを食い終わると、場は田嶋への質問ラッシュとなった。
生活のこと、町のこと、この世界のこと。あらゆる疑問や不安が、次々と田嶋に投げかけられる。
坂本の質問内容は、現場で支給される弁当や景洛町にある飲食店のことなど、相変わらず食い物の事ばかりだ。
俺は、酒やたばこの事などを聞いてみたが、ここにはどちらも存在しないから諦めろと言われた。
田嶋は、新たな質問を受けるたびに面倒くさそうな素振りをみせていたが、口元が揺るんでいるところをみると、まんざらでもなさそうだ。すっかり先輩気取りでそれぞれの質問に答えている。
が、田嶋の流暢な説明も、藪内からの「景洛駅以外から、この町を出ることはできますか?」という質問で途切れた。
「わかりません」
田嶋がそう答え数秒の沈黙が生まれたところに、カウンターに座っていた一人の客が話しに割り込んできたのだ。
「出方がわかってれば、ここにはいねぇべさ」
皆がカウンターに目を向けると、赤いつなぎを着た男が、回転式の椅子をくるりと回して俺たちの方を向き、訛りのきついイントネーションで話を続けた。
「あんたらは、いつここさ来た?」
「昨日です。あ、この人は三週間ほど前から…」と、藪内が田嶋を指差しながら答える。
「やっぱり新人さんかい。なに、兄ちゃん、ここから出たいってか」
藪内が無言で頷くと、カウンター席の男は満面の笑みを浮かべながら藪内に言った。
「大丈夫だ、なんも心配することね。メシだって、すぐ慣れるってばよ。何の不自由もねぇもの、ここも、天国みたいなもんだ。そんな毛嫌いしてねぇで、受け入れてみれや。ここでの暮らしもいいもんだって」
「いや、そういうことじゃ…」
「なに?おめ、そんなに虫きらいか?すったらこだわり、さっさと捨ててまえって。わかってねぇなぁ。そやって自分の常識に縛られてっから苦しむんだべや。『メシはこうあるべき』って決めつけてんのは、自分だべ?自分でそやって目の前の状況ば拒絶してるから、いつまで経っても苦しいんだべや。そりゃよ、他に選択の余地があるってんならいいけどよ、そうでねぇもの。どうにもなんねぇもの。したら、受け入れてまうしかねぇべ。状況が変えられねぇんなら、自分の常識捨てる方が楽だべよ」
「いや、だから、そうじゃないんですって。ここでのメシがどうとか、生活がどうとか、そういうことじゃなくて…。俺、残してきた家族のこととか、そういうことが気になってるから…」
「気にしたとこでどうすんのよ。兄ちゃんが墓場から生き返れるわけじゃなし。どうにもなんねぇべや。それによ、ちょっと待っときゃその家族だって、いずれここさ来るんだから。死なねぇヤツなんておらんもの。んだべ?」
「いや、そう言われればそうかもしれないですけど。でも……」
藪内がそう言うと、カウンターの男は何かを思い出したような顔をしてこう続けた。
「あぁ、あれか。兄ちゃん、守護霊になりてぇとか、そういう類のあれか」
「守護霊?」
「んだ。あれでねぇの?案内のヤツに『見守る存在になれ』とか、そういうのば聞かされたんでねの?」
「そ、そう!それです!」
すると男は腕を組み、「むぅ」と唸った。
「んだどもなぁ…」
「おじさん、知ってるんですか?どうすれば守護霊になれるんすか?」
「いや、それが、誰も知らなんだよ」
「え?」
「あいつらな、そう言って『見守る存在になれ』とか『景洛町を出ろ』とか、しょっちゅうそう言う割には、その方法は一切しゃべらねぇんだわ。なんぼ教えれっても、『最低限の法則を知りなさい』って言うばかりでな」
「なんですか、最低限の法則って」
「だから、それがわからねぇのよ。教えられるもんでねぇってんだもの。なんぼ聞いても、『自分で気づいてください』つってな。冷てぇもんよ」
それを聞いた藪内は、しょぼんと肩を落として下を向いた。
「あなたは、いつからここに?」と、白井が聞く。
「ん?オレか?オレは…どうだべ…かれこれ二十年ぐらいだべか」
「二十年!?そ、そんなに長く…」
「なんも、オレなんて長い方でねぇよ。なんでだか、ここでは歳もとらねぇし、寿命もねぇからな。長いヤツは、もっと長い。ただ、あんまり長くいるとさすがに飽きてきてな、別に不自由はねぇんだけども、苦労を承知で駅に行っちまうヤツも出るんだわ。だから、何百年もここにいるってヤツには会ったことねぇな」
藪内が「長くいても、ここから出られないんですね…」と、ぼそりとつぶやき落胆していると、その様子を見た白井が代わりに聞いた。
「あなたがここに来てから、駅以外からこの町を出た人はいませんか?」
「いや、聞いた事ねぇ。ただ…」
「ただ?」
「ある日突然、行方不明になるヤツはちょくちょく出るんだわ」
「行方不明?」
「んだ。何度か、ある日突然現場に現れなくなる班がいてな。最初は担当の現場が変わったのかと思ってたんだども、それっきり、町でも宿舎でも見かけることがなくなったんだ。景洛駅に行ったとこを見た者もいねぇし、不思議なんだよな。あぁ、そういえば…、大抵は兄ちゃんみたいに、ここを出たがってたヤツらだな」
…つづく。
 ←ある日突然、ボタン押さなくなるヤツもちょくちょく出るんだわ。
←ある日突然、ボタン押さなくなるヤツもちょくちょく出るんだわ。
********************************************
メシを食い終わると、場は田嶋への質問ラッシュとなった。
生活のこと、町のこと、この世界のこと。あらゆる疑問や不安が、次々と田嶋に投げかけられる。
坂本の質問内容は、現場で支給される弁当や景洛町にある飲食店のことなど、相変わらず食い物の事ばかりだ。
俺は、酒やたばこの事などを聞いてみたが、ここにはどちらも存在しないから諦めろと言われた。
田嶋は、新たな質問を受けるたびに面倒くさそうな素振りをみせていたが、口元が揺るんでいるところをみると、まんざらでもなさそうだ。すっかり先輩気取りでそれぞれの質問に答えている。
が、田嶋の流暢な説明も、藪内からの「景洛駅以外から、この町を出ることはできますか?」という質問で途切れた。
「わかりません」
田嶋がそう答え数秒の沈黙が生まれたところに、カウンターに座っていた一人の客が話しに割り込んできたのだ。
「出方がわかってれば、ここにはいねぇべさ」
皆がカウンターに目を向けると、赤いつなぎを着た男が、回転式の椅子をくるりと回して俺たちの方を向き、訛りのきついイントネーションで話を続けた。
「あんたらは、いつここさ来た?」
「昨日です。あ、この人は三週間ほど前から…」と、藪内が田嶋を指差しながら答える。
「やっぱり新人さんかい。なに、兄ちゃん、ここから出たいってか」
藪内が無言で頷くと、カウンター席の男は満面の笑みを浮かべながら藪内に言った。
「大丈夫だ、なんも心配することね。メシだって、すぐ慣れるってばよ。何の不自由もねぇもの、ここも、天国みたいなもんだ。そんな毛嫌いしてねぇで、受け入れてみれや。ここでの暮らしもいいもんだって」
「いや、そういうことじゃ…」
「なに?おめ、そんなに虫きらいか?すったらこだわり、さっさと捨ててまえって。わかってねぇなぁ。そやって自分の常識に縛られてっから苦しむんだべや。『メシはこうあるべき』って決めつけてんのは、自分だべ?自分でそやって目の前の状況ば拒絶してるから、いつまで経っても苦しいんだべや。そりゃよ、他に選択の余地があるってんならいいけどよ、そうでねぇもの。どうにもなんねぇもの。したら、受け入れてまうしかねぇべ。状況が変えられねぇんなら、自分の常識捨てる方が楽だべよ」
「いや、だから、そうじゃないんですって。ここでのメシがどうとか、生活がどうとか、そういうことじゃなくて…。俺、残してきた家族のこととか、そういうことが気になってるから…」
「気にしたとこでどうすんのよ。兄ちゃんが墓場から生き返れるわけじゃなし。どうにもなんねぇべや。それによ、ちょっと待っときゃその家族だって、いずれここさ来るんだから。死なねぇヤツなんておらんもの。んだべ?」
「いや、そう言われればそうかもしれないですけど。でも……」
藪内がそう言うと、カウンターの男は何かを思い出したような顔をしてこう続けた。
「あぁ、あれか。兄ちゃん、守護霊になりてぇとか、そういう類のあれか」
「守護霊?」
「んだ。あれでねぇの?案内のヤツに『見守る存在になれ』とか、そういうのば聞かされたんでねの?」
「そ、そう!それです!」
すると男は腕を組み、「むぅ」と唸った。
「んだどもなぁ…」
「おじさん、知ってるんですか?どうすれば守護霊になれるんすか?」
「いや、それが、誰も知らなんだよ」
「え?」
「あいつらな、そう言って『見守る存在になれ』とか『景洛町を出ろ』とか、しょっちゅうそう言う割には、その方法は一切しゃべらねぇんだわ。なんぼ教えれっても、『最低限の法則を知りなさい』って言うばかりでな」
「なんですか、最低限の法則って」
「だから、それがわからねぇのよ。教えられるもんでねぇってんだもの。なんぼ聞いても、『自分で気づいてください』つってな。冷てぇもんよ」
それを聞いた藪内は、しょぼんと肩を落として下を向いた。
「あなたは、いつからここに?」と、白井が聞く。
「ん?オレか?オレは…どうだべ…かれこれ二十年ぐらいだべか」
「二十年!?そ、そんなに長く…」
「なんも、オレなんて長い方でねぇよ。なんでだか、ここでは歳もとらねぇし、寿命もねぇからな。長いヤツは、もっと長い。ただ、あんまり長くいるとさすがに飽きてきてな、別に不自由はねぇんだけども、苦労を承知で駅に行っちまうヤツも出るんだわ。だから、何百年もここにいるってヤツには会ったことねぇな」
藪内が「長くいても、ここから出られないんですね…」と、ぼそりとつぶやき落胆していると、その様子を見た白井が代わりに聞いた。
「あなたがここに来てから、駅以外からこの町を出た人はいませんか?」
「いや、聞いた事ねぇ。ただ…」
「ただ?」
「ある日突然、行方不明になるヤツはちょくちょく出るんだわ」
「行方不明?」
「んだ。何度か、ある日突然現場に現れなくなる班がいてな。最初は担当の現場が変わったのかと思ってたんだども、それっきり、町でも宿舎でも見かけることがなくなったんだ。景洛駅に行ったとこを見た者もいねぇし、不思議なんだよな。あぁ、そういえば…、大抵は兄ちゃんみたいに、ここを出たがってたヤツらだな」
…つづく。
 ←ある日突然、ボタン押さなくなるヤツもちょくちょく出るんだわ。
←ある日突然、ボタン押さなくなるヤツもちょくちょく出るんだわ。コメント ( 132 ) | Trackback ( )
極楽飯店.14
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
俺と藪内が、文字通り出口の見えない会話を続けているうちに、バスは景洛町の宿舎へ到着した。
メンバーがバスから出ると、田嶋が振り返りながら「夕食は、どうしますか?」と改めて聞いてくる。
坂本が「本当に、虫以外の、まともなものを食わせてくれるところはないのか」と聞き返すと、田嶋はしばし考え込んだ後、やっぱりやめたといった表情を浮かべて顔を振り、「知らない方が身のためです」と、小さな声で答えた。
意味深な返答に、坂本が食いついた。
「そりゃ、ど、ど、どういう意味だ?」
腹が減っているせいだろうか、坂本の口調には苛立ちめいたものがあった。
唾を飛ばしながらにじり寄る坂本に、田嶋がうろたえている。
「お、落ち着いてくださいよ。少しは食べやすいところを紹介しますから」
「食べやすいところ?」
「ここでの暮らしを続けるつもりなら、食事に慣れないと。抵抗があるのはわかりますが、選択の余地が無い以上、ここの食文化に慣れるしかないじゃないですか。……食いたくないなら、無理にすすめませんよ」
そんなやりとりの最中も、皆の腹は「グゥ」と鳴り続けている。
「とにかく、田嶋さんに連れってってもらいましょうよ。俺ら、どんな店があるのかも知らないんすから」
藪内がそう言うと、田嶋はニヤリと気持ちの悪い笑みを浮かべて「じゃ、行きましょう」と町中に向けて歩きだした。
その後を、四人の男がしぶしぶとついて行く。結局、宿舎に戻る者はいなかった。釈然としないが、今の状況を考えると、田嶋について行くか、景洛駅に向かうか、それとも、このまま腹を空かせたままでいるかしかないのだ。
その店は、宿舎から歩いて五分ほどのところにあった。
田嶋が「あそこです」と指差す洒落た洋食店風のその店には「RISTORANTE HELL GETEMORNO」と書かれた赤い看板が掲げられている。
「リストランテ、ヘル、…ゲテモーノ?」
白井がそう音読すると、藪内が「藤子不二雄のマンガみたいだ」と苦笑いを浮かべた。
確かにふざけた名前だ。シェフがオオカミ男だったら、拍手を送ろう。
田嶋が店のドアに手を添えながら「ここのパスタなら、まだ食べられるかもしれません。何も聞かずに、僕の注文する品を食べてもらえますか?」と、皆に確認した。
「どういうことだ?」
坂本がそう聞くと、田嶋は「メニューを見ても、それがどんな料理かなんて分からないですから。それに…、先に何を食べるのかを知っちゃったら、また食べづらくなりますよ」
田嶋の言葉を受けた俺たちは、互いの顔を見合わせた後に、無言で頷いた。
田嶋に続いて、恐る恐るドアを通る。喫茶店とファミレスの間ぐらいの広さだろうか。ふざけた店名とは不釣り合いの、カジュアルな雰囲気が漂う小洒落た内装の店だった。入ってすぐにカウンターがあり、既に何名かの客が席に着いていた。料理の様子を知りたかったが、幸か不幸か、テーブルの上には、まだ料理はあがっていない。
店の奥にあるボックス席に着くと、田嶋はメニューも見ずに「ルンブルクス・ルベルスのフリッター添えを五人分」と注文する。
ウエイターが恭しく頭を下げて厨房へ消えると、田嶋はへへへと笑いながら「いいですか。イメージトレーニングですよ。これから、エビの素揚げが添えられたトマトソーススパゲティが来ると思っていてください」と言う。
その言葉に、坂本が目をむきだして喜んでいる。
「エ、エビ!エビのスパゲティが食えるのか!」
「だから、イメージトレーニングって言ってるじゃないですか。過度な期待は持たないでくださいよ」と、田嶋が諭す。
そんな、不毛なやりとりを聞いているうちに、人数分の料理が運ばれてきた。
白い大きな皿の中央に、ふんわりした湯気をまとった赤いパスタが盛られている。その上には…
「どこがエビだよ…。バッタの素揚げじゃねえか」と、坂本が肩を落とす。
「ですから、エビのつもりで。ほら、イメージを膨らませればエビに…」
「見えねえよ」
坂本は拗ねた子供の様に椅子の背に身体を預け、プイと横を向いて口をとがらせている。
「でも…」お構いなしでメシを頬張る田嶋が続けた。
「モグモグ…、考えてみればヘンだと思いません?」
「何がですか?」と、藪内がちょんちょんとバッタをフォークでつっつきながら聞く。
「だって…モグモグ、思いませんか?なんで、エビは『旨そう』って思えるのに…モグモグ、バッタだと抵抗があるんだろうって…、ゴクッ…。エビの素揚げだって、よくよく見たら、虫っぽいとこ、ありますでしょ。足、いっぱい生えてるし。触覚もあるし。なんでエビは食べられるのに、バッタだと食べられないんですかね。どうして、シャコはOKで、セミはNGなんですかね。ここに来て色々食べてるうちに、わからなくなってきたんですよ。あはははは。ほら、これだって食ってみれば、案外いけますって」
田嶋はそういうとバッタをフォークで刺し、おもむろに口元に運ぶと、サクサクとわざとらしく音を立てて食べて見せる。
すると、藪内が「俺…いってみます」といって目をつぶり、勢いよくバッタを口に運んだ。
サクサクと音を立ててバッタを噛む藪内を、じっと見つめながら白井が聞いた。
「ど、どうですか?」
モグモグ…、ゴクン。藪内は力強く喉仏を上下させてバッタを飲み込むと「い、意外ですが…。うまいっす…。バッタも、食えるんですね」と、微妙な表情で笑って見せた。
それを見た坂本が、グッと目をつぶり、皿の上のものをエイと頬張り、俺と白井がそれに続く。無言の内に、結局全員が全てを平らげた。
完食した俺たちを見届けた田嶋が「いかがでしたか?」と尋ねると、白井が「バッタはいいとして…。麺は…、スパゲティ、パスタ、では、なかったですよね…」とぼそりと答えた。
田嶋以外の面々が、顔を見合わせて無言で頷く。分かってはいたが、食べ終わるまで口には出すまいと思っていたのだろう。あの頼りない歯ごたえは、パスタではない。たぶん…
「あれ…、ミミズ…ですよね?」
白井がそう言うと、田嶋はニヤリと笑い、メニューをおもむろに開くと「ルンブルクス・ルベルス」はミミズの品種名だと話し出した。ミミズに品種まであるとは知らなかったが、やはり皆、食べながらミミズであることにはうすうす気づいていたらしい。
バッタやミミズを食した後だったが、不思議なことに、そのことは大したことではなくなっていた。
それよりも、いま食べていたものが何なのかに気づいていたにも関わらず、皆が食べ終わるまでは話さずにおこうという、暗黙の了解が生まれていたことに、連帯感にも似た、妙な嬉しさを感じていた。
…つづく。
 ←長らくのお休み、失礼いたしました。
←長らくのお休み、失礼いたしました。
********************************************
俺と藪内が、文字通り出口の見えない会話を続けているうちに、バスは景洛町の宿舎へ到着した。
メンバーがバスから出ると、田嶋が振り返りながら「夕食は、どうしますか?」と改めて聞いてくる。
坂本が「本当に、虫以外の、まともなものを食わせてくれるところはないのか」と聞き返すと、田嶋はしばし考え込んだ後、やっぱりやめたといった表情を浮かべて顔を振り、「知らない方が身のためです」と、小さな声で答えた。
意味深な返答に、坂本が食いついた。
「そりゃ、ど、ど、どういう意味だ?」
腹が減っているせいだろうか、坂本の口調には苛立ちめいたものがあった。
唾を飛ばしながらにじり寄る坂本に、田嶋がうろたえている。
「お、落ち着いてくださいよ。少しは食べやすいところを紹介しますから」
「食べやすいところ?」
「ここでの暮らしを続けるつもりなら、食事に慣れないと。抵抗があるのはわかりますが、選択の余地が無い以上、ここの食文化に慣れるしかないじゃないですか。……食いたくないなら、無理にすすめませんよ」
そんなやりとりの最中も、皆の腹は「グゥ」と鳴り続けている。
「とにかく、田嶋さんに連れってってもらいましょうよ。俺ら、どんな店があるのかも知らないんすから」
藪内がそう言うと、田嶋はニヤリと気持ちの悪い笑みを浮かべて「じゃ、行きましょう」と町中に向けて歩きだした。
その後を、四人の男がしぶしぶとついて行く。結局、宿舎に戻る者はいなかった。釈然としないが、今の状況を考えると、田嶋について行くか、景洛駅に向かうか、それとも、このまま腹を空かせたままでいるかしかないのだ。
その店は、宿舎から歩いて五分ほどのところにあった。
田嶋が「あそこです」と指差す洒落た洋食店風のその店には「RISTORANTE HELL GETEMORNO」と書かれた赤い看板が掲げられている。
「リストランテ、ヘル、…ゲテモーノ?」
白井がそう音読すると、藪内が「藤子不二雄のマンガみたいだ」と苦笑いを浮かべた。
確かにふざけた名前だ。シェフがオオカミ男だったら、拍手を送ろう。
田嶋が店のドアに手を添えながら「ここのパスタなら、まだ食べられるかもしれません。何も聞かずに、僕の注文する品を食べてもらえますか?」と、皆に確認した。
「どういうことだ?」
坂本がそう聞くと、田嶋は「メニューを見ても、それがどんな料理かなんて分からないですから。それに…、先に何を食べるのかを知っちゃったら、また食べづらくなりますよ」
田嶋の言葉を受けた俺たちは、互いの顔を見合わせた後に、無言で頷いた。
田嶋に続いて、恐る恐るドアを通る。喫茶店とファミレスの間ぐらいの広さだろうか。ふざけた店名とは不釣り合いの、カジュアルな雰囲気が漂う小洒落た内装の店だった。入ってすぐにカウンターがあり、既に何名かの客が席に着いていた。料理の様子を知りたかったが、幸か不幸か、テーブルの上には、まだ料理はあがっていない。
店の奥にあるボックス席に着くと、田嶋はメニューも見ずに「ルンブルクス・ルベルスのフリッター添えを五人分」と注文する。
ウエイターが恭しく頭を下げて厨房へ消えると、田嶋はへへへと笑いながら「いいですか。イメージトレーニングですよ。これから、エビの素揚げが添えられたトマトソーススパゲティが来ると思っていてください」と言う。
その言葉に、坂本が目をむきだして喜んでいる。
「エ、エビ!エビのスパゲティが食えるのか!」
「だから、イメージトレーニングって言ってるじゃないですか。過度な期待は持たないでくださいよ」と、田嶋が諭す。
そんな、不毛なやりとりを聞いているうちに、人数分の料理が運ばれてきた。
白い大きな皿の中央に、ふんわりした湯気をまとった赤いパスタが盛られている。その上には…
「どこがエビだよ…。バッタの素揚げじゃねえか」と、坂本が肩を落とす。
「ですから、エビのつもりで。ほら、イメージを膨らませればエビに…」
「見えねえよ」
坂本は拗ねた子供の様に椅子の背に身体を預け、プイと横を向いて口をとがらせている。
「でも…」お構いなしでメシを頬張る田嶋が続けた。
「モグモグ…、考えてみればヘンだと思いません?」
「何がですか?」と、藪内がちょんちょんとバッタをフォークでつっつきながら聞く。
「だって…モグモグ、思いませんか?なんで、エビは『旨そう』って思えるのに…モグモグ、バッタだと抵抗があるんだろうって…、ゴクッ…。エビの素揚げだって、よくよく見たら、虫っぽいとこ、ありますでしょ。足、いっぱい生えてるし。触覚もあるし。なんでエビは食べられるのに、バッタだと食べられないんですかね。どうして、シャコはOKで、セミはNGなんですかね。ここに来て色々食べてるうちに、わからなくなってきたんですよ。あはははは。ほら、これだって食ってみれば、案外いけますって」
田嶋はそういうとバッタをフォークで刺し、おもむろに口元に運ぶと、サクサクとわざとらしく音を立てて食べて見せる。
すると、藪内が「俺…いってみます」といって目をつぶり、勢いよくバッタを口に運んだ。
サクサクと音を立ててバッタを噛む藪内を、じっと見つめながら白井が聞いた。
「ど、どうですか?」
モグモグ…、ゴクン。藪内は力強く喉仏を上下させてバッタを飲み込むと「い、意外ですが…。うまいっす…。バッタも、食えるんですね」と、微妙な表情で笑って見せた。
それを見た坂本が、グッと目をつぶり、皿の上のものをエイと頬張り、俺と白井がそれに続く。無言の内に、結局全員が全てを平らげた。
完食した俺たちを見届けた田嶋が「いかがでしたか?」と尋ねると、白井が「バッタはいいとして…。麺は…、スパゲティ、パスタ、では、なかったですよね…」とぼそりと答えた。
田嶋以外の面々が、顔を見合わせて無言で頷く。分かってはいたが、食べ終わるまで口には出すまいと思っていたのだろう。あの頼りない歯ごたえは、パスタではない。たぶん…
「あれ…、ミミズ…ですよね?」
白井がそう言うと、田嶋はニヤリと笑い、メニューをおもむろに開くと「ルンブルクス・ルベルス」はミミズの品種名だと話し出した。ミミズに品種まであるとは知らなかったが、やはり皆、食べながらミミズであることにはうすうす気づいていたらしい。
バッタやミミズを食した後だったが、不思議なことに、そのことは大したことではなくなっていた。
それよりも、いま食べていたものが何なのかに気づいていたにも関わらず、皆が食べ終わるまでは話さずにおこうという、暗黙の了解が生まれていたことに、連帯感にも似た、妙な嬉しさを感じていた。
…つづく。
 ←長らくのお休み、失礼いたしました。
←長らくのお休み、失礼いたしました。コメント ( 89 ) | Trackback ( )
| « 前ページ |