人に好かれる方法(職場編)
→笑いの効果 →人に好かれる方法(基本編) →人に好かれる方法(恋愛編)
●高いプライドを捨て一流のビジネスマンになる!
●人に話しを聞かせる方法とは!?
●上手に部下を動かす方法! ●「はい」「いいえ」をはっきり伝え信頼関係を築こう!
●活字の使い方をマスターしよう!
高いプライドを捨て一流のビジネスマンになる!
まず最初にいっておくと、高すぎるプライドは人間的魅力を下げるということです。社会人になり多くの仕事をこなしていくと、出世していきます。すると自分に大きな自信がつき、高いプライドを持つようになる人も少なくありません。しかし、自分の仕事にプライドを持つのは大切ですが、不必要に天狗になってはいけません。
※1
そういう人は、分かりにくい専門用語や外国語をあえて見栄をはって使う傾向があります。自分の知識をひけらかすような話し方をして相手に不快感を与えている可能性が高いので、充分注意したほうがいいでしょう。
仮に内容が分かりにくい可能性が少しでもある場合は、事前に簡単な説明を入れてあげれば、嫌味のないスマートな会話ができますよ!(^_^)
高いプライドを持っている人は、一見、自信満々にも思えますが、実は自分に本当の自信がないために、そういった態度で武装しなければ落ち着けない人なのです。(自分では自覚していない場合がほとんどですが…(^_^;))
「自分は人よりできる存在でなくてはいけない」
「人前で失敗はできない」
…そういったプライドが膨らんでくると、いわゆる完璧主義な人間になってきます。そのような人は、自分で自分の行動は完璧と思い込んでいるため、自分の考えにそぐわない他人の行動は、ちょっとしたことでも許せなく思います。他人が失敗したりすると「自分はこんなに一生懸命やっているのに、何であいつは失敗するんだ!」と、すぐに怒りだしたりする人です。(^_^;)
(完璧主義でなくても同じ会社に長く勤めていると、誰でもそのような傾向がでてくるので注意!)
また「他人に無様な姿を見せられない」と思うあまり、失敗することに対して恐れを抱くようになります。そのため、必要以上にプレッシャーを感じてしまい、結果的に余計に失敗します。このように完璧主義とは、余計なことで気を遣い、ストレスを溜め、人間関係をも崩していくものなのです。
誰でも、天狗になっている人間を認めようとはしません。本人は自分の素晴らしさを必死でアピールしますが、いえばいうほど周りは白けてくるのです。周りから認められないと、人は無意識に不安を感じるため、それを解消するために余計に自慢話が多くなるという悪循環に陥ります。そして、権威のある人の話などを持ちだしてきては、「自分の考えは先生方もいっているから間違いない!」と、他人の受け売りで話をするようになるのです。(※1)
完璧主義な人は「何事も真面目に一生懸命こなし、人に弱いところも見せず、すべて自分一人でやりとげる」という、スキのない行動をとります。一見、素晴らしい行動にも思えますが、どうしてそれがいけないのでしょうか?
それは、そのような行動は周りから見れば心にゆとりのない行動であり、一緒にいて非常に窮屈に感じてしまうのです。悪くいえば、工場で動くロボットのような感じで、人間味を感じられないのです。まして、その完璧さを周りの人にも求めるとなると、なおさらです。(そのような人は心にゆとりがないため、忙しくなってくると人に八つ当たりをしがちです(^_^;))
そのため、実際はそうでなくても「冷たい人」「接しにくい人」といったイメージがつきやすく、人間関係は悪い方向へ向かっていきます。考えてみれば、実際にそんな人と一緒にいても、少しも楽しくないことは容易に想像できます。仮にそれが上司なら、部下はいいたいこともいえず、ギクシャクした関係しか築けないことは目に見えています。なぜなら、部下の気持ちを理解できない人間が、部下を効率良く動かせるわけがないからです。(重要!)
人間誰でも固いイメージの人には近付きがたいもので、むしろどこか失敗したり、ちょっと間抜けなところがある人の方が接しやすいのです。弱い部分、悪い部分であっても、それを人前にさらけだして始めて相手も安心して心を開けるのです。弱い部分を見せることは、決して恥じることではありません。どんなに虚勢をはっていても、落ち込んだり、悲しんだりすることは人間である以上、誰でもあるのです。そういった部分を素直にだせる人には誰でも親近感が湧き、「何とか力になりたい!」という気持ちがでてくるものです。
今の時代、仕事ができるだけでは一流のビジネスマンとはいえません!一流のビジネスマンには、何よりコミュニケーションスキルが必要なのです。近年になってようやく「コミュニケーションスキルを高めよう!」という動きもでてきていますが、それでもまだまだ多くの会社では昔ながらのやり方であるのが現状です。(私もそういう会社をいくつか経験してますが、本当にストレス溜まります。(笑))
部下に信頼され、仕事もプライベートも本気で頼られる。あなたも、そんな理想の上司になってみてはいかがでしょうか。
人に話しを聞かせる方法とは!?
会話には、常に「話す側」と「聞く側」が存在しています。しかし、聞く側が内心でそれを拒否している場合、つまり「聞く耳を持たない」状態になっていては、少なくともコミュニケーションが成立しているとはいえません。
具体的に説明しましょう。次のような状況を想像して下さい…。
あなたは職場の仲間に色々と自分の意見を熱心に述べています。しかし、あなたはいわゆる「真面目一本」というような性格で、何かというと真面目な堅い話しかしません。(そうではなくても「必要以上に細かいことをいう…」など、仕事にうるさい状況なら何でも可) しかし、いっていることは正しいのですが、毎回そんな話ばかりでは説教をされているようで、相手は疲れてしまいます。
そして、次第に相手は「なんとなく聞いている」「無意識の内に聞き流している」といった行動をとり、それが続くと「この人の話は聞きたくない」という心の拒否反応がでてきます。そうなってしまうと、こちら側がいくら熱心に話しても相手の耳には届きません。つまり、会話は内容以前に、相手が話をきちんと聞こうとしている状態でなければ、意味がないのです。(重要!)
「会話には話す側と聞く側が存在する」と述べましたが、これでは聞く側が存在していないのと同じなのです。相手に話を聞かせるというのは、このような意味合いもあるわけで、自分の話に集中させるのも、上手な話し方の1つといえるでしょう。
※1
ある会社では、匿名の社内メールでアイディアを出し合ったり、社長に直接意見をいえるようなところもあります。
こういったところでは、自由な意見がいえるという環境から、大ヒットアイディア商品が生まれたり、人間関係の改善がスムーズにいく、というような良い成果が現れています。
これと似たような状況もあります。
例えば、上司に対して何か意見をいうと、意味なく却下されたり、「うるさいやつだ」とけむたがられたりする会社があります。しかし、そんな会社に限って「もっと会社をよくするにはどうしたらいいかアイディアがほしい!」「売り上げアップ方法を募集する!」などといったりします。普段は部下の意見など聞こうともしないくせに、そういうときだけ都合良く「アイディアほしい」といっても、もらえるわけがありません。アイディアがほしいならば、上司にでも気軽に意見がいえる体制をつくっておく必要があるのです。それをせずに部下にだけ責任をきせるのは、虫のいい話です。(※1)
もちろん、仕事ですから辛いことでも理不尽なこともやらなけばいけないときはあります。しかし、これはそういう次元の問題ではありません。「仕事なんだから文句いわず、下の者は何でも上司のいうことさえ聞いていればいいんだ。それができないなら、一人前の社会人ではない!」という考えは、今の時代でははっきりいってナンセンスです!(このへんを勘違いしているビジネスマンが本当に多い(^_^;))
「IT革命で当社はグローバルスタンダードを確立し…」 そんな安易な横文字はいりません!
「絶対勝ち組になるぞ!」 流行り文句もいりません!
そんなときだけ流行リを先取りしようとするくせに、肝心の会社体制が旧態依然のままではまったく意味がないのです。安易なフレーズで格好ばかりつけるのではなく、本質を見つめることのできる会社体制が必要なのです。(重要!)
もちろん、部下は部下なりに認められる人間でなくてはいけません。遅刻、欠勤などは論外ですが、きちんと仕事もこなし、誰が見ても立派にやっている者だからこそ意見をいえるわけです。
「あいつがいうなら、間違いはないだろう」
「あいつは頑張っているから、こっちも意見をきいてやらないとな」
部下がきちんとしていればこそ、上司も考慮するのです。しかし、仕事もできない、人間関係も良くないでは、誰も意見を聞くわけがありません。
話を戻しましょう。では、どうすれば相手を自分の話に引きつけることができるのでしょうか?
まず大事なのは、自分の意見をしっかりと持つことです。周りがいう度に意見が左右していては話の信頼性もなくなります。どんな状況でも自分の意見をはっきりいえる人は、非常にたくましく見え、聞く側もパワーを感じ、つい聞き入ってしまう場合が多いのです。(上司の受け売りばかり話していても、人を惹きつけることはできません)
そして、その話の内容はたとえ職場であっても、ユーモアのある話題をとり入れること。どんな話題でもつまらないものより、面白いものに集中して聞いてしまうのは当前のことです。硬い話の後の、一種の清涼剤にもなります。普段の会話では、皆が笑えるような楽しい会話を、そしていざというときには真剣に話してあげる、というバランスが大切なのです。
では普段の会話についても説明しておきましょう。世の中には、「真面目な話しかしない人」、逆に「軟らかい話しかしない人」が、少なからずいます。
前者は、悪くいえば冗談が通じなかったり、ユーモアセンスがあまりない人です。別に悪い人ではないのですが、根が真面目すぎるのです。このような人は、コミュニケーションを行う上では損をしているといえるでしょう。…というのも、確かに真面目な話題のときはいいでしょう。しかし、それだけでは周りは疲れるし、気を抜いて楽しみたいときには「つまらない話」にしかならないからです。ですから、少しでも軟らかい話もするように意識するれは、もっと上手なコミュニケーションが可能になると思います。(^_^)
後者は、笑えるような話題には積極的に参加するが、真面目な話になると急に黙ってしまう人です。その理由に、「単純に楽しくない話はしたくない」という人もいれば、「真面目な話は上手にできない」「真面目な話は恥ずかしい」というような人まで様々です。また「真面目な討論では喧嘩口調になり、嫌な思いをする場合もあるので話さない」という人もいます。
これも前者と同様に、コミュニケーションを行う上では損をしています。確かに、普段から楽しい話題ができる人は、軟らかいイメージも定着し、話しやすく好感を持たれることが多いでしょう。しかし、それだけでは相手は「真面目な話をしても軽く流され、深く考えてくれないのではないか?」という恐れから、真剣な相談事はできないのです。
人は、自分の悩みや意見を伝えることで、「この人はこういう考えを持っているんだ」と本質を見極めることができ、そうやって自分をさらけだせる人には気を許せるのです。いくら表面で楽しい話をしていても、それだけではその人の本心は掴めないため、警戒心もある以上、心を許せないわけです。
何事もそうですが、普段はおちゃらけていても、いざ真剣に「やるぞ!」となったら力を発揮する人は非常に頼もしいものです。職場でも、普段は面白い話ばかりしているけど、いざとなったら自分の意見をはっきりいう人は「この人は実はきちんと考えている人だ!」「やるときはやる人だ!」という目で見られ、1人の人間としての評価も上がるのです。そしてこういう人の話というのは、部下、上司に関わらず、誰でも無意識のうちに聞き入ってしまうものなのです。
上手に部下を動かす方法!
会話は相手あってのものなので、自分の考えに固執してはいけません。
お笑いの世界では、基本中の基本なのですが、「そのネタが本当に面白いか?」「ネタをより面白く聞かせるにはどうすればいいか?」などは、常にそれを聞く観客の立場になって考えないとできないものです。
※1
私は討論番組も好きでよく見るのですが、日本の番組はつまらないものが多いです。その原因は、主に次の2つです。
第一に、「相手のいうことに耳をかさない」
まず「人の話をゆっくり落ち着いて聞く」という当たり前のことが、できていません。(^_^;)
第二に、「話の根拠を第三者に分かるように提示して、客観性や確実性が競われることが少ない」
自分達の主張を延々繰り返すだけで、その根拠が提示されることがありません。
要は、単なる思い込みだけで、自分の主張を支えるきちんとした根拠を持ち合わせていないのです。
しかし、日常ではこれができていない人が非常に多いのです。1番良くないのが「絶対~だ!」「~である!」という、自分の考えだけで物事を断言するいい方です。議論などでも、白熱すると我を忘れてこういった口調になりやすいので、注意しましょう。
仮に根拠があっても、必ずしもそれが正しいとは限らないし、自分だけがそう思っている1人よがりの可能性もあります。そのため、どんなに自信のある話題でも、相手の意見に耳を傾ける姿勢を忘れてはいけません。(※1)別の意見があるという事実をきちんと受け止め、その上で意見があれば、丁寧に答えることです。
失敗例としてよくあるのが、会社の上司と部下という関係での会話です…。
上司は立場が上ということから、部下の立場や気持ちを考慮せずに、
「会社とはこういうもんだ!」
「人生の先輩の私がいうんだから間違いない!」
…というような発言をしがちです。
しかし、本当にそうなのでしょうか?確かに、長年勤めているだけに自社のことに関しては詳しいかもしれません。ただ世の中にはたくさんの会社が存在し、会社によってその方針は様々なのです。もちろん、あるていど基本的な考え方はあるでしょうが、いちがいに会社というものを、1つの枠でくくることはできないはずです。逆に長年勤めていることが却って頭を固くさせ、新しい意見を受け入れない体制をつくってしまうことも多いのです。
また、上司は部下よりも世間を知っているような態度をとりがちですが、それも勝手な思い込みです。自分は相手のことをどこまで知っているのでしょうか?部下であっても、その人は自分よりも多くの職歴、経験、人脈、知識を持っている可能性もあるわけです。それを部下というだけで、相手の技量を勝手に計っては、失礼ではないでしょうか。
それもこれも、すべては上から物をいう姿勢が原因なのです。どんな相手であろうと、意見を交わしあう際には、同じ目線に立って物をいわなければ、相手に対し気持ちが伝わらないし、説得力を持ちません。(例えば、子供と話すときに、子供の目線に立って話してあげなければ、子供は心を開いてくれません。それと同じことです) もちろん立場上、相手を部下として見ることはかまいません。ただし、あくまで部下としてであって、人間として下に見てはいけないのです。(重要!)
とくに人を動かす立場にいる人間は、こういった部分で技量を判断されます。相手はロボットではないのですから、無理やり動かそうとしても動いてはくれません。仮に強引に動かしたとしても、そんな状況では能率の良い仕事など望めるわけもありません。
近年、日本でも評判の「コーチ」というものがあります。(コーチの詳細は、こちら)
コーチは、大手企業の社員教育にも使われています。とくに人を使う立場にいる人間には必須の技術であり、これによって良い上司、悪い上司が決まるといっても過言ではありません。
悪い上司は、何でも自分の考えを押しつけ、何かトラブルが起こると頭から叱ることしかしません。しかし、それでは部下は伸びないのです。
良い上司は、トラブルが起こると「どうしてトラブルが起きたんだい?」と、まず相手に委ねます。そして原因が分かれば、「じゃあ、解決策はどうすればいい?」と、部下に発想をださせます。最後に「君を認めているから、本当に頑張ってほしいと思っているんだよ」などと、期待の言葉をかけてあげれば、「自分で考えた!」という結果がやる気をださせ、部下は自発的に行動を起こすようになるのです。もちろん、状況によっては厳しく叱る必要もあります。ただ、トラブルが起こったときに「何も考えずに叱るだけ」では、部下を活かし、伸ばすことはできないということです。
このように人間関係は、「上から命令すれば良い仕事をする」というほど単純なものではありません。仕事ですから、中には嫌なことも辛いことも、やらなければいけないときはあります。意見をいっても通らないこともあります。しかし、それは皆分かっていることです。分かっていても「つべこべいわずやれ」「部下の意見はしょせん戯言だ」と門前払いの状態では、誰もそこで頑張って働こうとは思わないでしょう。
会社組織は、上にいけばいくほど、保身主義、権威主義になり、下の状況が掴みにくくなる傾向があります。それだけに、自分が人を動かす立場にいるときは、できるだけ下の身になってあげることです。そして表面的な言葉だけでなく、本当に心から相手を労り、その立場を理解してあげる。そうすればその気持ちが相手にも伝わり、自分を理解してくれる人に対して、期待に答えようと自主的に一生懸命働いてくれるようになるのです。
上司と部下という関係であっても、互いに一人の人間には違いがありません。相手を説得したり、心を動かすためには「ただ正論をいえばいい」というわけではないのです。相手を理解し、自分自身を高めることが何より大事なのです…。
「はい」「いいえ」をはっきり伝え信頼関係を築こう!
人間関係は、何事も信用が大事です。トラブルの大きな要因には、誤解の他にも「互いに信頼関係を築けていない」ことが挙げられます。
例えば、友人があなたの性格の悪い部分を指摘して、あなたも「分かった。これから直すように努力する」と約束したとします。しかし、いつまで経っても、何度いわれても直る気配がない…。すると、友人はあなたに対して不信感を抱くはずです。
自分の行動を直すのは大変な努力が必要です。それは自分のためでもありますが、同時に相手を想っての行動でもあるわけです。つまり、あなたが努力することで、友人は「自分のために頑張ってくれている」と、感じるのです。約束を守らないということは、それを感れないわけですから、当然、不信感もでて喧嘩になりやすくなります。このような人は、次の点に注意するといいでしょう。
1.自分の言葉には、責任を持つ。
2.協調性をもち、相手のことを考慮する。
3.自分の悪い部分を認め、素直に謝る。
まず、口にだしていったことは責任を持って必ず実行することです。実行できなければ約束を破ることになり、信用を失うことになります。仮に無理なら、最初から「できない」ことを相手に伝えるべきでしょう。とくに日本人は「相手に悪いから断りづらい」という人が多いですが、安請け合いして実行できなければ、余計に迷惑をかけることになります。本当に相手のことを想う気持ちがあるのなら、何でも安易な約束はしないことです。
もちろん、そうかといって努力する姿勢を見せずに、すべて「できません」では誠意を感じないため、結局は良い関係は築けません。「自分が頑張れはできることか?」を見極め、なるべく相手の気持ちに答えてあげるのです。それがどうしても無理であれば、丁寧な言葉で断ればいいだけです。(その際も丁寧に断りましょう)
とくにビジネスの場においては、非常に重要でしょう。先方の要件を安易にのみ、それに答えられなければ一気に信頼を失います。仕事付き合いといっても、相手も人間です。人間関係は、自分よりも相手のことを考えて行動する協調性が大事なのですよ。
他には、自分の行動で何か悪い部分があれは、素直に謝ることです。悪い部分を認めようとせず、反発するから喧嘩になるわけです。冷静に相手の言葉を受け止め、素直に謝ることも必要です。
ただ、これはあくまで自分がミスしたときの最終手段であって、そのような状況をつくらないに越したことはありません。よく「浮気しても謝れば済む」と思い、「浮気→謝り→浮気…」の繰り返しの人がいます。しかし、謝るという行為はあくまでフォロー的な意味があるだけで、ミスした事実がなくなるわけではありません。人間関係は、たった1度のミスで関係が断たれてしまうことも珍しくないため、充分注意しましょう。
世の中の良い信頼関係を築いている人たちは、責任のある行動をしているため、「あの人のいうことだから間違いはない」「あの人だから安心してまかせられる」と、互いに思っています。それだけに、仮にミスがあっても「誤解の可能性が高い」「何か理由があるのだろう」と考えることができるわけです。当然、トラブルが起きたとしても、感情的にならず冷静に対処ができ、相手を許すこともできるのです。
人は自分の価値観で物事を見ようとしますが、どんなに仲の良い友人、長い付き合いのビジネスパートナーであっても、同じ人間ではない以上、すれ違いも生じます。その中で上手い付き合いをしていくには、信頼関係が何よりも重要なのです。そして、そのためには普段から相手のことを考え、自分の発言と行動には責任を持つことです。そうした行動の1つ1つの積み重ねが、大きな信頼関係を築いていくのですよ。
http://yuki-takizawa.com/commu/syokuba.htm
→笑いの効果 →人に好かれる方法(基本編) →人に好かれる方法(恋愛編)
●高いプライドを捨て一流のビジネスマンになる!
●人に話しを聞かせる方法とは!?
●上手に部下を動かす方法! ●「はい」「いいえ」をはっきり伝え信頼関係を築こう!
●活字の使い方をマスターしよう!
高いプライドを捨て一流のビジネスマンになる!
まず最初にいっておくと、高すぎるプライドは人間的魅力を下げるということです。社会人になり多くの仕事をこなしていくと、出世していきます。すると自分に大きな自信がつき、高いプライドを持つようになる人も少なくありません。しかし、自分の仕事にプライドを持つのは大切ですが、不必要に天狗になってはいけません。
※1
そういう人は、分かりにくい専門用語や外国語をあえて見栄をはって使う傾向があります。自分の知識をひけらかすような話し方をして相手に不快感を与えている可能性が高いので、充分注意したほうがいいでしょう。
仮に内容が分かりにくい可能性が少しでもある場合は、事前に簡単な説明を入れてあげれば、嫌味のないスマートな会話ができますよ!(^_^)
高いプライドを持っている人は、一見、自信満々にも思えますが、実は自分に本当の自信がないために、そういった態度で武装しなければ落ち着けない人なのです。(自分では自覚していない場合がほとんどですが…(^_^;))
「自分は人よりできる存在でなくてはいけない」
「人前で失敗はできない」
…そういったプライドが膨らんでくると、いわゆる完璧主義な人間になってきます。そのような人は、自分で自分の行動は完璧と思い込んでいるため、自分の考えにそぐわない他人の行動は、ちょっとしたことでも許せなく思います。他人が失敗したりすると「自分はこんなに一生懸命やっているのに、何であいつは失敗するんだ!」と、すぐに怒りだしたりする人です。(^_^;)
(完璧主義でなくても同じ会社に長く勤めていると、誰でもそのような傾向がでてくるので注意!)
また「他人に無様な姿を見せられない」と思うあまり、失敗することに対して恐れを抱くようになります。そのため、必要以上にプレッシャーを感じてしまい、結果的に余計に失敗します。このように完璧主義とは、余計なことで気を遣い、ストレスを溜め、人間関係をも崩していくものなのです。
誰でも、天狗になっている人間を認めようとはしません。本人は自分の素晴らしさを必死でアピールしますが、いえばいうほど周りは白けてくるのです。周りから認められないと、人は無意識に不安を感じるため、それを解消するために余計に自慢話が多くなるという悪循環に陥ります。そして、権威のある人の話などを持ちだしてきては、「自分の考えは先生方もいっているから間違いない!」と、他人の受け売りで話をするようになるのです。(※1)
完璧主義な人は「何事も真面目に一生懸命こなし、人に弱いところも見せず、すべて自分一人でやりとげる」という、スキのない行動をとります。一見、素晴らしい行動にも思えますが、どうしてそれがいけないのでしょうか?
それは、そのような行動は周りから見れば心にゆとりのない行動であり、一緒にいて非常に窮屈に感じてしまうのです。悪くいえば、工場で動くロボットのような感じで、人間味を感じられないのです。まして、その完璧さを周りの人にも求めるとなると、なおさらです。(そのような人は心にゆとりがないため、忙しくなってくると人に八つ当たりをしがちです(^_^;))
そのため、実際はそうでなくても「冷たい人」「接しにくい人」といったイメージがつきやすく、人間関係は悪い方向へ向かっていきます。考えてみれば、実際にそんな人と一緒にいても、少しも楽しくないことは容易に想像できます。仮にそれが上司なら、部下はいいたいこともいえず、ギクシャクした関係しか築けないことは目に見えています。なぜなら、部下の気持ちを理解できない人間が、部下を効率良く動かせるわけがないからです。(重要!)
人間誰でも固いイメージの人には近付きがたいもので、むしろどこか失敗したり、ちょっと間抜けなところがある人の方が接しやすいのです。弱い部分、悪い部分であっても、それを人前にさらけだして始めて相手も安心して心を開けるのです。弱い部分を見せることは、決して恥じることではありません。どんなに虚勢をはっていても、落ち込んだり、悲しんだりすることは人間である以上、誰でもあるのです。そういった部分を素直にだせる人には誰でも親近感が湧き、「何とか力になりたい!」という気持ちがでてくるものです。
今の時代、仕事ができるだけでは一流のビジネスマンとはいえません!一流のビジネスマンには、何よりコミュニケーションスキルが必要なのです。近年になってようやく「コミュニケーションスキルを高めよう!」という動きもでてきていますが、それでもまだまだ多くの会社では昔ながらのやり方であるのが現状です。(私もそういう会社をいくつか経験してますが、本当にストレス溜まります。(笑))
部下に信頼され、仕事もプライベートも本気で頼られる。あなたも、そんな理想の上司になってみてはいかがでしょうか。
人に話しを聞かせる方法とは!?
会話には、常に「話す側」と「聞く側」が存在しています。しかし、聞く側が内心でそれを拒否している場合、つまり「聞く耳を持たない」状態になっていては、少なくともコミュニケーションが成立しているとはいえません。
具体的に説明しましょう。次のような状況を想像して下さい…。
あなたは職場の仲間に色々と自分の意見を熱心に述べています。しかし、あなたはいわゆる「真面目一本」というような性格で、何かというと真面目な堅い話しかしません。(そうではなくても「必要以上に細かいことをいう…」など、仕事にうるさい状況なら何でも可) しかし、いっていることは正しいのですが、毎回そんな話ばかりでは説教をされているようで、相手は疲れてしまいます。
そして、次第に相手は「なんとなく聞いている」「無意識の内に聞き流している」といった行動をとり、それが続くと「この人の話は聞きたくない」という心の拒否反応がでてきます。そうなってしまうと、こちら側がいくら熱心に話しても相手の耳には届きません。つまり、会話は内容以前に、相手が話をきちんと聞こうとしている状態でなければ、意味がないのです。(重要!)
「会話には話す側と聞く側が存在する」と述べましたが、これでは聞く側が存在していないのと同じなのです。相手に話を聞かせるというのは、このような意味合いもあるわけで、自分の話に集中させるのも、上手な話し方の1つといえるでしょう。
※1
ある会社では、匿名の社内メールでアイディアを出し合ったり、社長に直接意見をいえるようなところもあります。
こういったところでは、自由な意見がいえるという環境から、大ヒットアイディア商品が生まれたり、人間関係の改善がスムーズにいく、というような良い成果が現れています。
これと似たような状況もあります。
例えば、上司に対して何か意見をいうと、意味なく却下されたり、「うるさいやつだ」とけむたがられたりする会社があります。しかし、そんな会社に限って「もっと会社をよくするにはどうしたらいいかアイディアがほしい!」「売り上げアップ方法を募集する!」などといったりします。普段は部下の意見など聞こうともしないくせに、そういうときだけ都合良く「アイディアほしい」といっても、もらえるわけがありません。アイディアがほしいならば、上司にでも気軽に意見がいえる体制をつくっておく必要があるのです。それをせずに部下にだけ責任をきせるのは、虫のいい話です。(※1)
もちろん、仕事ですから辛いことでも理不尽なこともやらなけばいけないときはあります。しかし、これはそういう次元の問題ではありません。「仕事なんだから文句いわず、下の者は何でも上司のいうことさえ聞いていればいいんだ。それができないなら、一人前の社会人ではない!」という考えは、今の時代でははっきりいってナンセンスです!(このへんを勘違いしているビジネスマンが本当に多い(^_^;))
「IT革命で当社はグローバルスタンダードを確立し…」 そんな安易な横文字はいりません!
「絶対勝ち組になるぞ!」 流行り文句もいりません!
そんなときだけ流行リを先取りしようとするくせに、肝心の会社体制が旧態依然のままではまったく意味がないのです。安易なフレーズで格好ばかりつけるのではなく、本質を見つめることのできる会社体制が必要なのです。(重要!)
もちろん、部下は部下なりに認められる人間でなくてはいけません。遅刻、欠勤などは論外ですが、きちんと仕事もこなし、誰が見ても立派にやっている者だからこそ意見をいえるわけです。
「あいつがいうなら、間違いはないだろう」
「あいつは頑張っているから、こっちも意見をきいてやらないとな」
部下がきちんとしていればこそ、上司も考慮するのです。しかし、仕事もできない、人間関係も良くないでは、誰も意見を聞くわけがありません。
話を戻しましょう。では、どうすれば相手を自分の話に引きつけることができるのでしょうか?
まず大事なのは、自分の意見をしっかりと持つことです。周りがいう度に意見が左右していては話の信頼性もなくなります。どんな状況でも自分の意見をはっきりいえる人は、非常にたくましく見え、聞く側もパワーを感じ、つい聞き入ってしまう場合が多いのです。(上司の受け売りばかり話していても、人を惹きつけることはできません)
そして、その話の内容はたとえ職場であっても、ユーモアのある話題をとり入れること。どんな話題でもつまらないものより、面白いものに集中して聞いてしまうのは当前のことです。硬い話の後の、一種の清涼剤にもなります。普段の会話では、皆が笑えるような楽しい会話を、そしていざというときには真剣に話してあげる、というバランスが大切なのです。
では普段の会話についても説明しておきましょう。世の中には、「真面目な話しかしない人」、逆に「軟らかい話しかしない人」が、少なからずいます。
前者は、悪くいえば冗談が通じなかったり、ユーモアセンスがあまりない人です。別に悪い人ではないのですが、根が真面目すぎるのです。このような人は、コミュニケーションを行う上では損をしているといえるでしょう。…というのも、確かに真面目な話題のときはいいでしょう。しかし、それだけでは周りは疲れるし、気を抜いて楽しみたいときには「つまらない話」にしかならないからです。ですから、少しでも軟らかい話もするように意識するれは、もっと上手なコミュニケーションが可能になると思います。(^_^)
後者は、笑えるような話題には積極的に参加するが、真面目な話になると急に黙ってしまう人です。その理由に、「単純に楽しくない話はしたくない」という人もいれば、「真面目な話は上手にできない」「真面目な話は恥ずかしい」というような人まで様々です。また「真面目な討論では喧嘩口調になり、嫌な思いをする場合もあるので話さない」という人もいます。
これも前者と同様に、コミュニケーションを行う上では損をしています。確かに、普段から楽しい話題ができる人は、軟らかいイメージも定着し、話しやすく好感を持たれることが多いでしょう。しかし、それだけでは相手は「真面目な話をしても軽く流され、深く考えてくれないのではないか?」という恐れから、真剣な相談事はできないのです。
人は、自分の悩みや意見を伝えることで、「この人はこういう考えを持っているんだ」と本質を見極めることができ、そうやって自分をさらけだせる人には気を許せるのです。いくら表面で楽しい話をしていても、それだけではその人の本心は掴めないため、警戒心もある以上、心を許せないわけです。
何事もそうですが、普段はおちゃらけていても、いざ真剣に「やるぞ!」となったら力を発揮する人は非常に頼もしいものです。職場でも、普段は面白い話ばかりしているけど、いざとなったら自分の意見をはっきりいう人は「この人は実はきちんと考えている人だ!」「やるときはやる人だ!」という目で見られ、1人の人間としての評価も上がるのです。そしてこういう人の話というのは、部下、上司に関わらず、誰でも無意識のうちに聞き入ってしまうものなのです。
上手に部下を動かす方法!
会話は相手あってのものなので、自分の考えに固執してはいけません。
お笑いの世界では、基本中の基本なのですが、「そのネタが本当に面白いか?」「ネタをより面白く聞かせるにはどうすればいいか?」などは、常にそれを聞く観客の立場になって考えないとできないものです。
※1
私は討論番組も好きでよく見るのですが、日本の番組はつまらないものが多いです。その原因は、主に次の2つです。
第一に、「相手のいうことに耳をかさない」
まず「人の話をゆっくり落ち着いて聞く」という当たり前のことが、できていません。(^_^;)
第二に、「話の根拠を第三者に分かるように提示して、客観性や確実性が競われることが少ない」
自分達の主張を延々繰り返すだけで、その根拠が提示されることがありません。
要は、単なる思い込みだけで、自分の主張を支えるきちんとした根拠を持ち合わせていないのです。
しかし、日常ではこれができていない人が非常に多いのです。1番良くないのが「絶対~だ!」「~である!」という、自分の考えだけで物事を断言するいい方です。議論などでも、白熱すると我を忘れてこういった口調になりやすいので、注意しましょう。
仮に根拠があっても、必ずしもそれが正しいとは限らないし、自分だけがそう思っている1人よがりの可能性もあります。そのため、どんなに自信のある話題でも、相手の意見に耳を傾ける姿勢を忘れてはいけません。(※1)別の意見があるという事実をきちんと受け止め、その上で意見があれば、丁寧に答えることです。
失敗例としてよくあるのが、会社の上司と部下という関係での会話です…。
上司は立場が上ということから、部下の立場や気持ちを考慮せずに、
「会社とはこういうもんだ!」
「人生の先輩の私がいうんだから間違いない!」
…というような発言をしがちです。
しかし、本当にそうなのでしょうか?確かに、長年勤めているだけに自社のことに関しては詳しいかもしれません。ただ世の中にはたくさんの会社が存在し、会社によってその方針は様々なのです。もちろん、あるていど基本的な考え方はあるでしょうが、いちがいに会社というものを、1つの枠でくくることはできないはずです。逆に長年勤めていることが却って頭を固くさせ、新しい意見を受け入れない体制をつくってしまうことも多いのです。
また、上司は部下よりも世間を知っているような態度をとりがちですが、それも勝手な思い込みです。自分は相手のことをどこまで知っているのでしょうか?部下であっても、その人は自分よりも多くの職歴、経験、人脈、知識を持っている可能性もあるわけです。それを部下というだけで、相手の技量を勝手に計っては、失礼ではないでしょうか。
それもこれも、すべては上から物をいう姿勢が原因なのです。どんな相手であろうと、意見を交わしあう際には、同じ目線に立って物をいわなければ、相手に対し気持ちが伝わらないし、説得力を持ちません。(例えば、子供と話すときに、子供の目線に立って話してあげなければ、子供は心を開いてくれません。それと同じことです) もちろん立場上、相手を部下として見ることはかまいません。ただし、あくまで部下としてであって、人間として下に見てはいけないのです。(重要!)
とくに人を動かす立場にいる人間は、こういった部分で技量を判断されます。相手はロボットではないのですから、無理やり動かそうとしても動いてはくれません。仮に強引に動かしたとしても、そんな状況では能率の良い仕事など望めるわけもありません。
近年、日本でも評判の「コーチ」というものがあります。(コーチの詳細は、こちら)
コーチは、大手企業の社員教育にも使われています。とくに人を使う立場にいる人間には必須の技術であり、これによって良い上司、悪い上司が決まるといっても過言ではありません。
悪い上司は、何でも自分の考えを押しつけ、何かトラブルが起こると頭から叱ることしかしません。しかし、それでは部下は伸びないのです。
良い上司は、トラブルが起こると「どうしてトラブルが起きたんだい?」と、まず相手に委ねます。そして原因が分かれば、「じゃあ、解決策はどうすればいい?」と、部下に発想をださせます。最後に「君を認めているから、本当に頑張ってほしいと思っているんだよ」などと、期待の言葉をかけてあげれば、「自分で考えた!」という結果がやる気をださせ、部下は自発的に行動を起こすようになるのです。もちろん、状況によっては厳しく叱る必要もあります。ただ、トラブルが起こったときに「何も考えずに叱るだけ」では、部下を活かし、伸ばすことはできないということです。
このように人間関係は、「上から命令すれば良い仕事をする」というほど単純なものではありません。仕事ですから、中には嫌なことも辛いことも、やらなければいけないときはあります。意見をいっても通らないこともあります。しかし、それは皆分かっていることです。分かっていても「つべこべいわずやれ」「部下の意見はしょせん戯言だ」と門前払いの状態では、誰もそこで頑張って働こうとは思わないでしょう。
会社組織は、上にいけばいくほど、保身主義、権威主義になり、下の状況が掴みにくくなる傾向があります。それだけに、自分が人を動かす立場にいるときは、できるだけ下の身になってあげることです。そして表面的な言葉だけでなく、本当に心から相手を労り、その立場を理解してあげる。そうすればその気持ちが相手にも伝わり、自分を理解してくれる人に対して、期待に答えようと自主的に一生懸命働いてくれるようになるのです。
上司と部下という関係であっても、互いに一人の人間には違いがありません。相手を説得したり、心を動かすためには「ただ正論をいえばいい」というわけではないのです。相手を理解し、自分自身を高めることが何より大事なのです…。
「はい」「いいえ」をはっきり伝え信頼関係を築こう!
人間関係は、何事も信用が大事です。トラブルの大きな要因には、誤解の他にも「互いに信頼関係を築けていない」ことが挙げられます。
例えば、友人があなたの性格の悪い部分を指摘して、あなたも「分かった。これから直すように努力する」と約束したとします。しかし、いつまで経っても、何度いわれても直る気配がない…。すると、友人はあなたに対して不信感を抱くはずです。
自分の行動を直すのは大変な努力が必要です。それは自分のためでもありますが、同時に相手を想っての行動でもあるわけです。つまり、あなたが努力することで、友人は「自分のために頑張ってくれている」と、感じるのです。約束を守らないということは、それを感れないわけですから、当然、不信感もでて喧嘩になりやすくなります。このような人は、次の点に注意するといいでしょう。
1.自分の言葉には、責任を持つ。
2.協調性をもち、相手のことを考慮する。
3.自分の悪い部分を認め、素直に謝る。
まず、口にだしていったことは責任を持って必ず実行することです。実行できなければ約束を破ることになり、信用を失うことになります。仮に無理なら、最初から「できない」ことを相手に伝えるべきでしょう。とくに日本人は「相手に悪いから断りづらい」という人が多いですが、安請け合いして実行できなければ、余計に迷惑をかけることになります。本当に相手のことを想う気持ちがあるのなら、何でも安易な約束はしないことです。
もちろん、そうかといって努力する姿勢を見せずに、すべて「できません」では誠意を感じないため、結局は良い関係は築けません。「自分が頑張れはできることか?」を見極め、なるべく相手の気持ちに答えてあげるのです。それがどうしても無理であれば、丁寧な言葉で断ればいいだけです。(その際も丁寧に断りましょう)
とくにビジネスの場においては、非常に重要でしょう。先方の要件を安易にのみ、それに答えられなければ一気に信頼を失います。仕事付き合いといっても、相手も人間です。人間関係は、自分よりも相手のことを考えて行動する協調性が大事なのですよ。
他には、自分の行動で何か悪い部分があれは、素直に謝ることです。悪い部分を認めようとせず、反発するから喧嘩になるわけです。冷静に相手の言葉を受け止め、素直に謝ることも必要です。
ただ、これはあくまで自分がミスしたときの最終手段であって、そのような状況をつくらないに越したことはありません。よく「浮気しても謝れば済む」と思い、「浮気→謝り→浮気…」の繰り返しの人がいます。しかし、謝るという行為はあくまでフォロー的な意味があるだけで、ミスした事実がなくなるわけではありません。人間関係は、たった1度のミスで関係が断たれてしまうことも珍しくないため、充分注意しましょう。
世の中の良い信頼関係を築いている人たちは、責任のある行動をしているため、「あの人のいうことだから間違いはない」「あの人だから安心してまかせられる」と、互いに思っています。それだけに、仮にミスがあっても「誤解の可能性が高い」「何か理由があるのだろう」と考えることができるわけです。当然、トラブルが起きたとしても、感情的にならず冷静に対処ができ、相手を許すこともできるのです。
人は自分の価値観で物事を見ようとしますが、どんなに仲の良い友人、長い付き合いのビジネスパートナーであっても、同じ人間ではない以上、すれ違いも生じます。その中で上手い付き合いをしていくには、信頼関係が何よりも重要なのです。そして、そのためには普段から相手のことを考え、自分の発言と行動には責任を持つことです。そうした行動の1つ1つの積み重ねが、大きな信頼関係を築いていくのですよ。
http://yuki-takizawa.com/commu/syokuba.htm










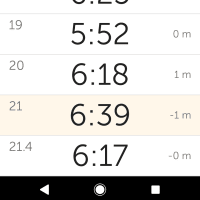

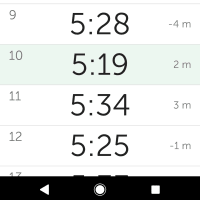
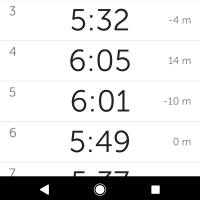
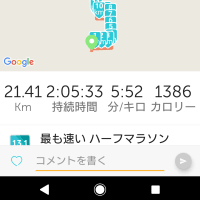





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます